隠れたベストセラーだという本書を新聞で知り、購入しました。内容は、近代化以前のこの国の人々の姿や感性を、幕末から明治初期にかけて来日した外国人の記録を通して明らかにしようとしたものです。外国人の感じた当時の日本各地の人々の姿といっても、肯定的なほめ言葉を集めたといってもよいでしょう。近世のこの国に暗い面があることは事実だが、多くの賛辞を贈られていることも事実なのだと著者は述べている。そこで、この本について評することはなかなか難しい。うっかりすると、日本賛辞、昔はよかった、だから近代化以前の心性に戻らなければならないとなってしまうからです。反対に、フェミニズム・オリエンタリズム・ヒューマニズムなどから見ると、にべもなく一刀両断されてしまうような内容です。
少し章を紹介すると、簡素とゆたかさ、親和と礼節、雑多と充溢、労働と身体、自由と身分、裸体と性、女の位相 、子どもの楽園、風景とコスモス、などです。こうした内容は、極めて民俗学あるいは人類学の視点に近いものですし、民俗学以上に民俗学的にエトノスを追求しているといっていいでしょう。中でも自分が興味をひかれたのは、「裸体と性」について書かれた章です。明治の初めに混浴が外国人に対して恥ずべき事と、法律で規制したことは、それほどに感性の落差があったととの例として、明治維新の学習で生徒に教えました。しかし、混浴が違和感なく受け入れられていた幕末の感性までは扱えませんでした。というか、何だかうまく説明できない違和感のようなものがありました。それは同時に、土間にスエブロを置いて家族中が入浴したことは、昔は暗くて見えなかったんだよ、といわれても、何だかすっきりしない思いと重なるものでした。今回これを読んで、裸体を見ても何とも思わない、たとえば入浴中の女性と顔をあわせても、普通に挨拶をかわしてむしろ淫らな妄想を考える自分(外国人)が恥ずかしいようなことが書かれています。もっとも、悪意のある外国人は恥を知らない野蛮人であると書いているのですが。幕末ころは、タヒチの人々と同じような感性をこの国の人々は持っていたことがわかるのです。
はじから書いていけばきりがないのですが、裸体に関する感性は1つの例なのですが、近代化以前の人々は、現在のわれわれとは異なる感性を持っていたといえるような気がします。労働をとってみますと、ありきたりの言葉で言えば労働から阻害されていない、お金のための労働ではなく、生きることと楽しむことと働くことが渾然一体としていたのです。外国人がみると、こんな怠け者はない、すぐ歌ったりどっかへ行ってしまったり人が来るといつまでも話しているというのです。そりゃそうです。働くことも生きていることのうちですから、この時間のうちは勤務でお金で労働時間を売っているなどという意識はないのです。それで、これは貧しくとも生活満足度が高いとひところ随分報道されたブータンの人々と同じだったと思ったのです。
ウルトラナショナリストの心をくすぐるような賛辞が並んでいます。解説で、石原慎太郎が本書を高く評価しているとありましたが、そうだろうと思います。分をわきまえて暮らせば人間は幸せであるし、男女同権が必ずしも女に幸せをもたらしたわけではないと、都合の良い部分だけとりだせば読めてしまうのです。










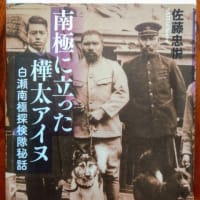

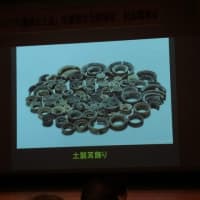


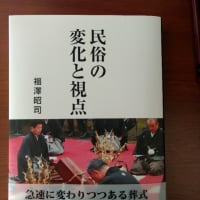




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます