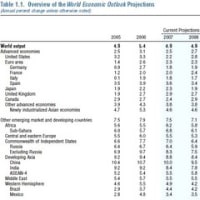| 脳に悪い7つの習慣 (幻冬舎新書 は 5-1) |
| 林 成之 | |
| 幻冬舎 |
☆脳科学の本ではない。
☆大脳皮質神経細胞に、脳に悪い情報を入れないようにすると、
☆そのあと様々な脳の領域が連合して循環する
☆ダイナミック・センターコアが良質循環し、
☆やる気は起こるは、創造力はみなぎるは、
☆人助けはするは、
☆世の中ハッピーに出来るよ!
☆という痛快丸かじり元気がでる本。
☆だから、次のように疑問を持ってはいけない。
☆脳に良いこととは、自己のためではなく、人のために働くことだと。
☆しかし、すでに悪循環しているダイナミック・センターコアの存在は、
☆いかにしてこの人のために働くことを認識できるのだろう?
☆情けは人のためならずだから、結局自己保身じゃん。
☆などと愚痴をいっちゃあ脳には悪い。
☆「疲れた~」と言っていたら、脳に悪いし、周りの人の脳も悪くしちゃうと。
☆しかし、そんな相手をなんとか助ける貢献が、脳にはよいわけなのだから、
☆「疲れた~」連発の人とつきあうことはよいことか?
☆でもそうするとこっちも脳に悪い習慣ができてしまう。
☆このジレンマどうしたらよいのか~?
☆とブログなど書いていることは脳にとってもよいとも書いてある。
☆しかし、そもそも脳に悪いとはどういうことか?
☆生命危機情報(もちろん毒物もふくめ)以外、悪いということはそもそもない。
☆これだ!!!!!
☆実は愚痴も「疲れた~」もよい情報なのである♪
☆だってそういう寛容さこそが、人間関係を柔軟にし、
☆社会貢献することにもつながるではないか。
☆生命危機情報以外、すべて悪い情報なんてないのだ。
☆そう考えることにしよう♪











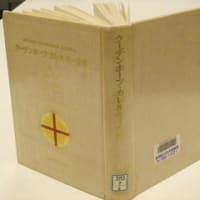


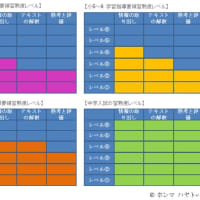
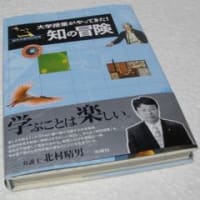
![府知事選の行方[了]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/e9/3d13aadc415722befc574b161350f584.jpg)
![府知事選の行方[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/80/2c2c23ed16365dd67e6b840f66b72c44.jpg)