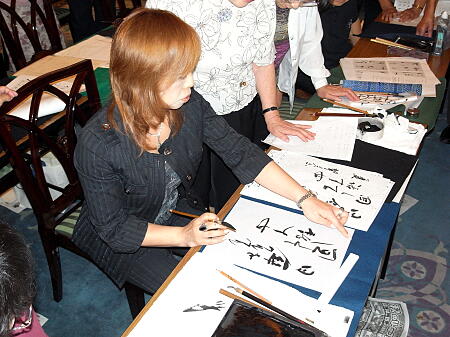秋の書・展覧会シーズンに向けて大忙し
10月街は、秋祭りの太鼓練習の音が響く。
ああ、今週末は「お祭りだ」。山車を引かねば……と思いつつも‥‥
ところが、10月というのは11月から始まる展覧会への前哨戦、いや準備段階というものである。
9月は、グループ展や社中展と11月からの県展を踏まえて練習の総仕上げ的な展覧会ばかりだったのだが、10月は大方1社中展ぐらいなものである。
実際、県展の裏方、事務方である小生などは、気がついてみれば材料の発注やら委員、委嘱作家の出品受付表が未完のままだった。
特に、今年から新装になった群馬県立美術館に戻るために、IDカードをそれなりに作らなければならない。
だから、今は嵐の前の静けさと言うところである。
一方、自身の作品は3日程かけてようやく完成し、7日の夕刻額と共に表具屋に持ち込んで置いた。
昨日は、T額装から請求書通りの表具代を支払ったのであるが、昔はもっと安かった様な気がする。兎に角、秋は物いりなのである。
実を言うと、県展作品が出来上がらないと細かい事務作業が出来ない質(たち)で、一息。
そして、こういう何か追われるように作品を作るというのが、来年3月まで続くのである。
しかも、必ず見て批評する人がいるから、気が抜けない作品作りでもある。
さて、最近ネットで「書道」というリンクを見ていると色々な人物がネット上で「書家」、「書道家」として登場している。
我々のように、地方の市民展、県展、中央書団、毎日、読売、日展などに絡む人達というのは、いわゆる表の世界の書道家というところだろう。
たとえば、(社)群馬県書道協会というところに所属する会員で組織された、群馬県書道展というのは、「官展」の意味合いが強いからである。(県の組織が主催者に名を連ねる)
逆に言うと、県内で活動する書道家は、ほとんど(社)群馬県書道協会に所属する。
事実、群馬県書道展・出品総点数約3000弱。公募2000を越える書道展であれば、群馬県展の審査員まで昇れば充分という意識と、別に「書の登竜門」と表現する場合もある。
そして、一方、全く別に「通信教育」で、いわゆる「師範」という称号をもらって、その仲間だけの展覧会に出品して限られた空間にのみ存在するという書道家がいるというのは知っていた。
そう言う人達というのは、(社)群馬県書道協会などによる学生のための群馬教育書道展とかその他の展覧会には無縁である。
又一方、地方ではあまり存在していないものの、書道系の大学、たとえば東京学芸大学教育学部の書道科とか出身で、単なる書塾をやっているという人物を見つけたりする。
普通、この手の人物は教員になるから、珍しいしどこかの書団に所属しているかと思えばそうではないらしいと言うところが不思議なものである。
そして、4番目に位置するのが首都圏とか都心にしか住んでいないと思われる「書デザイナー」とかの「ロゴ作家」である。ただこの人達は、デザイナーで書家ではないとはっきり言う場合が多いので、除外するのが穏当だろう。
只、5番目に位置するのが、ネット上に登場する‥‥というか見たことも聞いたこともない書家、書道家という人達だ。
そして、その人のWebサイトを追ってみると、いわゆる駆け出しの書道家だったり、「デザイナー」という職業だったり色々であるから面倒ではある。
これでは何が何だか分からぬではないかと言うものだろう。
しかし、小生などの地方では、書に関係していれば一目瞭然と言うところである。
但し、書歴の誤魔化しはなくとも、学歴の誤魔化しがあったりして面白いものではある。
もう20数年前、まだ健在だった師匠のY先生(元群馬県書道協会会長)に、書の何が大切かと聞いたのか、書の見方を聞いたのか忘れたが、兎に角何やら聞いたことが耳に残っている。
それは、「書に品があるかないか」と言うことだった。
いくら上手くても、品がない書というものはロクでもないと言うものだった。
そして、本当に「良い作品」は、書を全くやっていない人でも良さが分かると言うものだった。
それでかどうか知らないが、ある展覧会で今年の毎日書道展会員賞をもらった先生に会ったとき、部門が違うので門外漢ながら「素晴らしかった」と誉めておいた。
元々嘘が言えないタイプなので、こういう時は素直に出るというのは不思議。
本人も余程の自信作だったと見えて、「非常に喜んでいた」と言うことがあった。
但し、上毛書道30人展で「この作品良いでしょう」と先にある「偉い先生?」に言われたとき、絶句してしまったのには困ったものだった。
そう言えば、むかし群馬教育書道展の審査員を何年かしていたとき、この「おばさん先生」が部長だった様な??
そんな自画自賛する人物‥‥おばさん先生には困ったものだ。