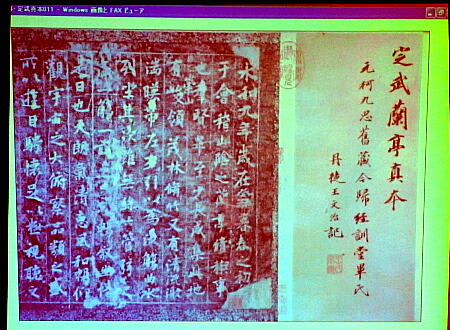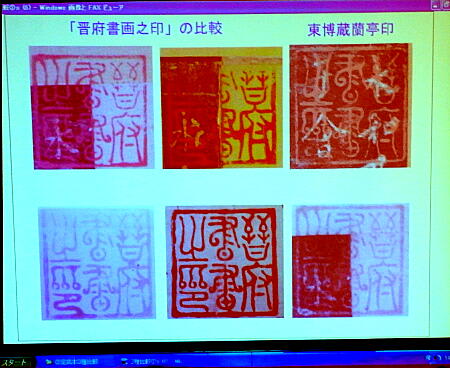平成21年6月1日施行される改正薬事法。
この法律で特徴的なのは、「大半の大衆薬のインターネット販売を禁止する一方、新たに設けた資格を持つ人材を配置すれば、薬剤師がいないコンビニなどでも販売が可能となる。」と言う事。
そして、その新たな試験というのが「登録販売者」資格というもの。
(医薬品の店舗販売業者等において、第二類および第三類一般用医薬品を販売する際に、2009年6月1日より必要(有効)となる都道府県実施試験資格。)
従来の「薬種商販売業認定試験」とは「開業の計画がある者だけに制限されており、個人に与えられる資格というよりも、店舗に与えられる許可という性質が強かった。(ウィキペディア(Wikipedia))」
今回の「登録販売者」は、「高等学校卒業かつ、1年間の実務経験のある者」で個人資格であるために、今まで事実上薬剤師常駐を余儀なくされたドラッグストアなどでは、第一類の調剤などを置かなければ必要なくなったという事だ。
これで、一時期の「薬剤師」資格ブームというのは過ぎ去ると言う事だろう。
そして、薬剤師資格ブームによって今後大量に生み出される薬剤師はどうするのかなどとゲスの勘ぐりを思ったりもする。
さて、「登録販売者」資格試験というものは、都道府県で行われるのであるが、「厚生労働省の検討会のとりまとめや薬事法施行規則改正案では、国の作成する「試験問題作成の手引き」等に準拠し、都道府県が問題を作成し試験を実施することとなっている。(ウィキペディア(Wikipedia))」
一応、「都道府県が問題を作成し試験を実施する」と言う事なのだか、現在では実施する都道府県によって合格率が84.5%から36.9%と難易度に差がありすぎる。(平均68%)
試験は住所に関係なくどの県でも受験可能だから、このままだと合格率の高い場所に集中する可能性がある。
これでは「登録販売者」資格試験と言うものの統一性が失われるというものだろう。
いずれ、この試験を行う特殊法人が設立されて統一問題又は、都道府県によって選べるサンプル試験問題というものが出来るはずだ。
場合によっては、その機関に一任すると言う事もあり得る。
今までの「薬種商販売業認定試験」とは違って、個人資格となる以上避けられないことだ。
こう考えてみると、規制の法律が一つ出来ると必ずその規制を満たす特殊法人が出来そうな事だ。しかも誰が見ても正当にだ。
「厚労省が、強硬な反対意見の中、当初方針通り、ネット販売を含む大衆薬の通信販売規制に踏み切ったのは、過去の薬害への反省から、利便性より安全性が重視されるべきだとの意識が働いたためです。(サンケイエクスプレス)」
という役人の一見まっとうそうな責任逃れは、実はあの「改正建築基準法」の考え方と全く同じなのである。
そして、「改正建築基準法」によって、建物構造が変わったのかと言えば全く建築に関して関係がなかった。原因となったのは、単なる悪質な手抜き工事会社だったにすぎない。そして、「改正建築基準法」、改正建築士法によって膨大で高額な更新講習収入、認定講習を生み出し、特殊法人の仕事を増やすのは、改正薬事法も基本的には同じ。
近年の規制強化という官僚の流れは、「一見反対出来ないような正当論」を振りかざして、知らず新たな利権を生み出す、規制緩和の流れに逆行するものである事を明記すべきだろう。