この部屋では、日本語こそ世界共通語にと、下記一覧のように何度も書いてきました。
5月08日 、第 1419回の「★ 日本語が世界共通語に最適な訳」
2014 年3月3日(月) 第 5279回 日 本語を 世界共通語に
2014 年4月30日(水) 第 5337回 鶯 の鳴き声が分らない
2014 年5月12日(月) 第 5349回 い よいよ世界共通語か
2017年 4 月 16日(日) 第 1032回 外 国人には虫の声が聞こえ無い?
2017年 5 月 13日(土) 第 1059回 日 本語で世界を平和に
と言うのも、上記のようにネットで知るにつれ、こんな素晴らしい言語はないと確信するようになったからです。こんな素晴らしい言葉を捨てて英語を世界共通語にすれば、世界は劣化するばかりでしょう。
それに比べて、日本語なら世界の人にとっても幸せを齎すと思われます。
何と、何時ものねずさんが、その日本語の凄さを取り上げてくれました。これは心強い。何時ものように、全文をリンク元で読んでください。
大和心を語る ねずさんのひとりごとよ り 2018年05月14日
実 はとてつもなく古かった日本語
かつて谷村新司がロンドン交響楽団をバックにレコーディングをしたことがあります。
そのとき日本語の素晴らしさを再認識し、日本語を大切に歌っていくことを信念にしたそうです。
ディズニー・アニメの『アナと雪の女王』は、世界的ヒットとなったアニメ映画ですが、そのなかの挿入歌の『レット・イット・ ゴー、ありのままで』は、世界25ヶ国語に翻訳され、それぞれの国の歌手が歌ったものがyoutubeで公開されました。
このとき、世界中の人たちが驚き、そして圧倒的な人気をはくしたのが日本語バージョンです。
それは、歌った松たか子さんの声の素晴らしさももちろんあるでしょうが、日本語による発声が、メロディに+αの効果をもたらした のかもしれません。
どこの国でも、それぞれにお国自慢があります。
ここで日本語が世界一だと述べるつもりは毛頭ありません。
ただ、ひとついえることは、どうやら日本語には、他の言語にはない、不思議なところがあるということです。
ひとつは言霊(ことだま)です。
言葉に魂が宿る。
ではどうして言葉に魂が宿るのかというと、日本語が実はもともとそのように構造された言葉だからなのだそうです。
構造とは、日本語の文法や発音や語彙のことです。
どうして魂が宿るのかというと、日本語がそもそも自然との共生を大切にして育まれてきたから言語だからなのだそうです。
2つ目はオノマトペ(仏:onomatopee)です。
オノマトペというのは擬声語を意味するフランス語です。
擬声語は、たとえば
わんわん、メーメー、ブーブー、ニャーオ、ホウホウといった動物の鳴き声を真似たものや、ドキドキ、パチパチ、バキューン、チ リーン、ドカン、カリカリ、バタン、ガタピシ、ガタンゴトン、パチバチ、ビリビリ、ジュージュー、グワァ〜ン、パタパタ、ボキポ キなどなど、音を真似たもの、あるいは、おずおず、おどおど、めろめろ、ふらふら、きゅんきゅん、きらきら、ぴかぴか、ぐずぐ ず、ツルツル、サラサラのように、本来音を発しない感情などを言葉で表現するものなどのことです。
おもしろいことに、擬声語(オノマトペ)は、言語ごとに、表現がまったく異なります。
冒頭にあるのは、その違いを示した絵本の抜粋で、クリックしていただくと当該ページに飛びますが、たとえば食事をするときは、日 本では「PAKU PAKU」ですが、英語では「CHOMP」、フランス語では「MIAM」、イタリア語では「GNAMグナム」、Korea語では「NYAM」です。
キスは日本語では「CHU」ですが、英語では「MWAH」、China語では「BOH」です。
つまり言語によって擬声語(オノマトペ)は、まったく異なります。
ということは、それぞれの言語圏においては、音がそのように聞こえているということです。
そして日本語の擬声語(オノマトペ)は、China語やKorea語ともまったく異なるものです。
ということは、日本語はChinaやKorea半島からの輸入語では絶対に「ない」ということです。
はありません。
日本語は、この擬声語(オノマトペ)が、他の国の言語と比べて著(いちじる)しく多いのです。
その数、なんと5千語です。
日本語の単語数は、たとえば『日本国語大辞典』の収録単語数が50万語です。
このことは、日本語の1%、およそ100語にひとつが擬声語(オノマトペ)であるということです。
そして単語の中には、日常生活でよく使われるものと、そうでない(たとえば学術用語)ものがあります。
オノマトペは日常的によく使われる語です。
早い話、今朝起きたとき、ご家族に「ぐっすり寝れた?」と聞く。
その「ぐっすり」というのがオノマトペです。
しかし睡眠は「ぐっすり」などという音は立てません。
ではなぜ「ぐっすり」というのかというと、「ぐうぐう、すやすや」寝ているからです。
その「ぐうぐう+すやすや」が短縮されて「ぐっすり」です。
「ぐうぐう」も「すやすや」も、なんとなく、そのような音を立てているといわれれば、なんとなくそうかもしれないと思われるか もしれません。
では、
風が「そよそよ」と吹く
太陽が「かんかん」に照る
白い雲が「ぽっかり」浮かぶ
星が「きらきら」光る
などはどうでしょうか。
風は「そよそよ」などという音をたてないし、太陽は「かんかん」なんてしゃべったりしません。
ではなぜこのようなオノマトペが使われているのでしょうか。
きたのかといえば、、自然がそのような音を立てているのではなくて、受け止める側が自然が発する音をそのように聞いているので す。
このことについて考古学者の小林達雄先生は、「人々が、人と人との間で行うコミュニケーションのための言語活動と同じか、ある いはそれに近いレベルで自然と向き合い、自然との間で活発な言語活動を行ってきた結果」(『縄文文化が日本人の未来を拓く』 p.134)と述べておいでです。
つまり、日本語は「自然と対話しながら発達してきた言語」なのです。
だから欧米人にはただの雑音にしか聞こえないカエルの鳴き声や虫の声も、日本人には美しい秋の音色となって聞こえる。なぜ美し いのかといえば、それは人がカエルや虫たちとコミュニケーションしているからです。
では日本語は、いつ頃の時代から形成されはじめたのでしょうか。
言語の発達には、ムラの形成が欠かせません。
なぜならムラを営むには、言語が必要だからです。
そしてそれは磨製石器の登場と時期を同じにするというのが世界の考古学会の定説です。…以下略
こんな豊な表現力を持った日本語をすたらすのは余りにも勿体無い。それを防ぐには、世界共通語にすることです。
世界の人に虫の声を聞き分けさせてあげましょう。
最新の画像[もっと見る]










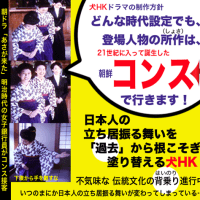
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます