温暖化の影響か、はたまた福島原発の汚染水の影響か、この時期に漁獲量が多くなる鮭とイカの、漁が薄い。・・・いや、薄すぎるぐらいだ。
ところが初秋からブリが大漁だ。ブリは出世魚と呼ばれ、大きくなるにつれ、名称が4回ほど変わる。名称は土地によって違うようだ。
最大のもの(10キロ以上)をブリ(鰤)という。
魚に師だから、出世して偉いという意味で、値も張るのだろう。
※前浜の漂着物で作成した鮭。先日釣りのお客様に見せたら、このサイズなら5キロ近い大物だと、結構真剣に見ていた。

先日、私は6キロのものを浜で購入してきた。
6キロというのは相当大きい。イナダというそうだが、マグロのように背丈は短く胴体は太い。
見た目はブリブリしているから、このぐらい大きなものであれば世間一般にはブリと呼ばれてもいいだろう。
スーパーでは切り身になると、ほとんどがブリの名称だ。
1~2キロ程度の切り身でも、ブリと表示しているが、これはいただけない。脂もなく美味しくないからだ。
売る側が意図的におこなっているような気もするが、消費者だってブリと呼ばれる代物ではないのは承知だ。ブリと表示した方が消費者にとっても心地よいからだと思う。正式な表示ではないかもしれないが、値段もそこそこで消費者が納得していれば、誤表示とは言えないのかもしれない。
私の地区ではその程度のサイズは“アオ”と呼んでいる。
全体が青いからそう呼ぶのだろうが、アオでは、身が成熟していないという感じで、いただけない。
大漁で異常に安値のブリ(総称で呼ぶ)だが、行く先はといえば、東京方面や富山県だと聞いている。
築地では北海道のブリが安くて美味しいと、テレビに出ていた。
この冬の鍋料理は、鮭は高値なのでブリだろうといわれてもいる。
大物のブリは富山へ向かっているというのを漁業関係者から聞いた。
暮れには数千円が数万円になり、富山の市場に出回るかもしれない。
明治の初期、道路が整備されていなかった時代、私たちの地域一体は、マグロ漁が盛んだった。
トラックの走る道路がなかった時代、馬の背にマグロを乗せて、遠くの町まで運んだという。鮮度はずいぶん落ちたに違いない。
それから見ると流通も全国レベルになった。
それにより、大きな儲けをしている人もいるのだろうが、相変わらず生産者の利益は薄いようだ。
そういえば“氷見の鰤”。師走には、10万円を超えるものも出てくると、富山の人から聞いたことがある。
ところが初秋からブリが大漁だ。ブリは出世魚と呼ばれ、大きくなるにつれ、名称が4回ほど変わる。名称は土地によって違うようだ。
最大のもの(10キロ以上)をブリ(鰤)という。
魚に師だから、出世して偉いという意味で、値も張るのだろう。
※前浜の漂着物で作成した鮭。先日釣りのお客様に見せたら、このサイズなら5キロ近い大物だと、結構真剣に見ていた。

先日、私は6キロのものを浜で購入してきた。
6キロというのは相当大きい。イナダというそうだが、マグロのように背丈は短く胴体は太い。
見た目はブリブリしているから、このぐらい大きなものであれば世間一般にはブリと呼ばれてもいいだろう。
スーパーでは切り身になると、ほとんどがブリの名称だ。
1~2キロ程度の切り身でも、ブリと表示しているが、これはいただけない。脂もなく美味しくないからだ。
売る側が意図的におこなっているような気もするが、消費者だってブリと呼ばれる代物ではないのは承知だ。ブリと表示した方が消費者にとっても心地よいからだと思う。正式な表示ではないかもしれないが、値段もそこそこで消費者が納得していれば、誤表示とは言えないのかもしれない。
私の地区ではその程度のサイズは“アオ”と呼んでいる。
全体が青いからそう呼ぶのだろうが、アオでは、身が成熟していないという感じで、いただけない。
大漁で異常に安値のブリ(総称で呼ぶ)だが、行く先はといえば、東京方面や富山県だと聞いている。
築地では北海道のブリが安くて美味しいと、テレビに出ていた。
この冬の鍋料理は、鮭は高値なのでブリだろうといわれてもいる。
大物のブリは富山へ向かっているというのを漁業関係者から聞いた。
暮れには数千円が数万円になり、富山の市場に出回るかもしれない。
明治の初期、道路が整備されていなかった時代、私たちの地域一体は、マグロ漁が盛んだった。
トラックの走る道路がなかった時代、馬の背にマグロを乗せて、遠くの町まで運んだという。鮮度はずいぶん落ちたに違いない。
それから見ると流通も全国レベルになった。
それにより、大きな儲けをしている人もいるのだろうが、相変わらず生産者の利益は薄いようだ。
そういえば“氷見の鰤”。師走には、10万円を超えるものも出てくると、富山の人から聞いたことがある。















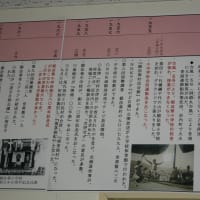




ところでえいこうさんたちが漁に出られる港の景色を一度も見たことがないような気がしますが、今度機会があったら写真を載せてください。