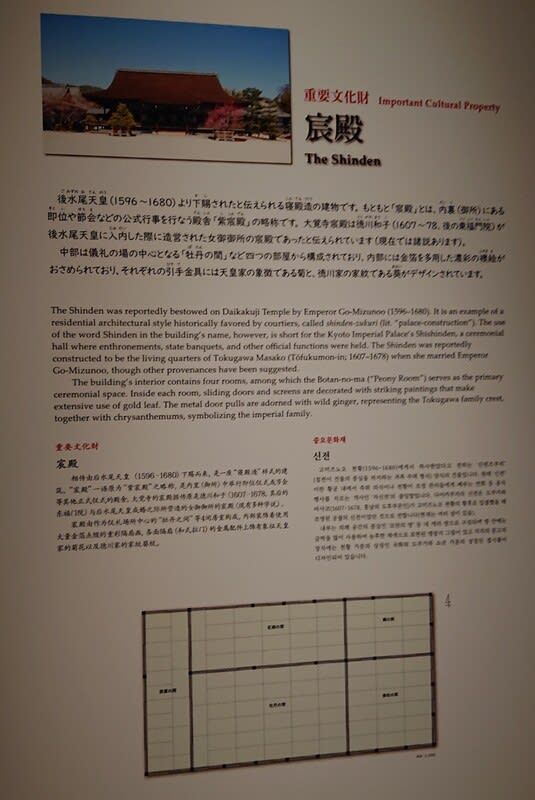谷中など下町情緒満載ですが、必ずしも一般的な想像と異なるかと。
谷中自体はお寺の多い街並みです。
1 黒門の再掲です。日暮里駅近くの夕焼けだんだんの坂に向かうには丁度良い時間だと思い歩きだした。黒門前に停まっている車は中国人送迎の在日中国人が行っている白タクです。税金も払わずタクシーの事業免許も取らずに拡散し始めている悪行です。この運転手とは黒門の写真を撮りたいので、車を前に移動して欲し旨伝えて移動してもらいました。皇居前でも渋谷でも何処でも見かける風景です。甘い日本の警察です。

2 旧東京音楽学校奏楽堂が見えてきました。こちらの奏楽堂については別スレッドでアップします。

3 東博の一部を構成する黒田記念館の一階に上島珈琲店があります。過去に黒田記念館へ訪問したときの記事はこちらです。

4 芸大のアートプラザに入るのも二度目ですが、今回よく理解が出来ました。こちらの人物が誰だか知りませんでした。で、帰宅してから Google レンズで調べて誰だか分かりました。

5 31年在籍の東京美術学校の5代目校長だそうです。
長期に君臨したのですから、政治力に長けていたものと想像できます。

6 大学の理事長や学長などアカデミックな組織ですから、民主的でアカデミックな方法で選出されると一般の方は思っているかも。でも、実際は大違いです。株式会社などならまだ民主的な力がはたらきますが、学校などの組織では民主的な力が働きにくいのです。

7 その藝大のアートプラザです。

8 店内の作品を数点アップします。芸大生や院生の方の作品のようです。値段も付いていますから、販売されているようです。気に入った作品があれば一点購入するのも如何でしょうか。投資としても良いかも。

9

10 販売価格が68000円です。猫好きなら安い買い物かもね。

11 超有名な言問通りに面しているカヤバ珈琲店の道路挟んだ向かいにある吉田屋本店(吉田屋酒店)です。今は店舗ではありません。歴史的建造物として一般公開されています。カヤバさんは満席で入れませんでした。

11-2 こちらがカヤバ珈琲店です。今回は写真を撮りませんでしたが、2018年に撮影していました。その時の外観をアップします。その時の記事はこちらです。

12 斬新ですが、早い話庶民の憩いの場であり社交の場であった銭湯です。今はリノベーションされてギャラリーとなっています。

13

14 谷中墓地内に入り第15代将軍の徳川慶喜の墓地を探していると眼前にスカイツリーが見えました。

15

16

17

18

19 墓地から出て日暮里に向かう途中に在ったお地蔵さんの祠です。願いをお願いしているのか千羽鶴が色褪せていました。

20 天王寺さんだそうです。駅を確認する良い目印になりました。大仏と言う程大きくありませんから丈六さんでしょうか。

21 日暮里の夕焼けだんだんに向いたかったが、歩き疲れと見学疲れで電車に乗って帰りました。

99