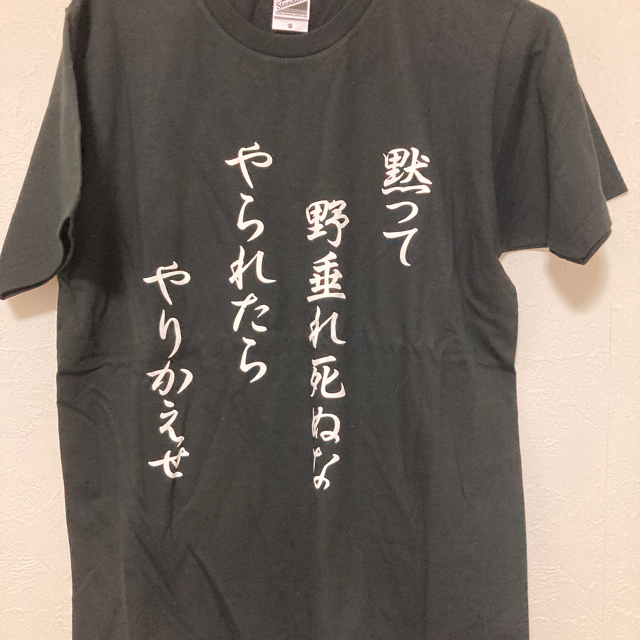| 永遠の0 (講談社文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 講談社 |
百田尚樹の小説「永遠の0」(講談社文庫)を読み終えました。文庫本とは言え、600ページもの大作なので、読み終えるまで大分時間がかかりました。
私がこの本を読むようになったのは、このブログの中で、戦時中の特攻隊員を今のブラック企業の社員になぞらえた事がきっかけでした。「時代背景は違っても、国や企業の為に個人が一方的に犠牲を強いられる構図は何も変わっていない」と私が述べたのに対して、「特攻隊の事を取り上げるなら是非読んで貰いたい」と、ブログ読者の方から勧められたのがこの本でした。
現代のプータローの息子(佐伯健太郎)が、フリーライターの姉の仕事の関係で、特攻隊員として亡くなった自分の最初の祖父(宮部久蔵)の取材をする事になり、伝を頼りに元特攻隊員から次々に話を聞いていく中で、それまで記憶も定かでなかった宮部の生き様が、この本の小説の中で次第に明らかになっていきます。
宮部は、類まれな技量をもつゼロ戦パイロットの下士官でしたが、他の特攻隊員とは違い、ひたすら生き延びようとし、部下にも「絶対に犬死にするな」と指導します。また、米軍機を撃墜した後も、パラシュートで脱出する米兵に機銃掃射を浴びせかけた事もありました。その為に、一部の特攻隊員からは臆病者、卑怯者と罵られました。その一方で、戦闘中に宮部に命を救われたパイロットも多くおり、その人たちからは非常に慕われていました。その宮部が、最後には生き延びるチャンスを自ら放棄し、部下の身代わりとして特攻で死んでいったのです。
その小説の中では、開戦初期のゼロ戦がどんなに優れた戦闘機だったか、機動性(身軽さ)や耐空性(航続距離の長さ)にかけては世界一だった事についても語られていました。この辺については、宮崎駿のアニメ「風立ちぬ」にも詳しく描かれていると思いますが、私はくだんのアニメはまだ見ていないので、ここでは割愛します。その反面、ゼロ戦は、攻撃機としては非常に高性能でしたが、防護機能は貧弱で、後ろから攻撃されたら一たまりもありませんでした。また、当時既に米軍は最新鋭のレーダーを備えていたのに、ゼロ戦の無線は殆ど雑音ばかりで全然役に立たず、それをひたすら現場の精神論・根性論だけでカバーしていたのです。勝ち戦の間はそれでも何とか持っていましたが、やがて負け戦となり根こそぎ動員で軍需工場から熟練工がいなくなると、さしものゼロ戦も次第に粗悪品が目につくようになり、終戦間際にはパワーアップした米軍機にバサバサ撃ち落されるようになります。
そして、当時の特攻作戦や玉砕の醜い面も、包み隠さず語られていました。戦時中の特攻作戦と言えば、とかく無謀さだけが強調されますが、実際はもっと醜いものでした。下っ端の兵隊には玉砕・特攻を強いておきながら、肝心の将校はと言うと、「大和ホテル」と皮肉られるほど優雅に戦艦「大和」の中で高級料理に舌鼓を打ちながら、自分の保身の為には下っ端の兵隊がどれだけ死のうが知ったこっちゃないといわんばかりの、出鱈目な作戦指揮を行っていたのです。緒戦の勝利に奢り高ぶり、米軍を舐めてかかり兵力を出し惜しみし、物量作戦で木端微塵にやられると、今度は勝算のないまま無謀な突撃作戦が繰り返されました。その挙句に、ミッドウェーでもガダルカナルでも敗退を重ね、気が付いた時には沖縄も本土も焼野原となり、原爆まで落とされた末に無条件降伏。その中で、下々の兵隊だけが「お国の為に」と、ろくに食料の補給もされないまま非業の死を遂げていった様子も、非常にリアルに描かれています。
そういう話が次から次へと出てきた後で、最後の舞台装置がまた意表を突くものでした。宮部が最後に特攻出撃する際に、自機のエンジンの不調に気付きながら、その機で出撃しておればエンジントラブルの為に特攻作戦から離脱し喜界島に不時着できる可能性があったのに、わざわざ部下にその戦闘機を譲り、自身は「正常な」戦闘機で米軍の空母に突撃して亡くなりました。その宮部と引き換えに生き延びた部下が、何と今の健太郎の祖父だったのです。今の祖父は、実は母とは血の繋がらない赤の他人だったにも関わらず、肉親以上に母を、そして自分たちを愛してくれていた・・・というのが、この小説のあらすじです。
そういう元特攻隊員の証言の中でも、とりわけ南洋のラバウル航空隊で宮部小隊長の下についた井崎一等飛行兵の話は圧巻でした。末期がんに侵され余命いくばくもない井崎が、病室でインタビューに答える訳ですが、そこに暴走族くずれの井崎の息子も敢えて同席させます。その中で、宮部が父の家業の失敗で借金を抱え、棋士になる夢を断念せざるを得ず、海軍飛行兵の道を選んだのもひたすら生活の為だった事、その中で、ひたすら訓練に励み身体を鍛える中で、やがてベテランパンロットとして頭角を現してきた事、パラシュート脱出した米軍パイロットを撃ち落したのも、再びその米軍が戦場に舞い戻ってくるのを予期しての事、それでも特攻を拒否し、当時血気盛んだった軍国青年の井崎にも、ひたすら生き延びる事の大切さを説き、そのお蔭で何度も命拾いさせられた事・・・。その中で、宮部が井崎と二人きりの時に、「若し戦争が終わり何十年か後に、孫にお爺ちゃんも昔パイロットだったと縁側で話す頃には、日本も平和になっていたら良い」と井崎に話しかけるくだりで、最初はふてくされて渋々聞いていた井崎の孫が、まるで人が変わった様に泣き崩れる場面では、私も思わず泣きそうになりました。
でも、読み終えた後で何か物足りなさが残りました。それは一つには、あんなに特攻を忌み嫌い、部下にも生き延びるように言っていた宮部が、何故最後に自ら死を選んだのか、その理由が最後まで明かされなかったからです。
そして二つ目に、小説ではあんなに戦争の醜さを描いた作者の百田尚樹が、関西ローカルのテレビ番組で右翼色の強い「たかじんのそこまで言って委員会」等で、何故あからさまに憲法改正や軍拡に賛成する発言を繰り返す事が出来るのか。そんなに戦争が醜いのなら、なおさら反戦の立場に立つのが筋なのに。これでは、戦前には戦争熱を煽りながら戦後は一転して反戦平和を説いたマスコミの変節を、小説の中で非難する資格なぞないじゃないか。
その二つがずっと気掛かりでした。この小説も、反戦色を織り交ぜつつも、主人公の宮部を「悲劇のヒーロー」に祭り上げる事で、結局は戦争を美化してしまっているのじゃないかと。本当に戦争に反対ならば、主人公を特攻で死なすような筋書にはしない筈です。とことん生きながらえさせる中で、生きる事の大切さを強調する筈だし、仮に死なすとしても、あんな綺麗に描くのではなく、もっと悲惨な死を強調する筈です。でも、そこまで書いてしまうと身も蓋もなくなり、ドラマにならない(小説として売れない)から、あくまでも主人公だけは「綺麗に」死なせたのかな、という気がします。
そこが放送作家としての百田尚樹の限界ではないでしょうか。幾ら戦争の悲惨や軍部の横暴・腐敗を背景に描いても、単なるヒーロー個人の悲劇物語で終わってしまうと、せっかくの時代背景も悲劇の「引き立て役、刺身のツマ」にしかならず、寧ろ「今の日本の平和も特攻の犠牲があってこそ、それに引き替え今の若者は甘えている、昔の特攻を見習え」というように、批判していた筈の特攻や戦争を逆に美化する事にもなりかねません。
でも、放送作家としては、そういう筋書きの方がドラマとしてヒットする。視聴率も稼げ本も売れる。だから、たとえ小説の中では戦争や特攻を批判しても、テレビに出ると「改憲・軍拡に賛成」なぞという正反対の事も平気で言えるのです。そういう意味では、同じ戦争の悲惨さを描いていても、漫画「はだしのゲン」とは似て非なる作品だと思いました。
 | はだしのゲン 2 |
| クリエーター情報なし | |
| 中央公論新社 |
※後半の結論部分を現行の記述に差し替え、タイトル名も少し変えました。(9月16日19:00)