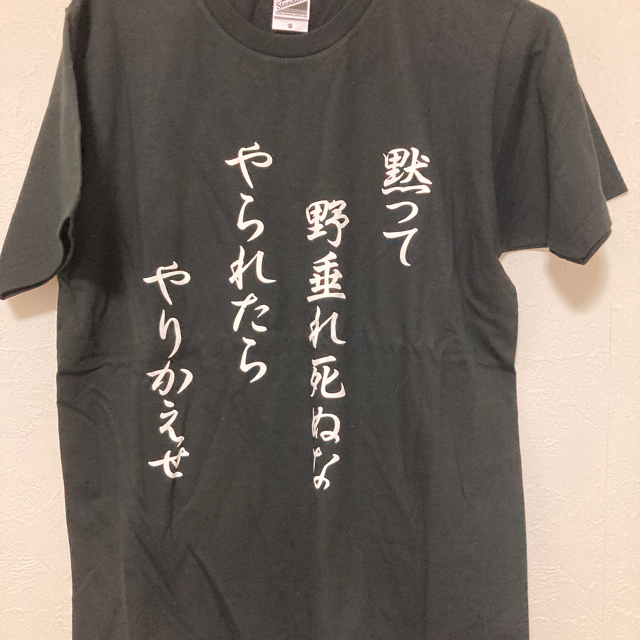| 一週間 de 資本論的場 昭弘日本放送出版協会このアイテムの詳細を見る |
 | 超訳『資本論』 (祥伝社新書 111)的場 昭弘祥伝社このアイテムの詳細を見る |
9月27日(月)から30日(木)まで、夜10時25分から25分間、NHK教育テレビで「一週間de資本論」という番組をやっていたのをご存知でしょうか。あの分厚く超難解なマルクスの名著「資本論」のエッセンスを、一回たった25分×僅か4回の放送で分かりやすく解説してしまおうという、超無謀ともいえる番組です。的場昭弘さんという経済学者が番組案内役を務められ、各回一人づつ登場するゲストとの対話形式で、この本のエッセンスが紹介されていました。
私は、ネット掲示板の告知で、たまたまこの番組の事を知りました。私も最初はこんな地味な番組なぞ観る気がしませんでした。「それでなくても、いつも朝早くから仕事なのに、今さら資本論なんて」と思っていましたから。でも、何か惹かれるものがあり、その第2回目の28日(火)放送分だけは観る事が出来ました。
なかなか良い番組でした。少なくとも、昨今やたら目に付く、民放の視聴率稼ぎ目当ての、派手なだけで中身の全然無いバラエティ番組なんかよりは、よっぽど観る価値のある番組でした。
「資本論」は、資本主義の搾取の仕組みを史上初めて明らかにした書物であるにも関わらず、その内容は非常に難解であり、とても労働者が簡単に読める本ではありません。それは、分量が膨大である上に、「使用価値」「交換価値」「不変資本」「可変資本」「必要労働時間」「剰余労働時間」などの専門用語が頻繁に出てくるからです。それに加えて、19世紀のヨーロッパで書かれた書物なので、当時の経済学者の学説や歌劇の台詞からの引用が多い為に、今の日本人にはあまりにも馴染みがないからです。
しかし、書いている事はしごく正論です。たとえば「交換価値」というのは、平たく言えば商品の価格の事です。それを自動車の例で考えてみましょう。自動車の価格は何で決まりますか。自動車一台当たりの物件費・人件費などの製造コストによって決まります。まかり間違っても、「俺も自動車が欲しい、でも俺は貧乏だから一台千円で売ってくれ」なんて理由で決まったりはしませんよね。だったら、我々も労働力という商品を会社に売って生活しているのだから、食べたり服を買ったり、たまには旅行したりして、その労働力を維持していけるだけの賃金が貰えて当然ではないですか。「俺は貧乏だから一台千円で自動車を売ってくれ」という理屈は通らないのに、何故「うちの会社は貧乏だからこれだけしか払えない」という理屈はすんなり通るのですか?しかし、みんなその事になかなか気がつかないのです。
その騙しのカラクリを、世界で初めて暴いたのがこの本です。しかし、当時はそんな騙しが当たり前のようにまかり通っていたので、その嘘を暴こうにも、なかなか適切な言葉が見つかりませんでした。この本が難解なのには、そういう時代背景もあるのです。今ならもっと適切な訳語に置き換えられている筈です。
私が観た第2回目の内容は、「労働時間の中に潜む搾取のカラクリ」についての話でした。「資本論」のページで言うと、その第1巻の第8章「労働日」に当たります。「労働日」というのは、今でいう「1日の労働時間」の事です。その直ぐ後に出てくる「標準労働日」というのも、同様に「1日の標準労働時間」の事です。今はこれは8時間ですよね。
この様に、この本には鍵となる専門用語が幾つか出てきます。そのキーワードを、今の言葉で置き換えてやれば良いのです。そうしたら書いてある事が徐々に分かってきます。その他の細かな専門用語は、後でゆっくりネットや事典で調べれば良いのです。
それで、その「労働時間」について説明すると、産業革命以前は、押しなべて晴耕雨読というか、労働時間は長くても日の出から日没までで、その中身も至ってのんびりしたものでした。それが、やがて近代ヨーロッパで産業革命が始まり、それが全世界に広まっていくにつれて、働き方も、後のチャップリンの映画「モダンタイムス」に出てくるようなものに急激に変わってきたのです。それもこれも、蒸気機関や電気の発明によって、工場に機械が導入され、24時間稼動が可能になったからです。そうして、産業革命で勃興した資本家が、農民や職人が没落して生まれた大量の労働者を、牛馬のようにこき使うようになりました。
「資本論」には、7歳の子どもを工場に連れて行き、そこで16時間も働かさなければならなかった、貧しい母親の話が出てきます。子どもは機械につきっきりの為、母親が傍について食事をやらなければならなかった。今からみれば立派な児童虐待ですが、当時はこれが当たり前の姿でした。それが今もなお世界中に残っています。一例を挙げれば、FIFAワールドカップで使われるサッカーボールは、今も幾つかの開発途上国で、このような児童労働によって作られています。
>ある大きな鉄道事故によって数百人の乗客が死んだ。鉄道労働者の怠慢が原因である。彼らは陪審員の前でこう弁解する。10年から12年前までの労働日は8時間に過ぎなかったと。最近5、6年の間に、14、18、20時間と引き上げられ、またバカンスの客の多い時などのように、旅好きが押し寄せるときには、休みもなく40~50時間働くことも珍しくはない、と。(「資本論」第1巻・第8章「労働日」・第3節「搾取に対する法的制限のないイギリスの産業における労働日」)
その他にも色々な事象が取り上げられています。上記のくだりなぞ、まるで数年前のJR尼崎事故を予見していたかのような記述です。
>ここで明らかなことは、労働者とは労働力として生命を持つものにすぎないこと。
結果、彼が自由にできる時間は、法的にも、自然的にも、資本とその増殖に属する労働時間だということである。教育のための時間、知的発展のための時間、社会機能を充実させるための時間、友人や両親との関係の時間、肉体や精神を自由に発展させるための時間、日曜の礼拝の時間などは、それを厳守している国においてさえも、まったく無駄な時間ということである。(第8章・第5節「標準労働日のための闘争(1)」)
>今や全体の労働者は、同じ程度の生産的能力を持ち、特殊の労働、特殊の労働グループの中で自らの器官を特殊の機能のために使う点において、その能力をもっとも経済的に使うのである。部分労働者であることの一面性そして不完全性でさえ、全労働者という枠から見れば完全なものなのである。
一面的機能だけを担当するという習慣によって、彼自身はこの機能を自然にそして確実に発揮するだけの一器官になり、メカニズム全体と関連することで、機械の部品のように規則的に動くことを強制されるのである。
(第12章「分業とマニュファクチュア」・第3節「マニュファクチュアの一般的メカニズム、その二つの基本形態」)
これも今の現実に置き換えて考えればすぐに分かります。「労働者とは労働力として生命を持つものにすぎないこと」、つまり、労働者は資本家にとっては単なる「人間機械」「電源を入れなくても勝手に動いてくれる道具」にすぎない、という事です。だから、自分の手足もまるで機械の一部であるかのように、「機械の部品のように規則的に動くことを強制され」、一人の人間が一個のハンディ(バーコード読取端末)の一部と化してしまうのです。



勿論、それに対して当時の労働者も黙ってはいませんでした。すぐに反撃が始まります。それは、最初は「機械打ちこわし運動」という形で始まります。やがて、酷使の原因が機械ではなく社会の仕組みにある事を知り、次第に賃上げや労働時間短縮や参政権を要求するようになります。これが労働運動の始まりです。その中で、労働時間についても、最初は1日10時間、やがて今の8時間の上限規制を要求し始めます。今の1日8時間・週40時間労働制は、当時からの労働者の闘争と犠牲の賜物なのです。
しかし、その歩みは決して一直線ではありませんでした。資本家は、今までのような1日12時間から酷い場合は20時間近くにも及ぶ働かせ方が出来なくなるや否や、今度は時間当たりの労働密度を上げようと画策してきました。ライン・スピードを上げたり、今まで二人でやっていた仕事を一人にやらせたり、昼夜二交代制を導入して機械を休みなしに動かしたりするようになってきます。
場合によっては、今までとは打って変わり、今度は資本家のほうから労働時間の短縮を申し出てくるようになったりもしました。但し、その場合でも、狙いはあくまでも物件費や人件費の削減にあり、決して労働者の健康や福利厚生を慮っての事ではありませんでした。だから、労働時間は多少減っても、仕事は以前よりもはるかにきつくなってきたのです。
>労働の強化の主観的条件―労働日―の短縮が法律で強制されるやいなや、機械は、資本家の手の中でたちまち同じ時間内により多くの労働を搾り取るための客観的な、かつ組織的に応用された手段となる。
これは二重の方法で行われる。つまり機械の速度を高めることと、同じ労働者が監視する機械装置の範囲、すなわち労働者の作業場面の範囲を拡大することによって。
(第13章「機械装置と大工業」・第3節「機械経営が労働者に及ぼす第一次的影響」)
>機械労働は神経系統を極度に疲れさせ、筋肉のいろいろな動きを阻害し、肉体と精神のあらゆる自由な活動を奪う。労働が楽になったということでさえ、機械は労働者に労働を与えないで、労働者の利益を奪ってしまうという点において、一種の拷問となる。(第13章・第4節「工場」)
「機械の速度を高め」、あるいは「労働者の作業場面の範囲を拡大することによって」不断に時間当たりの労働密度が上げられる事で、労働者は逆にますます「神経系統を極度に疲れさせ」られ「筋肉のいろいろな動きを阻害」され、「肉体と精神のあらゆる自由な活動を奪」われていく破目に陥ります。
実際にも、1日12~16時間も働かされれば、人は次第に物を考えられなくなります。目の前しか見えなくなり、自分の事しか考えられなくなります。こうして労働者は社畜にさせられていくのです。現に今の私たちの勤め先の社員がそうじゃないですか。そこまで行くと、もう後は過労死か暴発するかしかありません。だから、そうなる前に立ち上がらないとダメなのです。
また、そうやって労働生産性が上がり、製品や商品の製造単価が下がれば下がるほど、それを口実に労働者の賃金も下げられ、首切りが横行するようになる。それがまた更なるコストダウン・リストラ・不景気を呼び込む事になる。これが、「ネオリベラリズム循環」「悪魔のサイクル」とも呼ばれる、デフレ・スパイラルの「負の連鎖」です。今の牛丼チェーン、ハンバーガー・チェーンの安売り競争や、百均ショップの賑わいも、あくまでもこのような「負の連鎖」の一環として起こっている現象です。その裏には、必ず労働者の賃下げ・長時間労働や下請け・納品業者虐めが潜んでいます。従って、これらの安売り競争も、決して「モノが安くなった、便利になった」と手放しで喜べるものではないのです。


また、これは単に19世紀ヨーロッパだけに限った話ではないという事も、きちんと押さえておく必要があります。この21世紀の日本で今も起こっている事なのです。それは私がいちいち「資本論」から引用しなくても、既に読者の方が一番よくご存知の筈です。しかし、その搾取のカラクリを知らないと、つい目先の安売り競争に目を奪われたり、「俺は12時間以上も働かされているのに、非正規のパート・アルバイトや公務員は何故8時間しか働かなくて良いのか」とか、「俺は12時間も働かされているが、もっと悲惨な飲食チェーンの従業員や、IT土方と呼ばれるSEなんかと比べたら、まだマシだ」という歪んだ方向に、頭がいってしまうのです。
そうは言っても、「マルクスが理想とする社会主義は、ソ連・東欧の崩壊で終わってしまったではないか」「資本論なんてもはや時代遅れだ」と思う人も、なかには居られるかも知れません。しかし、ソ連・東欧などの事態は、出来合いの社会主義の不十分さを示すものではあっても、決して「資本主義の勝利」なんかではありません。今や、当時それを「資本主義の勝利」として礼賛した一人である、フランシス・フクヤマという日系人で保守派の政治学者自身が、「アメリカの終わり」(講談社)という本の中で、その非を認めているのですから。マルクスの「資本論」に書かれている事は、今でも充分通用します。


「資本論」には、この他にも下記のような解説書もあります。それと同時に、一度は原典にも目を通してみる価値はあるでしょう。斯く言う私も、記事冒頭で紹介した的場先生の本と、「資本論の要綱」(国民文庫)しか読んだ事はありませんが。
 | 池上彰の講義の時間 高校生からわかる「資本論」池上 彰集英社このアイテムの詳細を見る |
 | 資本論 1 (岩波文庫 白 125-1)マルクス岩波書店このアイテムの詳細を見る |