今回は、レースの組み合わせ・ローテーション編のお話です。2011年12月11日に掲載した記事を編集しました。
ローテーションでは、すべてのレーンを1レーンずつずれながら走るため、自分の両隣を走る人はずっと変わりません。そのため、自分はソコソコ速いのに、もっと速い人たちとばかり同じレースで走らされて好成績を残せず、自分よりも予選やポイントが低いのに対戦相手に恵まれて好成績を残し、本来なら自分より下位に来るであろう人が、決勝レースに進出したり、自分より総合成績では上位に来てしまうということがあります。
これは、誰が何番目に走るかを、予選・ポイント順に自由に選べることにより、組み合わせに有利・不利が生じるからです。誰が何番目に走るかを、抽選にした場合には、運も実力のうちと考えることもできますが、より実力を反映させたいなら、予選・ポイント順に自動的に走る順番が決まるようにするべきです。
その決め方ですが、トーナメントの場合には、山ごとに上位同士がなるべく最後まで当たらないように振り分けました。つまり、上位同士は、山の中で両端に来るようにするということです。
しかし、トーナメントとローテーションで同じ考え方はできません。トーナメントは線で考えられますが、ローテーションは円状になって行う椅子取りゲームと同じで円で考えなければならないからです。
具体的には、1位と2位を円の対極上(180度反対側)に置きます。次に、3位と4位を1位と2位をつないだ線と十字を切るような線の両側に置きます。つまり、1位から4位までは、1位、3位、2位、4位か、1位、4位、2位、3位と、90度ずつ並ぶわけです。
その次に、5位から8位までをその90度ずつのちょうど半分の45度のところに、近い順位を対角線上に置きます。この際、5位から8位までの両隣の数字を足した数が、なるべく上位に有利になるようにしながら、近くなるように配置します。具体的には、1位、6位、3位、7位、2位、5位、4位、8位、となります。
最後に、9位から16位までをその45度ずつのちょうど半分の22.5度のところに、近い順位を対角線上に置きます。
ここでも、9位から16位までの両隣の数字を足した数が、なるべく上位に有利になるようにしながら、近くなるように配置します。具体的には、1位、11位、6位、14位、3位、10位、7位、15位、2位、12位、5位、13位、4位、9位、8位、16位となります。
なお、16人未満、8人未満の際は、単純に下位を省いていきます。
この組み合わせは、レーン数が4レーンであろうと、6レーンであろうと、8レーンであろうと、適用することができます。どこ(どの4人、どの6人、どの8人)からスタートするかは、1位が決めればいいでしょう。
また、ローテーションは、レーン数の倍以下にしておくのが望ましいと思われます。4レーンなら8人以下、6レーンなら12人以下、8レーンなら16人以下、ということです。
私のスロットカーの記事の索引は、メインサイトのSLOT CARにあります。
ローテーションでは、すべてのレーンを1レーンずつずれながら走るため、自分の両隣を走る人はずっと変わりません。そのため、自分はソコソコ速いのに、もっと速い人たちとばかり同じレースで走らされて好成績を残せず、自分よりも予選やポイントが低いのに対戦相手に恵まれて好成績を残し、本来なら自分より下位に来るであろう人が、決勝レースに進出したり、自分より総合成績では上位に来てしまうということがあります。
これは、誰が何番目に走るかを、予選・ポイント順に自由に選べることにより、組み合わせに有利・不利が生じるからです。誰が何番目に走るかを、抽選にした場合には、運も実力のうちと考えることもできますが、より実力を反映させたいなら、予選・ポイント順に自動的に走る順番が決まるようにするべきです。
その決め方ですが、トーナメントの場合には、山ごとに上位同士がなるべく最後まで当たらないように振り分けました。つまり、上位同士は、山の中で両端に来るようにするということです。
しかし、トーナメントとローテーションで同じ考え方はできません。トーナメントは線で考えられますが、ローテーションは円状になって行う椅子取りゲームと同じで円で考えなければならないからです。
具体的には、1位と2位を円の対極上(180度反対側)に置きます。次に、3位と4位を1位と2位をつないだ線と十字を切るような線の両側に置きます。つまり、1位から4位までは、1位、3位、2位、4位か、1位、4位、2位、3位と、90度ずつ並ぶわけです。
その次に、5位から8位までをその90度ずつのちょうど半分の45度のところに、近い順位を対角線上に置きます。この際、5位から8位までの両隣の数字を足した数が、なるべく上位に有利になるようにしながら、近くなるように配置します。具体的には、1位、6位、3位、7位、2位、5位、4位、8位、となります。
最後に、9位から16位までをその45度ずつのちょうど半分の22.5度のところに、近い順位を対角線上に置きます。
ここでも、9位から16位までの両隣の数字を足した数が、なるべく上位に有利になるようにしながら、近くなるように配置します。具体的には、1位、11位、6位、14位、3位、10位、7位、15位、2位、12位、5位、13位、4位、9位、8位、16位となります。
なお、16人未満、8人未満の際は、単純に下位を省いていきます。
この組み合わせは、レーン数が4レーンであろうと、6レーンであろうと、8レーンであろうと、適用することができます。どこ(どの4人、どの6人、どの8人)からスタートするかは、1位が決めればいいでしょう。
また、ローテーションは、レーン数の倍以下にしておくのが望ましいと思われます。4レーンなら8人以下、6レーンなら12人以下、8レーンなら16人以下、ということです。
私のスロットカーの記事の索引は、メインサイトのSLOT CARにあります。












 次に、16人と32人のトーナメントの実例をご紹介します。
次に、16人と32人のトーナメントの実例をご紹介します。
 電圧は12Vということですが、1/24スケールに適したオーム数のコントローラーを借りて走らせ、スピードにも乗り、キビキビとした走りを楽しむことができました。
電圧は12Vということですが、1/24スケールに適したオーム数のコントローラーを借りて走らせ、スピードにも乗り、キビキビとした走りを楽しむことができました。
 どれも今ひとつ速さがなく、これはというクルマはなかったのですが、小柄なボディやホイールベースの短いクルマの方が向いているはずなので、フォードGTとアウディR8の2台に絞りました。
どれも今ひとつ速さがなく、これはというクルマはなかったのですが、小柄なボディやホイールベースの短いクルマの方が向いているはずなので、フォードGTとアウディR8の2台に絞りました。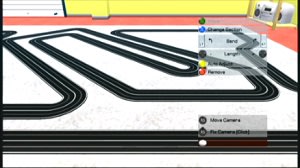
 また、アンロック要素があり、イージーなら1つ、ミディアムなら2つ、ハードなら3つ、アンロックすることができます。
また、アンロック要素があり、イージーなら1つ、ミディアムなら2つ、ハードなら3つ、アンロックすることができます。
 また、「SINGLE PLAYER」には、「CHALLENGE MODE」と「FREE MODE」があり、全部で24のサーキットで走らせることが可能です。
また、「SINGLE PLAYER」には、「CHALLENGE MODE」と「FREE MODE」があり、全部で24のサーキットで走らせることが可能です。


 そんなわけで、NASCAR 2010 CHEVROLET IMPALA #5 MARK MARTINを注文した際に、パーマのRTRであるFLEXI-5 RTR DOME GT-1もセットで注文しました。
そんなわけで、NASCAR 2010 CHEVROLET IMPALA #5 MARK MARTINを注文した際に、パーマのRTRであるFLEXI-5 RTR DOME GT-1もセットで注文しました。
 それでいて、価格は$26.25、そのショップでは$16.95で売られていました。ペイントや接着といった手間がかからないことを考えると、プラモデルよりも価格面では有利です。
それでいて、価格は$26.25、そのショップでは$16.95で売られていました。ペイントや接着といった手間がかからないことを考えると、プラモデルよりも価格面では有利です。