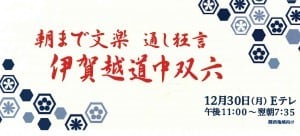国立文楽劇場友の会の催し「第97回文楽のつどい」に行ってまいりました。今回は夏休み特別公演第3部のサマーレイトショー「夏祭浪花鑑」にちなんだ内容でした。↑プログラムです。
最初の「大阪の夏祭り」のお話は、時々意識を失っておりましたが、なかなか面白いお話でした。講師の澤井浩一先生が「大阪市内の夏祭りと言えば、愛染さんに始まり住吉さんで終わる」というフレーズをお使いでしたが、久しぶりに聞きました。先生もおっしゃっていましたが、少し前までは、ローカルニュースなどでよくこのフレーズが使われていましたが、最近はとんと聞きませんね。天神祭りがド派手になりすぎて、他の夏祭りが目立たなくなってきたのでしょうか(←これは私の個人的な意見です)。
澤井先生のお話で大阪府指定有形民俗文化財の「だいがく」というものの存在を初めて知りました。漢字で書くと台額、台楽となるそうです。

写真は、大阪市西成区玉出にある生根神社に唯一残っている「だいがく」です(Wikiの写真です)。秋田の竿灯のような、祇園祭の鉾のような形です。これが「夏祭浪花鑑」の中に登場するそうです。浄瑠璃丸本には「祇園囃子の太鼓鉦」としか記されてないそうですが、演出で、背景の町屋の屋根の上にだいがく、地車囃子が登場しています。文楽を見始めてようやく1年が経とうかというワタクシですので、「夏祭浪花鑑」はもちろん未見、ただ歌舞伎のほうでは何度か見ていますが、背景のところまでは気がつきませんでした。このお話の後、公演記録映像上映で「夏祭浪花鑑長町裏の段」の上映があり、それを見ていたら、確かにこの「だいがく」ありました。
その公演記録映像は昭和60年の文楽公演のもので、人形役割は団七を吉田玉男さん、義平次を吉田文雀さんでした。吉田玉男さんは初めてでした。簑助さん

と名コンビだったんですよね。私はひそかに文楽の孝玉コンビ

コンビと思っていましたが、でも、よく考えると玉男さんと簑助さん

のほうがずっと年上なんですよね。失礼を申し上げました。
「夏祭」ですが、義平次の人形を見たとき、「あ、笹野高史さんと違うわ」って瞬間的に思ってしまいました。それぐらい、歌舞伎の「夏祭」は中村屋さんの印象が強いんでしょうね。ただ、秀太郎さんによれば、中村屋さんの「夏祭」は上方歌舞伎ではないそうです。今度10月に松竹座で愛之助さんが座頭の歌舞伎公演があって「夏祭」が出るみたいですが、それにはわざわざ「上方演出による通し狂言」と注意書き?がつけてあるので、それはきっと秀太郎さんこだわりの「夏祭」になるんでしょうね。ってことはより文楽に近くなるんでしょうか。文楽の「夏祭」は2回見る予定なので、がんばって見ておきたいと思います。
話がそれました。文楽の「夏祭」は夏にしかかからないそうです。その点、歌舞伎は“自由”というか、季節関係なくいろいろな演目がかかります。いいのか、悪いのか、よくわかりませんが…。夏公演は、人形の主遣いさんたちは皆さん白い着付け(麻?)になるそうです。ご本人たちが暑いのもありますが、お客さんから見ても暑苦しいからという理由があるみたいです。この白い着付けは夏公演のみだそうで、9月に東京公演がありますが、そちらは黒紋付に戻ります。司会の方が「白いお召し物を拝見できるのは大阪だけなんですよね。東京にはないんですよね」と強調されていましたが、それで喜ぶって、私はちょっとさびしいものを感じてしまいました。
映像鑑賞の後は玉女さんが実際に団七の人形を持ってきて実演してくださいました。団七の人形は刺青の肉襦袢を着せるそうで、その上に着物を着せます。内側の肉襦袢がふわふわして遣いづらいとおっしゃっていました。左遣いさんと足遣いさんも登場して、実際に団七を遣ってくださいましたが、義平次にいたぶられる場面はじっと我慢をして、腰を低くしてその後を大きく動くというのを見せてくださいました。まだお稽古中だそうで、イキが合わない場面があったのはご愛嬌、こういう催しならではでした。












 です。豪華な段でございますね。
です。豪華な段でございますね。