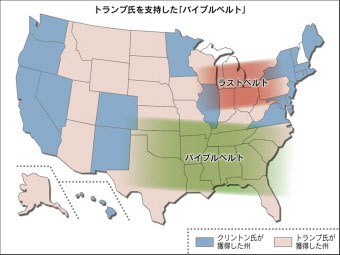映画『スノーデン』(2)―自由(Liberty)のための孤独な闘い―
前回の映画『スノーデン』(1)に続いて、今回は映画とは別に、スノーデンが受けた二つのインタビューを紹介します。
現在、日本では、かつての「共謀罪」の焼き直しともいえる「テロ等準備罪」について政府が国会に法案を提出しようとしています。
これには、電話の盗聴や電子メールメールなど、あらゆる通信を傍受することを可能にする危険性が含まれています。
この法案はまさに、スノーデンがアメリカ国家と闘った、国家による個人の監視、そのもので、私たち日本の問題でもあります。
最初は、映画『スンーデン』にも登場する、香港での最初のインタビュー、『ザ・ガーディアン紙』のグレン・グリーンウォルド氏
との香港でのインタビュー(2013年6月11日)から、重要なポイントを引用します(注1)。
この内容は、映画と重なる部分も多いし、前回の(1)でも紹介しているので、ここでは映画では取り上げられなかった彼の証言を
引用しようと思います。
彼が、国家の最高機密情報を海外に持ち出し、いくつかのメディアにその情報を渡した動機についてスノーデンは、「唯一の動機は、
国民の名において、国民(の利益)に反することを政府がやっていることを、国民に知らせることです」、と語っています。
彼は、年報2000万円以上をもらいハワイの家でガールフレンドとの非常に快適な生活を全て犠牲にしてまでもこのような行動を
とったのは、
私は良心から、アメリカ政府が、秘密裏に世界中に構築した大規模な監視システムを使って、(私たちの)プライバシー、
インターネットの自由(freedom)と基本的な自由(liberties)とを破壊することを許しておくことができないからです。
オバマ政権が、内部告発者を、歴史上例のないほど訴追していることをみると、オバマは彼(スンーデン)をあらゆる手段
を講じて罰しようとしていた。
それでも、“私は恐れない。なぜなら、これは私が決断したことなのだから”と静かに語りました。
しかし、彼は決して最初からアメリカ政府の方針に反対していたわけではなかった。それどころか、
私は人間として、人々を抑圧から解放することを助ける義務があると感じ、イラクでの戦闘に加わりたかった。
実際、彼はイラクでの特殊部隊に加わりましたが、訓練中に足を骨折し、イラクへは行きませんでした。
その後彼は、CIA、NSA(国家安全保障局)などで情報担当の職員として働くことになったのですが、そこで大いに失望します。
彼がスイスのジュネーブでCIA要因として働いていた時、銀行の秘密情報を得るために次のような謀略により目的を達したことを
明らかにしています。
CIAの秘密工作員は、ある銀行家を意図的に酔わせた上で家まで運転するように仕向けました。彼が飲酒運転で逮捕されると、こ
の工作員は友情の印に彼を助け、それによってこの銀行家を情報提供者として取り込むことに成功した。
これに関してスノーデンは、
私がジュネーブで見た多くのことは、我々の政府が何をしているのか、世界でどんな影響をもっているかについて、本当に
幻滅した。私がしていることは、善よりも害をなすことに加担していることを痛感した。
とも語っています。
CIAからNSA(国家安全保障局)に移ってからの3年間、スノーデンは、NSAが、いかに、あらゆる活動を監視しいているか
を知ることになります。
彼ら(NSA局員)は全ての会話や行動を彼らの世界に取り込むことに熱中している。
スノーデンは、彼の基本的な姿勢を、
私はプライバシーがなく、したがって知的な探求も創造性への余地がない世界に住もうとは思わない
と語っています。
なぜ、そのようなことになったのかと言えば、政府が、本来その権限を与えられていない権力を自らに付与してしまった。つまり、
個人のプライバシーを侵害する権限は、政府にはなかったのに、政府は勝手にその権限を自分たちに与えてしまったからだ。
しかも、そこには政府が誰を、どのように関しているのかについて、国民の監視は及ばない公の監視はない、とスノーデンはイン
タビュアーのグリーンウォルド氏んい語っています。
そして彼は、プライバシーの大切さ、それがいかに情報工作員の行動によって着実に侵害されてきたかについて、非常に情熱的に
語ったという。
次に、テレビ局としては初めてNBCのB・ウィリアムスとのインタビューでスノーデンが語った内容をみてみよう(注2)
スノーデンの政府の対する深刻な疑念は、9・11事件にたいする政府の対応が一つにきっかけになっています。
政府は、その国民的トラウマを逆手にとったとでもいいましょうか。・・・・
合衆国憲法が保障する国民の自由やプラバシーの権利を脅かす情報収集プログラムを正当化しているのです。これは、極
めて不誠実なことではないでしょうか。
これにたいしてインタビュアーのウィリアムスは、
しかし、アメリカは攻撃を受けたのです。9・11によってパールハーバー並の危機に陥ったのです。なぜ、敵を一掃す
るために、広くいきわたる網をかけてはならないのですか?・・・後ろめたいことがない国民は何も困ることはないので
はないですか?
と誰もが言いそうな疑問をスノーデンにぶつけます。
スノーデンは、通常、国家は国防を最優先することを認めますが、
しかし、私は、アメリカは、その様な国家であるべきではないし、なるべきではないと考えるのです。もし私たちが自由
を望むのなら、国民は政府の監視の対象になってはならないのです。プライバシーや国民の権利を放棄してはならないの
です。和足たち国民が国家を成り立たせているのですから。
ここには、スノーデンの、個人のプライバシーと自由にたいする徹底した信念が見られます。
この時、ウィリアムスが一定のセキュリティーのかかった携帯を見せ、NSAはこの携帯にどのように関与できるのかという問い
を投げかけました。
スノーデンによると、アメリカのみならず、ロシアでも中国でも、それだけ資金力と技術を持った国の諜報機関であれば、電源が入
った瞬間に、その形態を「所有」すること、またそこからデータを入手したら、写真を撮ったりするだけでなく、外部操作によって
電源をコントロールすることも可能だと言う。
ウィリアムスが食い下がって、聞きます。
たとえば私がこの携帯で昨日の大リーグの試合結果をチェックしたなどという情報を、いったい誰が何のやくにたてるとい
うのですか?
スノーデンは答えます。
政府やハッカーたちにとって、それらは極めて重要な情報なのです。その情報はあなたという人物について多くのことを教
えてくれます。あなたが英語を話すこと、おそらくアメリカ人であること、スポーツに関心をもっていること、大リーグの
試合結果をチェックした時どこにいたか、出先だったか、自宅だったかなどをしることができます。
こうした情報は、ある人が何時に起き、どこにゆき、誰と会っているか、という日常の行動パターンを教えてくれるし、そ
の人がどんな活動をしているかも教えてくれるし、これは誤解や何らかの被害をもたらす可能性さえある。
問題はこうした監視が、何のコントロールもなく政府によって行われていることにスノーデンは強い危機感を抱いています。
しかも、外面的な行動パターンだけでなく、個人の思考経路まで入り込むことができる、という驚くべき事実も指摘しています。
NSAの諜報員たちは、特定の個人のパソコンに入り込み、その人が考えを活 字にしていく様子をリアルタイムで観察する
ことができます。つまり、その人がある文字を入力し、しばしば止まって考え、バックスペースで消去し、修正して再入力す
るようなプロセスの一部始終を手に取るようにみることができます。・・・
人の思考プロセスそのものをモニタリングできるというのは、信じがたい個人領域への侵害だと言わざるを得ません。
NBCは、スノーデン事件とは何であったかを次のように総括します。
突き詰めていけば、スノーデン事件は、アメリカにおける「国家権力」と「自由=Liberty」との闘いである。ここでいう自由
とは、(一般的な自由を意味する)Freedom ではなくLiberty、すなわち、国家権力による監視や圧力や差別からの解放とい
う自由である。
アメリカにおける自由への強い信念、時には自分の生活や命さえも犠牲にして守ろうとするスノーデンの孤独な闘いに大きな希望を感じ
ました。
一方、日本ではどんな個人の監視が行われているのでしょうか? そして監視への抵抗が行われるのでしょうか?不安になりました。
(注1)https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance
このインタビューの内容は、https://genius.com/Edward-snowden-interview-on-nsa-whistleblowing-full-transcript-annotated1deo でもみることができます。
(注2)Wisdom Begins in Wonder, http://ocean-love.seesaa.net/article/399559864.html。このインタビュー は、2014年5月28日 “Inside Mind of Edward Snoden”というタイトルの番組として放送された。
大木昌のtwitter https://twitter.com/oki50093319
-----------------------------------------------
3月3日 地元のサイクリングロード沿いの河津桜(千本桜)は満開でした。

前回の映画『スノーデン』(1)に続いて、今回は映画とは別に、スノーデンが受けた二つのインタビューを紹介します。
現在、日本では、かつての「共謀罪」の焼き直しともいえる「テロ等準備罪」について政府が国会に法案を提出しようとしています。
これには、電話の盗聴や電子メールメールなど、あらゆる通信を傍受することを可能にする危険性が含まれています。
この法案はまさに、スノーデンがアメリカ国家と闘った、国家による個人の監視、そのもので、私たち日本の問題でもあります。
最初は、映画『スンーデン』にも登場する、香港での最初のインタビュー、『ザ・ガーディアン紙』のグレン・グリーンウォルド氏
との香港でのインタビュー(2013年6月11日)から、重要なポイントを引用します(注1)。
この内容は、映画と重なる部分も多いし、前回の(1)でも紹介しているので、ここでは映画では取り上げられなかった彼の証言を
引用しようと思います。
彼が、国家の最高機密情報を海外に持ち出し、いくつかのメディアにその情報を渡した動機についてスノーデンは、「唯一の動機は、
国民の名において、国民(の利益)に反することを政府がやっていることを、国民に知らせることです」、と語っています。
彼は、年報2000万円以上をもらいハワイの家でガールフレンドとの非常に快適な生活を全て犠牲にしてまでもこのような行動を
とったのは、
私は良心から、アメリカ政府が、秘密裏に世界中に構築した大規模な監視システムを使って、(私たちの)プライバシー、
インターネットの自由(freedom)と基本的な自由(liberties)とを破壊することを許しておくことができないからです。
オバマ政権が、内部告発者を、歴史上例のないほど訴追していることをみると、オバマは彼(スンーデン)をあらゆる手段
を講じて罰しようとしていた。
それでも、“私は恐れない。なぜなら、これは私が決断したことなのだから”と静かに語りました。
しかし、彼は決して最初からアメリカ政府の方針に反対していたわけではなかった。それどころか、
私は人間として、人々を抑圧から解放することを助ける義務があると感じ、イラクでの戦闘に加わりたかった。
実際、彼はイラクでの特殊部隊に加わりましたが、訓練中に足を骨折し、イラクへは行きませんでした。
その後彼は、CIA、NSA(国家安全保障局)などで情報担当の職員として働くことになったのですが、そこで大いに失望します。
彼がスイスのジュネーブでCIA要因として働いていた時、銀行の秘密情報を得るために次のような謀略により目的を達したことを
明らかにしています。
CIAの秘密工作員は、ある銀行家を意図的に酔わせた上で家まで運転するように仕向けました。彼が飲酒運転で逮捕されると、こ
の工作員は友情の印に彼を助け、それによってこの銀行家を情報提供者として取り込むことに成功した。
これに関してスノーデンは、
私がジュネーブで見た多くのことは、我々の政府が何をしているのか、世界でどんな影響をもっているかについて、本当に
幻滅した。私がしていることは、善よりも害をなすことに加担していることを痛感した。
とも語っています。
CIAからNSA(国家安全保障局)に移ってからの3年間、スノーデンは、NSAが、いかに、あらゆる活動を監視しいているか
を知ることになります。
彼ら(NSA局員)は全ての会話や行動を彼らの世界に取り込むことに熱中している。
スノーデンは、彼の基本的な姿勢を、
私はプライバシーがなく、したがって知的な探求も創造性への余地がない世界に住もうとは思わない
と語っています。
なぜ、そのようなことになったのかと言えば、政府が、本来その権限を与えられていない権力を自らに付与してしまった。つまり、
個人のプライバシーを侵害する権限は、政府にはなかったのに、政府は勝手にその権限を自分たちに与えてしまったからだ。
しかも、そこには政府が誰を、どのように関しているのかについて、国民の監視は及ばない公の監視はない、とスノーデンはイン
タビュアーのグリーンウォルド氏んい語っています。
そして彼は、プライバシーの大切さ、それがいかに情報工作員の行動によって着実に侵害されてきたかについて、非常に情熱的に
語ったという。
次に、テレビ局としては初めてNBCのB・ウィリアムスとのインタビューでスノーデンが語った内容をみてみよう(注2)
スノーデンの政府の対する深刻な疑念は、9・11事件にたいする政府の対応が一つにきっかけになっています。
政府は、その国民的トラウマを逆手にとったとでもいいましょうか。・・・・
合衆国憲法が保障する国民の自由やプラバシーの権利を脅かす情報収集プログラムを正当化しているのです。これは、極
めて不誠実なことではないでしょうか。
これにたいしてインタビュアーのウィリアムスは、
しかし、アメリカは攻撃を受けたのです。9・11によってパールハーバー並の危機に陥ったのです。なぜ、敵を一掃す
るために、広くいきわたる網をかけてはならないのですか?・・・後ろめたいことがない国民は何も困ることはないので
はないですか?
と誰もが言いそうな疑問をスノーデンにぶつけます。
スノーデンは、通常、国家は国防を最優先することを認めますが、
しかし、私は、アメリカは、その様な国家であるべきではないし、なるべきではないと考えるのです。もし私たちが自由
を望むのなら、国民は政府の監視の対象になってはならないのです。プライバシーや国民の権利を放棄してはならないの
です。和足たち国民が国家を成り立たせているのですから。
ここには、スノーデンの、個人のプライバシーと自由にたいする徹底した信念が見られます。
この時、ウィリアムスが一定のセキュリティーのかかった携帯を見せ、NSAはこの携帯にどのように関与できるのかという問い
を投げかけました。
スノーデンによると、アメリカのみならず、ロシアでも中国でも、それだけ資金力と技術を持った国の諜報機関であれば、電源が入
った瞬間に、その形態を「所有」すること、またそこからデータを入手したら、写真を撮ったりするだけでなく、外部操作によって
電源をコントロールすることも可能だと言う。
ウィリアムスが食い下がって、聞きます。
たとえば私がこの携帯で昨日の大リーグの試合結果をチェックしたなどという情報を、いったい誰が何のやくにたてるとい
うのですか?
スノーデンは答えます。
政府やハッカーたちにとって、それらは極めて重要な情報なのです。その情報はあなたという人物について多くのことを教
えてくれます。あなたが英語を話すこと、おそらくアメリカ人であること、スポーツに関心をもっていること、大リーグの
試合結果をチェックした時どこにいたか、出先だったか、自宅だったかなどをしることができます。
こうした情報は、ある人が何時に起き、どこにゆき、誰と会っているか、という日常の行動パターンを教えてくれるし、そ
の人がどんな活動をしているかも教えてくれるし、これは誤解や何らかの被害をもたらす可能性さえある。
問題はこうした監視が、何のコントロールもなく政府によって行われていることにスノーデンは強い危機感を抱いています。
しかも、外面的な行動パターンだけでなく、個人の思考経路まで入り込むことができる、という驚くべき事実も指摘しています。
NSAの諜報員たちは、特定の個人のパソコンに入り込み、その人が考えを活 字にしていく様子をリアルタイムで観察する
ことができます。つまり、その人がある文字を入力し、しばしば止まって考え、バックスペースで消去し、修正して再入力す
るようなプロセスの一部始終を手に取るようにみることができます。・・・
人の思考プロセスそのものをモニタリングできるというのは、信じがたい個人領域への侵害だと言わざるを得ません。
NBCは、スノーデン事件とは何であったかを次のように総括します。
突き詰めていけば、スノーデン事件は、アメリカにおける「国家権力」と「自由=Liberty」との闘いである。ここでいう自由
とは、(一般的な自由を意味する)Freedom ではなくLiberty、すなわち、国家権力による監視や圧力や差別からの解放とい
う自由である。
アメリカにおける自由への強い信念、時には自分の生活や命さえも犠牲にして守ろうとするスノーデンの孤独な闘いに大きな希望を感じ
ました。
一方、日本ではどんな個人の監視が行われているのでしょうか? そして監視への抵抗が行われるのでしょうか?不安になりました。
(注1)https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance
このインタビューの内容は、https://genius.com/Edward-snowden-interview-on-nsa-whistleblowing-full-transcript-annotated1deo でもみることができます。
(注2)Wisdom Begins in Wonder, http://ocean-love.seesaa.net/article/399559864.html。このインタビュー は、2014年5月28日 “Inside Mind of Edward Snoden”というタイトルの番組として放送された。
大木昌のtwitter https://twitter.com/oki50093319
-----------------------------------------------
3月3日 地元のサイクリングロード沿いの河津桜(千本桜)は満開でした。