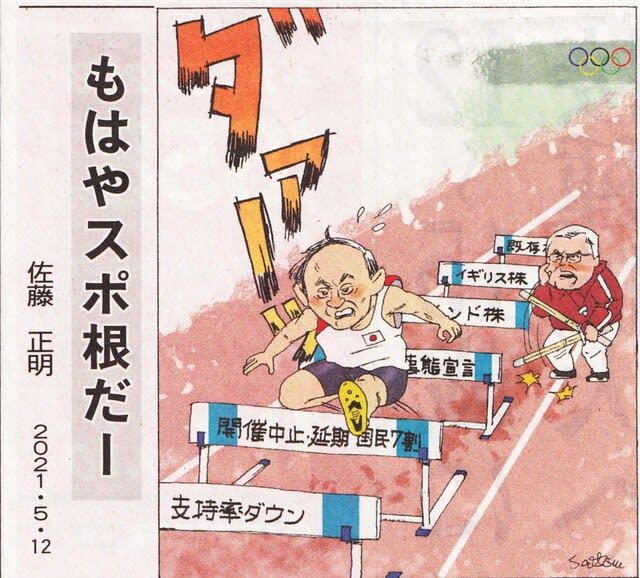イチロー野球殿堂入りの陰で
2025年1月21日、アメリカのプロ野球団体『メジャーリーグ・ベースボール』(MLB)
はイチロー・スズキの殿堂入りが決定してしたことを発表しました。
これに関連して、BSTBSでは特別番組『密着!イチロー 米国野球殿堂入りSP』
(2025年3月8日放送)という2時間番組を制作しました。
私はこのブログでも以前、数回にわたってイチローについて書いてきましたが、今回は
「米国野球殿堂入り」をテーマにした番組で、これまでのイチローの歩みと現在のイチ
ローの姿を見ることができるのではないか、と楽しみにしていました。
また、私がこれまでイチローについて書いたのは主に、彼がシアトル・マリナーズに入
団した2001年から5~6年間の野球選手としての活躍が中心で、彼の私生活や内面の精
神性などはほとんど知りませんでした。今回の密着取材では、それらが語られるのでは
ないか、との期待もありました。
入団当時、アメリカのプロ野球界で打者として評価されていたのは、パワフルなホーム
ランを多く打つ選手でした。
ところがイチローは、コツコツとヒットを打ち、塁に出れば全力で盗塁し、守備につけ
ば「レーザー・ビーム」(2001年4月11日)と命名された素晴らしい送球でランナーを
アウトにするなど、それまでのアメリカの「ベースボール」のヒーローとは全く異なる
プレー・スタイルでファンを魅了しました。
また、平凡なゴロでも、彼なら俊足を飛ばしてセーフにしてしまうのではないか、とい
う期待とスリルを観客にあたえました。
こうした一見地味なプレー・スタイルは日本の「野球」なら当たり前ですが、当時のア
メリカでは、ちょこまかとした野球は「スモール・ベースボール」と呼ばれ、評価され
ませんでした。
しかしアメリカの野球ファンは次第に、イチローの一つ一つのプレーに、これまで忘れ
ていたスリルや面白さを再発見し、そのことが徐々に「ベースボール」に大きな変化を
もたらしたのです。
日本は「ベースボール」というアメリカ生まれのスポーツ文化を輸入し、日本人の感性
で「再解釈」して「野球」というスポーツ文化を作り上げました。
イチローは、日本育ちの「野球」(スモール・ベースボール)の最良の部分の体現者で
あり、彼がアメリカの「ベースボール」にそれを持ち込んで、やがて後者を変えてし
まった「革命家」なのです。
以上は、現役時代の野球選手としてのイチローにたいする私の個人的な評価ですが、彼
は自分自身の内面的な部分や私生活などについて多くを語りませんでした。
イチローは2001年にマリナーズに入団、その後ヤンキース、マーリンズと移籍し1918
年に再びマリナーズに戻ってきました。
そして19年目に突入した2019年3月21日、東京ドームでのアスレチックス戦を最後
に、45歳で現役を引退しました。日本で9年、アメリカで19年の選手生活でした。
殿堂入りが決まった今年1月21日前後の6日間にわたる密着取材で、イチローは入団から
殿堂入りの決定までの選手生活や私生活を振り返って語りました。以下は、その中で私に
とって特に印象深かった話を紹介します。
2001年に日本人の野手として初めてメジャーリーグに挑戦した当初、“そもそもアメリカ
で通用するのかって(言われたけど―筆者注)。通用するのかってどういうことだよって、
僕からすれば失礼な評判から始まった”、と当時の評価にたいして憤りを感じていました。
公式戦が始まる前のキャンプのスタート、スプリングトレーニングのゲームが始まったこ
ろには”日本に帰れ”と毎日言われた、と告白しています。
ところが、この年の4月11日に見せた、レーザービーム送球で、彼の名は一気に全国レベ
ルに高まりました。
それでも、彼に対して蔑むような態度を見せるファンもたくさんいました。レーザービー
ムの背後では身の危険を感じることが起きていたのです。
オークランドファンが、僕に向けてコインをばんばん投げつけてくるんですよ。
その一つが僕の頭に当たって、これはシャレにならない。もし目に当たったら
シャレにならない。帽子のつばをここまで(目の位置まで)下げて絶対に目に
当たらないようにしました。
(なぜ観客はコインを投げたんですか、との質問に)“お前は何者なんだ、という冷やか
しですよ”。おそらく、本心は、「冷やかし」ではなく見下した「蔑み」と言いたかったと
思われます。
マリナーズ専属アナウンサー、リック・リズ氏によれば、(日本からきて8試合目)それ
までイチローのことを誰も知らなかったが、レーザービーム送球以後「彼は野球界で最も
偉大な選手であることを世界に示した」とコメントしています。そして、以後。コインも
投げられなくなったという。
そして1年目のシーズンが終わってみるとマリナーズは116勝して久しぶりに地区優勝
しました。イチローはそのことを一応「形になった」と表現しました。
すると世間の評価は手のひら返しでイチローをヒーロー扱いし始めました。“人の評価なん
てこんなに変わるんだ、第三者の評価,人からの評価は当てにならないものなんだ、幻想
に近い“と、当時の心境を語っています。
しかし、イチローは2006年に大きな選択に迫られました。彼は全国レベルの選手になった
が、2006年にはその心が乱される状況に直面していたのです。
この年、シーズン途中にもかかわらずマリナーズは8月に11連敗を喫し自力優勝が消えて
しまいました。チームメートは誰も意気消沈していました。“チームが結束していく時って、
ネガティブなことで結束していくことが多いんですよ。ダメなチームって”。
そんな中で彼はひたすらヒットを打ち続けますが、そのことで彼はチームメートから離れ
てしまい、孤独に悩んでいました。
そこに巻き込まれたくない。だから僕は外れるんですね、そこから。その中で
200本、3割、僕が続けてきたことを続けたいし、チームが希望を失っている
時にお客さんに喜んでもらえるとしたら、個人パフォーマンスじゃないですか。
いいプレーで。野球ファンですから、来ている人たちって、基本的には。グラウ
ンド上ではしっかり仕事をするっていうのがプロだと思っている。
まさに、イチローのプロ魂そのものです。
こうした状況で、2007年には日本に戻ろうかと思ったこともあったという。その時、想像
していた日本の球団は巨人だったようです。
しかし、彼は“そこを踏みとどまった”のです。記者から、でもメジャーに残ったのはなぜ、
と問われて、
そこで逃げたら負けだと思ったからです。結論的にはそうです。悩みましたけどね。
それを止めてくれたのも妻だったんですよね。あまりにもそれはもったいない。「大
変だろうけど、もう少し踏ん張ってみてはどうか」という助言をもらいました。
時間が経った時に。5年10年経った時にどうかって想像したときに。じゃ、日本に
戻ります。瞬間的にはおそらく盛り上がってくれる。じゃ、翌年、3年、4年、続き
ますか。確かにそれは難しいという想像もしました。その熱量は続かないです。それ
も大きかったです。冷静に考えると、瞬間的なものだなって。もう一度アメリカに戻る
ことは極めて困難なことになるだろうなと。
帰国を止め、コツコツと自分のやるべきことをやる。こうした積み重ねの結果が、米国野球殿
堂入りへと繋がって行きました。ここで「殿堂入り」がいかにすごいことなのかを見ておきまし
ょう。
まず、対象となる候補者は10年以上メジャーリーグでプレーし、引退から5年以上経過した
時に初めて候補者の資格が与えられます。そして、投票権をもった約400人の記者の75%以
上の票を獲得した人物が殿堂入りとなります。
75%というのは、とてつもなく大きな数字で、日本人では野茂英雄 1.1%、松井秀喜0.9%
でした。しかも、5%以下で資格を失ってしまい、5%以上を得ていても10年以内に殿堂入り
を果たさなければ資格を失います。
殿堂入りとはこれほど高い壁があるのにイチローは資格を得た1年目に99.7%を獲得しまし
た。これは史上3番目の高さです。
イチローが現役時代に築き上げた数々の記録もさることながら、私は投票した記者の頭の中には、
アメリカの「ベースボール」に日本的な「野球」を持ち込んで、「ベースボール」の魅力を高めて
くれた、という点を高く評価していたのではないかと思います。
殿堂入りに関して、人びとの関心は“果たしてイチローは満票で選ばれるか否か”、でした。フタを
開けてみると、記者の中の一人だけイチローに投票しなかった、つまり満票ではなかったことが
明らかになしました。
アメリカのメディアでは、イチローに投票しなかった記者(誰であるかは不明)にたいする批判が
噴出しました。冒頭で触れた番組はこれに“ただ一人イチローを除いて”と注釈しています。
イチローはこの点に関して
面白いなと思ったのは、みんな満票の方が良かったと思っている。じゃ、どっちが僕にと
ってこれからの将来に、どちらが考えさせられる数字だったかと考えると、断然1票足り
ない方が良いわけですよ。もし満票だったら、「いやぁすごいね」、以上。だと思うんです。
1票足りなかったというのは、不完全であるから進める頑張れる。ストーリーができるの
はすごくいいと思うし、満票ではそれができないわけですよ。
(満票だったら)「これまでやってきたことがアメリカでも認められて本当に良かった、以
上」なんですよね。そういうストーリーがあるのが僕好きなんで。メッセージ性を考えて
も2票(足りなかった)だと悔しい、3票だと悔しい。それなら満票の方が良かった。で
も1票足りなかったのは一番良かったと思いますね。
この発言は、1票足りなかったことに対する恨みつらみを言っているのではありません。そうでは
なくて、ここにはイチローの人生観というか価値観がはっきり表れています。
つまり、不完全な部分があるからこそ、それを埋めるという目標ができ、それに向かって努力する
という「ストーリー」(物語)が生まれる、というのです。
同様のことは、
注意しなきゃいけないのは、周りがそうやって持ち上げる。それで僕が気分良くなってい
たら僕は終わるので、そこは要注意。今回、特にそう思いました。
と語っています。これは、人々の称賛に浮かれていると、足元をすくわれてしまうぞ、というイチ
ローらしい謙虚さの表れであり、また“戒め”でもあります。
ところで、殿堂入りの電話を受けた自宅でのインタビューで、これまで多くを語らなかった弓子夫
人への感謝と思いを語りました。
2001年間から19年間の現役生活と6年目が今ですけど、妻がよく頑張ってくれた事。こ
こにまず大きな感謝の気持。僕はコツコツとヒットを重ねる選手、いろんなことをコツコ
ツとやってきたけど最後こんなとこまで来られるんだ。
少し補足すると、コツコツとやってこれたのも、その積み重ねが殿堂入りという高みに登ることが
できたのも彼女が支えてくれたから、という感謝の気持を言いたかったのでしょう。続いて彼は
“妻の喜んでいる姿は僕の喜びでもある”、とその場に同席していた弓子夫人の前で語りました。
同席したインタビューアーが、”一緒に戦って勝ち得たという感覚は強いですか?“ との問いに、
もちろん。ずっと一緒にやってきたわけですから。いろいろありましたからね。
アメリカにポスティング・システムで挑戦しようという時、近くにいる人たちも誰も応
援してくれてないわけじゃないけど、“行っておいでよっていうスタンスの人たちもほと
んどいなかったので、そんななかで(弓子さんが)”私はもうイチローが下した決断。そ
れについていく」って言ってくれたから。それがなかったら、そもそも始まっていなか
った。
これらの言葉から、日比生生活においても、重要な決断に際しても、イチローにとって弓子夫人
の存在が非常に大きかったことが分かります。
そして、一見クールなイチローと弓子夫人との信頼関係と暖かな夫婦関係が垣間見えて、私はと
ても心温まる思いをしました。
2025年1月21日、アメリカのプロ野球団体『メジャーリーグ・ベースボール』(MLB)
はイチロー・スズキの殿堂入りが決定してしたことを発表しました。
これに関連して、BSTBSでは特別番組『密着!イチロー 米国野球殿堂入りSP』
(2025年3月8日放送)という2時間番組を制作しました。
私はこのブログでも以前、数回にわたってイチローについて書いてきましたが、今回は
「米国野球殿堂入り」をテーマにした番組で、これまでのイチローの歩みと現在のイチ
ローの姿を見ることができるのではないか、と楽しみにしていました。
また、私がこれまでイチローについて書いたのは主に、彼がシアトル・マリナーズに入
団した2001年から5~6年間の野球選手としての活躍が中心で、彼の私生活や内面の精
神性などはほとんど知りませんでした。今回の密着取材では、それらが語られるのでは
ないか、との期待もありました。
入団当時、アメリカのプロ野球界で打者として評価されていたのは、パワフルなホーム
ランを多く打つ選手でした。
ところがイチローは、コツコツとヒットを打ち、塁に出れば全力で盗塁し、守備につけ
ば「レーザー・ビーム」(2001年4月11日)と命名された素晴らしい送球でランナーを
アウトにするなど、それまでのアメリカの「ベースボール」のヒーローとは全く異なる
プレー・スタイルでファンを魅了しました。
また、平凡なゴロでも、彼なら俊足を飛ばしてセーフにしてしまうのではないか、とい
う期待とスリルを観客にあたえました。
こうした一見地味なプレー・スタイルは日本の「野球」なら当たり前ですが、当時のア
メリカでは、ちょこまかとした野球は「スモール・ベースボール」と呼ばれ、評価され
ませんでした。
しかしアメリカの野球ファンは次第に、イチローの一つ一つのプレーに、これまで忘れ
ていたスリルや面白さを再発見し、そのことが徐々に「ベースボール」に大きな変化を
もたらしたのです。
日本は「ベースボール」というアメリカ生まれのスポーツ文化を輸入し、日本人の感性
で「再解釈」して「野球」というスポーツ文化を作り上げました。
イチローは、日本育ちの「野球」(スモール・ベースボール)の最良の部分の体現者で
あり、彼がアメリカの「ベースボール」にそれを持ち込んで、やがて後者を変えてし
まった「革命家」なのです。
以上は、現役時代の野球選手としてのイチローにたいする私の個人的な評価ですが、彼
は自分自身の内面的な部分や私生活などについて多くを語りませんでした。
イチローは2001年にマリナーズに入団、その後ヤンキース、マーリンズと移籍し1918
年に再びマリナーズに戻ってきました。
そして19年目に突入した2019年3月21日、東京ドームでのアスレチックス戦を最後
に、45歳で現役を引退しました。日本で9年、アメリカで19年の選手生活でした。
殿堂入りが決まった今年1月21日前後の6日間にわたる密着取材で、イチローは入団から
殿堂入りの決定までの選手生活や私生活を振り返って語りました。以下は、その中で私に
とって特に印象深かった話を紹介します。
2001年に日本人の野手として初めてメジャーリーグに挑戦した当初、“そもそもアメリカ
で通用するのかって(言われたけど―筆者注)。通用するのかってどういうことだよって、
僕からすれば失礼な評判から始まった”、と当時の評価にたいして憤りを感じていました。
公式戦が始まる前のキャンプのスタート、スプリングトレーニングのゲームが始まったこ
ろには”日本に帰れ”と毎日言われた、と告白しています。
ところが、この年の4月11日に見せた、レーザービーム送球で、彼の名は一気に全国レベ
ルに高まりました。
それでも、彼に対して蔑むような態度を見せるファンもたくさんいました。レーザービー
ムの背後では身の危険を感じることが起きていたのです。
オークランドファンが、僕に向けてコインをばんばん投げつけてくるんですよ。
その一つが僕の頭に当たって、これはシャレにならない。もし目に当たったら
シャレにならない。帽子のつばをここまで(目の位置まで)下げて絶対に目に
当たらないようにしました。
(なぜ観客はコインを投げたんですか、との質問に)“お前は何者なんだ、という冷やか
しですよ”。おそらく、本心は、「冷やかし」ではなく見下した「蔑み」と言いたかったと
思われます。
マリナーズ専属アナウンサー、リック・リズ氏によれば、(日本からきて8試合目)それ
までイチローのことを誰も知らなかったが、レーザービーム送球以後「彼は野球界で最も
偉大な選手であることを世界に示した」とコメントしています。そして、以後。コインも
投げられなくなったという。
そして1年目のシーズンが終わってみるとマリナーズは116勝して久しぶりに地区優勝
しました。イチローはそのことを一応「形になった」と表現しました。
すると世間の評価は手のひら返しでイチローをヒーロー扱いし始めました。“人の評価なん
てこんなに変わるんだ、第三者の評価,人からの評価は当てにならないものなんだ、幻想
に近い“と、当時の心境を語っています。
しかし、イチローは2006年に大きな選択に迫られました。彼は全国レベルの選手になった
が、2006年にはその心が乱される状況に直面していたのです。
この年、シーズン途中にもかかわらずマリナーズは8月に11連敗を喫し自力優勝が消えて
しまいました。チームメートは誰も意気消沈していました。“チームが結束していく時って、
ネガティブなことで結束していくことが多いんですよ。ダメなチームって”。
そんな中で彼はひたすらヒットを打ち続けますが、そのことで彼はチームメートから離れ
てしまい、孤独に悩んでいました。
そこに巻き込まれたくない。だから僕は外れるんですね、そこから。その中で
200本、3割、僕が続けてきたことを続けたいし、チームが希望を失っている
時にお客さんに喜んでもらえるとしたら、個人パフォーマンスじゃないですか。
いいプレーで。野球ファンですから、来ている人たちって、基本的には。グラウ
ンド上ではしっかり仕事をするっていうのがプロだと思っている。
まさに、イチローのプロ魂そのものです。
こうした状況で、2007年には日本に戻ろうかと思ったこともあったという。その時、想像
していた日本の球団は巨人だったようです。
しかし、彼は“そこを踏みとどまった”のです。記者から、でもメジャーに残ったのはなぜ、
と問われて、
そこで逃げたら負けだと思ったからです。結論的にはそうです。悩みましたけどね。
それを止めてくれたのも妻だったんですよね。あまりにもそれはもったいない。「大
変だろうけど、もう少し踏ん張ってみてはどうか」という助言をもらいました。
時間が経った時に。5年10年経った時にどうかって想像したときに。じゃ、日本に
戻ります。瞬間的にはおそらく盛り上がってくれる。じゃ、翌年、3年、4年、続き
ますか。確かにそれは難しいという想像もしました。その熱量は続かないです。それ
も大きかったです。冷静に考えると、瞬間的なものだなって。もう一度アメリカに戻る
ことは極めて困難なことになるだろうなと。
帰国を止め、コツコツと自分のやるべきことをやる。こうした積み重ねの結果が、米国野球殿
堂入りへと繋がって行きました。ここで「殿堂入り」がいかにすごいことなのかを見ておきまし
ょう。
まず、対象となる候補者は10年以上メジャーリーグでプレーし、引退から5年以上経過した
時に初めて候補者の資格が与えられます。そして、投票権をもった約400人の記者の75%以
上の票を獲得した人物が殿堂入りとなります。
75%というのは、とてつもなく大きな数字で、日本人では野茂英雄 1.1%、松井秀喜0.9%
でした。しかも、5%以下で資格を失ってしまい、5%以上を得ていても10年以内に殿堂入り
を果たさなければ資格を失います。
殿堂入りとはこれほど高い壁があるのにイチローは資格を得た1年目に99.7%を獲得しまし
た。これは史上3番目の高さです。
イチローが現役時代に築き上げた数々の記録もさることながら、私は投票した記者の頭の中には、
アメリカの「ベースボール」に日本的な「野球」を持ち込んで、「ベースボール」の魅力を高めて
くれた、という点を高く評価していたのではないかと思います。
殿堂入りに関して、人びとの関心は“果たしてイチローは満票で選ばれるか否か”、でした。フタを
開けてみると、記者の中の一人だけイチローに投票しなかった、つまり満票ではなかったことが
明らかになしました。
アメリカのメディアでは、イチローに投票しなかった記者(誰であるかは不明)にたいする批判が
噴出しました。冒頭で触れた番組はこれに“ただ一人イチローを除いて”と注釈しています。
イチローはこの点に関して
面白いなと思ったのは、みんな満票の方が良かったと思っている。じゃ、どっちが僕にと
ってこれからの将来に、どちらが考えさせられる数字だったかと考えると、断然1票足り
ない方が良いわけですよ。もし満票だったら、「いやぁすごいね」、以上。だと思うんです。
1票足りなかったというのは、不完全であるから進める頑張れる。ストーリーができるの
はすごくいいと思うし、満票ではそれができないわけですよ。
(満票だったら)「これまでやってきたことがアメリカでも認められて本当に良かった、以
上」なんですよね。そういうストーリーがあるのが僕好きなんで。メッセージ性を考えて
も2票(足りなかった)だと悔しい、3票だと悔しい。それなら満票の方が良かった。で
も1票足りなかったのは一番良かったと思いますね。
この発言は、1票足りなかったことに対する恨みつらみを言っているのではありません。そうでは
なくて、ここにはイチローの人生観というか価値観がはっきり表れています。
つまり、不完全な部分があるからこそ、それを埋めるという目標ができ、それに向かって努力する
という「ストーリー」(物語)が生まれる、というのです。
同様のことは、
注意しなきゃいけないのは、周りがそうやって持ち上げる。それで僕が気分良くなってい
たら僕は終わるので、そこは要注意。今回、特にそう思いました。
と語っています。これは、人々の称賛に浮かれていると、足元をすくわれてしまうぞ、というイチ
ローらしい謙虚さの表れであり、また“戒め”でもあります。
ところで、殿堂入りの電話を受けた自宅でのインタビューで、これまで多くを語らなかった弓子夫
人への感謝と思いを語りました。
2001年間から19年間の現役生活と6年目が今ですけど、妻がよく頑張ってくれた事。こ
こにまず大きな感謝の気持。僕はコツコツとヒットを重ねる選手、いろんなことをコツコ
ツとやってきたけど最後こんなとこまで来られるんだ。
少し補足すると、コツコツとやってこれたのも、その積み重ねが殿堂入りという高みに登ることが
できたのも彼女が支えてくれたから、という感謝の気持を言いたかったのでしょう。続いて彼は
“妻の喜んでいる姿は僕の喜びでもある”、とその場に同席していた弓子夫人の前で語りました。
同席したインタビューアーが、”一緒に戦って勝ち得たという感覚は強いですか?“ との問いに、
もちろん。ずっと一緒にやってきたわけですから。いろいろありましたからね。
アメリカにポスティング・システムで挑戦しようという時、近くにいる人たちも誰も応
援してくれてないわけじゃないけど、“行っておいでよっていうスタンスの人たちもほと
んどいなかったので、そんななかで(弓子さんが)”私はもうイチローが下した決断。そ
れについていく」って言ってくれたから。それがなかったら、そもそも始まっていなか
った。
これらの言葉から、日比生生活においても、重要な決断に際しても、イチローにとって弓子夫人
の存在が非常に大きかったことが分かります。
そして、一見クールなイチローと弓子夫人との信頼関係と暖かな夫婦関係が垣間見えて、私はと
ても心温まる思いをしました。