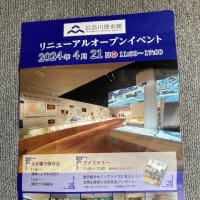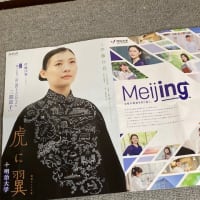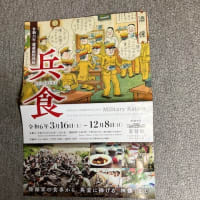昭和の60年代に開館し、先月20日にリニュ-アルした品川区立品川歴史館へ再度訪問した。ここは漬物のタクワン漬の名称となった、品川東海寺のある区域の歴史館で東海寺の資料も多い。改修以前に訪問した時は図書室はカギがかかり、節電で電気も消されていて、誰も利用する人がいないと感じて、本を読んだこともある。リニュ-アル後ひと月経ったので様子見の訪問をしてみた。
訪問者は数名で図書室は1名だけで、ゆっくり静けさを楽しむ。どこの図書館でも地域の資料の所は貴重書があって、地域の宝が眠っている。自分の中では地域の霊安室と思っていて、いつも幽霊と付き合っている気分がする。ここには忘れ去られた人たち、今は知られているが50年100年過ぎると、評価の基準も変わり、記憶から消える。
品川歴史館では沢庵の本を探した。開館初期には結構東海寺の関連のイベントがあったようだが最近は鉄道開業と品川宿の方が多いと感じる。
品川歴史館紀要を読み、今まで知らなかった京都と江戸幕府の対立の間に沢庵が京都・朝廷側についていて、その対立を煽った行為を沢庵がしていた。その行為は今でも諺に残っていて(三日坊主)という言葉の始まりという。これは沢庵が住職に任じ、三日で辞退し、次の住持への道を開けた。この住持の任命権が幕府の政策に反抗するものだった。住持の任命には多額の費用が掛かり、それが寺院経営を潤している様に幕府は見ていた。これが紫衣事件の根本でもある。ここから沢庵の苦闘が始まる。茶道の千宗旦、幕府大目付の柳生宗矩との京都大徳寺での修行仲間から来る江戸時代の諸制度の設定が理解できる。
朝廷と幕府の間で、紫衣事件の赦免後に沢庵が鎌倉へ行き、建長寺等の寺院の荒廃を見て、幕府の支援が無いと、平和な国になると寺院が衰退することを知ったようだ。
沢庵の人生は評価が時代によって変わり、さらに小説家によって、正確でもなく、間違いでもなく、新規の評伝が出来る。そんな資料が見つかり、家に帰って古書店のサイトで、歴史館で見た紀要を購入決断をした。しかしネットでの決済制度が最近変わり、二段認証と言うことで1000円程度の決済でも、認証コードが二重に必要となったようで、まだ決済できない。思わぬ壁にぶつかった。いつもはス-パ-でカ-ド決済で5000円以上も自動決済なのに、古書の決済で1000円で、スマホに認証コ-ドを送信し、パソコンにも認証コ-ドが要求されている。もうあきらめてもう一度品川歴史館で今は読むことを考えている。
訪問者は数名で図書室は1名だけで、ゆっくり静けさを楽しむ。どこの図書館でも地域の資料の所は貴重書があって、地域の宝が眠っている。自分の中では地域の霊安室と思っていて、いつも幽霊と付き合っている気分がする。ここには忘れ去られた人たち、今は知られているが50年100年過ぎると、評価の基準も変わり、記憶から消える。
品川歴史館では沢庵の本を探した。開館初期には結構東海寺の関連のイベントがあったようだが最近は鉄道開業と品川宿の方が多いと感じる。
品川歴史館紀要を読み、今まで知らなかった京都と江戸幕府の対立の間に沢庵が京都・朝廷側についていて、その対立を煽った行為を沢庵がしていた。その行為は今でも諺に残っていて(三日坊主)という言葉の始まりという。これは沢庵が住職に任じ、三日で辞退し、次の住持への道を開けた。この住持の任命権が幕府の政策に反抗するものだった。住持の任命には多額の費用が掛かり、それが寺院経営を潤している様に幕府は見ていた。これが紫衣事件の根本でもある。ここから沢庵の苦闘が始まる。茶道の千宗旦、幕府大目付の柳生宗矩との京都大徳寺での修行仲間から来る江戸時代の諸制度の設定が理解できる。
朝廷と幕府の間で、紫衣事件の赦免後に沢庵が鎌倉へ行き、建長寺等の寺院の荒廃を見て、幕府の支援が無いと、平和な国になると寺院が衰退することを知ったようだ。
沢庵の人生は評価が時代によって変わり、さらに小説家によって、正確でもなく、間違いでもなく、新規の評伝が出来る。そんな資料が見つかり、家に帰って古書店のサイトで、歴史館で見た紀要を購入決断をした。しかしネットでの決済制度が最近変わり、二段認証と言うことで1000円程度の決済でも、認証コードが二重に必要となったようで、まだ決済できない。思わぬ壁にぶつかった。いつもはス-パ-でカ-ド決済で5000円以上も自動決済なのに、古書の決済で1000円で、スマホに認証コ-ドを送信し、パソコンにも認証コ-ドが要求されている。もうあきらめてもう一度品川歴史館で今は読むことを考えている。