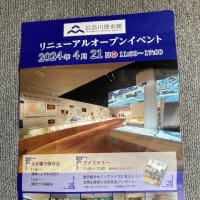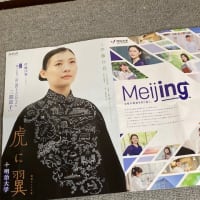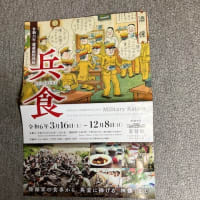図書館で資料確認をしたところ貸し出しされていた。東洋文庫・小野蘭山著(本草綱目啓蒙)この様な本を借り出し読んでいる人がいることに驚く。
在庫している図書館での様子はかなり古い本なのに中を触ると新刊のような感じがする。年に一度程度借り出されているのだろうか。
小野蘭山は江戸時代の本草学者で本草のことを知るには必要な本と思える。ただ自分はナタマメしか興味がないので他の部分はパラパラ読み。
刃豆 なたまめ たちはき(四国・九州)たてはき(土州)
(一名)葛豆 衢州府志 〖衢州市(くしゅう-し)は中華人民共和国浙江省に位置する地級市。地理 浙江省の西部に位置し、杭州市、金華市、麗水市、安徽省、江西省、福建省に接する。〗
莢豆 泉州府志〘中国福建省南部の港湾都市。台湾海峡に臨み、唐・宋時代から南海貿易の拠点として発展。〗
刃鋏荳 郷談正音
葉は豇豆(ささげのこと)より大きい、花も又大きくて紫色。莢(さや)の形は長大にて菜の刀のようである。未熟のものは莢を連ねて煮て食べる。
汝南圃史に(汝南とは中華人民共和国河南省の駐馬店市に位置する。)
普通豆類はその種を食する。ただ豇豆(ささげ)は連なっている莢(さや)食す、而ち刃豆の味は全部莢にあるという。熟すれば豆が成長すると八九分淡い虹色に光って見える。白い花の一種のものは豆もまた白い。白なた豆と呼ぶ。
小野蘭山の本でも刀豆の薬としての効能書きが無いと感じる。用途は何だろうか。