およそ一国の政治には二つの重要事項が常にある。一つは「国民の生活を守る」という重要事項、そしてもう一つは諸外国との外交政策と「安全保障政策」という重要事項。現代日本の「国民生活を守る」という政治的課題として、最大の問題は働く人たちの約半数近くの2100万人にものぼる非正規雇用者の存在をどう解決していくのかという重要事項。そして、二つ目の「安全保障政策」は最近では特に「対中国問題」だ。それに関連しての「米中関係」。
菅義偉政権が発足した9月中旬から2カ月あまりが経過した。この間、アメリカ大統領選挙が行われバイデン候補が勝利し、次期大統領となることがほぼ決まってきた。朝日新聞の11月2日朝刊に「菅義偉首相とは何者か―権力への強い信奉"政策は人に聞く"」(編集委員 秋山訓子)との見出し記事が掲載された。「たたき上げ首相に 強烈な自負がうかがわれる まめさが身上」「権力への確固たる信奉と、それによる人事の差配。むやみに力を振るえばあやうさも」「引け目や気後れもある。それをバネに"人に聞く"流儀を確立。相談相手を周囲に」というようなことが書かれていた。
「政策の議論になると勝てない」とつぶやいたこともある菅首相。「政策をきれいに語るのは苦手でも、いろいろな意見を聞いて判断し、実行までできるのは自分だからこそ」との自負は強くあるとされる。「だが半面では、国家間やビジョンがないと指摘されている。場当たり的な対応に終始しないか、という懸念だ。たとえば、不妊治療の保険適用は、苦しむ人々を救済する。それは大切なことだ。しかし一方で、少子高齢化の構造的な問題、子どもを生み育てることが困難な社会になっているのはなぜかという根本的な問いかけに目をそらすことにならないだろうか。菅首相が日本学術会議の問題で繰り返す"総合的・俯瞰的"な視点は、自身に対してなのかもしれない。」と記事は指摘する。
菅政権が発足して主なブレーンが発表された。「成長戦略会議」と「内閣官房参与」のメンバーたちだ。特に「成長戦略会議」のメンバー(11人)がその中核を担う。そして、そのメンバーの中心的人物が二人いる。一人は竹中平蔵、もう一人はデービット・アトキンソン(英国人)。アトキンソンはゴールドマン・サックス出身で2011年から国宝などの修復を手掛ける「小西美術工藝社」社長を務めている。『日本人の勝算』『日本企業の勝算』なども著書もあり、日本の中小企業再編を持論とする。つまり、中小企業の倒産・淘汰により企業再編を推進すべきという持論だ。
そして、特に竹中平蔵は、菅首相から「師」と仰がれる特別な存在だ。彼は、諸規制緩和「新自由主義」の旗振り役で、2000年に発足した小泉政権下で総務相を務め、「非正規雇用」をその後大量に生み出した人物。この二人が、「国民生活・経済」分野での最重要ブレーン(参謀)。
三浦瑠偉(国際政治学者)なども成長戦略会議のメンバーの一人となっている。女性ブレーンを一人は置くという"華をそえる"という意味合いもあるかと思うが、それなりに国際政治や外交分野で見識のある人ではある。最近、『政治を選ぶ力』という対談書籍を「日本維新の会」の橋下徹と共に出している。菅首相はこの維新の会とも蜜月の関係だ。
『週刊文春』の10月15日号に、「菅"恐怖人事"と5人の怪ブレーン」と題された見出し記事が掲載された。①「外すのは当然だろう―菅官房長時代の"腹案"実行」(杉田官房副長官)、②「ワクチン、不妊治療を牛耳る」(不倫関係にあるとされる和泉補佐官と大坪審議官)、③「年金や生活保護は不要に―経済ブレーン」(竹中平蔵)、④「英国人・観光ブレーン、日光東照宮修繕でブーイング」(アトキンソン)、⑤「サシで面会―外交ブレーンは幸福実現党の顧問だった」(渡瀬裕哉)。
『文藝春秋』11月号には、竹中平蔵「東京を政府直轄地にせよ―菅政権ブレーン提言」との見出し記事。「フェアーな競争を」「教育にも競争を」の言葉なども並ぶ。著者名には「東洋大学教授・慶応大学名誉教授 竹中平蔵」とある。「国民の生き血を吸う」会社の会長名などの政商部分は表に出さず国民を欺いている。橋下徹「日本に必要なのは新陳代謝―縦割り打破はコロナ対策から―古い既得権益層は退場していただこう」の見出し記事も。
竹中平蔵と維新の立役者・橋本徹は、「同じ穴の狢(むじな)」で、改革の名のもとに国民の格差、分断を進める時代の狢でもある。橋下は典型的なポピュリズム政治家。思考が同じ「自助」論者だと思う。橋下は最近、毎日テレビの朝のモーニングショー(報道)のレギュラーコメンテーターを務め始めている。
『週刊ポスト』10月16・23日合併号には「年金消滅!―健康保険も失業保険も廃止になる!」、11月6・13日合併号には「定年崩壊―70歳就業法施行でサラリーマンの人生設計が変わる!」「大倒産時代に備えよう」などの特集記事が掲載されていた。来年の4月に施行予定の「70歳就業法」と年金支給開始の70歳開始、菅首相の政策ブレーン竹中平蔵の言い出した「国民1人に7万円配り、年金を廃止するというベーシックインカム構想の企み‥。菅政権の「自助」「デジタル化」「行革」の先にあるもの‥を」俯瞰した記事。これらの政策化は竹中平蔵やアトキンソンの政策進言によるものだ。
※日本の4大週刊誌『ポスト』『現代』『文春』『新潮』、この中で『週刊現代』は、政権批判は一切行わず、なさけないが「老後生活や健康問題の記事内容ばかりの"体(てい)たらく"な編集方針」に1~2年ほど前から変貌している。おそらく、この編集方針を良しとせず、多くの編集者や記者が退社しているかと推測される。
日刊紙(夕刊紙)はコンビニに置かれているが、『夕刊(日刊)フジ』『夕刊(日刊)ゲンダイ』は、以前の競輪・競馬・プロ野球・エロサイトの編集方針から様変わりし、ちょっとドギツイ大げさ観はあるものの、現代日本の「警鐘を鳴らす"社会の木鐸(ぼくたく)"」的な記事をメインとする編集方針となっている。
竹中平蔵という人物について書かれた『竹中平蔵 市場と権利―"改革"に憑かれた経済学者の肖像』(講談社文庫)2013年初版・佐々木実著。「日本で最も危険な男の物語—"改革"の名の下、法律を駆使しながら、社会を次々と大胆に改造してしまう。まるで政商のように利にさとく、革新官僚のごとく政治家を操る経済学者―。"フェイク(偽物)"の時代に先駆けた"革命家"の等身大の姿とは」「この国を超格差社会に変えてしまったのはこの男だった!経済学者、大学教授、国会議員、企業経営者の顔を使い分け、"日本の構造改革"を20年にわたり推し進めてきた"剛腕"竹中平蔵。猛烈な野心と虚実相半ばする人生を徹底した取材で描き切る、大宅壮一ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞ダブル受賞の評伝。」と裏表紙などにこの書籍が紹介されている。
竹中平蔵は和歌山県和歌山市に1951年に生まれた。現在69歳。履物屋の次男で、家は比較的裕福な家庭だった。和歌山県立桐蔭高校に入学、高校時代の一時期「民主青年同盟(民青―日本共産党系)」に加入したが1年ほどでやめている。近代経済学(近経)の国立・一橋大学経済学部に入学。マンドリン部に所属。大学卒業後、日本開発銀行に入社。その後、銀行に所属しながらハーバード大学に客員研究員として留学。留学後は銀行から大蔵省への出向。この時の部下に高橋洋一(菅政権のブレーンの一人・テレビなどにコメンテーターとして最近はよく出演している)がいる。
1987年、大阪大学助教授となる。その後、ハーバード大学客員准教授。そして慶応大学の教授となる。1998年の小淵内閣から政権のブレーンの一人となる。2001年の小泉政権下から中心的なブレーンとなり、2004年に参議院議員(比例区)に初当選。小泉内閣の「総務大臣(相)」「IT担当大臣」などを歴任。20年間にわたって自民党政権下のブレーン。菅義偉は竹中が総務相時代の副総務相(大臣)。これが菅の初めての閣僚入りだった。「竹中さんのおかげで大臣になれた」と竹中に感謝し続けているし、「竹中を師と仰いでいる」特別な関係と言われる。
竹中平蔵がかって『東洋経済』のインタビューに、「(若い人に)一つだけ言いたいことは、みなさんは貧しくなる自由があります。何もしたくないのなら、何もしなくても大いに結構。その代わりに貧しくなるので、貧しさをエンジョイしたらいいです。ただ一つ、その時には、頑張って成功した人の足を引っ張っぱらないでほしいことです。」と発言している。これは、今の竹中平蔵の考え方を示す典型的な考え・言葉なのだろうかと思う。
その竹中平蔵、「パソナグループ」(大手・人材派遣会社)の取締役会長をしている。非正規労働者を蔓延させ、そして、自分は非正規人材派遣会社を創立して、莫大な財を成している。「国民の生き血を吸いつ続けている」学者・政商だ。他に、オリックス生命の社外取締役などなど、10余りの民間会社のさまざまな役職にある。さらに、慶応大学教授退任後、東洋大学の教授や関西大学の客員教授なども兼務している。オリックス生命は、関西国際空港の民営化や水道民営化事業に参画してきている。これらも竹中の政策との関連・パイプが大きい。竹中平蔵は都心のタワーマンションを3戸分所有し暮らす。
菅義偉は首相としての初めての所信表明演説で、「自助・共助・公助」政策を表明。まずは「自助」(自分でなんとかしろ)である。次に「共助」(親族や仲間からの相互支援を)である。今の日本社会、親戚の共同体意識がほとんど無くなっている中での「共助」はほぼ難しい。そして、最後に「公助」。できる範囲でしてあげましょうという感じだが、期待しないでくださいねという感じでもある。竹中平蔵を師と仰ぐ菅義偉の面目躍進の所信表明演説だった。
『文藝春秋』12月号に、「亡国の改革至上主義—菅総理よ、"改革"を売り物にするなかれ」(藤原正彦)という見出しの文が掲載されていた。「新自由主義にもとづく、国家観なき構造改革は、日本をさらに分断させる。日本社会には効率より大切なものがある」とサブテーマが。
◆政治の重点政策「①「国民の生活・経済」、②「外交・安全保障」。②については、安倍政権を引き継いでいるが、私は菅政権の政策は基本的に一定の評価はしている。しかし、①に関しては「亡民のシナリオ」をしていると思う。菅政権への支持率は発足当時65~75%(各種調査)、そして、政権推移後の11月上旬の支持率は減少はしてきているものの56%~66%(各種調査)と高い水準を維持している。菅首相とは何者なのか、どのように国を、国民を導こうとしているのかをもっと国民は知る必要があるように思うが‥。
11月1日(日)、大阪都構想の是非を問う選挙が大阪市で行われた。今回の選挙は、コロナ問題で大阪府民の大きな人気をとりつけた維新の吉村知事の存在や公明党の支持を取り付けるという背景下の選挙だったために圧勝が予測もされていた。しかし、選挙結果は「反対50.63%、賛成49.37%」という僅差で、維新の会が敗北をした。
菅政権と維新の会は蜜月関係で菅政権の強力な支持・援護政治組織だったため、菅政権にも大きなダメージとなった。この予想外の選挙結果の原因について、さまざまな論評がなされてきているが、私が思うに、要は、「国民生活への大きな不安」が大きく影響していたかと思う。つまり、維新の会は国民・府民・市民の生活・暮らしを守るのではないと思われ始めたからではないかと思う。つまり維新の化けの皮が少しはがれ始めてきているからだと思う。
しかしそれでも、半数は維新をいまだ支持しているという選挙結果でもある。「維新と吉本が日本をだめにする」と、以前にブログで書いたことがあるが、「竹中と維新と吉本が日本をダメにする」という現状だろうか。(※吉本の自称芸人たちは日本のテレビ番組に多く出演し[バカ番組―特に午後7時〜9時の時間帯はオンパレード]、日本人を痴呆化している。)













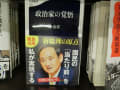



















































※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます