
ウクライナにあるスキタイ人の石像
明日香村の猿石とそっくり
明日香村の猿石とそっくり

スキタイ人はソグド人と同じ遊牧民ですが、ソグド人は交易の民でスキタイ人は騎馬遊牧民。また、ソグド人はソグディアナ(現ウズベキスタンとタジキスタンの一部)を中心として中央~東アジア、スキタイは現ウクライナを中心とした西アジアが勢力範囲だったようで、スキタイ人=ソグド人ではありません(両者とも同じコーカソイドでアーリア人=インド・ヨーロッパ語族ですが)。活躍した時代も若干差があり、スキタイは8B.C.~3B.C.なのに対しソグド人は4B.C.あたりから活発に活動してきたそうです。
ウクライナの遺跡には、このような人型石像が点在してあり、その下は墓になっていたそうです。とすると石像は埋葬された人の生前の姿を模した物なのでしょうか?この本を読んだ上では、何ともわからないようです。しかし、スキタイ人の石像とそっくりな明日香村の猿石は、古代日本の飛鳥時代にスキタイ人が来ていた(もしかしたら埋葬された?)証拠なのではないでしょうか。ウクライナからシベリアの辺りまで、スキタイの古墳も多数発見されていて、その古墳は日本の古墳に似ています。
ただ、個人的には明日香村の猿石は、スキタイ人ではなくソグド人のような気がします。

猿石が斉明天皇期(600年代中期)に造られたものならば、ソグド人たちはそれ以前から飛鳥に居たと考えられそうです。彼らが日本の記録に残っていないのは、商人として非公式に日本に渡って来たからなのかもしれません。
今年1月、橿原考古学研究所の所長さんが「東アジアのソグド人」をテーマに講演をされ、『日本書紀』孝徳天皇期と斉明天皇期のトカラ国から来た人たちの中に、ソグド人が同行していた可能性を指摘されたそうです。この講演、拝聴したかったです。
橿原市の益田岩船がゾロアスター教の拝火壇だとは思いませんが、飛鳥時代の石造物の謎を解く鍵は「ソグド人」ではないか、と思いました。そして、中央アジアのコーカソイドは弥生時代(縄文時代後期から?)に既に日本列島に侵入していたのでは・・・出雲を旅した後、そんなふうにも感じました。

















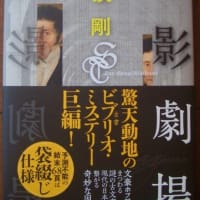

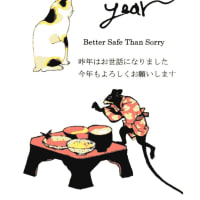
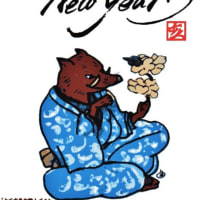





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます