Ikku shows how to put the comics on the market
***江戸文化の挿絵3―十返舎一九***
江戸後期のベストセラーで現代でも読み継がれている滑稽本『東海道中膝栗毛』の作者、十返舎一九(1765-1831年:本名 重田貞一)の挿絵がartかどうかは脇へ置いておき、現代漫画の元祖・江戸時代のオトナの絵本黄表紙が売り出されるまでの製作工程を一九先輩のイラストを見ながら学習してみました。題して『的中地本問屋(あたりやしたじほんといや)』1802年享和2年刊・栄邑堂(えいゆうどう)村田屋治郎兵衛板。

地本問屋とは、上方(京都大坂方面)からの読み物に対して、江戸で独自に製作された絵本や戯作本、浮世絵など娯楽書の出版販売をする本屋のことで、蔦屋重三郎も最初は地本問屋でした。栄邑堂村田屋は『膝栗毛』を出版した版元です。

この本は、作画、筆耕(文字を書くこと)も一九がやっていて、序文は誤字が目立ちます。(といっても私には判別できませんが)
商売は草の種本。書けども尽きぬ、浜の真砂の洒落次第。金のなる木を彫って小刀細工の銭儲けは、作者の得意に。はまちもの(へそくりのこと)、趣向は書肆の金箱に。山吹色の黄表紙と。一寸祝って筆を執る。
*文字や句読点は現代風にしてあります。
「商売(本)の元となる種本(稿本)は、洒落やふざけ次第でどうとでもなる。版木を彫って金儲けをするのは作者が得意とするところで、作者が溜めておいた趣向は小判と同じ色をした山吹色の黄表紙にして版元の金箱を潤してあげようと書き始めた。」と言ってますが、実は一九はこの年同じ趣向の本を他に2冊書いていて、要はネタに詰まって戯作者内幕ものを書いた、ということですハイ。
この手の戯作者生みの苦しみを綴った本は、前に紹介した山東京伝の『作者胎内十月図(さくしゃたいないとつきのず)』がありますが、あれは一九がこれを書いた二年後に発売されたもので、京伝が戯作を完成させるまでのお話でした。
でも『的中地本問屋』は一九に限らず、当時の和書ができるまでをイラストで紹介した貴重な資料となるお話です。

版元・栄邑堂村田屋治郎兵衛が今年は一発当ててやろうと工夫をこらし、先ず怠け者の一九を呼び寄せて酒を出す。実はこの酒の中には、作のよく出来る薬がはいっている。その薬は干鰯(鰯の脂を絞って干したもの)・馬糞・鋤・鍬(全て田畑を耕すときに使うもの)を百姓の脂肪を絞って練り合わせ丸薬にしたもの。馬の糞を入れて飲まされているとは知らない一九は「これはいい酒だ。銚子で馬鹿を尽くしたことは『旅眼石(たびすずり)』という本に書いたよ」などといい気になってさり気なく宣伝。一九は前年銚子で妓楼に泊まって遊び続け、金が無くて揚げ代の代りに狂歌を詠んだという。そんな逸話も入ってる鹿島・香取・息栖三社詣をした紀行をまとめたのが『旅眼石』で同年発売されている。
頭を掻いているのが一九(36歳)。薬の効果はてきめんで、途方もなくよい種本ができあがった。
***江戸文化の挿絵3―十返舎一九***
江戸後期のベストセラーで現代でも読み継がれている滑稽本『東海道中膝栗毛』の作者、十返舎一九(1765-1831年:本名 重田貞一)の挿絵がartかどうかは脇へ置いておき、現代漫画の元祖・江戸時代のオトナの絵本黄表紙が売り出されるまでの製作工程を一九先輩のイラストを見ながら学習してみました。題して『的中地本問屋(あたりやしたじほんといや)』1802年享和2年刊・栄邑堂(えいゆうどう)村田屋治郎兵衛板。

地本問屋とは、上方(京都大坂方面)からの読み物に対して、江戸で独自に製作された絵本や戯作本、浮世絵など娯楽書の出版販売をする本屋のことで、蔦屋重三郎も最初は地本問屋でした。栄邑堂村田屋は『膝栗毛』を出版した版元です。

この本は、作画、筆耕(文字を書くこと)も一九がやっていて、序文は誤字が目立ちます。(といっても私には判別できませんが)
商売は草の種本。書けども尽きぬ、浜の真砂の洒落次第。金のなる木を彫って小刀細工の銭儲けは、作者の得意に。はまちもの(へそくりのこと)、趣向は書肆の金箱に。山吹色の黄表紙と。一寸祝って筆を執る。
*文字や句読点は現代風にしてあります。
「商売(本)の元となる種本(稿本)は、洒落やふざけ次第でどうとでもなる。版木を彫って金儲けをするのは作者が得意とするところで、作者が溜めておいた趣向は小判と同じ色をした山吹色の黄表紙にして版元の金箱を潤してあげようと書き始めた。」と言ってますが、実は一九はこの年同じ趣向の本を他に2冊書いていて、要はネタに詰まって戯作者内幕ものを書いた、ということですハイ。
この手の戯作者生みの苦しみを綴った本は、前に紹介した山東京伝の『作者胎内十月図(さくしゃたいないとつきのず)』がありますが、あれは一九がこれを書いた二年後に発売されたもので、京伝が戯作を完成させるまでのお話でした。
でも『的中地本問屋』は一九に限らず、当時の和書ができるまでをイラストで紹介した貴重な資料となるお話です。

版元・栄邑堂村田屋治郎兵衛が今年は一発当ててやろうと工夫をこらし、先ず怠け者の一九を呼び寄せて酒を出す。実はこの酒の中には、作のよく出来る薬がはいっている。その薬は干鰯(鰯の脂を絞って干したもの)・馬糞・鋤・鍬(全て田畑を耕すときに使うもの)を百姓の脂肪を絞って練り合わせ丸薬にしたもの。馬の糞を入れて飲まされているとは知らない一九は「これはいい酒だ。銚子で馬鹿を尽くしたことは『旅眼石(たびすずり)』という本に書いたよ」などといい気になってさり気なく宣伝。一九は前年銚子で妓楼に泊まって遊び続け、金が無くて揚げ代の代りに狂歌を詠んだという。そんな逸話も入ってる鹿島・香取・息栖三社詣をした紀行をまとめたのが『旅眼石』で同年発売されている。
頭を掻いているのが一九(36歳)。薬の効果はてきめんで、途方もなくよい種本ができあがった。














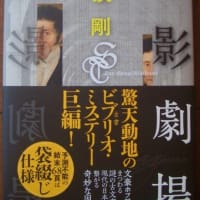

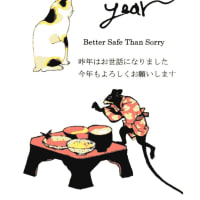
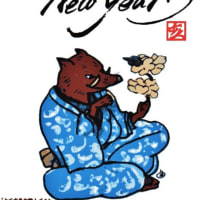
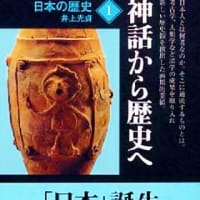






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます