***江戸文化の挿絵1―鳥居清長***
山東京伝の草双紙の挿絵を担当した絵師は、既に師匠の北尾重政のように超一流画工もいれば勝川春朗と名のっていた若かりし北斎なんかもいて、肉筆画や錦絵(多色刷り木版画)と比べると,単色なだけに「美しい」とか「芸術的」だとかいう感覚とは違う見方ができるので、絵草紙の挿絵は細かく見ると絵師の個性がよくわかって興味深いです。

山東京伝作『九界十年色地獄(くかいじゅうねんいろじごく)』1791年鶴屋刊の挿絵を描いたのは、天明期の美人画界を風靡した鳥居清長(1752-1815年)。
この戯作はタイトルからわかるように、遊廓での女郎の生活を描いたノンフィクション問題作(暴露本っすね)。上の画像は、遊廓に身売りした少女が主人(閻魔さまの姿をしている)に吟味されている図。可憐な乙女の嫌そうな表情がよく出ています。

晴れて花魁になっても、辛いことはいっぱい。暑い最中の花魁道中では、ししどの汗が流れます。時代劇ドラマでは夏でも冬でも花魁は同じような出で立ちだし涼しい顔しているので、どうだったんだろう…と思ってましたが、やっぱり現実は今も昔も変わりなかったのです。
汗さえなければ、良い美人画になるだろうに。

恥ずかしがって「水揚げ」を嫌がる娘は、遣手婆(やりてばばあ)が折檻して面の皮を剥ぎます。う~こわ~い。

小刀針を持った遣手婆に追っかけられることも。でも逃げる女郎の表情は怖がってません。実はこの女郎は仕事でズルしてたのを見つかった為折檻されそうになっているのです。でももう慣れっこになっているから「これから供部屋(客のお供が控えている部屋)へ逃げ込もう」と企んで平気で逃げているのです。遣手婆はいつも損な役。

ズルしたりサボったりするのうらく者はどこの世界にもいるものです。
色と酒に溺れて借金地獄になった女郎のところへ借金取りたちが押し寄せます。しかし女郎は裸ひとつで支払えぬ首でも持って行けと開き直ってキセルをぷか~。借金取りも呆れるその姿で「これでも体中を顔だと思えば平気さ。おまんまの代わりに風邪薬を食べれば風邪もひかない」とどこまでもふてぶてしい。
遊女は稼いでもなんだかんだと出費も多いので、常にお金が欲しいと思っています。そんな彼女たちは梅が枝(浄瑠璃『ひらかな盛衰記』に登場する遊女)の真似をして欲しいものを願います。

静岡県掛川市にある無間山観泉寺の鐘を撞くと、来世は無間地獄へ堕ちるが現世では金持ちになれるという伝説があり、『ひらかな盛衰記』四段目に登場する遊女・梅が枝は、この鐘になぞらえて手水鉢を打つと、三百両の金が落ちてくるという場面がこの当時有名だったようです。前出の『箱入娘面屋人魚』でも人魚が梅が枝の真似をする場面がでてきます。京伝お気に入りの場面だったのかもしれません。
この絵は清長らしい美人画の雰囲気が漂っています。彼は鈴木春信や北尾重政(京伝の絵の師匠)から美人画の作風を学んでいたそうで、恋川春町のキャラと同じくふっくらしたとぼけた表情が好きです。
山東京伝の草双紙の挿絵を担当した絵師は、既に師匠の北尾重政のように超一流画工もいれば勝川春朗と名のっていた若かりし北斎なんかもいて、肉筆画や錦絵(多色刷り木版画)と比べると,単色なだけに「美しい」とか「芸術的」だとかいう感覚とは違う見方ができるので、絵草紙の挿絵は細かく見ると絵師の個性がよくわかって興味深いです。

山東京伝作『九界十年色地獄(くかいじゅうねんいろじごく)』1791年鶴屋刊の挿絵を描いたのは、天明期の美人画界を風靡した鳥居清長(1752-1815年)。
この戯作はタイトルからわかるように、遊廓での女郎の生活を描いたノンフィクション問題作(暴露本っすね)。上の画像は、遊廓に身売りした少女が主人(閻魔さまの姿をしている)に吟味されている図。可憐な乙女の嫌そうな表情がよく出ています。

晴れて花魁になっても、辛いことはいっぱい。暑い最中の花魁道中では、ししどの汗が流れます。時代劇ドラマでは夏でも冬でも花魁は同じような出で立ちだし涼しい顔しているので、どうだったんだろう…と思ってましたが、やっぱり現実は今も昔も変わりなかったのです。
汗さえなければ、良い美人画になるだろうに。

恥ずかしがって「水揚げ」を嫌がる娘は、遣手婆(やりてばばあ)が折檻して面の皮を剥ぎます。う~こわ~い。

小刀針を持った遣手婆に追っかけられることも。でも逃げる女郎の表情は怖がってません。実はこの女郎は仕事でズルしてたのを見つかった為折檻されそうになっているのです。でももう慣れっこになっているから「これから供部屋(客のお供が控えている部屋)へ逃げ込もう」と企んで平気で逃げているのです。遣手婆はいつも損な役。

ズルしたりサボったりするのうらく者はどこの世界にもいるものです。
色と酒に溺れて借金地獄になった女郎のところへ借金取りたちが押し寄せます。しかし女郎は裸ひとつで支払えぬ首でも持って行けと開き直ってキセルをぷか~。借金取りも呆れるその姿で「これでも体中を顔だと思えば平気さ。おまんまの代わりに風邪薬を食べれば風邪もひかない」とどこまでもふてぶてしい。
遊女は稼いでもなんだかんだと出費も多いので、常にお金が欲しいと思っています。そんな彼女たちは梅が枝(浄瑠璃『ひらかな盛衰記』に登場する遊女)の真似をして欲しいものを願います。

静岡県掛川市にある無間山観泉寺の鐘を撞くと、来世は無間地獄へ堕ちるが現世では金持ちになれるという伝説があり、『ひらかな盛衰記』四段目に登場する遊女・梅が枝は、この鐘になぞらえて手水鉢を打つと、三百両の金が落ちてくるという場面がこの当時有名だったようです。前出の『箱入娘面屋人魚』でも人魚が梅が枝の真似をする場面がでてきます。京伝お気に入りの場面だったのかもしれません。
この絵は清長らしい美人画の雰囲気が漂っています。彼は鈴木春信や北尾重政(京伝の絵の師匠)から美人画の作風を学んでいたそうで、恋川春町のキャラと同じくふっくらしたとぼけた表情が好きです。














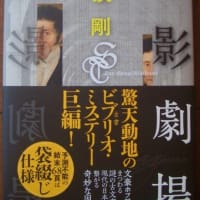

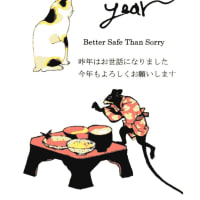
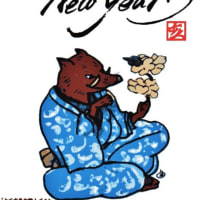
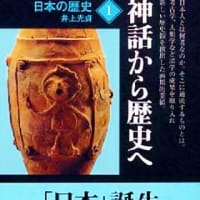






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます