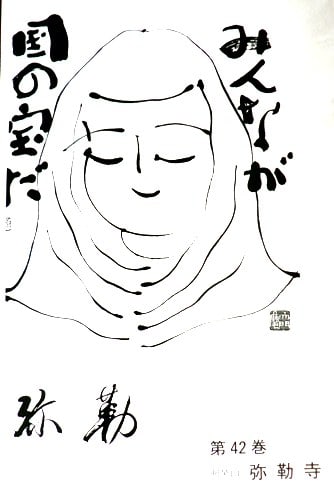12月30日、霊長類の脳で前頭葉の初期進化が始まります。
12月31日、
宇宙カレンダーの最後の日になって、ヒト科に属す生物がようやく創発します。
第3紀が終わり第4紀(更新世、完新世)に、いわゆる「人類」が創発しました。
もう少しくわしくいうと――このあたりは説がいろいろでまだ学会でほぼ合意された「標準的仮説」というのがないようですが――午後0時30分、プロコンスルとラマピテクスが誕生しています。これは類人猿と人類の祖先ではないかといわれてきました。
現生人類――生物学上の分類でいうと「ホモ・サピエンス・サピエンス」というんだそうですが――の登場は、宇宙カレンダーの最後の最後、説によってかなり幅がありますが、1000万年から200万年くらい前です。
250万年前としておくと、午後10時24分、もっとも古く1000万年前でも午後5時半ころです。
こういうふうに見てくると、人類は宇宙の歴史の中で、そして生命の歴史の中でもごくごく新米だということがわかります。
考えてみると、人類の歴史はほんとうに短いのですね。
だから、近代人がやってきたような偉そうな顔はあまりしないほうがいいんじゃないか、と私は思っています。
しかしそこまでに、エネルギーから素粒子、素粒子から原子、原子から分子、分子から高分子、そして高分子から遺伝子つまり物質から生命が創発し、細胞、細胞から器官、生命の歴史の中で生命からやがて哺乳類的脳と心、それから霊長類的な脳と心、人類の脳と心が創発し……と、ずうっと大変な積み重ねが、やっと人間という存在に達しています。
しかも、原人以来の人類の積み重ねが現代文明まで到達しているわけです。
そういうふうに、いわば積みあげ重なって複雑化してきた、つまり高度に発達してきたのが人類です。
ですから、そういう意味でいえば、やっぱり人間はすごいと思います。
進化学者のG・C・シンプソン(『進化の意味』草思社)は、こういっています。
「人間が動物であると認識することは大切であるが、人間独自の本質はまさに他のどんな動物にもみられない特徴の中にあることを認識することはさらに重要である。人間の自然における地位と、その地位のもつもっとも重要な意味とは、その動物性によってではなく、人間性(ヒューマニティ)によって規定される。」
最初の人間が、大脳新皮質、特に前頭葉を発達させて、シンボルや言葉を使うことができるようになったのが、31日の午後10時24分、夜もやや更けてきたころです。
石器つまり道具を使うことが普及したのが10時54分ころ。
原人が火を使ったのが11時2分(最近の再調査では、北京原人は私たち現生人類の直系のご先祖様ではないという説が有力になってきているようです)。
かつて、「人間は、言葉と火と道具を使う動物だ」といわれてきました。
使わないと、人間らしい生活ができないのです。
そういう、火を使う、道具を使う、言葉を使うという人間の条件がやっとそろったのが11時45分です。
(これも最近の研究で、チンパンジーも例えば枝を細工して木の実をたたき落とす棒=「道具」として使うことがあるとわかったので、この定義は少しあいまいになりましたが)。
その場合、それらを使うか使わないかも、今の私たちには選択の余地はありません。
火(エネルギー)を使わない、道具を使わない、言葉を使わないという自由選択の権利はないし、必要ないのですね。
積み重ねられてきた進化の遺産は相続しない権利はなく、相続する義務しかないし、それは不自由なことではなく、だからこそ生きられるのです。
どれもそうですが、特に言葉はそうです。
言葉を中心とした「文化」なしには、人間は人間らしく生きること、それどころか生きることそのものができません。
かつて「ブッシュマン」と呼ばれてきた「サン族」のようなきわめて原始的な生活をしている人でも、この件に関してはまったくおなじです。
言葉や文化を担った存在であるという点についても、私たちは自由ではないのです。
それこそ人間が人間であるための条件・「人間の条件」なのです。
*
言葉と文化によって、人間は環境と本能にしばられた〈動物〉から、さまざまな生き方の選択の幅・自由を獲得した〈人間〉になったと考えてまちがいないでしょう。
これもまた、大きな進化の飛躍です。
人気blogランキングへ