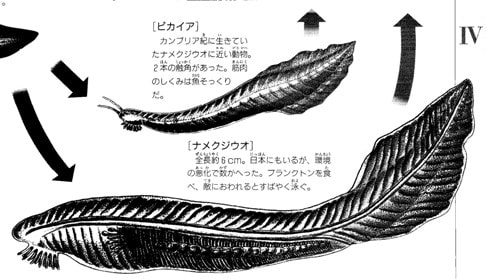生命は誕生してから何と25億年も、ひたすら細胞分裂をすることで繁殖をしていたようです。
個体は、いわば自分の単純なコピーを作って、いのちを増やし、引き継いでいたわけです。
そういう単細胞生物には性別はありませんから、そういう生殖の仕方を「無性生殖」というのはご存知のとおりです。
つまり、ただいのちをつなげていくだけなら、性は必要なかったらしいのです。
ところが今では、多くの生物は、同じ種の生命でありながらオスかメスかに分かれています(分化)。
といっても、分離、分裂したわけではなく、つながり結びあうことによって(統合)、生命を伝えていくわけです。
「有性生殖」といわれるかたちですね。
ここでも「分化と統合」という宇宙進化の基本パターンが現われています。
生命がオスとメスに分かれたのは、一説では15億年ほど前だと推測されています。宇宙カレンダーでは11月21日、そろそろ暮も近づいたという季節です。
(これにはいろいろ説があるようですが。)
ところで、私たちヒトという動物の場合も、それぞれの個体は基本的には男性か女性かどちらかの性であるわけです。
それはつまり、私たちが男か女かとして生きているということも、自分で決めたわけではなく、宇宙そして生命の進化史が決めたことから始まっているということではないでしょうか。
おそらく考えたこともないかもしれませんが、父と母がいて子ども=私が生まれるということも、基本的なかたちとしては今から15億年も前にすでに決まっていたわけです。
これもまた、考えてみると驚くべきことです。
毎回えらそうにいっていますが、私も学ぶまでは考えたこともなかったことばかりなんですよ。
学べば学ぶほど、世界・コスモスは驚きに満ちています。
ところで、たぶん読者も実感しておられるでしょうが、性があるということはとても魅力的なことであると同時に、いろいろな悩みやトラブルの元でもあります。
異性がいない世界を想像すると、実につまらない味気ない世界だろうと思われます。
私は、この世に女性が存在しなかったら、ほとんど生きている意味がなくなるのではないかと思うくらい、女性がこの世に存在していてくれるということはすばらしいことだと感じています。
幸いにして、女性の方にうかがっても、たいていの場合は、男性のいない世界なんてつまらないといってくださいます。
お互いが異なった性であるということは、とてもいいことですね。
でも、時には、異性なんかいなかったら、性というものがなかったら、どんなに人生が単純ですっきりとしているだろうという気がすることもありませんか。
どうして宇宙は、こういう素敵でもあり面倒でもあり、時にはとても醜く汚らしくもなるような性というものを創ったのでしょう。
そのいちばん出発点・原点のところ、つまり「性の創発」の意味を考えてみたいと思います。
(これは出発点での意味であって、すべての意味ではありませんが。)
ある生物学者がこういっています(ショップ『失われた化石記録』講談社現代新書)。
「あらゆる進化上の革新のなかで、二つの事柄がとりわけ重要なものとしてきわだっている。
その一つは、酸素を発生するシアノバクテリアの光合成……。
二つめは、真核生物の性であり、高等生物における遺伝的変異の主たる供給源で、かつ著しい多様性と急速な進化の原因となった革新であった。」
すでにお話しした光合成に続く、進化史上のもう一つの大事件が、性の始まりだというのです。
どういう意味で大事件なのでしょう。
生命の中にオスとメスの違いが生まれた決定的な意味は、無性生殖のように細胞分裂で遺伝子が単純にコピーされるだけではなく、オスとメスの遺伝子が半分ずつ組み合わされるようになったということらしいのです。
単純なコピーでは、コピーのズレやまちがいを除いて、新しいものが生まれてくる可能性はごくわずかです。
しかも生命情報としての遺伝子は、新しければいいというものではなく、環境に適応できるものでなければなりません。
単純なコピーのまちがいでできた新しい遺伝子のほとんどは、環境に不適応なものだったと推測されます。
したがって、生命の新しくてしかも適応的なかたちができる可能性はほとんどありません。
ですから、実際、初期の生命の進化は非常にゆっくりとしたものだったようです。
ところが、性というものが創発――新しく創造的に発生――して、オスとメスの別々の遺伝子が半分ずつ組み合わされるようになると、新しいものが生まれてくる可能性が驚くほど高まったのです。
どのくらい違うかというと、例えば無性生殖で1つの遺伝子に10の突然変異が起こったとすると、できる遺伝子の組み合わせは元のもの+10=11、つまり11通りだけです。
ところが、有性生殖だと、10通りの突然変異が混ぜられて3の10乗通り、約6万通りができるのだそうです。
大変な違いで、変異の数が増えれば、もちろん違いももっと大きくなります。
実際、
有性生殖によって生物の多様化が爆発的に促進されたといわれています。
今、この地球上に確認されているものは一説によれば500万種、推測2500万種の生命がいろいろ多様に存在しています。
さらに最近の説では、さらにその10倍くらい、2億5000万種くらいいるのではないかともいわれているようです。
何とも大変な数ですね。
そしてここで重要なポイントは、
実に豊かな生命の多様性は性によってもたらされたということです。
私たち人間の、個人個人のつごうとしてだけでなく、地球自体、性がなければ実に単調な世界のままだったでしょう。
これまで、宇宙には自己組織化―複雑化という方向性があるという話をしてきました。
「組織化」とは、混沌とした癒着状態でもなく、ばらばらな分離・分裂状態でもなく、全体がそれぞれの部分に分化――区分・区別できる状態になること――しながら、しかも統合されている、つまりつながりあってまとまりをなしているということです。
オスとメスも、分化しながら統合されたかたちで、いのちをつないでいき、さらに新しいいのちのかたちを生み出していくという働きをするために、生命の歴史の中で創発したもののようです。
そして、オスとメスのつながり-結びつきによって生命の新しい種が多様に生み出されてきたという生命進化の流れの中に、哺乳類も霊長類もそして現生人類もあるのです。
オスとメスの分化と統合がなかったら、こんなにも豊かな生命の種が存在する世界にはならなかったし、人類も発生しなかったし、私の両親も私も生まれなかったんですね。
そう考えると、確かに性の創発は進化の重大な事件の一つだという感じがしませんか。
それは、個人レベルでいえば、みなさんそれぞれが、男性あるいは女性であるということも、宇宙進化の流れの中、生命進化の流れの中で一つの役割を担うように、ヒトのオス・メスになっているということではないでしょうか。
生命進化における性の役割をまとめていえば、①いのちをつないでいくことと、②いのちをより豊かにしていくこと、の2つだといっていいでしょう。
ということはまた、自分が男か女であることには、生命進化上での決定的な意味があるといえます。
あるいは、さらに宇宙的な意味があるということもできるのです。
もちろんいろいろな事情で、生理的に男性か女性かはっきりしない人もいますし、自分の生理的な性と心理的な性が一致しないという人もいます。
もちろん、そういう人の人間としての権利は認める必要はあります。
しかし、だからといって男と女の区別はなくなったほうがいい、同じであるべきだ、あるいはあいまいでいい、ということにはならない、と私は考えています。
男と女が違った存在であり、男か女であるということには、生命の歴史の中ではっきり意味があるように思われます。
ですから、男も女も、自分に与えられた性を「自分の好きなように勝手に」使うと、宇宙の方向性から外れ、その結果として自分にもまわりにもいろいろな歪み、傷、悪影響を与えることになるでしょう。
この授業では、性の倫理について詳しくお話しすることはしません。
ただここでは、もっともスタートのところから現在に到るまで、私たちが生かされて生きているこの宇宙には「関係ないだろ」、「私の勝手でしょ」といってすますことのできない事実があり、性に関してもそうだ、ということだけ、伝えておきたいと思います。
ネット学生のみなさんは、ただの偶然だと思っていたかもしれませんが、「自分が男に生まれたこと、女に生まれたことには、宇宙的・進化史的な意味があるのではないか」ということを、ぜひ一度考えてみてください。
そして
よかったら、何となく恋をしたり、安易にセックスをしたりする前に、「もしかすると、私が恋をしたり、セックスしたりすることは、宇宙の進化という長い長いいのちの流れの、ちいさな、けれどもとても大切な一こまなのかもしれない」と考えてみてはどうでしょう。
そのほうが、恋もセックスも、それこそロマンティック、ドラマティックになるはずです。
*やや詳しくは、サングラハ心理学研究所のHPにアクセスして、会報第72号の「性と愛のコスモロジー」をお読みください。また、時々、「コスモロジー的恋愛論講座」を開催していますので、よかったらプログラムを見てお出かけください。
人気blogランキングへ