人間の身体は24歳まで成長し続け、そこで人間の身体は完成されます。それからは新陳代謝を繰り返しながら、天寿を全うすべく人間の精妙な機能が発揮され、徐々に死へ向かって機能が低下していきます。
その身体が完成するまでの成長期は、その後の人生を形成する重要な基盤づくりの時期でもあり、その時期が、それからの人生の身体やこころの状態を左右すると言っても言い過ぎでないくらい大切な時期なのです
◎思い通りにいかない虫捕りが、子どもを育てる
(養老)そういう意味の体育って、今、ゼロになっちゃっているんじゃない?体育といえば、オリンピックでやるような競技しか教えないでしょ。体操とかサッカーとかさ。だけど、宙返りしたり、球を蹴ったりしても、日常生活とは関係がない。言ってみれば、西洋風のダンスみたいなものでね。氷の上でサーカスみたいに滑れたって、廊下で転んだりしているんだよ、きっと(笑)。それを体育教育と思い込んでいるんじゃないのかな。
(奥本)野球のピッチャーに話を聞いたことがあるんだすけど、あの決まった距離じゃないと、凄い球を投げられないそうですよ。あれより近くても遠くても、コントロールが狂っちゃうらしい。ピッチャーの投球って、完全に型にはめて投げてますから。
(池田)スポーツも、今は細かい理論がありすぎらしいですね。しかも情報社会だから、世界的にすぐ普及しちゃう。少年サッカーを教えるメソッドも、世界的にかなり統一されつつあるんだって。
(奥本)ビデオとかDVDとか、映像でメソッドが普及されているからね。
(池田)だから、アフリカでも中国でも日本でも北朝鮮でも、子どもたちは同じやり方で練習させられている。ドリブル上達法とか、ターンの仕方とか、みんな同じ。世界標準なわけです。
(養老)まさしく調教だな。
(池田)だから、世界中から同じような選手しか出てこない。やっているサッカーもみんな同じようになっちゃう。大人のプロゲームも、学生の試合も、子どもの大会も、みんな同じようなサッカーしかやっていない。というより、やれない。標準メソッドに従わないような個性派は、クラブとか学校の部活に残れなくて、排除されちゃうから。
(養老)それは僕は、絶対に身体に関するファシズムだと思う。ヨーロッパ起源のスポーツには、似たようなものが多いんですよ。その点、日本の武道はちょっと変わっている。一見ファシズムみたいけど、実は自由なんです。剣道だって柔道だって、礼儀や技はいろいろあるけど、最後は気合でしょ。
(池田)そうなんです。スポーツの醍醐味というのは、技術、戦術、体力に劣る側が、勝る側にどうしたら勝てるかという一点にある。そりゃそうですよね。勝てそうにない相手に勝つことが、無上の喜びなのであってね。じゃあ、どうしたら勝てるかと。さらに言えば、選手それぞれがスタンダード以上のことを試合で実践する以外にない。要するに教えられた以上のこと、スタンダードを超えるプレーを実践するしかない。コーチや先生の顔色ばかり見ている奴は、結局のところ役に立たないわけですよ。
(養老)そうなんだ。それをふつう、「カンがいい選手」と言うわけだよ。「動物的な感覚」と言ってもいい。
(奥本)今流行のマニュアル頼りの教育では、そのカンが育たない。むしろ、殺してしまいます。
(養老)偏差値教育がダメにしているんだよ。
(池田)そもそもスポーツをマニュアルで教えられると思っていること自体が、間違いなんじゃないの? 実地で体を動かして、状況に反応して、インプットとアウトプットを繰り返しながら、自分でカンを鍛えていくしかないんじゃないかな。
(奥本)スポーツ選手にも、虫捕りが必要だ(笑)。
(養老)まったく、そのとおり。
(池田)虫捕りもスポーツも、辛抱とか努力の結果でしょ。思い通りにならないということを痛感する。思い通りにならないのが当たり前なんだということの意味が大きい。ゲームだって、本来はスポーツと同じようなもののはずなのに、攻撃本があったりして、思い通りになっちゃう。
(奥本)虫は思い通りにならない。不条理である。そこが魅力であって、ゲームにはない、思いがけない筋書きが展開していく。
(養老)自分の思い通りにならないはずがないと思っていれば、思い通りになったときに、嬉しいと感じる。捕れるわけがないと思いながら虫捕りをしていれば、たまに捕れるとすごく嬉しい。友達と一緒に行って、自分だけが捕りたい虫を捕れない時の惨めさとか、いろいろなことがあるじゃないですか。そういう経験は、子どもたちの成長にとって、とっても重要ですよね。で、絶対あいつよりたくさん捕ってやる、どうしたら捕れるだろうと工夫したり、探したりするでしょ。あるいは、あいつはこうやっているんだなと一目置いたりね。
(奥本)子どもをダメにしようと思えば、何でも与えればいい。これはルソーの言葉ですけどね。何でも次々に与えられたら、まったく欲望がなくなっちゃうと思うの。「何か食べたい?」って聞いても「べつに」って返事が返ってくる。「強いて言えば、マックのあれかな」ぐらいになっちゃうでしょ。今の子は、腹を減らしてないもんなぁ。
(池田)うまいものは、たまに食うからうまいわけで、毎日毎日ご馳走を食べていたら、ありがたみも何もないですよ。
(奥本)今の子には、死ぬほどお腹がすいたという体験がないでしょ。いつになったらご飯を食べさせてもらえるかわからないという、不安な状況もない。
(池田)僕らはうんとお腹が減っていたから、学校から帰ってきて、戸棚にせんべいでもあれば「やったぞ、今日はラッキー!!」とか思いましたね。
(養老)僕は食物自給率を上げろっていう農水省の会議に出ているんだけど、教育のためには、もっと食物自給率を下げるべきかな(笑)。
『虫捕る子だけが生き残る』 養老孟司 池田清彦 奥本大三郎 対談集
ちょっと長い引用になってしまいましたが、現在はスポーツに限らず情報を得ようと思えば、様々な媒体から多くのものを得ることができます。その情報が、やろうとしている事に対して、また、その環境において適しているのかどうか判断し、それを活かすも殺すも、それにより良くなるも悪くなるも、自分の状況判断と分析しだいということです。
子どもたちを取り巻くスポーツなども同様なことが言えると思います。プロや外国のスター選手が効果があったから言って、練習方法やトレーニング機器を取り入れても、それは成長期の選手には効果が出ないばかりか、害にさえなることもあります。
また、この練習は何のために、どこを鍛える目的で、実際の動きのどんな状況のために、など自分で理解し、納得しないまま、言われた通り、指示通り、監督やコーチに怒られないように、ただ機械的に練習をこなしていたのでは、これも自分の身につくこともありませんし、また、集中力の欠如や不注意を生み、傷害を引き起こすなど害になることもあります。
指導者の教えを聴くことは大事なことです。そこから一皮むけ、自分の身体に自然な動きを身につけるためには、「どうしてこの練習をするのか?」「目的は?」など、自分の心に問いかけながら、意識を身体内部部(身体感覚)に向けていくことが大切なことであると思います。自分でいろいろ考えて実践して、失敗して、そして学んでいくことが成長であり、自分勝手ではない、本当の自由というものがわかってくるのかもしれません。
飢餓状態なんてのは、体験したくはありませんが、本当に日本は食事にしても恵まれているんだということに感謝しつつ、ギリギリのところまでやってみることを小さい頃から体験していくことも必要なのかもしれません。
もうちょっと、お付き合いくださいね~パート3へ

二葉鍼灸療院 田中良和

その身体が完成するまでの成長期は、その後の人生を形成する重要な基盤づくりの時期でもあり、その時期が、それからの人生の身体やこころの状態を左右すると言っても言い過ぎでないくらい大切な時期なのです

◎思い通りにいかない虫捕りが、子どもを育てる
(養老)そういう意味の体育って、今、ゼロになっちゃっているんじゃない?体育といえば、オリンピックでやるような競技しか教えないでしょ。体操とかサッカーとかさ。だけど、宙返りしたり、球を蹴ったりしても、日常生活とは関係がない。言ってみれば、西洋風のダンスみたいなものでね。氷の上でサーカスみたいに滑れたって、廊下で転んだりしているんだよ、きっと(笑)。それを体育教育と思い込んでいるんじゃないのかな。
(奥本)野球のピッチャーに話を聞いたことがあるんだすけど、あの決まった距離じゃないと、凄い球を投げられないそうですよ。あれより近くても遠くても、コントロールが狂っちゃうらしい。ピッチャーの投球って、完全に型にはめて投げてますから。
(池田)スポーツも、今は細かい理論がありすぎらしいですね。しかも情報社会だから、世界的にすぐ普及しちゃう。少年サッカーを教えるメソッドも、世界的にかなり統一されつつあるんだって。
(奥本)ビデオとかDVDとか、映像でメソッドが普及されているからね。
(池田)だから、アフリカでも中国でも日本でも北朝鮮でも、子どもたちは同じやり方で練習させられている。ドリブル上達法とか、ターンの仕方とか、みんな同じ。世界標準なわけです。
(養老)まさしく調教だな。
(池田)だから、世界中から同じような選手しか出てこない。やっているサッカーもみんな同じようになっちゃう。大人のプロゲームも、学生の試合も、子どもの大会も、みんな同じようなサッカーしかやっていない。というより、やれない。標準メソッドに従わないような個性派は、クラブとか学校の部活に残れなくて、排除されちゃうから。
(養老)それは僕は、絶対に身体に関するファシズムだと思う。ヨーロッパ起源のスポーツには、似たようなものが多いんですよ。その点、日本の武道はちょっと変わっている。一見ファシズムみたいけど、実は自由なんです。剣道だって柔道だって、礼儀や技はいろいろあるけど、最後は気合でしょ。
(池田)そうなんです。スポーツの醍醐味というのは、技術、戦術、体力に劣る側が、勝る側にどうしたら勝てるかという一点にある。そりゃそうですよね。勝てそうにない相手に勝つことが、無上の喜びなのであってね。じゃあ、どうしたら勝てるかと。さらに言えば、選手それぞれがスタンダード以上のことを試合で実践する以外にない。要するに教えられた以上のこと、スタンダードを超えるプレーを実践するしかない。コーチや先生の顔色ばかり見ている奴は、結局のところ役に立たないわけですよ。
(養老)そうなんだ。それをふつう、「カンがいい選手」と言うわけだよ。「動物的な感覚」と言ってもいい。
(奥本)今流行のマニュアル頼りの教育では、そのカンが育たない。むしろ、殺してしまいます。
(養老)偏差値教育がダメにしているんだよ。
(池田)そもそもスポーツをマニュアルで教えられると思っていること自体が、間違いなんじゃないの? 実地で体を動かして、状況に反応して、インプットとアウトプットを繰り返しながら、自分でカンを鍛えていくしかないんじゃないかな。
(奥本)スポーツ選手にも、虫捕りが必要だ(笑)。
(養老)まったく、そのとおり。
(池田)虫捕りもスポーツも、辛抱とか努力の結果でしょ。思い通りにならないということを痛感する。思い通りにならないのが当たり前なんだということの意味が大きい。ゲームだって、本来はスポーツと同じようなもののはずなのに、攻撃本があったりして、思い通りになっちゃう。
(奥本)虫は思い通りにならない。不条理である。そこが魅力であって、ゲームにはない、思いがけない筋書きが展開していく。
(養老)自分の思い通りにならないはずがないと思っていれば、思い通りになったときに、嬉しいと感じる。捕れるわけがないと思いながら虫捕りをしていれば、たまに捕れるとすごく嬉しい。友達と一緒に行って、自分だけが捕りたい虫を捕れない時の惨めさとか、いろいろなことがあるじゃないですか。そういう経験は、子どもたちの成長にとって、とっても重要ですよね。で、絶対あいつよりたくさん捕ってやる、どうしたら捕れるだろうと工夫したり、探したりするでしょ。あるいは、あいつはこうやっているんだなと一目置いたりね。
(奥本)子どもをダメにしようと思えば、何でも与えればいい。これはルソーの言葉ですけどね。何でも次々に与えられたら、まったく欲望がなくなっちゃうと思うの。「何か食べたい?」って聞いても「べつに」って返事が返ってくる。「強いて言えば、マックのあれかな」ぐらいになっちゃうでしょ。今の子は、腹を減らしてないもんなぁ。
(池田)うまいものは、たまに食うからうまいわけで、毎日毎日ご馳走を食べていたら、ありがたみも何もないですよ。
(奥本)今の子には、死ぬほどお腹がすいたという体験がないでしょ。いつになったらご飯を食べさせてもらえるかわからないという、不安な状況もない。
(池田)僕らはうんとお腹が減っていたから、学校から帰ってきて、戸棚にせんべいでもあれば「やったぞ、今日はラッキー!!」とか思いましたね。
(養老)僕は食物自給率を上げろっていう農水省の会議に出ているんだけど、教育のためには、もっと食物自給率を下げるべきかな(笑)。
『虫捕る子だけが生き残る』 養老孟司 池田清彦 奥本大三郎 対談集
ちょっと長い引用になってしまいましたが、現在はスポーツに限らず情報を得ようと思えば、様々な媒体から多くのものを得ることができます。その情報が、やろうとしている事に対して、また、その環境において適しているのかどうか判断し、それを活かすも殺すも、それにより良くなるも悪くなるも、自分の状況判断と分析しだいということです。
子どもたちを取り巻くスポーツなども同様なことが言えると思います。プロや外国のスター選手が効果があったから言って、練習方法やトレーニング機器を取り入れても、それは成長期の選手には効果が出ないばかりか、害にさえなることもあります。
また、この練習は何のために、どこを鍛える目的で、実際の動きのどんな状況のために、など自分で理解し、納得しないまま、言われた通り、指示通り、監督やコーチに怒られないように、ただ機械的に練習をこなしていたのでは、これも自分の身につくこともありませんし、また、集中力の欠如や不注意を生み、傷害を引き起こすなど害になることもあります。
指導者の教えを聴くことは大事なことです。そこから一皮むけ、自分の身体に自然な動きを身につけるためには、「どうしてこの練習をするのか?」「目的は?」など、自分の心に問いかけながら、意識を身体内部部(身体感覚)に向けていくことが大切なことであると思います。自分でいろいろ考えて実践して、失敗して、そして学んでいくことが成長であり、自分勝手ではない、本当の自由というものがわかってくるのかもしれません。
飢餓状態なんてのは、体験したくはありませんが、本当に日本は食事にしても恵まれているんだということに感謝しつつ、ギリギリのところまでやってみることを小さい頃から体験していくことも必要なのかもしれません。

もうちょっと、お付き合いくださいね~パート3へ


二葉鍼灸療院 田中良和













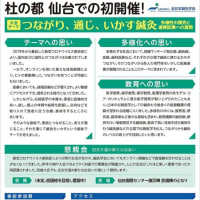
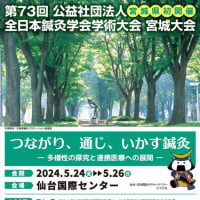











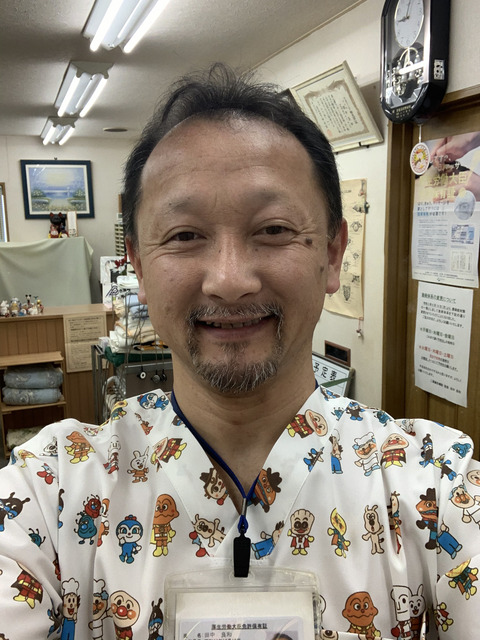

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます