
秋も深まりをみせ 、朝晩のみならず日中も肌寒い日が多くなってきました
、朝晩のみならず日中も肌寒い日が多くなってきました
皆様、寒暖の差が激しい季節の変わり目には十分体調をお気を付けくださいね。
汗をかいたら早めに着替え、身体をしっかりと温め、体調を整えましょう。来たるべき冬に備える身体づくりをしていきましょう。
さて、古代中国では漢字が発明され、様々な思想や文化が文字で残されるようになりました。この恩恵を現在でも私達は受けています。
この漢字文化を語るうえで重要な経典が四書五経です。
四書とは・・・大学 中庸 論語 孟子
五経とは・・・易経 詩経 書経 礼記 春秋
すべての書物が重要なのですが、とくに重要視されたのが易経です。
易経は、人と大自然は一体ですよ(天人合一)という思想をあらわしたものであり、宇宙の森羅万象を符号によって表現しようとする経典です。その符号の組み合わせを漢字にて表現しております。
また、過去、現在、未来をあらわすこともあり占い等で用いられることが多いのですが、一般的に流れている占いというものではなく人や自然の摂理や根本、その原理を説いた奥深い書物なのです。
実は、東洋医学もこの易経の考えを原理としているところが多くあり、気の考え方、陰陽の考え方、根本が大切(太極)という考え方、人は自然の一部なんだよ(天人合一)という考え方など、身体を全体から捉える思想は易経から来ているとみられています。
こう考える易経の思想は奥が深く、現代の宇宙物理学や量子力学にも繋がるところがあるのです。
易経は、人生を歩んでいく行く上での、心や精神、魂のあり方=行動を示しているのですね。
お一つ、これは今の私にぴったりの言葉と思った卦(符号の組み合わせ)をご紹介。
 地山謙(ちさんけん)
地山謙(ちさんけん) 
 盈(えい)をかきて謙に益す
盈(えい)をかきて謙に益す
天道は下済(かさい)にして光明なり。地道は卑くして上行す。天道は盈をかきて謙に益し、地道は盈を変じて謙に流(し)し、鬼神は盈を害して謙に福(さいわい)し、人道は盈を悪(にく)みて謙を好む。謙は尊くして光り、卑けれども踰(こ)ゆべからず。君子の終わりなり。
【解説】
易経は、謙虚、謙譲、謙遜の精神を最高の徳とします。低く謙(へりくだ)るものこそが、最も高みに至るといっています。
天は日差しや雨を地にふらせ、大地はそれを受けて、万物を育成し、また天に上昇させて還元します。大地はもとから低く、高い天でさえ謙ります。
また天は満ちたもの(盈)を欠けさせ、欠けたもの(謙)を満ちるようにします。地は山を谷に変え、また谷を山に変えます。
「鬼神は邪なし」という言葉がありますが、鬼神は慢心を嫌い、謙る者に幸いを運びます。
人は、たとえ成功者であっても高慢であれば嫌い、謙虚な人には惹かれて手を貸したいと思います。身分が低かろうと、謙虚に生きる人を誰も蔑(さげす)みはしません。
謙虚な態度を終わりまで貫いて崩さない、それが君子なのです。「謙」の徳は終わりを飾るものであるのです。
〈「易経」一日一話 致知出版社より〉
易経の、この世の生成・発展の捉え方に「三義」というものがあります。
簡易(かんい)・変易(へんえき)・不易(ふえき)です。
簡易とは・・・簡単明瞭なことで、変易、不易の循環を理解すること。
変易とは・・・身体で例えると、身体の細胞は毎日、新陳代謝が起こり、どこかで細胞が入れ替わっており、一日として同じ身体であることはないこと。常に変化していること
不易とは・・・しかし、あなたの身体自体はそこにあり続け、一日二日で無くなったりはしない。変わらない事象が存在すること。
ちょっと話が難しくなりましたが、自分の変化多き人生において、日々の生活態度としては、謙虚、謙譲、謙遜の気持ちで過ごした方がいいですよということです。
自分には身に沁みる言葉だったので紹介いたしました。
最後までお読みいただき、ありがとうございます


















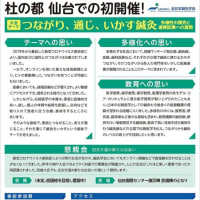
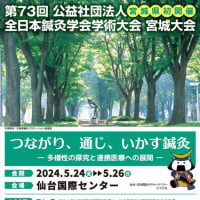







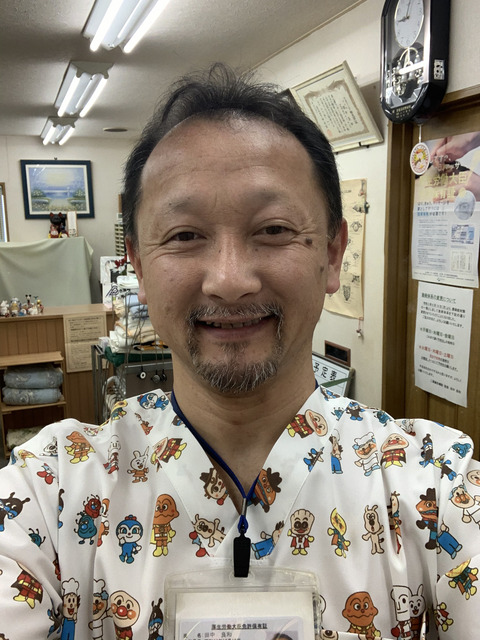

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます