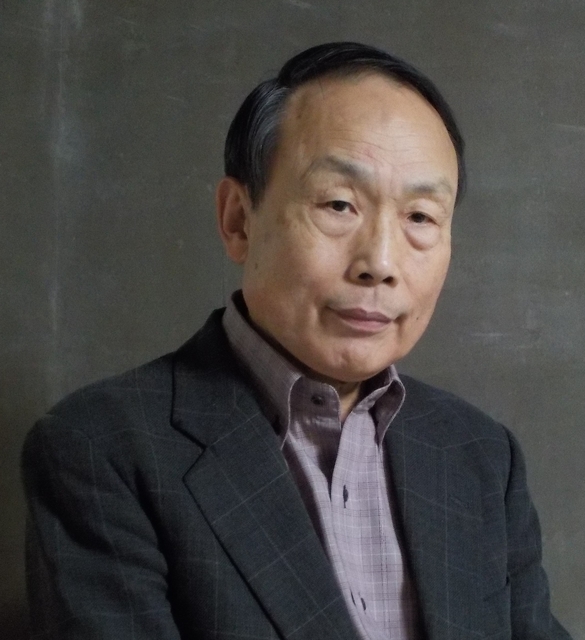Ⅱ「歌曲と歌劇」①
前回<Ⅰ「言葉と音楽」>は、「ヴォーカリーズ」という歌詞を伴わずに母音のみで歌われる作品やフランス語が分からない外国人観光客相手にレストランのメニュー表を歌って感動させた場末の歌手のエピソードを例に、声楽は詞がなくても成立するという事実を示した。しかし、歌曲や歌劇にとってそれらは例外中の例外で主たる対象にはならない。その基盤はあくまでも「言葉=詞」と「音楽」という二大要素によって成り立っているため、前者=詞の精神的受容は必須条件となる。
以前、音楽系大学における詞に関する表現教育(文学的理解と人物表現)がおろそかになっている点に触れた【「詞」――歌われるための文学~オペラおよび歌曲を中心として⑷】。クラシック歌手は、歌う以前に、五線譜を目にする以前に、詞の言葉と描かれている世界・人物の把握とその心情に対して深い理解・共感を持つよう心を砕いているのだろうか。
歌詞は、演劇・映画では、脚本のセリフにあたる。演出家や監督は、「そのセリフが言えるか」「その人物の心の痛みや喜びを体現できるか」を念頭に配役を決める。俳優個人の外見や性格・キャリアばかりでなく、人間としての幅や深さ個人史まで考慮に入れる。なぜなら、その配役によって舞台や映画の成否が決定されるからである。
 国民的映画「男はつらいよ・第一作」を例にとろう。山田洋次監督は敬愛する黒澤明映画の中心俳優・志村喬を特別出演として迎えた。場面は主人公寅次郎の妹の結婚披露宴。息子と疎遠になっていた新郎の父親の挨拶。無口で不愛想に見えた大学教授は訥々と語りだす。『この八年間は、私達にとって長い長い、冬でした。…そして今ようやく皆様のおかげで春を迎えられます。…』心の底から絞り出すような言葉に“寅さん”は心打たれ、映画の流れはがらりと変わる。出演時間数分のシーン、わずか数行のセリフだが、俳優の演技力と存在感でその人物の実在感がスクリーンいっぱいに表された。監督が配役にかけた思いが実ったのである。
国民的映画「男はつらいよ・第一作」を例にとろう。山田洋次監督は敬愛する黒澤明映画の中心俳優・志村喬を特別出演として迎えた。場面は主人公寅次郎の妹の結婚披露宴。息子と疎遠になっていた新郎の父親の挨拶。無口で不愛想に見えた大学教授は訥々と語りだす。『この八年間は、私達にとって長い長い、冬でした。…そして今ようやく皆様のおかげで春を迎えられます。…』心の底から絞り出すような言葉に“寅さん”は心打たれ、映画の流れはがらりと変わる。出演時間数分のシーン、わずか数行のセリフだが、俳優の演技力と存在感でその人物の実在感がスクリーンいっぱいに表された。監督が配役にかけた思いが実ったのである。 クラシック音楽に話を戻そう。映画・演劇における脚本の台詞と同様に、歌曲や歌劇の詞にも創作者の魂が込められている。したがって、声楽家はその詞(ことば)を全身で受け止め自身が共感しその人物を体現できる状態になってから楽曲に向かってほしいのである。
山田耕筰は少年時代、教会の施設で過ごし孤独な日々を過ごした。活版工場で働きながら夜学に通った。自伝で「工場でつらい目に遭うと、からたちの垣根まで逃げ出して泣いた」と書いているが、この思い出をもとに北原白秋が作詞し山田が作曲して『からたちの花』が生まれる。

からたちの花が咲いたよ 白い白い花が咲いたよ
からたちのとげはいたいよ 青い青い針のとげだよ
…
人間はつらい思いをしても暗い顔をしているとは限らない。むしろ表面的には明るくふるまうことが多い。内面に寂しさや切なさを抱きながらも笑顔を見せるものだ。この『からたちの花』の歌唱に当たっては、やさしく美しく歌いつつも「人物の孤独と痛み」を心の中いっぱいに広げておいてほしい。何人もの有名歌手の演奏に接してきたが、美しいソプラノを聴かせてもらえても、人物が「白い花が咲いたよ」「とげはいたいよ」とニコッとするイメージは現れないし、無邪気な笑顔の陰にある寂しさを想像させてはくれない。なぜなのか。声楽家としての「詞に接する姿勢」と「自らと詞の世界との共振」が問われることになる。












 有名なのはセルゲイ・ラフマニノフの『ヴォーカリーズ』(作品34-14)だ。初演のコンサート(1916年2月6日・モスクワ)では、ピアニストとしても高名な作曲者自身の伴奏で、ソプラノ歌手アントニーナ・ネジターノヴァが歌唱している。ロシア音楽の愁いを底流に、バロック音楽の「紡ぎ出しのモチーフ」などの西欧的な技法が施された傑作である。
有名なのはセルゲイ・ラフマニノフの『ヴォーカリーズ』(作品34-14)だ。初演のコンサート(1916年2月6日・モスクワ)では、ピアニストとしても高名な作曲者自身の伴奏で、ソプラノ歌手アントニーナ・ネジターノヴァが歌唱している。ロシア音楽の愁いを底流に、バロック音楽の「紡ぎ出しのモチーフ」などの西欧的な技法が施された傑作である。 ラフマニノフがこの言葉のない歌曲を初演者の彼女に献呈するにあたって、『あなたの美しい声とその表現力があれば、言葉なんかいらない』と語ったと伝えられている。ここに声楽という音楽芸術の本質の一端が示されている。優れた楽曲とその世界を深く理解し豊かに魅力的に歌唱できれば、詞がなくとも音楽は成立するだろう。というより、この『ヴォーカリーズ』は詞が存在しないがゆえに、ロシア語の制約を受けることがない。そのため、管弦楽版への編曲や様々な調性にアレンジされ、ラフマニノフの他のどの歌曲よりもよく知られることになったのである。音楽にとって言語は必要条件ではないし、声楽も詞がなくても成立するケースと言えるだろう。
ラフマニノフがこの言葉のない歌曲を初演者の彼女に献呈するにあたって、『あなたの美しい声とその表現力があれば、言葉なんかいらない』と語ったと伝えられている。ここに声楽という音楽芸術の本質の一端が示されている。優れた楽曲とその世界を深く理解し豊かに魅力的に歌唱できれば、詞がなくとも音楽は成立するだろう。というより、この『ヴォーカリーズ』は詞が存在しないがゆえに、ロシア語の制約を受けることがない。そのため、管弦楽版への編曲や様々な調性にアレンジされ、ラフマニノフの他のどの歌曲よりもよく知られることになったのである。音楽にとって言語は必要条件ではないし、声楽も詞がなくても成立するケースと言えるだろう。 また、クラシック音楽ばかりでなく大衆音楽のジャズでも「スキャット」という歌詞のない表現があるし、意味言語によらない「歌」で聴衆を惹きつけたシャンソン歌手のエピソードも残っている。パリにある場末のレストランで、外国人観光客に声を掛けられた流しの歌手が、彼らのテーブルを回りながら情感をこめて哀感漂う世界を歌って聴かせた。フランス語の分からない観光客はハンカチを取り出しながら訊ねた―『今のは何という歌なの?詞の意味は?』流しの男はいたずらっぽく手にしていたメニューを開いて見せ、『ここに載っている料理を片っ端から歌ったのです』…。
また、クラシック音楽ばかりでなく大衆音楽のジャズでも「スキャット」という歌詞のない表現があるし、意味言語によらない「歌」で聴衆を惹きつけたシャンソン歌手のエピソードも残っている。パリにある場末のレストランで、外国人観光客に声を掛けられた流しの歌手が、彼らのテーブルを回りながら情感をこめて哀感漂う世界を歌って聴かせた。フランス語の分からない観光客はハンカチを取り出しながら訊ねた―『今のは何という歌なの?詞の意味は?』流しの男はいたずらっぽく手にしていたメニューを開いて見せ、『ここに載っている料理を片っ端から歌ったのです』…。 しかし、大粒のダイヤモンドは宝石の山の1%にも満たないとすれば、その大半を占める宝石群の存在にこそオペラ芸術や声楽が内包する課題や可能性、そして新たな魅力が隠されているに違いない。小粒の宝石ながら、聴衆の心を打つティーバ(歌姫)はいる。エメラルド・サファイア・ルビー…それぞれに美しく輝くソリストたちがいるし、メゾソプラノ・アルトの声楽家たちはソプラノとは別の魅力をオペラ劇場や音楽ホールで表現している。男性歌手は、20世紀にその名を轟かした「三大テノール」ばかりではない。世界各国で活躍する逸材がテノール・バリトン・バスそれぞれの声域の魅力を聴く人に届けている。
しかし、大粒のダイヤモンドは宝石の山の1%にも満たないとすれば、その大半を占める宝石群の存在にこそオペラ芸術や声楽が内包する課題や可能性、そして新たな魅力が隠されているに違いない。小粒の宝石ながら、聴衆の心を打つティーバ(歌姫)はいる。エメラルド・サファイア・ルビー…それぞれに美しく輝くソリストたちがいるし、メゾソプラノ・アルトの声楽家たちはソプラノとは別の魅力をオペラ劇場や音楽ホールで表現している。男性歌手は、20世紀にその名を轟かした「三大テノール」ばかりではない。世界各国で活躍する逸材がテノール・バリトン・バスそれぞれの声域の魅力を聴く人に届けている。 新たなオペラユニット創設のキッカケとなった演奏(歌唱)鑑賞の数分間の体験。その感動と共感はどこから来たものだったのだろう。舞台で歌うソプラノ歌手と客席で見つめ耳を澄ます自分(聴衆)。両者を結びつけるのは音楽と歌唱。そこに描き出された世界(=主人公の心情と状況)を共有できたからに違いない。
新たなオペラユニット創設のキッカケとなった演奏(歌唱)鑑賞の数分間の体験。その感動と共感はどこから来たものだったのだろう。舞台で歌うソプラノ歌手と客席で見つめ耳を澄ます自分(聴衆)。両者を結びつけるのは音楽と歌唱。そこに描き出された世界(=主人公の心情と状況)を共有できたからに違いない。
 この「オペラ座ライブ」はマリア・カラスのレパートリーを中心としたプログラム構成である。第一部はカラスの持ち役である『ノルマ』の代表曲をはじめ、ご当地パリに縁の深い『イル・トロヴァトーレ』『セビリアの理髪師』のヒロインたちを演唱している。物語の舞台は、紀元前のローマ帝国支配下ガリア地方(現在のフランス)からピレネー山脈(現在のスペイン・アラゴン地方)、そしてフランス革命直前に発表されたボーマルシェのフィガロ三部作の一作目へ。
この「オペラ座ライブ」はマリア・カラスのレパートリーを中心としたプログラム構成である。第一部はカラスの持ち役である『ノルマ』の代表曲をはじめ、ご当地パリに縁の深い『イル・トロヴァトーレ』『セビリアの理髪師』のヒロインたちを演唱している。物語の舞台は、紀元前のローマ帝国支配下ガリア地方(現在のフランス)からピレネー山脈(現在のスペイン・アラゴン地方)、そしてフランス革命直前に発表されたボーマルシェのフィガロ三部作の一作目へ。 演劇人の私が『トスカ』というオペラに惹かれるのは、原典が戯曲で劇構造がしっかりした作品だからであろう。以前、私はTVでの放映がキッカケでこの名作を知り、1枚のDVDを買い求めた。NHKの企画制作による【伝説のイタリア・オペラ・ライヴ・シリーズ プッチーニ:歌劇「トスカ」全曲(1961年10月22日東京文化会館でのライヴ)】である。トスカを演じているのはレナータ・テバルディ、「マリア・カラスと人気を二分する世紀の大プリマ・ドンナ」であった。劇中の人物・ヒロインとして、私はカラスよりもむしろテバルディに惹かれた。アリアの名曲『歌に生き、恋に生き』はまさにトスカの心の真実、魂の響きのように聞こえた。
演劇人の私が『トスカ』というオペラに惹かれるのは、原典が戯曲で劇構造がしっかりした作品だからであろう。以前、私はTVでの放映がキッカケでこの名作を知り、1枚のDVDを買い求めた。NHKの企画制作による【伝説のイタリア・オペラ・ライヴ・シリーズ プッチーニ:歌劇「トスカ」全曲(1961年10月22日東京文化会館でのライヴ)】である。トスカを演じているのはレナータ・テバルディ、「マリア・カラスと人気を二分する世紀の大プリマ・ドンナ」であった。劇中の人物・ヒロインとして、私はカラスよりもむしろテバルディに惹かれた。アリアの名曲『歌に生き、恋に生き』はまさにトスカの心の真実、魂の響きのように聞こえた。