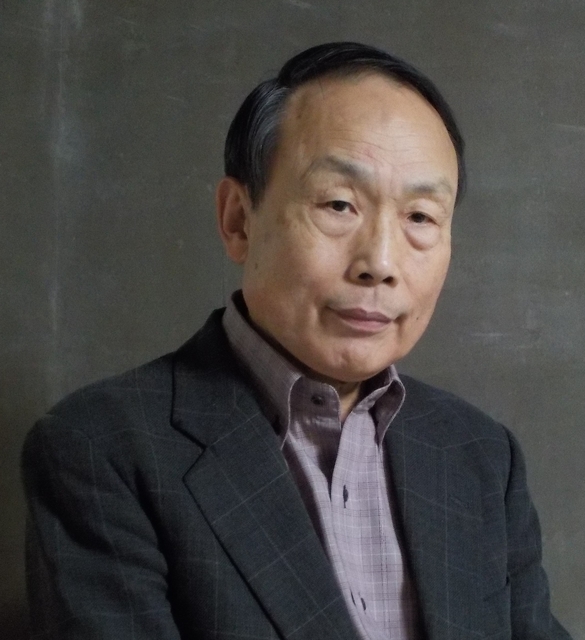満席。場内の照明が弱まり、ピンスポットがマエストロを浮かび上がらせオケピの指揮台へ導く。聴衆のざわめきが拍手に変わる。
第一幕
第一場
テーマ音楽。
劇場内に闇が広がる。音楽「民衆のソング」。徐々に舞台に光線が射しこんでくる。
静止していたオブジェのような塊(民衆八名)が動き出し平舞台いっぱいに広がる。
〈ソング&ダンス〉がダイナミックに展開される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
劇場内に闇が広がる。音楽「民衆のソング」。徐々に舞台に光線が射しこんでくる。
静止していたオブジェのような塊(民衆八名)が動き出し平舞台いっぱいに広がる。
〈ソング&ダンス〉がダイナミックに展開される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二場 エルシノア城下の空き地
つむじ風が吹き荒れ、木の葉やゴミが舞い踊っている。
素っ頓狂な声やざわめきとともに、平舞台に光が入る。
ある日。
肉屋、肉屋の女房、パン屋、酒屋、酒屋の女房、大工、鍛冶屋が、噂話にうつつを抜かしている。
離れた所で、伝令が竪笛を吹いている。
肉屋の女房: な、なんだって~!王妃様と王様の弟が?
酒屋: (伝令を気にして)こ、声がでかいよ!
パン屋: (声を潜めて)ホ、ホントか?
酒屋の女房: くっ、へっへっへ……。驚いたかい?
肉屋: ……まさかぁ。
大工: いや、火のない所に煙は立たぬ。王族貴族でも人は人、高貴な方でも男と女、あってもおかしくない話。
肉屋の女房: 王妃様と王様の弟が……ふ~ん。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・第一の物語はクローディアスとガートルードの物語であり、シェイクスピアが『ハムレット』で描くことのなかった彼らの致命的な愛情を切なくも美しく描き出している。
・第二の物語は、第二幕第七場で執事アルバートの求婚が女官長マリーに受け入れられた瞬間に突然前景化され、この作品を悲劇のモードから喜劇のそれへと変貌させている。
・これらふたつの物語を覆い包む形で、常に平舞台にいる民衆の物語がある。彼らは国の政治や戦争に常に生活を左右されながらも、王侯貴族のスキャンダルを楽しむたくましさも持っている。
【安田比呂志氏(イギリス文学・シェイクスピア/開智国際大学教授)/「雪女とオフィーリア、そしてクローディアス 東京ミニオペラカンパニーの挑戦」(2019年8月・幻冬舎刊)249~250ページ所収】

・…すでに触れた通り、オペレッタの場合、朗唱やレチタティーヴォは全くなく、会話や独白には普通の会話が使われる。(中略)大衆的で親しみやすい台詞が挿入されるものの、単なるオペレッタ形式に留まることなく、叙事詩風の合唱がさらに重要な役割を果たすことになる。しかし『雪女の恋』と異なり、「日本の民話」に拠らないため、いわゆる『夕鶴』に始まる「創作オペラ」には該当しない。すなわち、『クローディアスなのか、ガートルードなのか』は、おそらく日本の創作オペラ史上、異色の作品の一つになるのではないか。近い将来上演されることが望まれる。
【森佳子氏(音楽学・オペラ研究/早稲田大学ほか講師 )/同著247~248ページ所収】
演劇人である筆者がオペラ創作にシフトした切っ掛けは音楽が感性に直接訴えかける力であった。演劇は言葉を武器とする以上、音楽の分野としては器楽ではなく言葉を伴う「声楽」となる。そして「歌」は、クラシック音楽から大衆音楽まで幅は広い。となると、それら表現の多様性に惹かれるのは自然の成り行きであった。オペラのアリアは「王と王妃」に、オペレッタのデュエットは「女官長と執事」に、ソングは「民衆」によって歌われる。しかも、この三層における物語は時間的にシンクロしていて「城内と城外」で同時に起きている…これは面白いはずと考えたのが執筆動機であった。

この作品は「雪女とオフィーリア、そしてクローディアス 東京ミニオペラカンパニーの挑戦」(2019年8月・幻冬舎刊)出版の際に、将来の上演を目論んで書き下ろした脚本である。同著所収の『悲戀~ハムレットとオフィーリア』(2016年9月・JTアートホールアフィニス)『雪女の恋』(2019年2月・東京文化会館小ホール)は筆者主宰のカンパニーで上演可能であったが、この『喜歌劇 クローディアスなのか、ガートルードなのか』は大作で、しかもオペラ・オペレッタ/ミュージカル・ストレートプレイの3ジャンルの人材を必要とするため、広いネットワークと莫大な製作費が必須なので、興行会社(東宝や松竹)の主催公演でなければ不可能と考えられ、現時点では未上演となっているのだ。
暦がめくられ、新年となった今、作者として「『喜歌劇 クローディアスなのか、ガートルードなのか』初演」を夢見ている次第である。
※写真(中)は、「シェイクスピア時代のイギリス生活百科」(2017年・河出書房新社発行)の表紙から。














 一方、こうした超一流の名人たちとは別の「一流」も存在している。有名人ではないが知る人ぞ知るいわば隠れた名人――そのひとりが柳家さん喬である。五代目柳家小さん門下では出世が遅く本年75歳になって「落語協会会長」に就任している。
一方、こうした超一流の名人たちとは別の「一流」も存在している。有名人ではないが知る人ぞ知るいわば隠れた名人――そのひとりが柳家さん喬である。五代目柳家小さん門下では出世が遅く本年75歳になって「落語協会会長」に就任している。 柳家さん喬は、演目との相性という点では歴代の名人たちに引けを取らない。江戸落語の名作『死神』などを含めて「庶民のありのままの姿」「生きる上での願いや追い詰められた際の本音」「人間の油断と愚かさ」「命の尊さと悲しさ」の描写においては一流である。この人の「ニン(人柄・器量)に合っている」演目に限っては、超一流の名人たちも指をくわえて見つめるしかないと思える。
柳家さん喬は、演目との相性という点では歴代の名人たちに引けを取らない。江戸落語の名作『死神』などを含めて「庶民のありのままの姿」「生きる上での願いや追い詰められた際の本音」「人間の油断と愚かさ」「命の尊さと悲しさ」の描写においては一流である。この人の「ニン(人柄・器量)に合っている」演目に限っては、超一流の名人たちも指をくわえて見つめるしかないと思える。



 有史以来、一人ではなくむしろ集団で歌われる歌と踊りが世界各地で伝承され今も民族の伝統として残っているが、紀元前のギリシャでは、それが国家的行事としての演劇に発展し野外劇場が建設された。そこで演じられるギリシャ古典劇に欠かせない存在が舞踊合唱隊=コロス(15名)であり、「コーラス」の語源となっている。名作『オイディプス王』の場合、疫病が蔓延している現状を嘆き、主人公の王に訴え、劇の進行を担う民衆役として登場する。
有史以来、一人ではなくむしろ集団で歌われる歌と踊りが世界各地で伝承され今も民族の伝統として残っているが、紀元前のギリシャでは、それが国家的行事としての演劇に発展し野外劇場が建設された。そこで演じられるギリシャ古典劇に欠かせない存在が舞踊合唱隊=コロス(15名)であり、「コーラス」の語源となっている。名作『オイディプス王』の場合、疫病が蔓延している現状を嘆き、主人公の王に訴え、劇の進行を担う民衆役として登場する。 2019年2月25日、東京文化会館小ホールで上演された「東京ミニオペラカンパニー公演№2『雪女の恋 二幕』(作曲:鳥井俊之・指揮:佐藤宏充・演出:十川稔)」では、12名の混声合唱団が、日本語を大切にする指揮者の期待に応え見事な和声を聴かせた。
2019年2月25日、東京文化会館小ホールで上演された「東京ミニオペラカンパニー公演№2『雪女の恋 二幕』(作曲:鳥井俊之・指揮:佐藤宏充・演出:十川稔)」では、12名の混声合唱団が、日本語を大切にする指揮者の期待に応え見事な和声を聴かせた。

 ピアフは、自身が作詞家でもある。『愛の讃歌』『バラ色の人生』は彼女の心からほとばしり出た言葉に曲が付けられて生まれた作品である。したがって本質的にはシンガーソングライターに近いと言えるだろう。日本でもフォークソング・ニューミュージック・ロックのブームを巻き起こした歌手たちは自分自身の内面を自分の言葉で歌った。演じるのではない。いわば、マイクに向かって己をさらけ出したのである。
ピアフは、自身が作詞家でもある。『愛の讃歌』『バラ色の人生』は彼女の心からほとばしり出た言葉に曲が付けられて生まれた作品である。したがって本質的にはシンガーソングライターに近いと言えるだろう。日本でもフォークソング・ニューミュージック・ロックのブームを巻き起こした歌手たちは自分自身の内面を自分の言葉で歌った。演じるのではない。いわば、マイクに向かって己をさらけ出したのである。 他方、ひばりは、自身が女優でもあった。作詞家・作曲家の手による作品を演じる。己を消し主人公の女になりきって歌い、エンディングになると「美空ひばり」に戻る。「加藤和枝」本人をさらけ出すことはしない。だが、詞に描かれている女を歌う時、ひばり本人の内面と無関係ということではない。『悲しい酒』の涙について、『…あの時はね、小さいころのつらかった出来事を思い出しているのよ。』と語っている。それを「女の涙」に見せるところがプロなのである。俳優が毎回の舞台において「涙」を自在にコントロールしているのと同様である。
他方、ひばりは、自身が女優でもあった。作詞家・作曲家の手による作品を演じる。己を消し主人公の女になりきって歌い、エンディングになると「美空ひばり」に戻る。「加藤和枝」本人をさらけ出すことはしない。だが、詞に描かれている女を歌う時、ひばり本人の内面と無関係ということではない。『悲しい酒』の涙について、『…あの時はね、小さいころのつらかった出来事を思い出しているのよ。』と語っている。それを「女の涙」に見せるところがプロなのである。俳優が毎回の舞台において「涙」を自在にコントロールしているのと同様である。 マリア・カラスがなぜ不世出の歌姫なのか。天与の音楽的才能ばかりではない。人間的孤独、オペラ界での紆余曲折、女性としての葛藤、それらが生み出した魂の叫びが「歌詞」を生きた言葉にしたのである。※参照:当ブログ2009/05/03 16:13:50 カテゴリー:随想/映画『マリア・カラスの真実』を観る
マリア・カラスがなぜ不世出の歌姫なのか。天与の音楽的才能ばかりではない。人間的孤独、オペラ界での紆余曲折、女性としての葛藤、それらが生み出した魂の叫びが「歌詞」を生きた言葉にしたのである。※参照:当ブログ2009/05/03 16:13:50 カテゴリー:随想/映画『マリア・カラスの真実』を観る