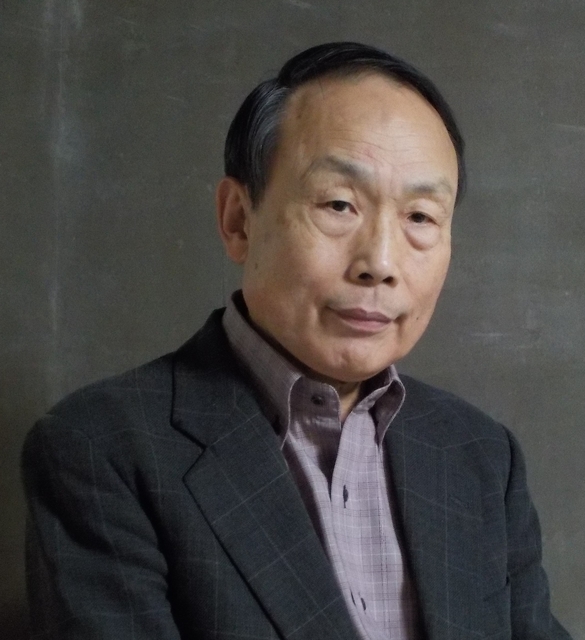早稲田大学文学部へ進学したのは、演劇理論や演劇史を学ぶためだった。高校時代、そして、卒業後3年間羽田空港で肉体労働に従事しながら私は演劇活動に身を投じていたので、演劇の実際については自らの経験の積み重ねによって会得しようと考えていた。その1965年以降の激動の数十年は、翻訳劇や創作劇の公演を横須賀・横浜・東京で主催していたのだが、改めて演劇に関する理論面での刺激が欲しくなっていた。
 ちょうどその頃、知遇を得た毛利先生から「西洋比較演劇研究会(日本演劇学会分科会)」へのお誘いがあった。私は、渡りに船で、月1回の例会に参加させていただくようになった。会場は、成城大学の会議室で、成城の毛利先生と慶応義塾の斎藤先生を中心に、豊かな知見を持った教授たちが見守る中、若手の演劇研究者たちが活発な議論を展開していた。そこは私にとって「第二の大学」となり、新たな人脈作りと交流の場となったのである。
ちょうどその頃、知遇を得た毛利先生から「西洋比較演劇研究会(日本演劇学会分科会)」へのお誘いがあった。私は、渡りに船で、月1回の例会に参加させていただくようになった。会場は、成城大学の会議室で、成城の毛利先生と慶応義塾の斎藤先生を中心に、豊かな知見を持った教授たちが見守る中、若手の演劇研究者たちが活発な議論を展開していた。そこは私にとって「第二の大学」となり、新たな人脈作りと交流の場となったのである。
現在の「西洋比較演劇研究会」は、当時の若手が今は中堅となって運営されているが、毛利先生と齋藤先生の信頼厚いタッグは今も力強く組まれている。去る6月18日、成城大学で「AMDの会」が開催された。この会は「西洋比較演劇研究会」の前身で、演劇研究論文・翻訳・舞台の合評とシンポジウムなどを機関誌に掲載していたのだが、その足跡をまとめた本が出版された。 「演劇を問う、批評を問う―ある演劇研究集団の試み」平井正子(※成城大学名誉教授)編・論創社刊、帯に「斎藤偕子傘寿記念出版」とある。「AMDの会」は、<モダン・ドラマの会>で、大学人ばかりでなく演出家や俳優、舞台スタッフなど演劇人も参加してその時々の舞台の批評をする場となっていたようだ。上掲の本の巻頭言で毛利先生は次のように述べている。
「演劇を問う、批評を問う―ある演劇研究集団の試み」平井正子(※成城大学名誉教授)編・論創社刊、帯に「斎藤偕子傘寿記念出版」とある。「AMDの会」は、<モダン・ドラマの会>で、大学人ばかりでなく演出家や俳優、舞台スタッフなど演劇人も参加してその時々の舞台の批評をする場となっていたようだ。上掲の本の巻頭言で毛利先生は次のように述べている。
…演劇上演の成立に観客が不可欠要素であると言いながら、…世に行われている演劇批評では、集合的な観客の反応/批評が具体的に示されることは稀で、それが批評家の意識に登ることさえ滅多にない。舞台に対する複数観客の集合的批評は、通常の、一人の批評家の反応を記す演劇批評とはまったく異なるものとなるに違いないが、たとえば、観客間で対立する反応がされたとき、それを上演後の批評として公にするにはどうすればいいか。…<AMD>や西洋比較演劇研究会の例会では、舞台合評や、特別な主題による討論会をしばしば開催したが、そこでは沸騰した議論の見られるのが常であった。そして、それをいつも先導していたのは斎藤さんで、彼女が、特に演劇批評のあり方に関心を持っていたのは、演劇研究者として大学で教える傍ら、著名な演劇批評家として健筆をふるっていたことから、当然であるとも言えるだろう。…
ところで、「AMDの会」は久しぶりに再開され、先日の会では、翻訳家・演出家の石澤秀二氏<劇作家・田中千禾夫をめぐって>を柱に、演劇現場に身を置く人や大学教員たちの活発な意見が飛び交い、会の終了後は、飲み物と軽食を楽しみながら交流と語らいが続けられた。 かつての演劇青年たちの髪にも白いものが混じってきたが、次回のテーマについて熱い発言が止まることはなかった。
かつての演劇青年たちの髪にも白いものが混じってきたが、次回のテーマについて熱い発言が止まることはなかった。
 ちょうどその頃、知遇を得た毛利先生から「西洋比較演劇研究会(日本演劇学会分科会)」へのお誘いがあった。私は、渡りに船で、月1回の例会に参加させていただくようになった。会場は、成城大学の会議室で、成城の毛利先生と慶応義塾の斎藤先生を中心に、豊かな知見を持った教授たちが見守る中、若手の演劇研究者たちが活発な議論を展開していた。そこは私にとって「第二の大学」となり、新たな人脈作りと交流の場となったのである。
ちょうどその頃、知遇を得た毛利先生から「西洋比較演劇研究会(日本演劇学会分科会)」へのお誘いがあった。私は、渡りに船で、月1回の例会に参加させていただくようになった。会場は、成城大学の会議室で、成城の毛利先生と慶応義塾の斎藤先生を中心に、豊かな知見を持った教授たちが見守る中、若手の演劇研究者たちが活発な議論を展開していた。そこは私にとって「第二の大学」となり、新たな人脈作りと交流の場となったのである。
現在の「西洋比較演劇研究会」は、当時の若手が今は中堅となって運営されているが、毛利先生と齋藤先生の信頼厚いタッグは今も力強く組まれている。去る6月18日、成城大学で「AMDの会」が開催された。この会は「西洋比較演劇研究会」の前身で、演劇研究論文・翻訳・舞台の合評とシンポジウムなどを機関誌に掲載していたのだが、その足跡をまとめた本が出版された。
 「演劇を問う、批評を問う―ある演劇研究集団の試み」平井正子(※成城大学名誉教授)編・論創社刊、帯に「斎藤偕子傘寿記念出版」とある。「AMDの会」は、<モダン・ドラマの会>で、大学人ばかりでなく演出家や俳優、舞台スタッフなど演劇人も参加してその時々の舞台の批評をする場となっていたようだ。上掲の本の巻頭言で毛利先生は次のように述べている。
「演劇を問う、批評を問う―ある演劇研究集団の試み」平井正子(※成城大学名誉教授)編・論創社刊、帯に「斎藤偕子傘寿記念出版」とある。「AMDの会」は、<モダン・ドラマの会>で、大学人ばかりでなく演出家や俳優、舞台スタッフなど演劇人も参加してその時々の舞台の批評をする場となっていたようだ。上掲の本の巻頭言で毛利先生は次のように述べている。…演劇上演の成立に観客が不可欠要素であると言いながら、…世に行われている演劇批評では、集合的な観客の反応/批評が具体的に示されることは稀で、それが批評家の意識に登ることさえ滅多にない。舞台に対する複数観客の集合的批評は、通常の、一人の批評家の反応を記す演劇批評とはまったく異なるものとなるに違いないが、たとえば、観客間で対立する反応がされたとき、それを上演後の批評として公にするにはどうすればいいか。…<AMD>や西洋比較演劇研究会の例会では、舞台合評や、特別な主題による討論会をしばしば開催したが、そこでは沸騰した議論の見られるのが常であった。そして、それをいつも先導していたのは斎藤さんで、彼女が、特に演劇批評のあり方に関心を持っていたのは、演劇研究者として大学で教える傍ら、著名な演劇批評家として健筆をふるっていたことから、当然であるとも言えるだろう。…

ところで、「AMDの会」は久しぶりに再開され、先日の会では、翻訳家・演出家の石澤秀二氏<劇作家・田中千禾夫をめぐって>を柱に、演劇現場に身を置く人や大学教員たちの活発な意見が飛び交い、会の終了後は、飲み物と軽食を楽しみながら交流と語らいが続けられた。
 かつての演劇青年たちの髪にも白いものが混じってきたが、次回のテーマについて熱い発言が止まることはなかった。
かつての演劇青年たちの髪にも白いものが混じってきたが、次回のテーマについて熱い発言が止まることはなかった。