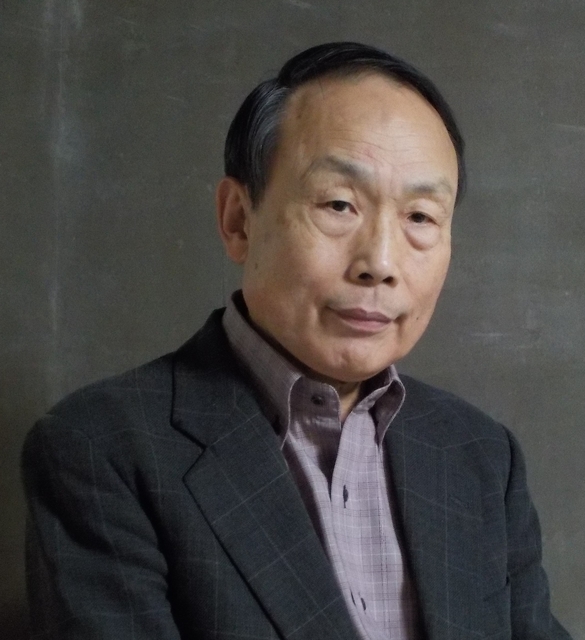県立神奈川総合高校が輩出した人材は各界で活躍しているが、私が10年ほど舞台系講師を務めた間に出会ったかつての生徒たちも、今、芸術分野で注目を集める存在になっている。

その一人、コンテンポラリーダンスのボヴェ太郎(http://tarobove.com)の公演が、世田谷美術館の主催で行なわれた。ひんやりとした気品のある大理石のエントランスホール、広い床面には透明のアクリル板が演技空間を切り取っている。仄かな光の中に浮かび上がるボヴェの身体。ゆるやかな動きは美しく、かつ内面のエネルギー・思念があふれ出る…固唾を呑んで見つめる満場の観客たち。
Setagaya Art Museum Trance/Entrance vol.7
『ボヴェ太郎|in statu nascendi』
2009.3.7.世田谷美術館エントランスホール
ボヴェ太郎は神奈川総合高校3期生だが、現在、東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科に在学中の村上史郎は、10期生である。作曲家であり打楽器演奏家でもある彼の企画が、今回、学内公募の最優秀作品に選ばれた。新奏楽堂十周年を記念しての公演だけに、関係者の一人として嬉しい限りである。史郎君は、「演劇ユニット 東京ドラマポケット」に参加している仲間で、昨夏の『音楽演劇 オフィーリアのかけら』では、音楽助監督を務め、パーカッションを担当してくれた。
明治を髣髴とさせる格調高い旧奏楽堂に対して、新奏楽堂はモダンなデザインで1000名収容の本格的音 楽ホールである。小泉八雲・志賀直哉・折口信夫の作品を素材に、オーケストラ音楽と演劇・舞踊・人形が織りなす刺激的な世界…会場を埋め尽くした観客・聴衆たちはカーテンコールで、『ブラボー!』と拍手を何度も贈った。
楽ホールである。小泉八雲・志賀直哉・折口信夫の作品を素材に、オーケストラ音楽と演劇・舞踊・人形が織りなす刺激的な世界…会場を埋め尽くした観客・聴衆たちはカーテンコールで、『ブラボー!』と拍手を何度も贈った。
藝大二十一 奏楽堂十周年 第四回「奏楽堂企画学内公募」最優秀企画
『怪談~前衛音楽が語る怪奇な物語~』
2009.3.14.東京藝術大学奏楽堂
■公式サイト:http://geidai.kimodameshi.com/
活躍する二人を支えているのも、神奈川総合高校の卒業生たちだ。ボヴェ太郎の公演では照明:深瀬元喜(1期生)。村上史郎の企画作品では出演:甲斐田裕子(1期生)、美術・照明:青木拓也(5期生)、演奏者統括/ヴィオラ:神原いづみ(10期生)。皆、プロとして活動し、将来を嘱望されている新進芸術家たちである。
*写真上は、ボヴェ太郎公演のチラシ。写真下右は、藝大学内公募公演のチラシ、新奏楽堂と旧奏楽堂の外観。

その一人、コンテンポラリーダンスのボヴェ太郎(http://tarobove.com)の公演が、世田谷美術館の主催で行なわれた。ひんやりとした気品のある大理石のエントランスホール、広い床面には透明のアクリル板が演技空間を切り取っている。仄かな光の中に浮かび上がるボヴェの身体。ゆるやかな動きは美しく、かつ内面のエネルギー・思念があふれ出る…固唾を呑んで見つめる満場の観客たち。
Setagaya Art Museum Trance/Entrance vol.7
『ボヴェ太郎|in statu nascendi』
2009.3.7.世田谷美術館エントランスホール

ボヴェ太郎は神奈川総合高校3期生だが、現在、東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科に在学中の村上史郎は、10期生である。作曲家であり打楽器演奏家でもある彼の企画が、今回、学内公募の最優秀作品に選ばれた。新奏楽堂十周年を記念しての公演だけに、関係者の一人として嬉しい限りである。史郎君は、「演劇ユニット 東京ドラマポケット」に参加している仲間で、昨夏の『音楽演劇 オフィーリアのかけら』では、音楽助監督を務め、パーカッションを担当してくれた。
明治を髣髴とさせる格調高い旧奏楽堂に対して、新奏楽堂はモダンなデザインで1000名収容の本格的音
 楽ホールである。小泉八雲・志賀直哉・折口信夫の作品を素材に、オーケストラ音楽と演劇・舞踊・人形が織りなす刺激的な世界…会場を埋め尽くした観客・聴衆たちはカーテンコールで、『ブラボー!』と拍手を何度も贈った。
楽ホールである。小泉八雲・志賀直哉・折口信夫の作品を素材に、オーケストラ音楽と演劇・舞踊・人形が織りなす刺激的な世界…会場を埋め尽くした観客・聴衆たちはカーテンコールで、『ブラボー!』と拍手を何度も贈った。藝大二十一 奏楽堂十周年 第四回「奏楽堂企画学内公募」最優秀企画
『怪談~前衛音楽が語る怪奇な物語~』

2009.3.14.東京藝術大学奏楽堂
■公式サイト:http://geidai.kimodameshi.com/
活躍する二人を支えているのも、神奈川総合高校の卒業生たちだ。ボヴェ太郎の公演では照明:深瀬元喜(1期生)。村上史郎の企画作品では出演:甲斐田裕子(1期生)、美術・照明:青木拓也(5期生)、演奏者統括/ヴィオラ:神原いづみ(10期生)。皆、プロとして活動し、将来を嘱望されている新進芸術家たちである。
*写真上は、ボヴェ太郎公演のチラシ。写真下右は、藝大学内公募公演のチラシ、新奏楽堂と旧奏楽堂の外観。