私は年の割に歯が丈夫です。若い折は、アサリを殻ごと食べることができるかどうかで賭けをし、見事、勝ったりしたこともあります。もちろん昨今はそんな無茶なことはしません。
ただし、若さにかまけ、人の下宿を泊まり歩いていてろくすっぽ歯も磨かなかった時期があり、その頃に虫歯にやられた歯が2、3本あって詰め物などしてあるのですが、50代以降は歯科医へいっても歯垢をとってもらったり、少しぐらついているものを固定してもらったりぐらいの治療で済んでいます。
特別なケアーはしていません。強いていうと、歯科医などで指導を受けるよりも強い力で磨きます。したがって、歯ブラシの毛の部分がすぐそっくり返ってきます。
しかし、どういうわけか、いま使っているものは使い始めてある程度経ち、相変わらず力を込めて磨いているのにかかわらず、形状が変化してきません。
道具に無頓着な私は、これをどこで手に入れたのかまったく覚えていないのですが、どこかで買った覚えはありませんから、おそらく、一昨年の秋、中国へ旅したときに太原か北京のホテルから持ってきたものだろうと思います。
中国産は粗悪だとイメージが、それもかなり一般的な固定観念を伴ってあるようですが、この歯ブラシについては感心するぐらい使い勝手がいいのです。
なお、中国産に神経質になっている向きも、実際には気が付かないところでそれと知らぬままその製品を使っている場合が多いと思います。
私の場合は、正直言って、食品に関してはいくぶん神経質ですが、その他はさほど気にしていません。
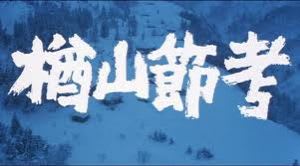

歯といえば、今村昌平の映画『楢山節考』(原作:深沢七郎)の主人公「おりん」が、老いてもなお丈夫な歯を持つことを自分の孫にからかわれ、石にその前歯をあてがって自ら砕くシーンがあります。
それは、自らの老いを完成し、山村共同体の掟に従って死にゆく己の定めを確固として成就しようとする決意の一環を示しています。
おりんがお山へ行く(=棄却される)のは七〇歳だといわれているのですが、この私は、それを数年過ぎても、なおかつ自分の歯をいたわっているのです。
思えば、歯が丈夫であることは、おりんにとってはもう残っていてはならない「若さ」の象徴であり、したがって、やがて消滅すべき身には、あってはならない恥ずべきものとして砕かれねばならなかったのですが、しつこくもまだ生き延びようとする私にとっては、やはりそれは私の中に残る若さの残像として、保存されねばならないものなのです。


とはいえ、雪の山でひっそりとその生を終えるという美学にも何がしか惹かれるものがあります。ただし、私の場合は、極上のスコッチを一本持たせてほしいと思うのですが。
おりんの毅然とした「おやま参り」(=棄却)に対し、まったく反するような映画を、今村昌平の長男、天願大介が撮っているのですが(『デンデラ』2011年)、もう、すでに長くなりすぎましたので、それについてはまた次回。
ただし、若さにかまけ、人の下宿を泊まり歩いていてろくすっぽ歯も磨かなかった時期があり、その頃に虫歯にやられた歯が2、3本あって詰め物などしてあるのですが、50代以降は歯科医へいっても歯垢をとってもらったり、少しぐらついているものを固定してもらったりぐらいの治療で済んでいます。
特別なケアーはしていません。強いていうと、歯科医などで指導を受けるよりも強い力で磨きます。したがって、歯ブラシの毛の部分がすぐそっくり返ってきます。
しかし、どういうわけか、いま使っているものは使い始めてある程度経ち、相変わらず力を込めて磨いているのにかかわらず、形状が変化してきません。
道具に無頓着な私は、これをどこで手に入れたのかまったく覚えていないのですが、どこかで買った覚えはありませんから、おそらく、一昨年の秋、中国へ旅したときに太原か北京のホテルから持ってきたものだろうと思います。
中国産は粗悪だとイメージが、それもかなり一般的な固定観念を伴ってあるようですが、この歯ブラシについては感心するぐらい使い勝手がいいのです。
なお、中国産に神経質になっている向きも、実際には気が付かないところでそれと知らぬままその製品を使っている場合が多いと思います。
私の場合は、正直言って、食品に関してはいくぶん神経質ですが、その他はさほど気にしていません。
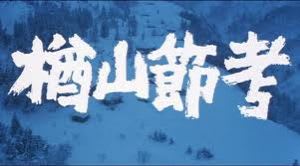

歯といえば、今村昌平の映画『楢山節考』(原作:深沢七郎)の主人公「おりん」が、老いてもなお丈夫な歯を持つことを自分の孫にからかわれ、石にその前歯をあてがって自ら砕くシーンがあります。
それは、自らの老いを完成し、山村共同体の掟に従って死にゆく己の定めを確固として成就しようとする決意の一環を示しています。
おりんがお山へ行く(=棄却される)のは七〇歳だといわれているのですが、この私は、それを数年過ぎても、なおかつ自分の歯をいたわっているのです。
思えば、歯が丈夫であることは、おりんにとってはもう残っていてはならない「若さ」の象徴であり、したがって、やがて消滅すべき身には、あってはならない恥ずべきものとして砕かれねばならなかったのですが、しつこくもまだ生き延びようとする私にとっては、やはりそれは私の中に残る若さの残像として、保存されねばならないものなのです。


とはいえ、雪の山でひっそりとその生を終えるという美学にも何がしか惹かれるものがあります。ただし、私の場合は、極上のスコッチを一本持たせてほしいと思うのですが。
おりんの毅然とした「おやま参り」(=棄却)に対し、まったく反するような映画を、今村昌平の長男、天願大介が撮っているのですが(『デンデラ』2011年)、もう、すでに長くなりすぎましたので、それについてはまた次回。




























せっかく仲良くなって、これからいろいろ聞きたいと思っていた矢先に逝ってしまいました。オアシスの下で「補習授業」をして、さらに居残り学習で女子大小路へ行ったこともしばしば。
益臣さんがお山へ行ったのは雪の日ではなく、爛漫の桜が笑っている時でしたね。
それは彼が鶴見俊輔・折原修三さん等と語らった「老いの会」のたどり着いたのは、有吉佐和子『恍惚の人』と深沢七郎『楢山節考』だったと記していたはずと思ったからです。
第2章にあり、そこでの折原さんの言。
「〈恍惚〉を絶対的に防止し得るもの、それは〈楢山参り〉以外ないのではないか」
それにしても、益臣逝ってもう5年!