
心地よさと切ない余韻が残る。嫌みのないフェミニズムが響く映画。「女性の性の定義は男性によって定義されてきた」というセリフに共感。男性が女性を知ることは、世界を知ることに等しいとみた。人生の先輩である3人のお姉さんたちに揉まれて成長する主人公に、自身の思春期の姿を重ねてノスタルジーに浸る。あの頃、仲良くしていた人たちは今何をしているのかな。
1979年の夏。母子家庭にいる15歳の少年が、母、幼馴染、下宿人の3人の女性との交流を経て成長していく姿を描く。
映画は思春期を迎えた15歳男子のリアルを追っていく。好奇心に満ち、新しい価値観に感化されやすい。性に目覚める。ときに意味不明な行動をとる(「溝落ち失神」って日本でも以前に、話題になった記憶があるな)。主人公の場合、自由で寛容な母親に育てられていることもあり、よくある「反抗期」とは無縁で、仲の良い親子関係を築いているようだ。その一方、母親は自立した個人として息子に接するものの、ある事件をきっかけに息子を理解できないことで悩む。そこで、たまたま身近にいた、主人公の幼馴染で2歳上の女子「ジュリー」と、下宿人でカメラマンの「アビー」の2人の女子に息子の教育を手伝ってほしいと頼む。「同じ男性が適当じゃない?」という問いに対して「そんなことないわ」という母親の勝算はどこにあったのだろう。
といっても、母親を含んだ3人が、主人公に何か特別なことをするわけではない。これまで通りの日常生活の関係性のなかで主人公に様々な影響を与えていく。幼馴染みの女子には恋の痛みを教わり、下宿人の姉貴にはパンクとフェミニズムを教わる。とりわけ前者の想いを寄せる女子への主人公の心情は身にしみて理解できる。好きな女子を性の対象とするのは自然であるが、「寝たら友情は終わり」と主人公は生殺し状態を強いられる。好きな女子の性生活を含めた恋愛事情が気になるものの、いざヒアリングしてみると激しく傷ついたりする。この時期において、片想いに悩む男子と女子では相手への感情はまったく異なるはずだ。
男子が求める女子と、女子が求める男子は異なる。男子優先で何事も決められてきた歴史があって、男子の尺度で女子を考えがちになる。そこで、アビーはフェミニズムについて説いた本を主人公に渡す。その本を通じて主人公は女性を知り、さらなる興味が湧き、女性への愛が深まったと想像する。そして、3人の女性の生き様が、主人公のもう1つの教科書になるのだ。
監督マイク・ミルズの女性へのリスペクトは、3人の女性の描き方によく表れている。彼女らがもれなく自然体でカッコいいのだ。自分に正直であり、ときに悩んで躓くけれど、しなやかに切り返して我が道を進もうとする。貫禄のアネット・ベニング、パンキッシュなグレタ・ガーウィグ(「フランシス・ハ」の人だ!)、魅惑のエル・ファニング(咥えタバコが素敵)。演じる女優陣のパフォーマンスに魅かれる。今年観た「ネオン・デーモン」に続いてエル・ファニングを見たけれど、女優として絵に書いたような美しいキャリアを歩んでいる模様。
本作のラストで視点が現代に映り、この物語以降のそれぞれの人生が過去の回想として語られる。主人公は50代のオッサンになっているはずだ。少年時代の特別なひとときは、もう戻ることのできない過去の出来事となっている。その儚さが切ない。出会って別れて、久しく会っていない人たちが自分にもたくさんいたことを思い出す。
【65点】
















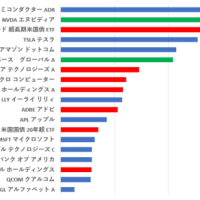


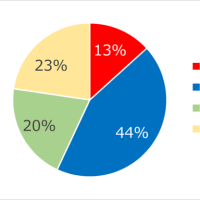
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます