自動車メーカー大手スズキの鈴木修会長85歳が、「90歳まで社長をやる」と宣言したその舌の根も乾かぬうちに、社長のイスを長男に譲ったことが話題になっています。事業承継の問題は、企業規模の大小を問わず非常に重要な経営課題でもありますので、少し取り上げておきます。
今回の社長交代に際しても、修会長は引き続きCEO兼務を続けるようで、結局実権はそのまま待ち続けたい訳なのでしょう。よく似たケースは、カシオ計算機。同じく今年の株主総会で、樫尾和雄会長は長男和宏氏に社長の座を譲ったものの、CEOは依然兼務を続けるとのこと。詳しい内部事情も存じ上げずに「老害」の一言で片づけてしまうのはどうかと思いますからそれはやめておきますが、その歳になるまで後継に道を譲れなかった原因と責任は確実に経営者ご自身にあるわけです。
スズキの修会長は創業家2代目の娘婿で、1978年に先代の後を継いで3代目社長に就任。既に40年近い年月にわたりトップ として企業を牽引しています。経営難にあった同社を軽自動車の商品性の向上で立て直し、インドはじめアジアへの積極進出を展開するなど卓越した経緯手腕を発揮してきました。経営者としての手腕がほめられることはあっても問題視されるようなことは少ないのですが、こと後継づくりに関しては決してほめられた状況ではないようです。
実は組織マネジメントにおいて、トップに課された最も重要な役割のひとつは、後継の育成とスムーズは事業承継なのです。トップがワンマンでカリスマであればあるほど本人自身が唯一無二の存在になってしまうわけであり、そのことは裏を返せばトップの身に万が一の事があれば、企業として大きなリスクを負うことになりかねないのです。中小企業などでは、それこそ会社の存続を揺るがしかねないわけで、後継の育成と事業承継はとにかく早期に着手しなくていけない大きなリスク管理案件であると言っていいでしょう。
ワンマン経営者はなぜ後継づくりが下手なのか。これまで見てきた多くの事例から経験則的に言えることは、ワンマン体制が長くなると経営者の立場がより高みに登ってしまい、「私経営する人」「私たち言うことを聞く人」という社内の意識のかい離が明確化され、イエスマンたちが増殖するようになるのです。そうなってしまうと、トップは皆が自分の言うことを聞く居心地の良い環境に安住しながらも、イエスマンの中から後継者を選ぶリスクをヒシヒシと感じてしまうことになります。
これは後継が親族であろうとも同じこと。父がカリスマ経営者の場合などには特に強く、親子言えども父と子ではなく社長と後継の関係を入社前から意識させられることになります。そうなると、結局偉大な社長の前にはイエスマン社員にならざるを得ない状況に追い込まれ、社長とすれば後継としては例え息子であろうとも、物足りない、まだまだ自分は辞められない、ということになるのです。スズキの場合もこれに近いようです。
それともうひとつは、歳を重ねることによる弊害も加わって来るように思います。ある知り合いの経営者が数年前にご子息に社長のイスを譲ったもののうまくいかず、70代半ばで会長職からも降りられた折にこう話されていました。
「自分はいつしか姑になっていた。自分が育てた可愛い可愛い会社という子供に、おかしなことを吹きこもうとする嫁にあたる後継を、ついついいびりたくなるわけです。テレビドラマの姑の嫁いびりを見て気がつかされ、これじゃいかんと思って身を引きました」
45年にわたってオリックスの経営を先導してきた宮内義彦氏は、引退後に「会社の事を世界観で語ってきた経営者が70歳を過ぎると自己中心の言動をとるようになる。そんな人を何人も見てきた」と話しています。氏はそれと知りつつも、実際に会長兼CEOの座を退いたのは79歳でした。長年ワンマン経営を続けた経営者が後進に道を譲り、身を引くことの難しさを如実に物語っているとも言えそうです。
話をスズキに戻します。
修会長は、一度は後継に社長の座を譲り会長職に退いたものの(00~08年)、結局実態は変わらず再び会長兼社長に逆戻りしたという“暗い過去”もあります。今回も会長専任とは言え実質トップであるCEOの地位を譲らなかったこと、会見でも「基本方針は私が決める。新社長には決められた範囲内でやってもらう」と公言してはばからないこと等から、まだまだ引退の二文字は見えていない、また同じ轍を踏む可能性もあるのではなかとの懸念も根強くあるわけなのです。
ホンダの創業者本田宗一郎氏は、ある時自ら育てた後進に道を譲ると、それ以降は決して会社に顔を出さなかったと言います。会社に顔を出せば、あれこれ目について絶対に口出しをしたくなる、そう思い会社へ行きたい気持ち、自分不在の不安な気持ちを抑えつつ事業承継を見事に貫徹させたことがホンダの自由闊達な文化をつくり、その後の同社の大躍進にもつながったと言えそうです。同業のスズキが今後ホンダのような発展軌道を描けるか否かは、修会長の今後の身の振り方にかかっているように思えてしまうのです。
※9月1日修正:カシオ電算機⇒カシオ計算機
今回の社長交代に際しても、修会長は引き続きCEO兼務を続けるようで、結局実権はそのまま待ち続けたい訳なのでしょう。よく似たケースは、カシオ計算機。同じく今年の株主総会で、樫尾和雄会長は長男和宏氏に社長の座を譲ったものの、CEOは依然兼務を続けるとのこと。詳しい内部事情も存じ上げずに「老害」の一言で片づけてしまうのはどうかと思いますからそれはやめておきますが、その歳になるまで後継に道を譲れなかった原因と責任は確実に経営者ご自身にあるわけです。
スズキの修会長は創業家2代目の娘婿で、1978年に先代の後を継いで3代目社長に就任。既に40年近い年月にわたりトップ として企業を牽引しています。経営難にあった同社を軽自動車の商品性の向上で立て直し、インドはじめアジアへの積極進出を展開するなど卓越した経緯手腕を発揮してきました。経営者としての手腕がほめられることはあっても問題視されるようなことは少ないのですが、こと後継づくりに関しては決してほめられた状況ではないようです。
実は組織マネジメントにおいて、トップに課された最も重要な役割のひとつは、後継の育成とスムーズは事業承継なのです。トップがワンマンでカリスマであればあるほど本人自身が唯一無二の存在になってしまうわけであり、そのことは裏を返せばトップの身に万が一の事があれば、企業として大きなリスクを負うことになりかねないのです。中小企業などでは、それこそ会社の存続を揺るがしかねないわけで、後継の育成と事業承継はとにかく早期に着手しなくていけない大きなリスク管理案件であると言っていいでしょう。
ワンマン経営者はなぜ後継づくりが下手なのか。これまで見てきた多くの事例から経験則的に言えることは、ワンマン体制が長くなると経営者の立場がより高みに登ってしまい、「私経営する人」「私たち言うことを聞く人」という社内の意識のかい離が明確化され、イエスマンたちが増殖するようになるのです。そうなってしまうと、トップは皆が自分の言うことを聞く居心地の良い環境に安住しながらも、イエスマンの中から後継者を選ぶリスクをヒシヒシと感じてしまうことになります。
これは後継が親族であろうとも同じこと。父がカリスマ経営者の場合などには特に強く、親子言えども父と子ではなく社長と後継の関係を入社前から意識させられることになります。そうなると、結局偉大な社長の前にはイエスマン社員にならざるを得ない状況に追い込まれ、社長とすれば後継としては例え息子であろうとも、物足りない、まだまだ自分は辞められない、ということになるのです。スズキの場合もこれに近いようです。
それともうひとつは、歳を重ねることによる弊害も加わって来るように思います。ある知り合いの経営者が数年前にご子息に社長のイスを譲ったもののうまくいかず、70代半ばで会長職からも降りられた折にこう話されていました。
「自分はいつしか姑になっていた。自分が育てた可愛い可愛い会社という子供に、おかしなことを吹きこもうとする嫁にあたる後継を、ついついいびりたくなるわけです。テレビドラマの姑の嫁いびりを見て気がつかされ、これじゃいかんと思って身を引きました」
45年にわたってオリックスの経営を先導してきた宮内義彦氏は、引退後に「会社の事を世界観で語ってきた経営者が70歳を過ぎると自己中心の言動をとるようになる。そんな人を何人も見てきた」と話しています。氏はそれと知りつつも、実際に会長兼CEOの座を退いたのは79歳でした。長年ワンマン経営を続けた経営者が後進に道を譲り、身を引くことの難しさを如実に物語っているとも言えそうです。
話をスズキに戻します。
修会長は、一度は後継に社長の座を譲り会長職に退いたものの(00~08年)、結局実態は変わらず再び会長兼社長に逆戻りしたという“暗い過去”もあります。今回も会長専任とは言え実質トップであるCEOの地位を譲らなかったこと、会見でも「基本方針は私が決める。新社長には決められた範囲内でやってもらう」と公言してはばからないこと等から、まだまだ引退の二文字は見えていない、また同じ轍を踏む可能性もあるのではなかとの懸念も根強くあるわけなのです。
ホンダの創業者本田宗一郎氏は、ある時自ら育てた後進に道を譲ると、それ以降は決して会社に顔を出さなかったと言います。会社に顔を出せば、あれこれ目について絶対に口出しをしたくなる、そう思い会社へ行きたい気持ち、自分不在の不安な気持ちを抑えつつ事業承継を見事に貫徹させたことがホンダの自由闊達な文化をつくり、その後の同社の大躍進にもつながったと言えそうです。同業のスズキが今後ホンダのような発展軌道を描けるか否かは、修会長の今後の身の振り方にかかっているように思えてしまうのです。
※9月1日修正:カシオ電算機⇒カシオ計算機











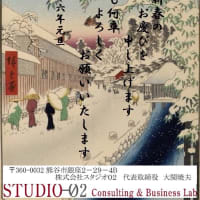
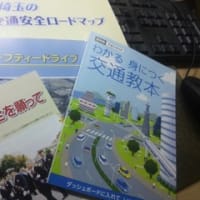
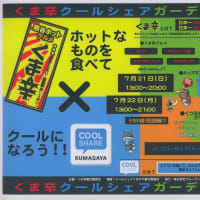
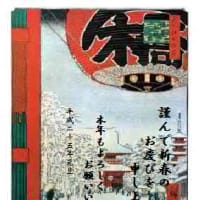


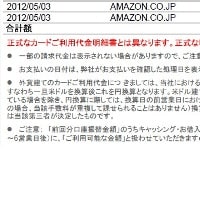

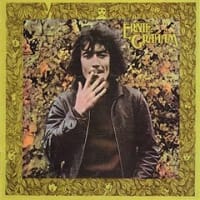
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます