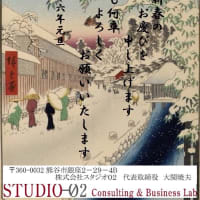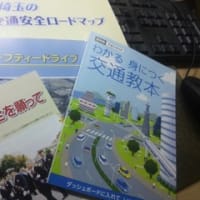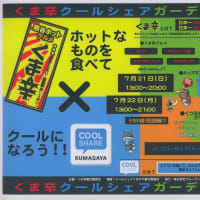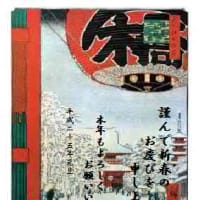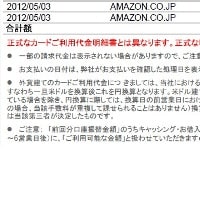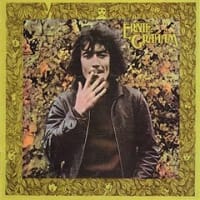日々の仕事を進めていく上での重要なポイントのひとつに、「JOB(業務)の優先順位をつける」ということがあります。
多くの方は、冒頭のマトリクスのような図を見たことがあるのではないでしょうか。このようなマトリックスは、スティーブン・R・コヴィー の「7つの習慣」はじめいくつかの経営指南本に出てきます。
JOBを図のように「重要性軸」と「緊急性軸」でマトリクス分類すると以下の通りです。
「A」:「重要性」「緊急性」ともに高い
「B」:「重要性」が高いが「緊急性」は低い
「C」:「重要性」は低いが「緊急性」は高い
「D」:「重要性」「緊急性」ともに低い
「重要性」「緊急性」で区分けした4つのMECEなマトリクスです。
誰が見ても、「A」は「目の前の重要な仕事」であり、最優先で取り組むべき課題であることは、すぐに分かると思います。同様に、「D」は「どうでもよい仕事」で、一番優先度合いの低い課題であることも分かるはずです。まず本マトリクスにおいて、この2点が「分からない」または「意識していない」スタッフが御社に存在するなら、即刻お引き取り願わなくてはいけません。まさに無駄な人件費を垂れ流している状態であります。
一般的にはこれが分からない社員が存在する確率はかなり低いのですが、中には分かっていて「A」を後回しにしている社員、または「A」、「B」、「C」を避けて意図的にこっそり「D」に逃げている社員がいます。「おい!そんな仕事今やらなくたっていいだろ!」って怒られているヤツがそれです。この「逃げ」あるいは「サボり」は、管理者の管理やチェックが甘いと、間々見られるケースです。
また中小企業では稀に、管理者自身が意図的にこのパターンに陥っているケースもありますので、経営者は要注意です。「言ったことをやらない」「期日が守られない」などが、わが社では多いなぁと思ったら、管理者まで含めた「意図的優先順位変更」や「仕事をしているフリ的サボり」が行われている可能性大です。
さて問題は、「B」と「C」の優先順位付けです。意外に、間違えてしまうのがこの「B」と「C」の順位付けです。「緊急性は高い」に惑わされてしまうと、「C」を「B」よりも優先上位に置いてしまいますが、これは間違いです。言葉で考えると「緊急性」は時間軸において“前倒し”を強制するように思われるため、このような間違いが発生します。要は「重要性軸」と「緊急性軸」は、経営にとってどちらがより上位かという問題なのです。
「B」は言いかえれば、「将来のための重要な仕事」、「C」を言いかえれば「目の前のささいな仕事」となります。こう考えると、どちらが優先順位が上か、答えは明白ですね。一生懸命やっているのに仕事のできない人、会社の統制はとれてムードはいいのに成長しない企業、などはこの優先順位に間違った理解をしているケースです。「B」(または「A」)を避けたり後回しにして「C」を優先し、「重要な業務」をしっかりこなしているかのような錯覚に陥っている社員や企業はけっこう多いものです。自分自身がどうか、自社がどうか、ぜひともセルフチェックしてみてください。
管理者(あるいは経営者)が気をつけなくてはいけないことは、「B」(または「A」)の仕事は難易度の高いものが多いということ。すなわち、「B」の取り組み方が分からずに、「サボる」つもりはなくとも、何かしないとまずいと思いやむなくとりあえず「C」から手をつけているケースも多いので、管理者は部下に目配せをしながら「B」のフォローをして、優先順位を逆転させないように方向修正をしなくていはいけないのです。
「仕事の優先順位」を見極めることは、簡単なように思えて間違いやすく、かつものすごく重要なことです。社員一人ひとりもたくさんの仕事を抱えているでしょうし、企業そのものもたくさんの取り組むべき「課題」を持っているはずです。個人も企業もJOBの「優先順位」を意図的であるか結果的であるかと問わず、誤ることは大きなロスにつながることになります。
「優先順位のマトリクス」の考え方に対する正しい理解と徹底を皆で実践し、企業の文化として根付かせることは、確実な発展につながる大きな力となるのです。
多くの方は、冒頭のマトリクスのような図を見たことがあるのではないでしょうか。このようなマトリックスは、スティーブン・R・コヴィー の「7つの習慣」はじめいくつかの経営指南本に出てきます。
JOBを図のように「重要性軸」と「緊急性軸」でマトリクス分類すると以下の通りです。
「A」:「重要性」「緊急性」ともに高い
「B」:「重要性」が高いが「緊急性」は低い
「C」:「重要性」は低いが「緊急性」は高い
「D」:「重要性」「緊急性」ともに低い
「重要性」「緊急性」で区分けした4つのMECEなマトリクスです。
誰が見ても、「A」は「目の前の重要な仕事」であり、最優先で取り組むべき課題であることは、すぐに分かると思います。同様に、「D」は「どうでもよい仕事」で、一番優先度合いの低い課題であることも分かるはずです。まず本マトリクスにおいて、この2点が「分からない」または「意識していない」スタッフが御社に存在するなら、即刻お引き取り願わなくてはいけません。まさに無駄な人件費を垂れ流している状態であります。
一般的にはこれが分からない社員が存在する確率はかなり低いのですが、中には分かっていて「A」を後回しにしている社員、または「A」、「B」、「C」を避けて意図的にこっそり「D」に逃げている社員がいます。「おい!そんな仕事今やらなくたっていいだろ!」って怒られているヤツがそれです。この「逃げ」あるいは「サボり」は、管理者の管理やチェックが甘いと、間々見られるケースです。
また中小企業では稀に、管理者自身が意図的にこのパターンに陥っているケースもありますので、経営者は要注意です。「言ったことをやらない」「期日が守られない」などが、わが社では多いなぁと思ったら、管理者まで含めた「意図的優先順位変更」や「仕事をしているフリ的サボり」が行われている可能性大です。
さて問題は、「B」と「C」の優先順位付けです。意外に、間違えてしまうのがこの「B」と「C」の順位付けです。「緊急性は高い」に惑わされてしまうと、「C」を「B」よりも優先上位に置いてしまいますが、これは間違いです。言葉で考えると「緊急性」は時間軸において“前倒し”を強制するように思われるため、このような間違いが発生します。要は「重要性軸」と「緊急性軸」は、経営にとってどちらがより上位かという問題なのです。
「B」は言いかえれば、「将来のための重要な仕事」、「C」を言いかえれば「目の前のささいな仕事」となります。こう考えると、どちらが優先順位が上か、答えは明白ですね。一生懸命やっているのに仕事のできない人、会社の統制はとれてムードはいいのに成長しない企業、などはこの優先順位に間違った理解をしているケースです。「B」(または「A」)を避けたり後回しにして「C」を優先し、「重要な業務」をしっかりこなしているかのような錯覚に陥っている社員や企業はけっこう多いものです。自分自身がどうか、自社がどうか、ぜひともセルフチェックしてみてください。
管理者(あるいは経営者)が気をつけなくてはいけないことは、「B」(または「A」)の仕事は難易度の高いものが多いということ。すなわち、「B」の取り組み方が分からずに、「サボる」つもりはなくとも、何かしないとまずいと思いやむなくとりあえず「C」から手をつけているケースも多いので、管理者は部下に目配せをしながら「B」のフォローをして、優先順位を逆転させないように方向修正をしなくていはいけないのです。
「仕事の優先順位」を見極めることは、簡単なように思えて間違いやすく、かつものすごく重要なことです。社員一人ひとりもたくさんの仕事を抱えているでしょうし、企業そのものもたくさんの取り組むべき「課題」を持っているはずです。個人も企業もJOBの「優先順位」を意図的であるか結果的であるかと問わず、誤ることは大きなロスにつながることになります。
「優先順位のマトリクス」の考え方に対する正しい理解と徹底を皆で実践し、企業の文化として根付かせることは、確実な発展につながる大きな力となるのです。