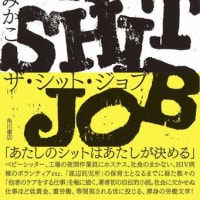今野浩『工学部ヒラノ教授』(新潮社、2011年)
 筒井康隆の『文学部唯野教授』を思わせる、工学部編とでも言えるような、日本でトップクラスの筑波大学、東京工業大学、中央大学の工学部の教授たちの生態や、文科省の理不尽さを描いた、一種のドキュメンタリー小説(?)とでも言ったらいいのかな。
筒井康隆の『文学部唯野教授』を思わせる、工学部編とでも言えるような、日本でトップクラスの筑波大学、東京工業大学、中央大学の工学部の教授たちの生態や、文科省の理不尽さを描いた、一種のドキュメンタリー小説(?)とでも言ったらいいのかな。
表紙の絵といい、新潮社特有の活字のせいか、ずいぶん古い著作のような印象を受けるが、上にも記したように、ほんの数年前のもの。このヒラノ教授シリーズが何本もあるようだが、私はどこかのブログでたまたま見つけて、興味を引かれた。
私は理系の、とくに実験系の知り合いというのは、あまりいないが、よくテレビなどで、シミュレーションをしてみせたりするのを見ると、理系の研究者というのはすごいなといつも感心する。コンピュータの時代なので、先端の実験をしながら、それを解析するのに、自分でプログラミングして、解析するソフトを作ったり、データを処理するプログラムを組んだり、あるいはそれをシミュレーションするためのプログラミングも自分でやるのだろうから、それがすごい。
私は一時期プログラミングの勉強をしたことがあるので分かるのだが、ほんとう難しい。子供でもプログラミングはできるというから、合う合わないの問題かもしれないけど。文系だと、まぁ私は社会科学系は知らないが、人文系なら、まぁコンピュータなしに仕事はできないとしても、自分でプログラミングするなんて聞いたこともない。
かつては京大式カードなんてものがあったりして、カードに抜粋や抜き書きを書きためて、分類し、整理するというようなことをしている人が多かった。
私も一時期そのようなことをしかけたが、生来の不精なので、これが面倒くさいことこの上なく、しかもどんなふうに使っていいのか分からない。テーマごとにすると、同じカードが複数のテーマになる場合には、テーマの数だけ作るか、見出しに複数のテーマを書いておいて、論文を書く時に、検索して、引っ張り出してきて、利用するかしなければならない。それに、そのカードがどの主題に関係するのか、不明な場合が多い。一行くらいの文章ならいいけど、長い文章になってくると、面倒くさい。
こんな調子で、もうすぐに面倒くさくなってきて、やめてしまった。ところがこういうデータ蓄積の点で、一番優れているのが、コンピュータである。どんどん書き込んでいけば、あとは、論文を書く時に、もう一度読みなおしていいし、ある単語で検索して、ヒットしたものを抜き出して、利用することもできる。この意味でも、いまでは文系の研究者にもコンピュータは必須のツールと言っていい。(かつては人文系向けのコンピュータ利用法の本が数冊でていた。最近ではあまり見ないが。)
それを理系の人たちは自分でやるのだからすごい、と思うのは私だけなんだろうか。おまけにすごい実験設備を自分たちで作ったり(もちろん実際には業者に依頼するのだろうけど)、論文を年に6本だって。毎日12時間くらい研究室に詰めているのだから、当たり前といえば言えるかも。それに比べたら、文系の研究者が遊んでいるように思われても仕方がないのかも。
私が行っている京都にある大学の教員(Aとする)が去年三月に退職した。紀要の退職記念号が出ていて、Aの研究業績を見たら、この大学でずっと40年位働いていたのに、著書は一冊もなし(共著も含めて)、論文数8本くらい。それだけ。この紀要には同じく退職する二人の教員の業績が載っている(この二人は社会科学系の人)が、こちらは大学教員を40年位やっていただけの、申し分ない業績が掲載されている。
私立大学の場合、数本論文を書けば、すぐに教授になれるし、それ以上のランクはないから、教授になってから、研究しなくても、給料は年齢給で自然に上がるし、解雇されるわけでもない。本当に天国みたいな世界だ。もちろんこんなAみたいな教員は少ないだろうけど、このAがこの退職記念号で今の学生は勉強しないだのなんだのと偉そうなことを書いているのを見ると、ほんとう笑けてくる。
 筒井康隆の『文学部唯野教授』を思わせる、工学部編とでも言えるような、日本でトップクラスの筑波大学、東京工業大学、中央大学の工学部の教授たちの生態や、文科省の理不尽さを描いた、一種のドキュメンタリー小説(?)とでも言ったらいいのかな。
筒井康隆の『文学部唯野教授』を思わせる、工学部編とでも言えるような、日本でトップクラスの筑波大学、東京工業大学、中央大学の工学部の教授たちの生態や、文科省の理不尽さを描いた、一種のドキュメンタリー小説(?)とでも言ったらいいのかな。表紙の絵といい、新潮社特有の活字のせいか、ずいぶん古い著作のような印象を受けるが、上にも記したように、ほんの数年前のもの。このヒラノ教授シリーズが何本もあるようだが、私はどこかのブログでたまたま見つけて、興味を引かれた。
私は理系の、とくに実験系の知り合いというのは、あまりいないが、よくテレビなどで、シミュレーションをしてみせたりするのを見ると、理系の研究者というのはすごいなといつも感心する。コンピュータの時代なので、先端の実験をしながら、それを解析するのに、自分でプログラミングして、解析するソフトを作ったり、データを処理するプログラムを組んだり、あるいはそれをシミュレーションするためのプログラミングも自分でやるのだろうから、それがすごい。
私は一時期プログラミングの勉強をしたことがあるので分かるのだが、ほんとう難しい。子供でもプログラミングはできるというから、合う合わないの問題かもしれないけど。文系だと、まぁ私は社会科学系は知らないが、人文系なら、まぁコンピュータなしに仕事はできないとしても、自分でプログラミングするなんて聞いたこともない。
かつては京大式カードなんてものがあったりして、カードに抜粋や抜き書きを書きためて、分類し、整理するというようなことをしている人が多かった。
私も一時期そのようなことをしかけたが、生来の不精なので、これが面倒くさいことこの上なく、しかもどんなふうに使っていいのか分からない。テーマごとにすると、同じカードが複数のテーマになる場合には、テーマの数だけ作るか、見出しに複数のテーマを書いておいて、論文を書く時に、検索して、引っ張り出してきて、利用するかしなければならない。それに、そのカードがどの主題に関係するのか、不明な場合が多い。一行くらいの文章ならいいけど、長い文章になってくると、面倒くさい。
こんな調子で、もうすぐに面倒くさくなってきて、やめてしまった。ところがこういうデータ蓄積の点で、一番優れているのが、コンピュータである。どんどん書き込んでいけば、あとは、論文を書く時に、もう一度読みなおしていいし、ある単語で検索して、ヒットしたものを抜き出して、利用することもできる。この意味でも、いまでは文系の研究者にもコンピュータは必須のツールと言っていい。(かつては人文系向けのコンピュータ利用法の本が数冊でていた。最近ではあまり見ないが。)
それを理系の人たちは自分でやるのだからすごい、と思うのは私だけなんだろうか。おまけにすごい実験設備を自分たちで作ったり(もちろん実際には業者に依頼するのだろうけど)、論文を年に6本だって。毎日12時間くらい研究室に詰めているのだから、当たり前といえば言えるかも。それに比べたら、文系の研究者が遊んでいるように思われても仕方がないのかも。
私が行っている京都にある大学の教員(Aとする)が去年三月に退職した。紀要の退職記念号が出ていて、Aの研究業績を見たら、この大学でずっと40年位働いていたのに、著書は一冊もなし(共著も含めて)、論文数8本くらい。それだけ。この紀要には同じく退職する二人の教員の業績が載っている(この二人は社会科学系の人)が、こちらは大学教員を40年位やっていただけの、申し分ない業績が掲載されている。
私立大学の場合、数本論文を書けば、すぐに教授になれるし、それ以上のランクはないから、教授になってから、研究しなくても、給料は年齢給で自然に上がるし、解雇されるわけでもない。本当に天国みたいな世界だ。もちろんこんなAみたいな教員は少ないだろうけど、このAがこの退職記念号で今の学生は勉強しないだのなんだのと偉そうなことを書いているのを見ると、ほんとう笑けてくる。