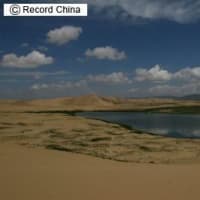■2月19日にチャイナの弁護団がフランスの司法当局に「競売」の差し止めを申請していた件は、23日にパリ市内の裁判所で行われてあっさり棄却されてしまいました。
2009年2月24日、中国国家文物局は、清朝末期に北京の円明園から英仏連合軍に略奪された動物像をめぐり、競売中止の申し立てが棄却されたことを受け、「国際社会の協力を仰ぎたい」とする声明を発表した。人民日報が伝えた。国家文物局は声明で「中国人民の正当な要求が尊重されることを願う。中国政府は断固として競売の反対を表明する」と改めてその立場を強調。「違法に流出した中国の文物を他人の金儲けの道具にしてはならない」と強く反発した。
■珍しく?真っ当な意見が述べられているようですが、チベットから持ち去られた大量の金銀財宝についても、同じ主張を受け入れるのでしょうか?やっぱり、チベットは歴史的に元々チャイナの一部だったのだから、国内での文物の移動でしかない、などという木で鼻を括ったような話になるのでしょうなあ。チベットの仏像などから剥ぎ取られた金や銀は略奪後に溶かされてしまい、跡形も無いそうですから、「競売」にさえも掛けられません。今は禿山になってしまった原生林から切り出された大木の山も何処に行ったのやら……。本当に「国際社会の協力を仰ぎたい」とチベット人やウイグル人は思っております。
また、パリの裁判所が棄却の理由を「法的に問題ない」としたことは、95年に採択された盗難文化財の返還に関する国際条約「ユニドロワ条約」に反すると指摘。所有者のピエール・ベルジェ氏が「ダライ・ラマ14世をチベットに戻すこと」と政治的な条件をつけたり、高額での買い取りを要求したりしたことを非難した。
■「盗難文化財」として扱え!ということは、相手を盗っ人呼ばわりしているわけですが、これを始めると気が遠くなるような「水掛論」になります。どうやら、チャイナ側としてはチベット問題に言及されたことを看過するわけには行かない事情があるようです。取ってつけたように「国際社会の協力を仰ぎたい」などと言い出しても、国際世論の多くはノーベル平和賞を受賞したダライ・ラマ法王に同情的ですから、こちらの要請も本気ではなかったのでしょうなあ。
競売にかけられるのは、円明園から英仏軍の略奪を受け流出した「十二支像」のうちのネズミとウサギの2体。中国の弁護士約80人が競売の中止を求め、パリの裁判所に提訴したが、裁判所は23日、訴えを棄却する判決を下した。競売は現地時間の25日午後7時から行われる。(翻訳・編集/NN)
2009-02-25 Record China
■「弁護士80人」とは、世界を傍若無人に駆け巡った聖火防衛隊よりも規模が大きくなっておりますぞ。自国内ではマトモな弁護の仕事が無いから暇だというわけでもないのでしょうが、それにしても何かと言うと人海戦術に訴えるお国柄は相変わらずのようであります。
■さてさて、問題のブロンズ像は2体と言っても頭部のみのようです。どうせ運び出すのなら、どうして全体像を無傷で持ち去らなかったのか?公開された写真から類推すれば、首を叩き落して掠奪したとしか思えません。歴史、特に戦争には当事者双方に言い分が有るものですが、円明園の焼き討ちは英仏側にとっては「報復」だったことになっております。そして、実に興味深いことに、この事件にはアテネのパルテノン神殿からレリーフを剥ぎ取った張本人の名前も出て来るのであります。日本では役人の天下りが非難の的ですが、大英帝国時代には貴族階級のジェントルマンが、世界中を引っ掻き回して巡り歩いた模様ですなあ。
2009年2月24日、中国国家文物局は、清朝末期に北京の円明園から英仏連合軍に略奪された動物像をめぐり、競売中止の申し立てが棄却されたことを受け、「国際社会の協力を仰ぎたい」とする声明を発表した。人民日報が伝えた。国家文物局は声明で「中国人民の正当な要求が尊重されることを願う。中国政府は断固として競売の反対を表明する」と改めてその立場を強調。「違法に流出した中国の文物を他人の金儲けの道具にしてはならない」と強く反発した。
■珍しく?真っ当な意見が述べられているようですが、チベットから持ち去られた大量の金銀財宝についても、同じ主張を受け入れるのでしょうか?やっぱり、チベットは歴史的に元々チャイナの一部だったのだから、国内での文物の移動でしかない、などという木で鼻を括ったような話になるのでしょうなあ。チベットの仏像などから剥ぎ取られた金や銀は略奪後に溶かされてしまい、跡形も無いそうですから、「競売」にさえも掛けられません。今は禿山になってしまった原生林から切り出された大木の山も何処に行ったのやら……。本当に「国際社会の協力を仰ぎたい」とチベット人やウイグル人は思っております。
また、パリの裁判所が棄却の理由を「法的に問題ない」としたことは、95年に採択された盗難文化財の返還に関する国際条約「ユニドロワ条約」に反すると指摘。所有者のピエール・ベルジェ氏が「ダライ・ラマ14世をチベットに戻すこと」と政治的な条件をつけたり、高額での買い取りを要求したりしたことを非難した。
■「盗難文化財」として扱え!ということは、相手を盗っ人呼ばわりしているわけですが、これを始めると気が遠くなるような「水掛論」になります。どうやら、チャイナ側としてはチベット問題に言及されたことを看過するわけには行かない事情があるようです。取ってつけたように「国際社会の協力を仰ぎたい」などと言い出しても、国際世論の多くはノーベル平和賞を受賞したダライ・ラマ法王に同情的ですから、こちらの要請も本気ではなかったのでしょうなあ。
競売にかけられるのは、円明園から英仏軍の略奪を受け流出した「十二支像」のうちのネズミとウサギの2体。中国の弁護士約80人が競売の中止を求め、パリの裁判所に提訴したが、裁判所は23日、訴えを棄却する判決を下した。競売は現地時間の25日午後7時から行われる。(翻訳・編集/NN)
2009-02-25 Record China
■「弁護士80人」とは、世界を傍若無人に駆け巡った聖火防衛隊よりも規模が大きくなっておりますぞ。自国内ではマトモな弁護の仕事が無いから暇だというわけでもないのでしょうが、それにしても何かと言うと人海戦術に訴えるお国柄は相変わらずのようであります。
■さてさて、問題のブロンズ像は2体と言っても頭部のみのようです。どうせ運び出すのなら、どうして全体像を無傷で持ち去らなかったのか?公開された写真から類推すれば、首を叩き落して掠奪したとしか思えません。歴史、特に戦争には当事者双方に言い分が有るものですが、円明園の焼き討ちは英仏側にとっては「報復」だったことになっております。そして、実に興味深いことに、この事件にはアテネのパルテノン神殿からレリーフを剥ぎ取った張本人の名前も出て来るのであります。日本では役人の天下りが非難の的ですが、大英帝国時代には貴族階級のジェントルマンが、世界中を引っ掻き回して巡り歩いた模様ですなあ。