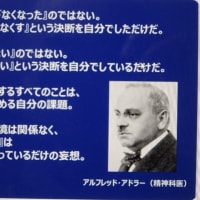引き続き、「悲劇の誕生」を読む。
「キリスト教は始めから、本質的に、また根本的に、生が生に対しておぼえる嘔吐であり倦怠であった」。あふンっっ!この間のルドルフ・オットーとは正反対で、クラクラするのにゃ。でも、似たようなことも、書いてある。「ある宗教の神話的諸前提が、正教的独断論のきびしい悟性的な目にさらされて、歴史的な出来事の総計として体系化され、人々はおずおずと神話の信ずべきことを弁護しながらも、神話が自然に生きのび生長しつづけることに対しては、ことごとに反抗しはじめるといった時、その宗教は通例生命を持たなくなる」。
この神話に関する記述には、ブレがある。この本の後の方にはこう書いてある。「国家でさえも、神話的基礎以上に強力な不文律を知らない。神話的基礎こそ、国家が宗教と関連を持つこと、国家が神話的表象の中から成長してきたことを裏づけるものなのだ」。「強力な不文律」。それは、前に書いた「神話の自然な生長」を否定する「正教的独断論」そのものではないだろうか。彼の説によれば、それは宗教を滅ぼし、国家をも滅ぼすことになる。後年のナチス・ドイツの滅亡は、その実証ではないだろうか。
また、さんざんギリシア神話を持ち上げておいて、「縁もゆかりもない外国の神話を移植し、この移植のために樹木(*ドイツ的本質)そのものを救いがたいまでに傷つけずに、好結果をいつまでもあげるということは、ほとんど不可能のように思われる」、などと書くのには驚かされる。まったく、支離滅裂だ。
だが、それでも、読みどころは多い。観客が合唱団(ディオニュソス的陶酔)と一体化し、舞台の俳優(アポロ的形象)を見つめる、というギリシア悲劇の構造の分析は、ニーチェ自身の演劇理論でもあるだろう。ここで展開されている劇と音楽の関係論は、後世の寺山修司の演劇に影響を与えているように思えてならない。寺山(言葉)=アポロで、J・A・シーザー(音楽)=ディオニュソスではないだろうか。また、演劇の批評家に対する批評も、そのまま現代に通用しそうだ。
ニーチェは演劇論だけでなく、文明論も展開している。彼によると、ギリシア悲劇を非合理的なものとして破壊したのはソクラテスだという。ソクラテス的文化、簡単にいうと、みんなで勉強して賢くなって科学を発展させれば幸せになれるという楽天主義が、近代世界を支配しているが、このような考え方は遅かれ早かれ行きづまり、破滅する。世界の本質は永遠の苦悩であり、それを受け入れるためには、悲劇による形而上学的慰めが必要なのだ、という。「蟹工船」など及びもつかないスケールの大きさだ。
巻末の解説は、本書はニーチェのフィクションであり、一種の詩作だとするが、私はそうとも言い切れないような気がする。たとえば、悲劇を堕落させたというエウリピデスは、本当にソクラテスから影響を受けたのか、という点についていうと、「ソクラテス」を、「ソクラテス的なもの」、「当時台頭しつつあった新しい精神」、と読み替えて考えることは可能だと思う。
前書き(1886年)と本文(1870年)の差が大きい。生の苦しみを慰めるために悲劇が必要だという、本文のいわゆるアポロ的なバランス感覚が、前書きからは消えている。ニーチェは叫ぶ。「若い友人たちよ、君たちがあくまでもペシミストにとどまる気なら、笑うことを学ぶべきなのだ。おそらく君たちはその結果、笑う者として、いつかはすべての形而上学的慰めなんか悪魔にくれてやることになろうー形而上学なんかまっ先にだ!」
・・・・・逆に、それだからこそ、ニーチェ嫌いの人でもまだこの本は許容範囲内、という見方もできるかもしれない。