The Sonnets
TO THE ONLY BEGETTER OF
THESE INSUING SONNETS
MR. W. H.
(このソネット集の唯一の産みの親であるW.H.氏に捧ぐ)
出版された『ソネット集』には次のような献呈辞が添えられている。
W.H.氏とは誰だろう?オスカー・ワイルドはこの人物を劇団の少年役者ウィリー・ヒューズと解いてみた。その謎解きは歴史的な裏づけを欠いてはいるものの、舞台という不思議な扉を通って現実と作品のあいだを行ったり来たりしていたシェイクスピアにとって何がいちばん魅力的に見えたのかを教えてくれる、という点ですぐれている。
さて、『ソネット集』には全部で4人の人物が登場する。まずシェイクスピア自身と思われる「私」。二人目は「君」と呼びかけられる「美青年」。三人目はこの美青年を誘惑する「黒い貴婦人」(dark lady)。最後がシェイクスピアがその才能に嫉妬する「対抗馬の詩人」(rival poet)。あやしい色香につつまれた黒い貴婦人をめぐる屈折した三角関係、対抗馬の詩人の出現によりますます気まずくなっていく私と美青年との仲--不滅の愛をテーマにした当時の連作ソネット集と違ってシェイクスピアの『ソネット集』はけっこうスキャンダラスなのだ。
18
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st,
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
君を夏の日にたとえようか。
いや、君の方がずっと美しく、おだやかだ。
荒々しい風は五月のいじらしい蕾をいじめるし、
なりよりも夏はあまりにあっけなく去っていく。
時に天なる瞳はあまりに暑く輝き、
かと思うとその黄金の顔はしばしば曇る。
どんなに美しいものもいつかその美をはぎ取られるのが宿命、
偶然によるか、自然の摂理によるかの違いはあっても。
でも、君の永遠の夏を色あせたりはさせない、
もちろん君の美しさはいつまでも君のものだ、
まして死神に君がその影の中でさまよっているなんて自慢話をさせてたまるか、
永遠の詩の中で君は時そのものへと熟しているのだから。
ひとが息をし、目がものを見るかぎり、
この詩は生き、君にいのちを与えつづける。
なんと美しい愛の絶唱だろう。シェイクスピアの『ソネット集』の中でもっとも有名なこの作品を何の説明もなしに読めば、十人中十人、男性が女性に捧げた愛の詩だと思うに違いない。それほどまでに「私」なる男性は「君」の美に陶酔している。しかし、『ソネット集』の「君」は女性ではなく若くて美しい男性貴族なのだ。これは推理とか仮説ではなく、明白な事実だ。そして、どうやら「君」はW.H.氏と同一人物のようだ。
えっ、この「君」って女じゃないの?ということは、シェイクスピアはホモってこと?多くの読者はすこしばかりうろたえながら自問し、さらに、じゃ一体W.H.氏って誰?とますます好奇心をかりたてられるだろう。
もちろん真相は誰にも分らない。謎は謎のまま残しておくよりほかに仕方ないが、ワイルドは天才を単なるホモのままにしておきたくはなかった。そこで考え出したのが少年役者説だ。法律で女優が舞台に上がることを禁じられた時代にあって、女役を演じる少年役者が二重の魅力を身にまとっていたことは確かである--作品中のヒロインの詩的魅力と初々しい少年の肉体的魅力を兼ねそなえて。少年役者はどう見ても特権的な存在だ。そういう意味でワイルド説には説得力がある。
古代ギリシア人は人間の本源となる霊的存在をアンドロギュヌス(ギリシア語で「男女」)と呼んだ。シェイクスピアがホモだったかどうかは別として、舞台上に現われたアンドロギュヌスに心惹かれていたことは十分想像できる。目の前にいながら、触れようと手をのばせば、その手をするりとすり抜けて遠くへ逃げ去ってしまう、そんな《女=男》というかげろうを演じる少年役者にこがれ、じらされ、心乱され、たまらずにシェイクスピアは『ソネット集』といくつもの舞台作品を書きあげた、そんな風に想像するのも楽しいではないか。
18番の大意は、肉体の美しさを誇ってみてもあっという間にかげりが見える、だから僕の詩で君の美に永遠のいのちを与えよう、というものだ。夏のはかなさから詩の不滅へと展開する運動が二段階の対比を通じてたくみに示されている。最初は不安定な夏と穏やかな美青年の対比であり、次は移りゆく人間の時間と詩の永遠不滅との対比だ。しかし、なんといってもこの詩の魅力は英語の響きを最大限に活かした高い調子にある。そのためだろう、映画『いまを生きる』(原題 The Dead Poets Society)でも、『恋に落ちたシェイクスピア』(原題Shakespeare in Love)でも効果的に使われている。どこで使われているのか記憶にないかたはもう一度注意して観ることをお勧めする。
次に「黒い貴婦人」(dark lady)と呼ばれる女性を歌ったソネットを紹介する。
130
My mistress' eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red, than her lips red,
If snow be white, why then her breasts are dun:
If hairs be wires, black wires grow on her head:
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks,
And in some perfumes is there more delight,
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know,
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet by heaven I think my love as rare,
As any she belied with false compare.
私の彼女の目は太陽みたいなんかじゃない。
唇だって珊瑚の方がずっと赤い。
雪の色が白いなら彼女の胸は褐色だ。
金糸の髪などというが、彼女の頭にあるのは黒糸だ。
紅白まだらのバラを見たことがあるが、
彼女の頬のどこを探してもそんなバラは見つからない。
香水の中のいくつかは
彼女の息よりずっといい。
彼女の話し声は大好きだ。でも正直な話
音楽を聴いてる方がもっと楽しい。
女神が歩くようだなんて見てきたように言う奴がいるが、
私の彼女はごく普通に歩いている。
でも、誓ってもいい、私の好きなひとは最高だ。
いつわりの比喩で飾り立てた女とは比べものにならない。
これはかなり挑戦的、かつ挑発的ソネットだ。ペトラルカの伝統に則った大げさな比喩をあざけるように真正直な描写を並べ、最後の最後でどんでん返しをねらっているのだが、果たして成功したろうか?こういうケレンでは愛人への並はずれた愛を強調するというよりむしろ、嫌悪感の方を印象づけてしまったのではないだろうか。少なくとも黒い貴婦人が誰もがこぞって認めるような美人でないことは決定的になった。いや、それもシェイクスピアのねらいだったかも知れない。というのも、ここで「いつわりの比喩」と皮肉った比喩を美青年をたたえるソネットでは堂々と使っているからだ。そこに愛と憎しみ、惑溺と反撥を抱きあわせた両面の感情を読み取るなら、黒い貴婦人に対するシェイクスピアの思いはおのずから明らかだろう。
それにしてもシェイクスピアは劇作品で様々な「黒い貴婦人」を登場させている。ロザリンド(『恋の骨折り損』)、カタリーナ(『じゃじゃ馬ならし』)、ヒーロー(『空騒ぎ』)、フィービー(『お気に召すまま』)、クレオパトラ(『アントニーとクレオパトラ』)などである。こうして並べているうちに、もしかすると『ソネット集』そのものが現実めかして書かれた巧妙な作り物かも知れない、そんな思いが湧きあがってきた。それこそシェイクスピアの得意技なのだから。
概して「黒い貴婦人」を歌ったソネット群は壮絶な男女関係を露骨に表現しておりルネサンスの連作ソネット集の枠からはみ出している。そこがまた、『ソネット集』の魅力でもあるのだが、同時に難解な部分でもある。
泥沼にはまった自分を外から眺め、でもこうするしかないんだからこうして遊ぶしかないよ、と自嘲気味につぶやくシェイクスピアがそこにいる。中期の作品群に問題劇と呼ばれる3篇の戯曲があるが、その中で男女関係の暗部が容赦なくあばき出されている。結婚初夜、自分への愛を誓うけなげな妻に、いっしょに暮らしたければ俺の子供を身ごもってみろと書き置きを残して外国へ旅立つ夫、特権を利用して修道女見習いに死刑囚の兄のいのちを助けたければ処女を差しだせと迫る国王代理、恋人からもらった贈り物を本人が見ているとも知らずに新しい恋人に贈りながら、まだ片方の目は前のひとを愛しているとうそぶく女--そこに愛の信義はかけらもない。「黒い貴婦人」のソネット群の精神風土はまさにこれら問題劇の延長線上にある。いや、これほど徹底して自他を欺瞞の砂あらしに巻きこみ、しかも、そうする自分をなぐさめとあざけりの両天秤にかけながら戯れつづける、そんな例は戯曲には見られない。このソネットはシェイクスピアの問題劇の上をゆく問題作品だ。
シェイクスピアの『ソネット集』の魅力は、色合いのよく似た布を情感の糸で撚り合わせているうちに、ふと気づくと、一枚一枚見ていた時には思いも寄らない多様な世界が広大なパッチワークの上でくり広げられているという妙味である。これはいわば俳諧の連句の魅力だ。しかし、『ソネット集』の楽しみ方はそれだけではない。4人の男女が織りなす甘く苦い錦絵模様から好きな1枚を抜きだしてみても、そこには十分自立した世界があり私たちのこころを捉える。たった14行の詩から人生の深淵をのぞくことができるのだ。まさに発句の魅力である。
最後に選りすぐりの一編を紹介しよう。
65
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o'ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O how shall summer's honey breath hold out,
Against the wrackful siege of batt'ring days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong but time decays?
O fearful meditation, where alack,
Shall Time's best jewel from Time's chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back,
Or who his spoil of beauty can forbid?
O none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright.
真鍮も、石も、大地も、無辺の海も、
重々しい死の支配をまぬがれることができないとなれば、
この暴虐の差しとめを訴えたところで
花ほどの力しか持たない美に何ができよう。
夏のそよ風がどんなにかぐわしくても
歳月の城攻めにあえばひとたまりもない。
石垣も、鉄の扉も、時の威力を前に
やすやすと崩れはててしまうのだから。
ああ、考えただけでも恐ろしいことだ。
美しいこの世の宝を時のひつぎに収めさせない手立てはないのか?
そうだ、たくましい腕なら早足の時を押しとどめ
花園を踏みにじるのをやめさせられないだろうか?
いや、そんなことはできない。奇跡が起こらないかぎり--
黒いインクの中で私の愛するひとが輝きつづけるという奇跡が。
「君を夏の日にたとえようか」ではじまるソネット18番と同じく《詩による永遠》を主題にした作品だが、ふたつを並べてみると違いが歴然とする。たしかに18番は名作だ。しかし、そのあまりに流麗な調子のために存在感が希薄になっている。ところが65番は「時」の猛威と生きるものの儚さを容赦なく対峙させ、その徹底ぶりがかえって《詩による永遠》という主題に人間の温気を授けている。ひとは限りなくもろい、しかし、限りなくたくましい。そういうパラドックスを実感させてくれるのがこの詩だ。
18番ではシェイクスピアは美青年のすぐそばにいる。愛する「君」を目の前にしているからこそ感動的な「殺し文句」が生まれたのだが、《詩による永遠》は二の次で「君」の気を惹くのが第一の感がある。それが証拠に7回も「君」が使われている。一方、65番には「君」が一度も出てこない。シェイクスピアは人間の側からではなく永遠の側から歌っているのだ。そして、最後の最後、喪の黒が永遠の黒に変容する奇跡のくだりではじめて「私の愛するひと」が三人称で登場する。こういった抑制が水面下に隠れた厚い感情の層を感じさせてくれるのではないだろうか。
TO THE ONLY BEGETTER OF
THESE INSUING SONNETS
MR. W. H.
(このソネット集の唯一の産みの親であるW.H.氏に捧ぐ)
出版された『ソネット集』には次のような献呈辞が添えられている。
W.H.氏とは誰だろう?オスカー・ワイルドはこの人物を劇団の少年役者ウィリー・ヒューズと解いてみた。その謎解きは歴史的な裏づけを欠いてはいるものの、舞台という不思議な扉を通って現実と作品のあいだを行ったり来たりしていたシェイクスピアにとって何がいちばん魅力的に見えたのかを教えてくれる、という点ですぐれている。
さて、『ソネット集』には全部で4人の人物が登場する。まずシェイクスピア自身と思われる「私」。二人目は「君」と呼びかけられる「美青年」。三人目はこの美青年を誘惑する「黒い貴婦人」(dark lady)。最後がシェイクスピアがその才能に嫉妬する「対抗馬の詩人」(rival poet)。あやしい色香につつまれた黒い貴婦人をめぐる屈折した三角関係、対抗馬の詩人の出現によりますます気まずくなっていく私と美青年との仲--不滅の愛をテーマにした当時の連作ソネット集と違ってシェイクスピアの『ソネット集』はけっこうスキャンダラスなのだ。
18
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st,
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
君を夏の日にたとえようか。
いや、君の方がずっと美しく、おだやかだ。
荒々しい風は五月のいじらしい蕾をいじめるし、
なりよりも夏はあまりにあっけなく去っていく。
時に天なる瞳はあまりに暑く輝き、
かと思うとその黄金の顔はしばしば曇る。
どんなに美しいものもいつかその美をはぎ取られるのが宿命、
偶然によるか、自然の摂理によるかの違いはあっても。
でも、君の永遠の夏を色あせたりはさせない、
もちろん君の美しさはいつまでも君のものだ、
まして死神に君がその影の中でさまよっているなんて自慢話をさせてたまるか、
永遠の詩の中で君は時そのものへと熟しているのだから。
ひとが息をし、目がものを見るかぎり、
この詩は生き、君にいのちを与えつづける。
なんと美しい愛の絶唱だろう。シェイクスピアの『ソネット集』の中でもっとも有名なこの作品を何の説明もなしに読めば、十人中十人、男性が女性に捧げた愛の詩だと思うに違いない。それほどまでに「私」なる男性は「君」の美に陶酔している。しかし、『ソネット集』の「君」は女性ではなく若くて美しい男性貴族なのだ。これは推理とか仮説ではなく、明白な事実だ。そして、どうやら「君」はW.H.氏と同一人物のようだ。
えっ、この「君」って女じゃないの?ということは、シェイクスピアはホモってこと?多くの読者はすこしばかりうろたえながら自問し、さらに、じゃ一体W.H.氏って誰?とますます好奇心をかりたてられるだろう。
もちろん真相は誰にも分らない。謎は謎のまま残しておくよりほかに仕方ないが、ワイルドは天才を単なるホモのままにしておきたくはなかった。そこで考え出したのが少年役者説だ。法律で女優が舞台に上がることを禁じられた時代にあって、女役を演じる少年役者が二重の魅力を身にまとっていたことは確かである--作品中のヒロインの詩的魅力と初々しい少年の肉体的魅力を兼ねそなえて。少年役者はどう見ても特権的な存在だ。そういう意味でワイルド説には説得力がある。
古代ギリシア人は人間の本源となる霊的存在をアンドロギュヌス(ギリシア語で「男女」)と呼んだ。シェイクスピアがホモだったかどうかは別として、舞台上に現われたアンドロギュヌスに心惹かれていたことは十分想像できる。目の前にいながら、触れようと手をのばせば、その手をするりとすり抜けて遠くへ逃げ去ってしまう、そんな《女=男》というかげろうを演じる少年役者にこがれ、じらされ、心乱され、たまらずにシェイクスピアは『ソネット集』といくつもの舞台作品を書きあげた、そんな風に想像するのも楽しいではないか。
18番の大意は、肉体の美しさを誇ってみてもあっという間にかげりが見える、だから僕の詩で君の美に永遠のいのちを与えよう、というものだ。夏のはかなさから詩の不滅へと展開する運動が二段階の対比を通じてたくみに示されている。最初は不安定な夏と穏やかな美青年の対比であり、次は移りゆく人間の時間と詩の永遠不滅との対比だ。しかし、なんといってもこの詩の魅力は英語の響きを最大限に活かした高い調子にある。そのためだろう、映画『いまを生きる』(原題 The Dead Poets Society)でも、『恋に落ちたシェイクスピア』(原題Shakespeare in Love)でも効果的に使われている。どこで使われているのか記憶にないかたはもう一度注意して観ることをお勧めする。
次に「黒い貴婦人」(dark lady)と呼ばれる女性を歌ったソネットを紹介する。
130
My mistress' eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red, than her lips red,
If snow be white, why then her breasts are dun:
If hairs be wires, black wires grow on her head:
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks,
And in some perfumes is there more delight,
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know,
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet by heaven I think my love as rare,
As any she belied with false compare.
私の彼女の目は太陽みたいなんかじゃない。
唇だって珊瑚の方がずっと赤い。
雪の色が白いなら彼女の胸は褐色だ。
金糸の髪などというが、彼女の頭にあるのは黒糸だ。
紅白まだらのバラを見たことがあるが、
彼女の頬のどこを探してもそんなバラは見つからない。
香水の中のいくつかは
彼女の息よりずっといい。
彼女の話し声は大好きだ。でも正直な話
音楽を聴いてる方がもっと楽しい。
女神が歩くようだなんて見てきたように言う奴がいるが、
私の彼女はごく普通に歩いている。
でも、誓ってもいい、私の好きなひとは最高だ。
いつわりの比喩で飾り立てた女とは比べものにならない。
これはかなり挑戦的、かつ挑発的ソネットだ。ペトラルカの伝統に則った大げさな比喩をあざけるように真正直な描写を並べ、最後の最後でどんでん返しをねらっているのだが、果たして成功したろうか?こういうケレンでは愛人への並はずれた愛を強調するというよりむしろ、嫌悪感の方を印象づけてしまったのではないだろうか。少なくとも黒い貴婦人が誰もがこぞって認めるような美人でないことは決定的になった。いや、それもシェイクスピアのねらいだったかも知れない。というのも、ここで「いつわりの比喩」と皮肉った比喩を美青年をたたえるソネットでは堂々と使っているからだ。そこに愛と憎しみ、惑溺と反撥を抱きあわせた両面の感情を読み取るなら、黒い貴婦人に対するシェイクスピアの思いはおのずから明らかだろう。
それにしてもシェイクスピアは劇作品で様々な「黒い貴婦人」を登場させている。ロザリンド(『恋の骨折り損』)、カタリーナ(『じゃじゃ馬ならし』)、ヒーロー(『空騒ぎ』)、フィービー(『お気に召すまま』)、クレオパトラ(『アントニーとクレオパトラ』)などである。こうして並べているうちに、もしかすると『ソネット集』そのものが現実めかして書かれた巧妙な作り物かも知れない、そんな思いが湧きあがってきた。それこそシェイクスピアの得意技なのだから。
概して「黒い貴婦人」を歌ったソネット群は壮絶な男女関係を露骨に表現しておりルネサンスの連作ソネット集の枠からはみ出している。そこがまた、『ソネット集』の魅力でもあるのだが、同時に難解な部分でもある。
泥沼にはまった自分を外から眺め、でもこうするしかないんだからこうして遊ぶしかないよ、と自嘲気味につぶやくシェイクスピアがそこにいる。中期の作品群に問題劇と呼ばれる3篇の戯曲があるが、その中で男女関係の暗部が容赦なくあばき出されている。結婚初夜、自分への愛を誓うけなげな妻に、いっしょに暮らしたければ俺の子供を身ごもってみろと書き置きを残して外国へ旅立つ夫、特権を利用して修道女見習いに死刑囚の兄のいのちを助けたければ処女を差しだせと迫る国王代理、恋人からもらった贈り物を本人が見ているとも知らずに新しい恋人に贈りながら、まだ片方の目は前のひとを愛しているとうそぶく女--そこに愛の信義はかけらもない。「黒い貴婦人」のソネット群の精神風土はまさにこれら問題劇の延長線上にある。いや、これほど徹底して自他を欺瞞の砂あらしに巻きこみ、しかも、そうする自分をなぐさめとあざけりの両天秤にかけながら戯れつづける、そんな例は戯曲には見られない。このソネットはシェイクスピアの問題劇の上をゆく問題作品だ。
シェイクスピアの『ソネット集』の魅力は、色合いのよく似た布を情感の糸で撚り合わせているうちに、ふと気づくと、一枚一枚見ていた時には思いも寄らない多様な世界が広大なパッチワークの上でくり広げられているという妙味である。これはいわば俳諧の連句の魅力だ。しかし、『ソネット集』の楽しみ方はそれだけではない。4人の男女が織りなす甘く苦い錦絵模様から好きな1枚を抜きだしてみても、そこには十分自立した世界があり私たちのこころを捉える。たった14行の詩から人生の深淵をのぞくことができるのだ。まさに発句の魅力である。
最後に選りすぐりの一編を紹介しよう。
65
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o'ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O how shall summer's honey breath hold out,
Against the wrackful siege of batt'ring days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong but time decays?
O fearful meditation, where alack,
Shall Time's best jewel from Time's chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back,
Or who his spoil of beauty can forbid?
O none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright.
真鍮も、石も、大地も、無辺の海も、
重々しい死の支配をまぬがれることができないとなれば、
この暴虐の差しとめを訴えたところで
花ほどの力しか持たない美に何ができよう。
夏のそよ風がどんなにかぐわしくても
歳月の城攻めにあえばひとたまりもない。
石垣も、鉄の扉も、時の威力を前に
やすやすと崩れはててしまうのだから。
ああ、考えただけでも恐ろしいことだ。
美しいこの世の宝を時のひつぎに収めさせない手立てはないのか?
そうだ、たくましい腕なら早足の時を押しとどめ
花園を踏みにじるのをやめさせられないだろうか?
いや、そんなことはできない。奇跡が起こらないかぎり--
黒いインクの中で私の愛するひとが輝きつづけるという奇跡が。
「君を夏の日にたとえようか」ではじまるソネット18番と同じく《詩による永遠》を主題にした作品だが、ふたつを並べてみると違いが歴然とする。たしかに18番は名作だ。しかし、そのあまりに流麗な調子のために存在感が希薄になっている。ところが65番は「時」の猛威と生きるものの儚さを容赦なく対峙させ、その徹底ぶりがかえって《詩による永遠》という主題に人間の温気を授けている。ひとは限りなくもろい、しかし、限りなくたくましい。そういうパラドックスを実感させてくれるのがこの詩だ。
18番ではシェイクスピアは美青年のすぐそばにいる。愛する「君」を目の前にしているからこそ感動的な「殺し文句」が生まれたのだが、《詩による永遠》は二の次で「君」の気を惹くのが第一の感がある。それが証拠に7回も「君」が使われている。一方、65番には「君」が一度も出てこない。シェイクスピアは人間の側からではなく永遠の側から歌っているのだ。そして、最後の最後、喪の黒が永遠の黒に変容する奇跡のくだりではじめて「私の愛するひと」が三人称で登場する。こういった抑制が水面下に隠れた厚い感情の層を感じさせてくれるのではないだろうか。










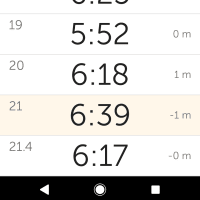
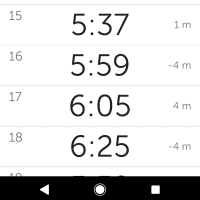
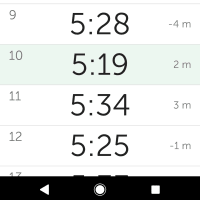
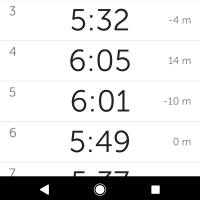
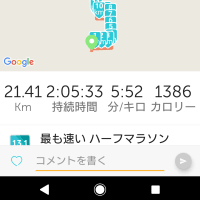





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます