
古くから沙沙貴(ささき)郷・佐々木庄と称されたこの辺りは
近江源氏(宇多源氏)佐々木発祥の地です。
沙沙貴神社には少名彦(すくなびこ)神・ 大彦(おおびこ)神・仁徳天皇・
宇多天皇・敦実親王(宇多天皇の皇子)を祭神として祀っています。
はじめ古代の豪族佐々貴山公(ささきのやまきみ)一族の氏神でしたが、
平安時代中期以降は、佐々木氏の氏神として
崇拝されてきた『延喜式』式内社の古い社です。
佐々木氏が別の系統の氏族であった佐々貴山公との間で、
婚姻関係を結びながらしだいに勢力を広げていったと考えられています。
この辺を本拠地とした佐々木秀義は、保元の乱で源義朝に属し勝利しましたが、
続く平治の乱で敗れ、関東に息子らを連れて落ち延びました。
その後、源平合戦で頼朝に従い手柄を立てた秀義の子、
定綱が近江の守護に任じられて本拠地に戻り近江各地を治めました。
その子孫は六角氏・京極氏に分かれ、戦国史にもその名を残しています。 さらに佐々木氏の子孫には、大名家の黒田氏や旧財閥の三井氏、
乃木希典らがいて、一族は全国で300万人にのぼるとされ、
例年10月第2日曜日に行われる近江源氏祭には、
全国から佐々木氏ゆかりの人々が集まり、
宇多天皇が愛護したという舞楽を奉納し、先祖を偲んでいます。

JR安土駅南側から沙沙貴神社への道順を追って画像にしました。

駅前にたつ織田信長像



駅から15分ほどで鎮守の森に囲まれた沙沙貴神社に到着しました。

表参道の鳥居の「佐佐木大明神」の神額は源頼朝の筆と伝えていますが、
文字は風化されて読み取れません。

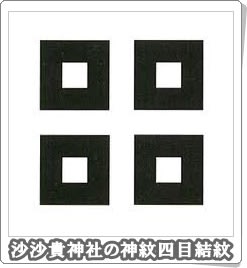
境内の所々で神紋であり、佐々木氏家紋の四目結紋が目につきます。




江戸時代中期に再建された楼門や19C中期再建の本殿・拝殿他八棟は県指定文化財、
茅葺の楼門からは東回廊・西回廊が延びています。

舞殿

拝殿

拝殿の背後に本殿
ここで源平合戦で活躍した佐々木一族を辿ってみましょう。
宇多天皇の末裔にあたる佐々木秀義(高綱の父)は、宇多源氏、
近江源氏を称します。秀義は源為義(頼朝の祖父)の娘を妻とし、
平治の乱では義朝軍として戦います。
敗戦後、平家に従わなかったため、先祖からの相伝の土地である
佐々木荘(現、滋賀県安土町南部一帯)を没収されます。
仕方なく藤原秀衡に嫁いでいる伯母を頼って息子たち(太郎定綱・次郎経高・
三郎盛綱・四郎高綱)とともに奥州に奥州に向う途中、
相模国まで来たところ渋谷庄司重国が秀義の勇敢な行動に感心し
勧められるままそこに身を寄せ二十年を過ごします。
息子たちはこの間に逞しく成長し、ひそかに伊豆の頼朝の許に出入りし、
頼朝が挙兵の際には伊豆国目代山木兼隆攻めの主力となって戦い、
兼隆を討取り緒戦を飾りました。
『平家物語』には、佐々木高綱・盛綱が活躍する様子が描かれています。
◆佐々木四郎高綱「平家物語・巻九・宇治川の事」
以仁王の令旨を受けた木曽義仲は木曽で挙兵、平家を都落ちさせ
都に入った義仲はまもなく後白河院と対立し、院は頼朝に義仲追討を命じます。
院宣を受け源範頼・義経兄弟が京へと二手に分かれ東と南から攻め上り、
範頼が瀬田川に義経は宇治川に迫ります。
義経勢の中の佐々木四郎高綱・梶原源太景季が頼朝に賜った名馬で
どちらが先に宇治川を渡って敵陣に突入するかと争います。
佐々木高綱は梶原景季を騙し、先陣をきって宇治川の流れを渡り
向こう岸に駆け上がりました。これを機に義経勢は一斉に川を渡り
義仲勢は総崩れ、高綱と景季の宇治川先陣争いは、平家物語名場面の一つです。
◆佐々木三郎盛綱「平家物語・巻十・藤戸の事」
一ノ谷合戦で平家に大勝した源氏軍は西国へと兵を進め、吉備国児島
藤戸海峡を挟んで源平両軍は陣どりました。盛綱が平氏のいる対岸に渡れる
浅瀬を知る漁師に案内させると、なるほど騎馬で渡れる浅瀬があります。
手柄を独り占めしたい盛綱は、口封じのためその場で漁師を刺し殺し、
郎党とともに海に飛び込み一番乗りを果たします。
これを見た源氏軍は続々と海峡を渡り児島を占拠、敗れた平氏は屋島へと退きました。
このエピソードを元にして作られたのが謡曲「藤戸」で、
盛綱が殺した漁師の老婆に恨まれ、懺悔し供養するという物語です。
『アクセス』
「沙沙貴神社」近江八幡市安土町常楽寺2 JR安土駅下車
主な祭礼 4月第1土~日沙沙貴まつり 10月第2日曜日近江源氏祭
『参考資料』
「滋賀県の地名」平凡社 「滋賀県の歴史散歩(下)」山川出版社
現代語訳「吾妻鏡」(1)吉川弘文館
そのお陰ではるか昔に必死に生きた人々の様子や気持ちを推し量りながら追体験しているような気分になります。
丁寧な参考資料のご提示、本当にありがとうございます。
観音寺も鳥羽離宮址を歩いた時のものです。
yukarikoさんのようにお仕事をされて、その合間に
あちこち旅行をなさって記事にされるのとは、ちょっと訳が違います。
記事を見せていただきながら、体力、気力の違いをいつも痛感しています。
私はといえば、お忙しい中、こんな記事でも毎回読んで頂けることが、大きな励みになっています。ありがとうございます。
規模が小さいから、友人達を誘って立ち寄るほどでもないかと勝手に決めてしまっていました。
桜が咲き初めた赤い橋を眺めて次回??の記事を楽しみに待ちますね。
広い二条城見学でくたびれてしまいます。
西行伝説も「文覚上人」「遊女妙」等まだまだ有名な話があります。
特に「遊女妙」の墓のある「江口の君堂」はこの近くですが、またの機会にさせて頂いて、
西行は次の弘川寺で終わりにさせていただきます。
仁和寺、法金剛院、勝持寺、弘川寺と西行に縁のある寺々の写真を見て頂きながら、花のない写真ばかりなので、桜には少々早いのですが西行の最後を
桜の花で飾ってあげたくなりました。