
西行(1118~1190)は俗名を佐藤義清(のりきよ)といい、鳥羽上皇の北面の
武士として活躍しました。また家人として徳大寺家に仕えますが、
23歳の時に出家、諸国を行脚し、多数の和歌を詠み後世に影響を与えています。
崇徳天皇(1119~1164)は鳥羽天皇の第一皇子として生まれ、
母は徳大寺家、権大納言藤原公実の娘・待賢門院璋子で、
雅仁(後白河天皇)は、同母弟にあたります。
崇徳天皇の出生について、鎌倉時代の説話集『古事談』には、
「実は天皇は鳥羽天皇の祖父・白河法皇と璋子の間に生まれた子で、
人々はこれを知っていて、鳥羽天皇も崇徳を叔父子とよんでいた。」とあり、
これが保元の乱の一因になったとされています。
この間の事情は、角田文衛氏が『崇徳天皇の生誕』、『王朝の残像』、
『待賢門院璋子の生涯』で、詳細な研究結果を発表されています。
崇徳天皇は優れた歌人で、ひとつ違いの西行とは和歌を通じて親交がありました。
西行が歌人として始めて認められたのは34歳の時です。
勅撰集『詞花和歌集』に読み人知らずとして一首入りました。当時、
西行はまだ歌人としても名をなさず、身分も低いため名をかくされたものです。
この歌集は、当時、歌壇の中心的存在であった崇徳上皇が、
藤原顕輔(あきすけ)に命じて選ばせ、仁平元年(1152)に完成しました。
その後、藤原俊成が撰者となった勅撰集『千載集』に18首入りましたが
千載集が完成した時には西行は71歳になっていました。
崇徳上皇も勅撰和歌集に77首も入っています。
生まれながらにして暗い影を負わされた崇徳上皇は悲しい歌を数多く詠んでいます。
西行と崇徳上皇は歌の上だけでなく、身分の違いをこえて
互いに親しい感情をいだいていました。
ある時、西行に縁のある人(一説に藤原俊成とも)が崇徳上皇の勘気にふれたので、
西行が許しを願う歌を上皇に送ると西行の願いを聞き入れて許されたことがあります。
上皇から西行が深く信頼されていたことがうかがわれるエピソードのひとつです。
皇位をめぐる争い、保元の乱で弟の後白河天皇に敗れた崇徳上皇の許へ、
いち早く西行は馳せ参じています。上皇は仁和寺の同母弟、覚性法親王を
頼って仁和寺に入ったのです。敵方に囲まれた仁和寺の上皇を訪ねることは、
身の危険をともないますが、それを承知で西行は思い切った行動をとっています。
二人の間には深い心のつながりがあったことが知れます。
そして崇徳上皇は讃岐に配流され、西行は心を鎮め仏道修行に励まれることを
願った歌を上皇の許に数多く送りましたが、
たずねて行くことはしませんでした。その心中は分かりません。
♪その日より落つる涙を形見にて 思い忘るる時の間もなし 西行
(讃岐へ配流された日から、別れの日に流した涙を形見にして、
上皇のことは片時も忘れたことはありません。)
配流の九年後の長寛二年(1164)八月、崇徳上皇は46歳で崩御、
その死は狂死、病死、自殺他、二条天皇(後白河法皇の子)の命を受けた
三木近安によって御子たちとともに柳の木の下で暗殺されたともいわれ、
そこには「柳田」という碑が立っています。
大魔王となって子々孫々まで皇室を滅ぼさんといわれたことが都に伝わり、
始末されたとしても不思議ではありません。これも崩御にまつわる伝説の一つです。
崩御の段階で崇徳上皇という謚(おくり名)は、まだなく
「讃岐の院」とよばれていました。
十四年後の安元三年、鹿ケ谷の謀反が勃発した時、
これは讃岐の院の祟りであるとされ、
その霊を慰めるため「讃岐の院」の院号が「崇徳院」と改められ、
保元の乱の古戦場、春日河原に「粟田宮」が祀られました。
上田秋成の『雨月物語』の巻頭を飾る白峰の「逢坂の関守に許されてより、秋来し山の
紅葉見過ごしがたく、浜千鳥の跡踏みつくる鳴海潟、不尽(富士)の高嶺の煙、
浮島が原、清見が関、大磯小磯の浦々、紫にほふ武蔵の原、塩釜の凪たる朝景色、
象潟の海士が苫屋、佐野の船橋、木曽の桟橋、心のとどまらぬかたぞなきに、
なほ西の国の歌枕見まほしとて…」という道行き文に誘われて、
白峯御陵を参拝したのはあちこちに山藤が咲き始める平成14年の晩春、
「西鉄旅行四国霊場巡礼」四国遍路のバスツァーでした。
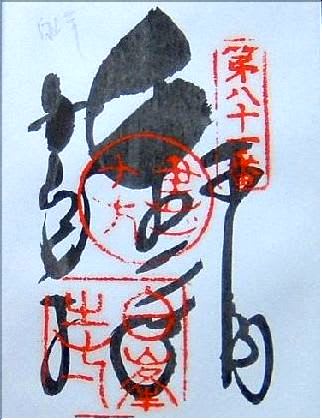
四国八十八ヶ所の八十一番札所「白峯寺」は高松市の少し西、
青、白、黒、紅、黄の峰々が連なる五色台の中、白峰(337m)にあります。
白峯寺の石段下、杉木立の奥に白峯御陵はありますが、
お遍路さんで賑わう境内と違って、ここは訪ねる人もない寂しい御陵です。
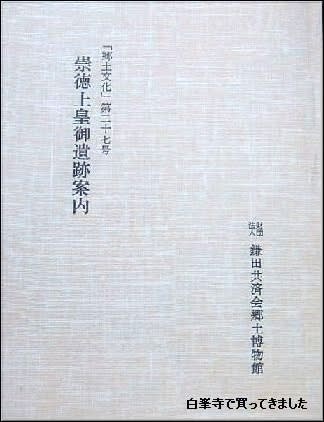

崇徳天皇白峯陵(平成28年3月撮影)

頓証寺殿(とんしょうじでん)は崇徳院の御廟所で
傍には参詣した西行をあらわした石像や西行と崇徳院の歌碑、
勅額門(勅使門)には保元の乱で崇徳院方について戦った源為義、為朝の像、
頓証寺殿後方には源頼朝寄進の燈籠や、
皇室、幕府が崇徳院の霊を慰めるために寄進したものも多く残っています。
♪啼けば聞く聞けば都の恋しさにこの里過ぎよ山ほととぎす
♪浜ちどり跡は都に通へども身は松山に音(ね)をのみぞ啼く
(浜ちどりの足跡のような文字だけは都に行くけれども、
我身は遠い松山に都が恋しくしのび泣いている。)
(上皇が写経を都に送った時添えた歌)
西行が讃岐へ行ったのは、上皇の死から四年後の仁安三年(1168)の
秋のことで、御陵参拝と弘法大師修行の地巡礼のために旅立ちます。
西行は讃岐につくとまず上皇が住まわれていた「雲井の御所」や
崩御される迄過ごされた「鼓ヶ岡行在所」を訪ね歩きますが、
その遺跡は跡形もなくなっていました。
♪松山の波に流れて来し舟の やがて空しくなりにけるかな
(松山で波に流され着いた舟がやがて朽ち果てたように
崇徳院は崩御されてしまったのだなぁ)
♪松山の波の景色は変わらじを かたなく君はなりましにけり
(松山に寄せる波は変わっていないのに、崇徳院は跡形もなく
なってしまわれたのだなぁ)と落胆した気持ちを詠み、
御陵へ向かいますが、粗末な御陵は荒れはてて
蔦や葛がからまり見る影もない有様です。
♪よしや君昔の玉の床とても かからん後は何にかはせん
(かって都でお住みになりました金殿、玉楼といってもこのように
崩御された後では何になりましょか、何の役にも立たぬものなのです。)
西行の詠んだこの三首の和歌が、崇徳上皇の亡霊と西行が
語り合ったとの伝説を生み、文学や芸能に大きな影響を与え、
『保元物語』、『撰集抄』、『沙石集』や謡曲『松山天狗』などがつくられ、
さまざまに語られてきました。
『保元物語』、『松山天狗』では、西行が「よしや君 昔の玉の…」の歌を詠むと
やがて廟所が鳴動したとあります。
江戸時代になると上田秋成は、『雨月物語・白峰』の中で、
崇徳院の御陵に詣でた西行が、あまりの荒廃ぶりに嘆き、
そこで読経しながら、一夜を過ごしていると「円位(西行の法号)」
「円位」と崇徳上皇の霊が呼びかけ、保元の乱の経緯や配流後の宮廷や
平家一族への恨みを盛んに語ります。そして大魔王と化した上皇の霊と
西行との論戦を伝説を交えながら幻想的に描いています。
崇徳院ゆかりの地(西行法師の道)
崇徳院ゆかりの地(白峯御陵)
崇徳院ゆかりの地(白峯寺)
『アクセス』
「白峯寺」「白峯御陵」 香川県坂出市青海町
JR予讃線坂出駅よりバス20分 「高屋」下車 徒歩約1時間
『参考資料』
高木きよ子「西行」大明堂 白洲正子「西行」新潮社 村井康彦「平家物語の世界」徳間書店
佐藤和彦・樋口州男「西行のすべて」新人物往来社 「崇徳上皇御遺跡案内」鎌田共済会郷土博物館
新潮日本古典集成「雨月物語 癇癖談」 新潮社 「香川県大百科事典」四国新聞社
日本古典文学大系「保元物語 平治物語」岩波書店
検索して「松岡正剛」の千夜千冊に書かれた言葉で却って興味が湧きました。
それは次のように書かれていました。
第一話は崇徳院天狗伝説を蘇らせる「白峯」で、不吉と凶悪が跋扈する夜の舞台が紹介される。読者はここでのっけから覚悟しなければならない。何を覚悟するかというと、幻想がわれわれの生存の根本にかかわっていることを覚悟する。なにしろ主人公は西行なのである。
一体どんなお話かと考える紹介文ですが(笑)sakuraさんがお書きくださったあらすじなら探して読んでみようかしら?
とおもえたりして…。
でもお二人の交わす歌の調べの物悲しさは二人の生きた時代を知らない人々にも凄い影響を与えたのですね。
ですが、9篇とも短編なので時間がなくても
すぐ読めます。
よければ「白峯」をコピーして、次回お持ちします。
私は昔浅茅ヶ宿を映画でみました。
評判のよくなかった後白河と違い、できのいい
重仁親王(崇徳院の子)が帝位の道を絶たれたことも、崇徳院への同情となったのでしょう。
歴史上の敗者をひいきにしてしまう「判官びいき」でしょうか。
私達でも残された和歌で二人の生きた時代を少し甦らすことができますね。
有名なお話なので、図書館で時間のある時に探してみます。
月に1~2回、姑を連れて芝生図書館に本を借りに行きますから。
利害が入り組み、どちらが正しいかも分からない時代、立場をはっきりさせる事すら危なくて言えない人間はひたすら頭を低くして通り過ぎるのを待つより他はありませんね。
内心の後悔と哀惜をこめて色々な歌や物語が編まれるのでしょう。
利害の絡まない者は後世の道徳で考えて『あんまりだ!』と同情する人に感情移入するのかも。
でも心に訴える歌がとても多いですね。
お二人とも沢山選ばれるのも当然だと思います。
図書館で借りた円地文子の訳本が手許にあります。
「白峯」はじまりの歌枕を並べながらの道行き文は、繰り返し読むと自然リズムが生まれます。(ここは原文で味わうのがベスト)
歌枕は西行が旅した所でしょうか。
図書館にも訳本は沢山ありますが、円地文子の訳本が原文の良さを損なってない気がしています。(私の勝手な見解です。)
短篇なのでゆっくり読んでも30分位で読めますし、
コピーしてもほんの数枚ですから大丈夫です。
お読みになった後は捨てておいてください。
いつもご指導頂いているyukarikoさんへ私にできるほんのささやかな事です。
西行は北面の武士であるだけでなく、「徳大家」の家人(家臣)でもあったので、
鳥羽上皇には可愛がられていたようですし、崇徳院とは、特に親しく同情もするし、西行出家の原因を
この政治原因説ととなえる研究者もいます。
コメント頂いたように西行はじっとしているより仕方なかったのかも知れませんね。
※佐藤家の故郷にある荘園は、「徳大家」に形の上で寄進して保護を受けていました。土地を仲立ちにした主従関係です。(一応佐藤家の荘園)
公家権門(院、女院、摂関家)や寺社権門(延暦寺、園城寺、興福寺、東大寺)にこの頃荘園の寄進が盛んに行われました。
佐藤家の隣地の荘園が、鳥羽上皇に荘園を寄進したのもこんな事情です。
高槻の土室も、平安時代待賢門院の法金剛院の荘園でした。