今年も当ブログにお付き合い下さり誠にありがとうございました。
あと一日ありますが今年はこれで最後の投稿とさせていただきます。
このブログでガソリンスタンドに関する記事を書き始めて7年くらいになるのかな...
業転、仕切り格差(卸格差)によって地場店が苦しい経営を強いられていること。そして地場店が姿を消すことで灯油難民が発生しているのだということを、兎に角世間に知ってもらおうと、その一念でやってきました。
世間の人はどこかの店が閉店したらすぐに「潰れた」という言い方をするけど、「そうじゃないよ」って知ってほしかったのです。
でも田舎の古い小さなガソリンスタンドがいくらそれを叫んでも負け犬の遠吠えみたいなところもあって、この7年ブログ記事を投稿しながらも歯痒い思いでいました。
でも今年、
ついに、仕入れ値に10円以上もの格差があることが毎日新聞で報道されました。
<石油元売り5社>ガソリン卸を価格操作 給油所半数は高値
それに先立ち、石油業界のアナリストの㈱伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー 伊藤 敏憲氏によって、
このような不合理な商慣行が採算を半ば度外視した価格競争を生み出す原因になったり、
販売事業者間での競争をゆがめ、
本来なら淘汰されるべきSSや事業者を存続させたり、
逆に勝ち残るべきSSや事業者を追いやったりしている
こうした記事がネット上に現れたのです。
業界(元売・系列店に業転を斡旋してきた組合・他社買いしてきた系列店)は、“業転”については消費者に知られたくないという思いがあるのかも知れませんが、隠し通すことなどできません。
販売価格の大き過ぎる差
ガソリンスタンドの激減
給油難民・灯油難民の顕現化
それによってガソリンスタンド減少の原因が価格差にあることに気付くのは当然で、
価格差に焦点が当てられることになれば、差別対価だけでなく過去の業転問題も浮かび上がる。
消費者を欺く販売店を容認している元売と監督官庁は犯罪幇助
この誹りから逃れることは出来ないと思います。
しかしまぁ、何はともあれ卸格差が全国紙で公にされたことは非常に大きな出来事でした。
今まで暴利だ悪徳だと誤解されながらも、また、自己資産を取り崩しながらも、安定供給を肝に全量系列仕入れを貫いてきた販売店の心が救われました。
来年は、仕切り格差が縮小され、少しでもマージンが回復し、そして・・・
投入した自己資産を、ちょびっとだけでも回収できますように!
((^┰^))ゞ
では皆さま、良いお年を!
\(^▽^)/
業界紙には元売の再編を控えて系列入りしたいPBが増えているという記事があります。
「時代の商流に乗る」と言えば聞こえは良いかも知れませんが.....
(st31掲示板より)
>灯油は、~~~自分手配が当たり前(の)油種
消費者の方には意味が分からないと思いますので説明させて頂きます。
業転は大昔から存在していました。
過当競争が始まる以前から、元売のマークを掲げているにも関わらず、灯油や軽油は“安い業転もの”を仕入れて何食わぬ顔で(系列モノとして)販売していた系列販売店が結構あったようなのです。
(当時は販売価格には殆ど差がない時代でしたので業転を仕入れることで粗利は倍になっていたと思われます)
そして元売も連帯保証している揮発油(ガソリン)と違い、灯油・軽油は系列店の他社買いを黙認しているーという話です。
>灯油・軽油は正規の系列ルートから仕入れないで業転から仕入れるのが当たり前
?!
これを知った時、私はとても驚きました。
一消費者だった私から見れば、
そんな首を傾げるような行いが罷り通っている、又それを業界を上げて是正していこうともしない、モラルの低い業界。
品質には違いが無いとしても、又今のように販売価格差がある状況では、「安ければそれで良い」「安い方が良い」という消費者もいるとは思います。
でも、企業倫理としてはどうでしょうか?
規制緩和以前からこのようなことが罷り通っていた業界だから、規制緩和で価格競争が始まったとき、ガソリンまで業転から仕入れだす系列販売店が簡単に現れたのだと思います。
(※背に腹は代えられないとして他社買いを始めたところは別としてー)
結局、今の販社や異業種による異次元の安売りも、
最初から差別対価を問題にして取り組まずに業転に逃げ、
「品質は同じなのだから」「元売だってバーターしてるのだから」と自分たちの行い(他社買い)を正当化し、
「水は低きに流れる」と安値仕入れによる安値販売を行って、全量系列仕入れの同業者をスケープゴートにしてきた“報い”なのだと思います。
PS
エネ庁・公取委が関与することになるであろう石油精製・流通研究会による「取引慣行策定」
これによって卸格差が無くなることはないと思います。
「販売数量が多ければ安値」には変わりなく、
ただ「いくら売ればいくら安く」と、いくらの部分の数量と金額が明確化されるだけなのではないでしょうか?
つまりそのためには今以上に“量”に重点を置かねばならなくなる販売店があるだろうーということです。
過当競争は終わらないと思います。
あれ? ココがいない、どこ行った?
ココ~!ココ~~!と探したけれど見つからない。
わ!あんなところにいつの間に?!



タマはカーペットのニオイを嗅いで、「ハァーッ」
ニオイ
匂いなのか、臭いなのか、
それは不明(^▽^;
12月27日燃料油脂新聞より
住民、自治体、危機感薄く SS過疎化厳しさ増す
地区で唯一の店が廃業を決断するまで、住民や自治体に危機感が現れないという指摘がある。
一民間企業の事業活動ではあるものの、地元ライフラインの維持という社会的に重要な役割を担っている点が軽視される向きがある。
地元客理解で運営継続
***
「セルフより10円も高く売っているのだから窓拭きゴミ捨て他諸々のサービスはして当たり前。そのサービスが無いのならフルへ行く理由がない」
以前、このような書き込みをインターネット上の掲示板でみました。
「13円高く売っても5円しか粗利がないときがある」
これが地場3者店の内情でも、卸格差の事を知らない消費者にしてみればインターネット上の書き込みは真っ当な意見です。
しかし卸格差による低マージンで、自己資産を取り崩しながら、満足に休みも取れずに営業を続けている身には辛いものがあります。
>地元ライフラインの維持という社会的に重要な役割を担っている
この思いが営業を続けるための精神的な支えだとしても、心を折られる場面は多々あります。
地域住民や自治体の無関心・無理解が廃業を決断させる要因となり得ることもあるでしょう。
12月26日ぜんせきより
「取引慣行策定」エネ庁・公取委関与を
需給適正化・販社問題など列挙 石油精製・流通研究会
全石連 河本副会長・専務理事
「仕切り価格の建値化、形骸化が進んでおり、コストが分からずに値付けをしていては商売のイロハのイができていないのも同然なので、ぜひ改善してもらいたいとの要望があった」と強調。
そのうえで「エネ庁と公取委が深く関与することによって、公正、透明な仕切り価格体系が形成されるような取引慣行のガイドラインをぜひ実現させてほしい。特に公取委に強くお願いしたい」と取引適正化ガイドラインの策定を強く求めた。
子会社問題については
「連結決算なので実態はわからないが、子会社単体では赤字という噂がある。子会社SSがこれ以上増えていくことに対して疑問視する意見がある」と指摘。エネ庁に対し「子会社の実態も定期的にヒアリングし明らかにしてほしい」
さらに仕切価格を下回る極端な廉売事案の背景に存在する供給過剰問題を指摘。
「(エネルギー供給構造高度化法の)第三次告示を実施し、過剰設備の削減や設備最適化の措置対策を行うことで乱売合戦が減って、SS過疎地が増えないようにすべき」と提言するとともに、「国として桟橋やタンクなどの輸出インフラ整備の予算措置を講じ、需給バランスを保ってほしい」と要請。
加えて、「前回会合の講演の中で、『米国にはSS産業はなくなったと。いずれは日本もそうなるだろう』との指摘にはものすごい違和感がある。販売業者は石油製品の安定供給を通じ、災害対応などの社会貢献に取り組んでいるという自負心がある。絶対にそうはならない。またはそうしてはならない」と強く訴えた。
元売代表委員
(エネ庁がヒアリングを通じ仕切価格の建値化状況を把握することについて)「政府が仕切価格の決定方式・水準にまで踏み込み、元売の仕切価格を指導するということにつながるような対応を行うことはいかがなものか。取引のあり方については、企業間の自律的な事業活動に委ねるべき」と強調。
差別対価に対する独禁法上の基準の明確化や信頼性・透明性の高い価格指標の構築を訴えた。
エネ庁
(第三次告示の取り扱いについて)「精製設備の廃棄を誘導することが長期的にみて本質の解決にはならないのではないか」
元売代表委員
「2度の高度化法によって資本の枠を超えた提携や企業再編に踏み込んできている。まだ多いと言って切ってしまうと、安定供給が担保できない可能性もある。精製能力の削減ですべてが解決することはない」
全石連河本副会長・専務理事
「もちろん過剰設備を廃棄するだけでいいと単純に言っているわけではない。身の丈にあった生産をしていただき、適正な利益が取れるような仕切価格体系が構築されれば問題はない。これが何十年も言ってきても直っていないので申し上げた」
(※↑これが私の中でイメージしてきた“中小零細組合員の為にご尽力下さる”河本さんです)
***
ガソリン代金の中には(消費税以外に)1リッター当たり約56円もの税金が含まれています。
(しかも消費税は2重課税です)
これだけの税金が含まれているガソリン、
激戦地区では僅か数円の粗利しか取れないガソリン。その販売価格に20円もの差がある地域もある。
(注:高値店が暴利を貪っている訳ではありません。念の為)
これだけの税金が含まれている公共性の高い商品の“価格”です。
国はこんな出鱈目を放置したままには出来ない筈ですよね。
でもこれが・・・
>何十年も言ってきても直っていないので
ガソリンスタンドの数は半数にまで減り、今現在も一日に3.5SSが減り続けています。
PS
私たちガソリンスタンドは、取引先の倒産などで貸し倒れにあっても仕入代金は卸先に支払わなくてはなりません。
もちろん 税金分も含めて、です。
私たち系列販売店は、元売(特約店)に取引金額の2か月分以上を担保として差し出しています。
もちろん税金分を含めて、です。
12月30日追記
担保については色々です。コメント欄をお読みください。
「100%系列仕入れで商売できる環境を」
元売再編後 需給バランス改善期待
(12月24日燃料油脂新聞より)
「近隣の安値にどうしても価格が引っ張られてしまう。業転をある程度仕入れて対応しているが勝負にならない。根本にある価格差を何とかしてもらわなければ、当店のような小規模店は商売できない」
「元売再編後に果たして需給は縮まってくるのだろうか。現在はその兆しさえも見られない。市況低迷を業転でしのいでいるが、真の解決策にはならない。100%系列仕入れで商売できる環境を切に願う」
価格差により深刻な影響を受けるのはこれら激戦区の地場SSだけではない。
採算市況を堅持する中山間地域のSSも顧客流出に見舞われている。
**以下masumi
>100%系列仕入れで商売できる環境を切に願う
業転でしのいでいる店でさえそうなのです。
業転玉を仕入れているPBや他社買いをしている一部の同業者から誹謗中傷されながらも、ずっと「業転は一時凌ぎにしかならない」と書いてきました。
官公需や補助金も真の解決策にはなりません。
「競争制限しない」でも書いたように、新規出店してきた元売系列フル店(2者店)が当店の仕切りと同額の価格看板を掲出したのはもう20年近くも前の話です。
>2014年後半ごろから元売りの卸価格の設定が割高になった。割高な価格は、競争の激しい地域を中心に値引きをするための原資になっている。(http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/business/mainichi-20161218k0000m020068000c.htmlより)
この2014年後半ごろというのは、
全量を業転から仕入れているPBでさえ元売系列の販売子会社や大手特約店の廉売に太刀打ちできなくなった頃じゃないでしょうか?
(実際にはもっと前からそういう地域もあったと思いますが、ハッキリと顕現化したのが2014年の後半?)
それから
>割高な価格は、競争の激しい地域を中心に値引きをするための原資になっている。
これも地場3者店の感覚ではこうなります。
>地場零細店への割高な価格は、販売子会社と販売数量の多い大手や資本提携をしている特約店へ値引きをするための原資になっている。
言い方を変えれば、
安値量販するガソリンスタンドで燃料を購入している消費者のために、地場3者店で燃料を購入している消費者が割高な価格を負担させられているー
元売による中小SS生存不能な現卸格差は、消費者に対する差別行為だと思います。
夕方電話がありました。
私は洗車でタイヤを洗っていたのでこうちゃんが出ました。
タイヤを洗っている私の横へ来てこうちゃんが言いました。
「昼前にポリ容器4つ、灯油、あったやろ。あれ、40リッターしか(POS)打ってなかったぞ」
「え?」
「今の電話、レシートみたら40リッターになってたからって、わざわざ電話くれはったんや」
「わ、マジで? 、ヽ`アセ(;~▼~;)アセ、ヽ`」
「ホンマにもう、大丈夫かいな。|;-_-|=3 フゥ 」
***
昔もありました。・・って、それは私じゃないですよ~
、ヽ`(~д~*)、ヽ`…(汗)
当時のバイトの子が燃料と洗車と中掃除と灯油の売り上げのうち、灯油をPOSで打ち忘れていたのを「レシートを見たら・・・」と言って、翌日わざわざ届けてくださった方もおられます。
お客様は有難いのです。
JXと東燃の新会社、来年4月発足を総会承認 巨大元売り「1強」に懸念も
経営統合で合意した石油元売り首位のJXホールディングス(HD)と3位の東燃ゼネラル石油は21日、それぞれ臨時株主総会を開き、会社側が提案した統合決議案を承認した。来年4月に新会社「JXTGホールディングス」を発足させる。直近の連結売上高の単純合算は11兆円を超え、ガソリンの販売シェアは5割に達する。国内で圧倒的な規模の巨大元売り誕生で、大手5社が激しいシェア争いを繰り広げてきた石油業界は「1強多弱」の新たな競争環境に突入する。
出光・昭シェル不透明
JXHD傘下のJXエネルギーと東燃を合併させ、東燃の1株に対してJXHDの2.55株を割り当てる株式交換方式で統合する。JXTGホールディングスの社長にはJXHDの内田幸雄社長(65)、副社長には東燃の武藤潤社長(57)の就任が内定している。
両社は人員削減や重複事業の解消などで経営合理化を加速させ、2019年度の連結経常利益を5000億円以上に引き上げる目標を掲げる。
石油元売り各社では、2位の出光興産と5位の昭和シェル石油の合併計画が出光創業家の反対でめどが立たず、4位のコスモエネルギーHDは単独での生き残り策を模索する。規模の拡大で先行する新たな“巨人”が順調に合理化などの統合効果を発揮していけば、他社は苦境を強いられる可能性がある。
もっとも、徹底的な経営合理化に乗り出すJXTGの統合効果は未知数だ。
JXと東燃は、川崎市内の石油化学製品の製造拠点を一体運営したり、製油所の統廃合を進めたりすることで統合後3年以内に年間で1000億円以上の収益改善効果を出す計画。一方で、消費者に身近なガソリンスタンドはJXの「エネオス」、東燃の「エッソ」「モービル」「ゼネラル」のブランドを当面維持するため、統合の相乗効果をどこまで高められるか不透明だ。
国際的環境も厳しく
JXと東燃の統合については、国内販売シェアが突出するものの、公正取引委員会が19日に独禁法に基づく審査を終了し承認した。背景には、人口減少やエコカーの普及で石油需要が1999年度をピークに減少傾向が続く中、経済産業省が業界全体の生産規模を適正化するため、「エネルギー供給構造高度化法」に基づいて製油所の統廃合や合併を求めてきたことに加え、脱石油政策や地球温暖化対策など国際的な厳しい競争環境がある。
経産省は、出光と昭和シェルの合併による「2強体制」を描いていたが、合併の実現が見通せないことで、市場は当面JXTGのみが突出するいびつな構造となってしまう。JXTGの統合効果を上げることは政府の狙いと合致するが、出光と昭和シェルの合併の行方によっては巨人誕生の弊害が生じる懸念もある。(古川有希)
***
ブランドの統一は個人的にはしてほしくないけど、
ブランドを統一しなければ、統合効果は薄いよね?
12月21日 22:46(朝日新聞)
国税庁は21日、お酒の過度な安売りを防ぐルールをまとめた。利益が出ない赤字販売を続けた場合は、罰則として販売免許の取り消しもできるようにする。来年6月に施行する予定だ。
ディスカウント店などの安売り攻勢に苦しむ、中小の酒販店を守るのがねらいだ。ただ、価格競争がゆるむことで、消費者の利益を損なう恐れがある。
今年5月に成立した改正酒税法などで、財務相が「公正な取引の基準」を定めることになり、国税庁が基準を検討。21日に開かれた有識者らの国税審議会で了承された。
昨日、組合から補助事業受付についてのFAXが届きました。
その3枚目と4枚目

ローリーの補助金、不正受給の噂は耳にしていました。
灯油のローリー購入補助金を、渡しちゃダメです。
不正受給を見つけ出してください。
そして補助金を返却させてください。
過疎地なら補助が3分の2も受けられる配達用ローリー。
当市はセルフが10軒近くあるのでSS過疎地でも供給不安地域でもありません。
セルフの安値に顧客を流出させ販売数量を減らし、疲弊し、
それでも配達を続けるために、“自力で”(またまた自己資産を投入して)ローリーを調達しました。
新しいこうちゃんのローリー
疲弊させられてから長いこの業界の地場店は、施設もそうですが「ローリーもそろそろ」という所も多いのではないでしょうか。
そのローリーが使えなくなり、その費用が捻出できず・・・。などとなってしまうとすれば、それは如何なものでしょうか。
だからもう一度書きます。
小口配達を担い続けている地場業者の経営を窮地に追いやる安値販売をしているセルフを運営しているような企業には、絶対に補助金を渡しちゃダメです。
ローリーの補助条件は、過疎地でなくとも小口配達を担い続けている地場零細店に広く行き渡らせてあげてほしいーと思うのは私だけでしょうか?
セルフの安値に顧客を流出させ販売数量を減らし、疲弊し、それでも小口配達を続けている。
全国にはこうした地場零細店がまだまだ頑張っているのです。
炬燵の天板を除けて、足や手で布団を下からツンツンしたり指を這わせたりして遊んでやります。




ふっ(笑)
言っとくけど、ワタシが母ちゃんの腹筋を鍛えてあげてるのよ。

あ~よく温もったニャ(炬燵から出てきたココ)
さて何して遊ぼ
やっぱ高い所が落ち着くニャン
・・・
ウルサイ父ちゃんはいないかニャ?
あ、おった。。。
・・・
ガマンできにゃいニャっと
嚙んでみる。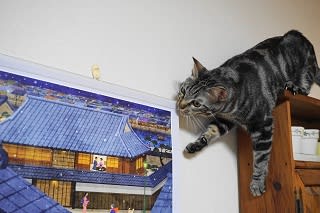
ガジガジ
ん~~~~っ、このコレが気になるニャンよ
おっとっと
「コラッ!ココ、何してる!!」
慌てて逃げるココちゃんナリ~~~(笑)
出光、昭和シェル株式31.3%を取得 統合協議は継続
(ロイター)[東京 19日 ロイター] - 出光興産<5019.T>は19日、昭和シェル石油<5002.T>との経営統合を進めるため、英蘭ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS)<RDSa.L>から昭和シェルの株式を取得したと発表した。公正取引委員会からもこの日、株式の取得について承認を得ていた。
取得したのは議決権ベースで31.3%。出光は当初、33.3%を取得する計画だったが、創業家が統合を阻止する狙いで取得した昭和シェル株と合わせると、公開買い付けのルールに抵触する水準(発行済み株式の3分の1超)になる恐れがあるため、多少の余裕を残し、取得株数を減らした。
取得価格は予定通り1株当たり1350円で、総額は1589億円。今回取得しなかった株式については、RDSが少数株主として保有する。
出光と昭和シェルは、今後も経営統合を目指して協議を続ける。
創業家は統合になお反対しており、先行きは不透明だ。
創業家の代理人を務める弁護士事務所はロイターに対し、「合併には引き続き反対。株式取得後、会社側がどのような経営判断をするか状況を見ていく」と話した。
一方、公取委は同日、来年4月に予定している石油元売りのJXホールディングス<5020.T>と東燃ゼネラル石油<5012.T>の経営統合を承認すると発表した。
出光と昭和シェルの統合計画の影響を受けてJXと東燃ゼネラルにも再編の波が押し寄せたはずだったが、大株主の同意を得られない出光・昭和シェルより一足先に、JX・東燃ゼネラルの統合が実現する。
JX・東燃ゼネラルは、それぞれ21日に臨時株主総会を開く予定。
12月21日燃料油脂新聞より
50%シェア「競争制限しない」公取委会見
ガソリンや灯油などで50%を超える販売シェアを持つことについては、各油種とも水平型企業結合のセーフバー基準に該当しないとし、出光と昭和シェルの統合を前提に「十分な供給余力のある有力な競争事業者があり、50%の販売シェアが競争を制限するものとはいえない」としてシェアについては問題解消措置の対象とはならなかった。
*****
>出光と昭和シェルの統合を前提に
>創業家は統合になお反対しており、先行きは不透明だ。
ガソリン取引慣行の適正化 仕切価格建値化対応策提示 精製・流通研
エネ庁は20日、石油産業中下流部門の課題を検討している「石油精製・流通研究会」第4回会合を開き、ガソリン取引慣行の適正化への方向性を示した。
元売り会社の特約店向け仕切価格が建値化している実態と問題点を明らかにし、解決を促す望ましい行為類型案(対応案)と政府の対応を提示。
対応案は今後策定を進める事業者ガイドラインに盛り込む方向だ。
(略)
業転玉をまったく仕入れていない販売業者は元売会社からの支援を受けやすい傾向がみられ、販売店よりも特約店のほうが支援を受けやすい傾向も把握した。
こうした実態を受け、エネ庁は元売り会社による望ましい対応案として、まず「卸価格指標の動向を踏まえつつ、可能な限り市況を反映した仕切価格を設定することにより修正を行わずにすむようにする」建値化防止策を提示した。
通知価格の構成要素の説明に関しては「仕切価格を一定のフォーミュラで取り決めている元売会社は、価格体系を見直す際の交渉ならびに、各構成要素の額および販売関連コストの趣旨や用途の説明を十分に行う」対応案を示した。
事後的な修正を行う場合の基準の明確化策では、系列SSの値引き額の予見性を高めるための「①値引きの基準・時期などを明確化し、取引先に事前に開示する②可能な限り早期に双方の合意に達するよう努力する」ことをあげている。
これらの行為類型は今後策定するガイドラインに盛り込む内容になる。
他方、エネ庁は政府の対応として、国内需給を適切に反映した卸価格指標の構築のための環境整備に引き続き取り組む方針を明らかにした。
以下masumi(興味のない方はスルーしてください)
>業転玉をまったく仕入れていない販売業者は元売会社からの支援を受けやすい傾向がみられ
?????
系列100%仕入れの当店です。確かにここ数年前からすべての担当者が(気持ち)寄り添ってくれるようになったと思っていますが、昔はこんな感じでした。
仕入れ努力 仕入れ努力(つづき) 仕入れ努力(つづきのつづき)
(※担当者が悪かったとは思っていません。当時の元売(特約店)の施策がそのようなものだったのです)
>2014年後半ごろから元売りの卸価格の設定が割高になった。割高な価格は、競争の激しい地域を中心に値引きをするための原資になっている。(http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/business/mainichi-20161218k0000m020068000c.htmlより)
?????
新規出店してきた外資系2者店フルが、当店の仕切りと同額の価格看板を掲出したのはもう20年近くも前の話です。そんな当店にしてみれば、その頃から“元売りの卸価格の設定が割高”でした。
**********
1994年から22年、ガソリンスタンドの数は半数になりました。
高値の仕切りを押し付けられた地場店の多くは、顧客が安値店に流れ、販売数量を落とし、発券店値付けカード等の“本来得られるべき利益の逸失”もあり、閉鎖、廃業へと追い込まれました。
不採算だとして小口配達を切り捨て安値量販に走った大手はより多くの“補助(金)”を得、逆に不採算を承知で小口配達を続けた地場店はその数を減らし、SS過疎地や灯油難民が生まれました。
今回の「監視強化」を目にしても、恐らくこれまで同様に時間だけが過ぎていくのだろうと思います。
行政の責任は重い。
12月19日ぜんせきより(※青系文字がmasumi)
J本田灯油値上げ69~71円
HC灯油60円割れに困惑
ガソリン市場と同様の過当競争が灯油でも繰り広げられている現状
「ジョイフル本田のようなPB系大手でさえ70円台まで上昇したのに、なぜ50円台という値段でできるのか不思議だ」
「灯油で利益が取れないなら、一体なにで食べていけばいいのか。せっかくの季節商品を投げ売りするのはおかしい」
※
例年ならセルフと当店との灯油の価格差も10円近くあった当市ですが、最近では値段はバラバラです。
(日曜日の価格ですが)出光CAセルフが76円 外資系セルフが74円 ホームセンターが65円。
当店は79円です。(建値仕切りが税込みで70円=こちらは事後調整がある模様です。いくらになるかは未定)
燃料油が主商品のガソリンスタンド、その中でも灯油は季節ものとして確実に粗利を確保したい商品です。
しかし、ホームセンターなら“客寄せ品”とすることも可能ですから例え仕入れ値が同じであっても価格差は生じると思いますが、如何せん、仕入れ値の時点で大きな価格差がありますからお手上げです。
レギュラー91.8円 県外業者プリカに呆然
「あれだけ安い看板を出せば、給油客はどうしても流れていく」
「セルフでも少なくてもマージン5円以上は必要だが、あの価格に追随していけば運営できなくなる」
※「セルフより13円も高く売っても粗利5円しかなかった」時期を経験している、セルフではない当店です。
この1年を振り返る 2016
全農系販売政策に困惑
全農系販売店の安値のせいで既に廃業した店もあり、廃業を検討する店も増えてきているーとあります。
12月20日燃料油脂新聞より
「社説」より (赤線の部分のみ)
原油や為替、需給などを総合的に勘案しても「どうしてこんな安値が出回るのだろう。不思議でならない」と元売が指摘すること度々であった。
※いったん流れ出た業転玉は、需給バランスの崩れでコントロール不能になることも...?
借金返済に業転不可欠
希薄な系列関係に憤り
黒字でもSS廃業 将来に期待持てず決断
最近は経営内容は黒字でも、SSの将来に明るい展望が開けないため閉鎖や廃業を決断する業者が現れている。
販売量は限られているが、ガソリンのほか灯油配達なども行っていた郡部のある若手経営者は「近い将来、設備老朽化対策などが必要になってくるが、回収のメドが立たない。赤字ではないが、SSの将来が期待できない」
※寂しいですね。
「継続は力なり」byこうちゃん
だけど、
やめるにも力が必要です。より大きな力が。
<最高裁>預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し
(毎日新聞) 12月19日 15:26
亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消される。
*****
5年前なら良かったのに。
こうちゃんは争う気なんて全く無かったのに、(以下省略)。w
ガソリン価格操作 監視強化へ 経産省、消費者に影響懸念
毎日新聞さん、ありがとうございます。
業界以外の人がここまで業界事情を把握して記事を書いて下さったことに感謝します。
***
補足
「地域」という部分もありますが、そうではないケースもあります。
大手の新設店が地場中小既存店から顧客を流出させるための「安値」です。
元売からの補助(事後調整)がなくてもセルフ等の安値に追随している特約店や販売店の場合は、正規での系列ルートではない業転玉を仕入れることでそれが可能となっていました。
しかし最近では安値に追随(対抗)するためではなく、粗利を確保するために他社買い(系列店でありながら業転玉を仕入れること)をするケースが増えています。
※そうしなければ店の営業を続ける事が出来ないからであり、SS過疎地や灯油難民等が顕在化した現在、他社買いで店を守るのも「背に腹は代えられない」事情ということです。
「ガソリンスタンドは儲かっている」という世間のイメージは、地場の零細店には全く当て嵌まりません。
追記
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/business/mainichi-20161218k0000m020068000c.html より
石油元売り大手5社が、市場の実勢より割高な価格で系列の給油所にガソリンを卸売りし、その後、競争の激しい一部の給油所には個別に値引きに応じて差を付ける形で価格を操作していた実態が、経済産業省の調査で明らかになった。競争の少ない地域の給油所などで割高なガソリンが販売される要因となっており、経産省はこうした不透明な取引の是正のために、監視を強化する方針だ。
経産省が今秋、実施した調査に回答した石油元売り大手5社系列約680の給油所のうち、半数を超える51%の給油所がガソリンの納入後に値引きを受けていた。値引き額は1リットル当たり3円未満の給油所が31%▽3円以上5円未満が15%▽5円以上10円未満は4%▽10円以上は1%−−だった。一方、49%の給油所は値引きを受けられず、元売りの決めた卸価格を受け入れていた。
ガソリン業界には、元売り大手が卸価格を決めて系列の給油所に納入し、その後、各給油所と交渉して値引きする「事後調整」と呼ばれる慣行がある。経産省によると、国内市場の縮小でガソリンが過剰になるなか、2014年後半ごろから元売りの卸価格の設定が割高になった。割高な価格は、競争の激しい地域を中心に値引きをするための原資になっている。
経産省は、販売量が多く交渉力のある一部の給油所を除けば、元売り会社の主導で値引き額が給油所ごとに決められ、小売価格を通じて消費者にも影響が及ぶことを問題視している。
このため同省は20日開く有識者会議で、今回の調査結果を公表。卸価格に対する国の監視を強めたり、元売りが給油所に卸価格を通知する際に、その内訳や理由をきちんと説明するよう求めたりするなどの対策を議論する。また、適正な価格を決めるための「国内需給を適切に反映した指標」(経産省)の構築も課題となる。【岡大介】
*****
このニュースに対して「何を今更」という声も多く、私も経産省の真意は何かと考えてしまうのですが・・・
でもまぁ、全国にはまだ安値店の価格を引き合いに出されて値引き交渉をされ困っているという販売店もあるようなので、そういう意味では助かると思います。
ところで、経産省が監視を強化して卸格差が是正された場合、市況(販売価格)は平準化されるのでしょうか?
もし平準化された場合、高値店を利用していた消費者には吉ですが、
「適正価格より安値、という消費者の声」もあります。
それまで“高値店と比べて”10円程度安く買えていた消費者の“お得感”は無くなります。
卸格差が是正されずに高値店が全て淘汰されることになれば、それはそれで価格を比べることもが出来なくなって、どちらにしてもお得感は無くなるのかも知れません。
12月20日 追記
経産省、ガソリン価格監視強化よりも先に解決しないといけない問題が?
HN:scoovaさんのブログ(?)より
それと暫定税率も。










