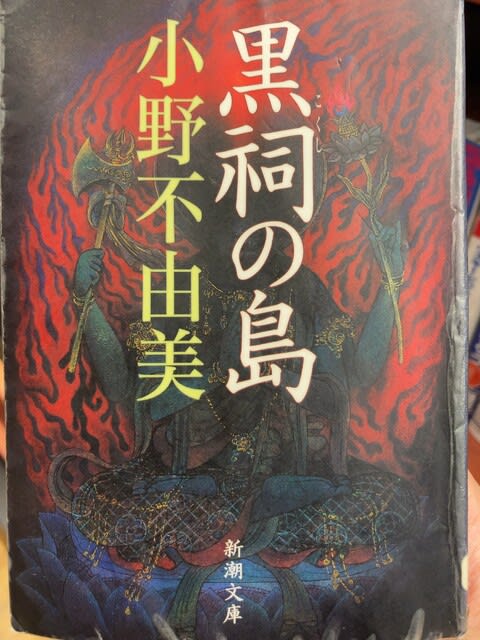うわぁー
これ読みたかったんだー。
な2022年1月の直木賞受賞作。
電車広告は偉大だな。
分厚いけれど一気に読めてしまう。
既読感があると思ったら
のぼうの城にまぁ似てる。
近江の国が舞台だが
百地三太夫は出てこない。
中国故事の矛盾を
日本の戦国に場面を移した
砲術vs城壁の熱い戦い。
熱すぎて時折目頭が熱くなる。
戦国末期の15年のみ存在し
関ケ原前哨戦となった
「大津城の戦い」を描いたもの。
京極高次と立花宗茂という
珍しい武将が出てくるのも面白い。
よくあるっちゃよくあるし
王道っちゃ王道の定番エンタメ作品なのだが
熱くならずいられない。
実写化を前提に書かれた作品のように思えるので
しゅららぼん、
翔んで埼玉2に続く琵琶湖作品として
ぜひ映画館でお会いしたいものだ。