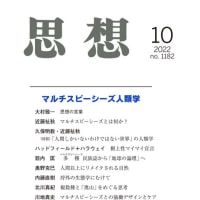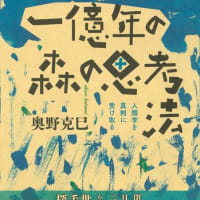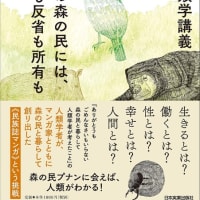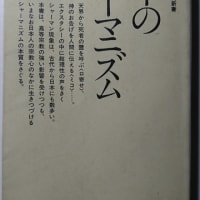対称性の人類学は、各項の間の圧倒的な非対称の関係(人間と動物、ある人間集団と別の人間集団などのそれ)の始原にまでさかのぼって、人類における<一>ではない、<多>の潜在を示そうとしている点で、レヴィ=ストロースの「野生の思考」の流れを汲む、しなやかな文明批判になっている。エスノグラファーが挑むことのひとつは、その壮大な構想を、ある社会集団の観察に照らして、考えてみることである。
プナン社会には、人間の行為の愚直さ、動物の起源などの示す豊富な神話群がある。しかし、人間と動物が溶け合って暮らしながら、対称性のなかで生きることを語るような神話は存在しない。プナン社会では、人間と動物の対称性は、神話とはことなる領域において現前する。
そこでは、動物をからかってはいけない、動物をさいなむべからずという規範が、人間と動物の間の対称性を保持するための実践的な哲学として存在する。獲れたての動物肉を解体する際、子らは、解体者のまわりで、肉の破片や身体のパーツを遊びの道具としたり、もて遊んだりしようとする。すると解体者や大人たちは、子らのそのような不作法を厳しく戒める。わたしたちがそれらによって生を永らえている動物を貶めるとみなされる行為は、つねに咎められなければならないのである。
そのような不作法が行われたならば、動物の魂 (balewen)は、雷神 (balei gau)のもとへと向かうことになる。雷神は、怒り狂って、洪水を引き起こし、ときには、人を石化させる。動物をさいなんではならないという規範は、雷神による強い制裁を発効させないためにあるのだといえる。
そのような実践は、人間と動物の間の対称的な関係を維持するためのものではないだろうか。その実践は、プナン人が、動物に対する人間の側の絶対的な優越、いいかえれば、人間中心主義に陥ることを、結果的に防いでいる。いったん人間の動物に対する圧倒的な非対称を認めるならば、人は動物をたんなる食材としてしか見なくなり、一元的な原理に支えられた資本主義社会へと転が(り落ち)るだけだからである。