
9月の半ば、わたしが滞在するプナンの村の周辺で、(諸説はあるが)以下のような風説が流布した。
舞台は、バルイ川の上流のある村。夫は、妻と子を残して、投網漁に出かけた。彼が家に戻ると、妻と子の首が狩られていた。首から下の身体だけで、血だらけで倒れていたのである。夫が叫んで助けを求めると、村人たちが集まり、犯人の追跡が始まった。人びとは、その後、二人の男が首をたずさえているのに出くわし、ライフル銃で、そのうちの一人を射殺した。もう一人の男は、射撃しても死ななかったので、家に連れ帰って、村人みなで刺し殺したという。その犯人たちは、クアラ・バラムの橋の建設計画で、土地の霊を鎮めるために、人の首を探していたのである。
まことしやかにささやかれた上記の話の真偽について、わたしは、行く先々でいろんな人に尋ねてみたが、いまに至るまで、はっきりしない。したがって、この話の、どこからどこまでが事実で、どこからどこまでが想像力の産物なのか、明らかではない。
そのバルイ川の事件が伝えられると、わたしが滞在するプナン人の村では、「首狩り人(penyamun)」に対する恐怖と警戒が、しだいに広がった。大人たちは、たえず、子どもたちの名を大声で呼んで、子どもたちが、近くにいることを確認し、「首狩り人」がうろうろしているので、子どもたちに、出歩かず、家でじっとしているようにうながした。村人たちは、わたしにも、近場であっても、けっして単独で出かけるな、「首狩り人」への警戒を怠るな、と命じた。一人の人間の首は、8万リンギット(約250万円)で売られる。首狩り人は、誰の首でもいいから持ち帰ろうとするので、気をつけろというのである。
それに並行して、プナン人の村では、かつての「首狩り人」にまつわる事件が、人びとによって想い出され、語られた。それによると、わたしが住んでいる村から5,6キロ離れたプナン人の村で、10年ほど前に、若い女性たちが糞場に行くと、見知らぬ男に遭遇した。村人たちは、その男は、「首狩り人」にちがいない、偵察に来ているのだと推察した。その後、プナン人が、糞場の近くをうろうろしていた一人のイバン人男性をライフル銃で射殺したという。
さて、バルイ川に「首狩り人」が出没したという話が流布して、10日ほど経ったある晩、午後11時ころ、わたしが住んでいるプナン人のロングハウスの住人が、急に、大きな声で話し始めた。ロングハウスの裏手から、人の話し声がするというのである。大人の男性数人が、ライフル銃を抱えて、懐中電灯で照らしながら、話し声のする方へと降りて行った。そこには、もう誰もいなかったが、数人の男のものと見られる足跡が残っていたことが報告された。
さらに、その翌日の午前11時ころ、リュックをかついだ6人の見知らぬ男たちが、ロングハウスの敷地を抜けて、川岸にある船着き場へ行こうとした。プナン人の男性が、見知らぬ男たちの一人に、どこから来たのかと尋ねると、聞いたこともないような土地の名前を口にした。どこに行くのかと尋ねると、ある会社の油ヤシのプランテーションだと答えた。その対話の間に、ある老人は、吹き矢を持ち出してきた。ある女性は、腰に刀を巻き、すでに吹き矢を手にしていた。プナン人の男性が、その油ヤシのプランテーションには、ここからは行くことができないと言うと、その6人の男たちは、来た道を引き返していった。
6人の男たちが引き返した後、プナン人たちは話し合い、彼らの言動は怪しい、「首狩り人」ではないかということになり、バイクと徒歩で、ライフル銃を抱えて、「首狩り人」の探索隊が送り込まれることになった。その後、戻ってきたその探索隊のメンバーは、彼らは、どこにもいない、すでにどこかに行ってしまったと報告した。それを聞いた村人たちは、口々に、なんであのとき(=ロングハウスを通り抜けようとしたとき)に、吹き矢で殺しておかなかったのだろうと、歯がゆい思いを語り合った。
その後、2週間ほどの間に、「首狩り人」が警察に捕まったという話が、2回伝えられた(これも、真偽のほどはさだかではない)。プナン人の村人たちは、いまにいたるまで、事あるごとに、「首狩り人」の恐怖を語り、警戒を怠らないように、お互いに、注意を喚起している。
これは、首狩りがおこなわれなくなった(1920~30年代)後にも、ボルネオ島に広く広がる、首狩りの恐怖言説のプナン・ヴァージョンである。1990年代には、何人かの人類学者が、現代の首狩りに対する現地人の想像力について論じたことがある(例えば、Janet Hoskins(ed.), Headhunting and the Social Imagination in Southeast Asia. Stanford University Press, 1996)。プナン人によると、今日、橋やダムなどの建築計画がある場合、マネージャーが、土地の霊を鎮めるために、人間の首を必要とするので、建築現場から離れた土地に、「首狩り人」を派遣するのだという。
フィールドの真っ只中では、首狩りに対する恐怖は、ものすごいリアリティー感で、わたし自身を圧倒した。何人もの人たちが、同じ内容の話をくりかえすのにつき合っていると、バルイ川の首狩りの話や周辺に「首狩り人」が出没しているという話は、「事実」以外の何ものでもない話として、しだいに、わたしの脳のなかに深くインプットされるようになった。「首狩り人」という言葉を口にしたとき、子どもたちが明らさまな怯えを示すのを目にすると、わたしは、そのことをつうじて、首狩りの恐ろしさに、戦慄を感じるようになった。その結果として、わたしは、彼らの言いつけを守って、けっして一人で、あたりをうろうろしないようになった。首狩りに対する想像力を、わたしは、プナンの人たちとともに共有することになったのである。
ところで、プナンには、首狩りに対する次のような逸話がある。現在60歳の男性が、若いころ、彼の祖父から聞いた話である。プナン人たちは、首狩りをしなかったとされる。それは、イバンやカヤンなど、焼畑稲作民の慣行だったのである。
プナン人がまだジャングルのなかで遊動して暮らしていた時代、あるイバンの男が、プナン人のリーダーのところに、他のプナン人の集落に首狩りに行くことを伝えに来た。リーダーは、そのことをすんなりと承諾した。イバン人たちは、そのプナン人の集落に首狩りに行ったが、逆に、吹き矢にあたって逃げ帰ってきた。そのため、イバン人たちは、そのプナン人のリーダーに助けを求めたという。プナンのリーダーは、燻製用の台をしつらえて、イバン人たちを煙の上に座らせ、上から葉を被せた。そして、暑くてもそこからけっして離れないように命じた。イバン人たちは、その命に従った。しかし、その結果、逆に、吹き矢の毒が体中に回って、イバン人全員が死んだという。プナン人のリーダーは、イバン人たちをだまして、殺害したのである。
この話は、プナンが、吹き矢という彼らの独自の道具を用いて、首狩り隊に対抗しうる人たちであるということを示している点で、非常に興味深い。
(上の写真は、料理される猿(bangat)。本文とは関係ない)










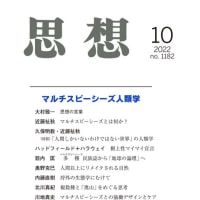

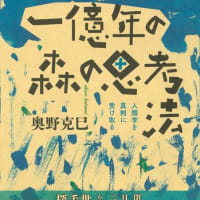
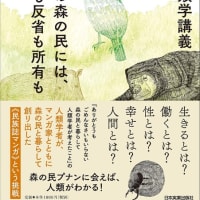



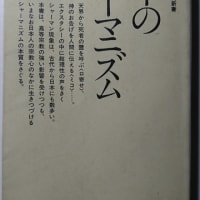


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます