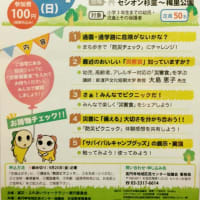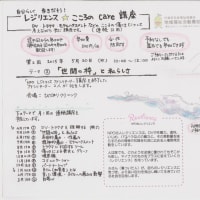ツイッターを最近こまめに見ていて、ちょっと思いついたこと、反応したいことにツイートするようになりました。
実は、アカウントは随分前につくってもらってたのですが(またしても人だのみ )、
)、
あまりにひだまりクラスに人が集まらないのよ~と車座委員会でぼやいてたら、ツイッターに限るとアドバイスされまして・・・
呟いてみたところ、本当に知ってもらえるようになったのです。
みんなに報告したら「『ぼやくよりつぶやけ』なる標語ができたね」と言われました。
そんなツイッターで、調子にのっていろいろ呟いてたら、
自宅出産のことで、あちゃー 地雷を踏んだりもしました。
地雷を踏んだりもしました。
今は、顔を知った人との交流と、医療・子育て情報を中心にツイートしてます。
あと、ひだまりクラスの情報なども。
で、今日、赤ちゃんの睡眠について書いてみたら、いろんな方から反応をいただき、
これは、ちょっと読みやすくまとめておこうかなとおもいまして・・・書いてみます。
赤ちゃんの睡眠は個人差が大きいものです。
でも、理想はありますし、リズムを作るのにコツがあるというのもわかってきました。
長年(15年近く)、週に2~4日ペースで健診を続けてきて、お母さんたちに赤ちゃんの睡眠の状況を聞いてきて、
いろんなケースを教えていただいた結果です。
産まれてすぐの睡眠はまだ昼と夜ははっきりしません。
が、一か月健診では赤ちゃんの昼と夜の違いがはっきりしてきています。
つまり、昼はぐずっている、夜は寝ている、です。
夜寝ているといっても、3時間がせいぜいですけど。
でも、夜は飲んだらすぐに寝る、という状態であるのが普通。
昼は飲んでもあまり寝ません。すぐに起きてしまうかぐずるかです。
昼に寝ないのは夜になるということなので、いいことなんですよ。
一日の中で、眠くて主に寝ている時間帯と、主にぐずっている時間帯があります。
昼間はおっぱい上げて寝ても、すぐに起きたり、ぐずったり。またはまたおっぱいほしがったり。
お母さんは非常にイライラするけど、それが赤ちゃんの昼なんだから仕方ないです。
特に1~2か月の赤ちゃんの昼はぐずるものです。
そして、昼にぐずるのは夜寝るということだから仕方ない。というか、むしろありがたいことです。
昼に機嫌よく起きている赤ちゃんのママはラッキーです。
夜、三時間でおなかがすいて目が覚めて飲んで、すぐに寝て・・・が二回あると9時間。
それが夜にあるのが大事で、昼に寝すぎていると夜ぐずります。
これは昼夜逆転。夜中1~2時から寝るとお昼前まで寝てたりして、これは遅寝遅起きというか夜が日中にずれ込んでるパターン。
あやすと笑ってこの世に慣れてくる2か月くらいまでは、昼間の機嫌の悪さは結構続きます。
抱っこしてあげたり、優しく揺らしてあげたりしたら泣き止むんですけどね。
2か月くらいになったら、5-6時間続けて寝る子が増えてきます。
3~4か月くらいになったら、もっと寝る子が増えます。
そして、結構この時期から夜中に起きるようになる5~7か月までが乳児期で一番続けて寝ることができる時期かもしれません。
この時期の健診では何時に寝て何時に起きるかということまでは聞かないのですが、(ちょっとプレッシャーかなと思い)
昼夜逆転がないことだけは確認してます。
中には10時間続けて寝るという赤ちゃんも・・・出てきます。
そして、あるとき、なんだか急に夜中に起きるようになった!という夜が5~7か月ころにやってきます・・・
「先週から急に夜中に何回か起きだしてしまって・・・おっぱい上げたらすぐに寝るんですけど」
これは、6~7か月健診の質問の定番。
何の前触れもなく、ある日突然なので、びっくりされますが、とりあえず授乳したらすぐに寝るし、
特におっぱいの人は添い乳すると楽だし・・・日中も変わった様子ないし・・・
とみなさんの訴え。
おなかがすいてるみたいな飲み方ではなく、安心感を得るためのような飲み方です。
中には寝られるように母乳のみの人がミルクを夜寝る前にあげてみたりという努力をしてみる方もいるけど、
それは何の役にもたたず、同じように起きる、同じように寝る、という報告が多いです。
ちょうど人見知りの時期、知的な発達が目覚ましい時期ですね。
感情が複雑になってきて、快不快で睡眠が決まってた(おなかがすかない限りは寝られてた)時期ではなくなったということなんでしょう。
この時期にはリズムがはっきりできているのが理想でそれはかならずしも難しいことではないと思うので、
何時に寝て何時に起きるか、何回夜中に目覚めてどのようにして寝かしつけるのか、すぐに寝ているか・・・
それを聞くようにしています。
その中でわかってきたことは
○赤ちゃんはだいたい10時間寝たら、機嫌よく起きられる。
○10時間寝るというのは起きずにという意味ではない。起きた回数は、すぐ寝ていればリズムに影響はない。
個人差はあるので、11時間で起きる子もいるし、9時間で機嫌よく起きる子もいるけど。
多くの子で10時間。
つまり、8時に寝たら6時、9時に寝たら7時、10時に寝たら8時に起きます。
10時までには寝られるようにするのが目標。8時がベスト、と思います。
放っておいて、自分のリズムで気にせずに生活していると、12時超える赤ちゃんも出てきます。
これは・・・やはり問題だよ、と伝えています。
12時に寝ても8時に起きるから、ちゃんと早起きできてるとおっしゃる方がいますが、これは勘違い。
8時に起きてるのは朝目覚めてすっきり起きてるのではないのです。
8時に寝て夜中の4時に起きてるみたいなもの。
夜中に目が覚めても、4時ならおっぱい飲んでそのまま寝ますよね?
明るくて、みんなが起きてうるさいから起きてしまっただけであり、頭はまだ目覚めていなくて、睡眠不足の状態(頭は夜中)。
なので、しばらくすると(すぐに寝る子もいる)長い時間の午前寝になります。たいてい2時間から3時間。
起きたときが朝すっきりという状態なのです。
夜のリズムは遅くずれこんでいるということなんですね。(遅寝遅起きです)
この6~7か月頃に生活リズムが整っているというのは、離乳食を始めるときにも大切です。
起きてから何時間くらいでよく食べるか・・・がわかってきやすいので。
離乳食のタイミング探しが初期では苦労するからです。
そういう点でも生活リズムを整えることは大事です。
そして、夜中に起きたらどうするか?
とにかく早く寝かす、につきます。
添い乳でもいい、おきておっぱいでもいい。ミルクでもいい。好きな子はおしゃぶりでもいい。
お母さんが一番楽に過ごせるというスタイルでいいので。
この時期、夜に起き始めたころ、おっぱいの子を、おっぱいなしに早く寝かすというのはたぶん無理だと思います。
努力してみてもいいとは思うけれど、結局あきらめることになることがほとんどです。
あげないで寝かそうと努力してみたけど激しく泣きだし、結局長い間おっぱい吸うことになってしまうので、
もうもぞもぞした段階であげることにしました、という人が多いです。
「いつまで、夜中の授乳が続くんですか?」と聞かれたら、がっかりされるけれど正直に答えるしかないです。
「起きる回数はかわるけれど、ぐっすり寝るようになるのはおっぱいがおわってからかもしれません」と。
暑い寒い病気のときは回数は多くなりますし、歯がはえる時期も起きるかもしれません。
発達してきて、つたい歩きなどして運動量が増えると起きる回数は減ってくることもあります。
でも、まったくぐっすり寝るようになる子はたぶん多くはないです。
夜寝はじめに何回も起きる子は、お母さんと一緒に寝たい~とぐずってる場合もあります。
やっと寝た、私の時間 と、赤ちゃんを一人にしてリビングに移動すると、すぐに起きてママを呼ぶ子はこの時期とても多いです。
と、赤ちゃんを一人にしてリビングに移動すると、すぐに起きてママを呼ぶ子はこの時期とても多いです。
特に一人目。(なぜなら二人目ママは疲れ切ってて赤ちゃんと寝落ちすることが多いので)
9~10か月健診のころは
10時間寝ている、そして、何回起きてもすぐ寝ていたらリズムに影響ない。
ここは同じ。
違うのは、赤ちゃんが夜中に覚醒して遊びだしたりすることが増えるということ。
ママに相手をしてもらいたくて、乗っかったり、たたいたり、髪をひっぱったり、中には目をこじ開ける子も・・・
大事なことは、夜は暗く静かに、として、夜は寝る時間だよと教えてあげること。
元気だし、私も目が覚めたから相手してあげようと夜中に遊んであげたりするとリズムが崩れます。
布団に戻そうと追いかけて引き戻すというのも、鬼ごっこみたいになって子どもも喜んでしまい遊んであげてることになるので、
親は寝たふりをするのがお勧めだと思います。
子どもは布団から出ても、暗く静かに・・・そして、寝たふり
寝室を安全にしておいて、ひとしきり遊んで眠くなったらもどってきますので、そこからまた寝かしつけです。
添い乳でもミルクでも。
夜中に遊びだすのは一時期ですから、しばらくすると落ち着いてくると思います。
この時期には、夜中の授乳をやめて、おっぱい以外で寝かしつける努力をして成功することも出てきます。
トントンしてみたり、添い寝でスキンシップでということもあります。
でも、やってみても失敗したという方も多いです。
お母さんが夜に楽に過ごすこと、リズムを崩さないこと、ここを大事にしてみたらいいでしょう。
1歳まではお昼寝は2~3回で、一回のお昼寝は30分くらいから1時間程度。
睡眠は本当に個人差があります。よく寝る子とあまり寝ない子。
リズムが良くて、日中元気なら心配はないです。
1歳から1歳半までにお昼寝は一回に定まってくると思います。
理想的なリズムに近づけるためには、午前中にしっかりと身体を使って遊ぶこと、です。
楽しくいっぱい遊んだらおなかがすく、身体を使って疲れてて、おなかも満たされたら、眠くなる。
そして、午後の早い時間に二時間くらい寝て、お昼寝がその一回なら、また、よい時間に眠くなります。
その繰り返しがよいリズムを作っていきます。
よいリズムはなぜよいか、ですが・・・
よい習慣はその人の一生を支えます。といったらちょっと大げさでしょうか。
子どもの生活習慣を作ってあげることは、親だからできることです。
親にとっても利点がいっぱいあります。
○生活のメリハリがつくので、よい食生活になりやすい、よく食べることにつながる
○よい食生活ができるとよい排便習慣にもつながります。早寝早起き朝ごはん→朝うんちが理想。
(朝、余裕があると急がせないでうんちの時間もしっかりとれますね)
○午前中に機嫌のよい時間をもってこれる、これは大切なことです。特に集団生活を意識すると。
子どもの集団生活は午前中が大事なのです。保育園・幼稚園・学校・・・すべて、午前中に主な活動時間があります。
たっぷり寝て、しっかりごはんを食べた子は午前中に機嫌のいい時間が過ごせます。
寝不足で食べてない子は幼稚園でどうなるかというと・・・
「すぐ泣く」「元気がない」とお友達にも言われることになるでしょう。
本当なら、お友達と仲良く遊べる力のある子なのに、リズムが悪いために機嫌の悪い時間帯に集団生活が始まるのは、恐ろしいことです。
午前中に、一日の中で一番機嫌のよい時間が来るようにリズムを整えるのは、集団生活前にできる親の一番の子どもへのプレゼントだと思います。
○病気のサインに気づきやすいです。こんな時間にぐずることないのに、と思ってたら熱が出てきた・・・など。
時間で生活が決まってたら、次にどうすべきかわかるし、生活もしやすいのです。
結局、生活リズムをきちんと作るのは、親のためにもとても大切なことで、子育てを楽にしていくでしょう。
さて、では生活リズムをどう変えていくか・・・ですが。
小さい赤ちゃんでは、特に環境で整えます。
朝は明るい部屋で過ごす、朝日を浴びさせる。
昼間は明るくうるさく、夜は暗く静かに・・・
悪いリズムがしっかりついてしまっていたら・・・遅寝遅起きを直す場合には寝る時間でなく起きる時間に目を向けることです。
眠くない時間に一生懸命寝かす努力というのは、実に苦行ですよね!
本当に苦痛でイライラするものです。
寝る時間を早めるのでなく、起きる時間を早める、からやっていくことです。
それも、特に赤ちゃんの場合は、無理なく少しずつ、がいいと思います。
12時に寝て10時に起きる赤ちゃんの場合、
夜から治そうとすると・・・10時に寝かせても無理で格闘しても結局12時まで起きてると思います。
朝起きる時間を少しずつ早めていきましょう。
一気に8時に起こすという具合に早めてもだめです。また寝てしまうから。
少しずつでいいのです。
この時間まで寝てたらもう寝ないだろうというくらい少しずつ。
でも、進歩を続けたら、確実に早く起きるから、その時はお昼寝もそれだけ早くなって、寝る時間も早くなります。
一か月で一時間でもいいです。確実に進歩することが大事。
少しずつ、理想の生活リズムに近づけていけたらいいんです。
生活習慣ですから、本当は親のリズムも極端な乱れがないかは気を付けてみる必要はあると思います。
午前中の外遊びに付き合うことができないのは、遅い就寝時間ではないかな?という反省点はないでしょうか?
脅すわけではないですけれど、不登校の子ども達は一様に遅寝遅起きなんです。
そして、一番元気な時間帯が午後遅くから夜中にかけて、なんです。
不登校・ひきこもり・朝起きられなくて体調不良を訴える子には、入院して朝早くに強い光を当てて身体を起こすという治療もあります。
そうなってしまわないように・・・これも、予防予防
親が管理できるうちによい習慣をつけてしまうのが手っ取り早いのです。