朝日新聞ブログ「ベルばらkidsぷらざ」に連載中の「世界史レッスン」第64回目の今日は、「山内一豊の妻ーー西洋男性版」⇒ http://bbkids.cocolog-nifty.com/bbkids/2007/05/post_ced0.html#more
マリア・テレジアの夫フランツ・シュテファンの、意外な能力の一端について書きました。
フランツ・シュテファンは家柄が格下だったので、入り婿になってずいぶんたってからも「フランス野郎」(領地がロレーヌだったため)と陰口を叩かれたり、公式行事でも無視されたりと、針のむしろ状態にされている。何しろ家柄自慢のハプスブルク家の面々は底意地が悪いのだ。
だが彼よりもっと辛い目にあわされた女性がいる。ほぼ150年後の、ハプスブル家末期、フランツ・ヨーゼフ皇帝時代だ。皇帝は甥のフランツ・フェルディナンド大公を帝位継承者に指名していた。そしてフェルディナンドが熱烈に恋した女性の身分が・・・女官だった。
ハプスブルク家には家訓があり、帝位継承者の妻たる女性は、外国人ならカトリック国の王女か、自国なら最高位貴族出身でなければならない。ところがこの女官、ゾフィは、ボヘミアの伯爵令嬢にすぎなかった。論外というわけだ。
たいへんな苦労の末、ふたりは結婚するのだが、ゾフィに加えられた意地悪の数々は陰険だった。彼女が園遊会を開けば、ハプスブルクの誰かが同日同時間に必ず同じパーティをぶつけてきて、出席者を根こそぎ持ってゆく。彼女が静養地へ行けば、城には誰かが居座っていて追い返す。
一度などベルヴェデーレ宮殿で夫妻が外交使節を謁見したあと、フェルディナンド大公が席を立った瞬間、近衛兵たちもその場を去り、ゾフィを守護する必要はないのだということをあからさまにした。さすがに大公も怒り、皇帝に食ってかかったと言われている。
身分によって相手を差別する心とは、浅ましいものだと思うが、どんな時代のどんな国、どんな場においても必ずあるのは、人間性に染みついたものだからだろうか・・・
☆新訳「マリー・アントワネット」(角川文庫)
☆☆ツヴァイクはフランツ・シュテファンを全く評価していなかったらしく、本書では、単なる遊び人で享楽的なところがアントワネットに遺伝した、というような書きぶりである。


☆新著「怖い絵」(朝日出版社)
☆☆アマゾンの読者評で、この本のグリューネヴァルトの章を読んで「泣いてしまいました」というのがありました。著者としては嬉しいことです♪
①ドガ「エトワール、または舞台の踊り子」
②ティントレット「受胎告知」
③ムンク「思春期」
④クノップフ「見捨てられた街」
⑤ブロンツィーノ「愛の寓意」
⑥ブリューゲル「絞首台の上のかささぎ」
⑦ルドン「キュクロプス」
⑧ボッティチェリ「ナスタジオ・デリ・オネスティの物語」
⑨ゴヤ「我が子を喰らうサトゥルヌス」
⑩アルテミジア・ジェンティレスキ「ホロフェルネスの首を斬るユーディト」
⑪ホルバイン「ヘンリー8世像」
⑫ベーコン「ベラスケス<教皇インノケンティウス10世像>による習作」
⑬ホガース「グラハム家の子どもたち」
⑭ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」
⑮グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」
⑯ジョルジョーネ「老婆の肖像」
⑰レーピン「イワン雷帝とその息子」
⑱コレッジョ「ガニュメデスの誘拐」
⑲ジェリコー「メデュース号の筏」
⑳ラ・トゥール「いかさま師」
マリア・テレジアの夫フランツ・シュテファンの、意外な能力の一端について書きました。
フランツ・シュテファンは家柄が格下だったので、入り婿になってずいぶんたってからも「フランス野郎」(領地がロレーヌだったため)と陰口を叩かれたり、公式行事でも無視されたりと、針のむしろ状態にされている。何しろ家柄自慢のハプスブルク家の面々は底意地が悪いのだ。
だが彼よりもっと辛い目にあわされた女性がいる。ほぼ150年後の、ハプスブル家末期、フランツ・ヨーゼフ皇帝時代だ。皇帝は甥のフランツ・フェルディナンド大公を帝位継承者に指名していた。そしてフェルディナンドが熱烈に恋した女性の身分が・・・女官だった。
ハプスブルク家には家訓があり、帝位継承者の妻たる女性は、外国人ならカトリック国の王女か、自国なら最高位貴族出身でなければならない。ところがこの女官、ゾフィは、ボヘミアの伯爵令嬢にすぎなかった。論外というわけだ。
たいへんな苦労の末、ふたりは結婚するのだが、ゾフィに加えられた意地悪の数々は陰険だった。彼女が園遊会を開けば、ハプスブルクの誰かが同日同時間に必ず同じパーティをぶつけてきて、出席者を根こそぎ持ってゆく。彼女が静養地へ行けば、城には誰かが居座っていて追い返す。
一度などベルヴェデーレ宮殿で夫妻が外交使節を謁見したあと、フェルディナンド大公が席を立った瞬間、近衛兵たちもその場を去り、ゾフィを守護する必要はないのだということをあからさまにした。さすがに大公も怒り、皇帝に食ってかかったと言われている。
身分によって相手を差別する心とは、浅ましいものだと思うが、どんな時代のどんな国、どんな場においても必ずあるのは、人間性に染みついたものだからだろうか・・・
☆新訳「マリー・アントワネット」(角川文庫)
☆☆ツヴァイクはフランツ・シュテファンを全く評価していなかったらしく、本書では、単なる遊び人で享楽的なところがアントワネットに遺伝した、というような書きぶりである。


☆新著「怖い絵」(朝日出版社)
☆☆アマゾンの読者評で、この本のグリューネヴァルトの章を読んで「泣いてしまいました」というのがありました。著者としては嬉しいことです♪
①ドガ「エトワール、または舞台の踊り子」
②ティントレット「受胎告知」
③ムンク「思春期」
④クノップフ「見捨てられた街」
⑤ブロンツィーノ「愛の寓意」
⑥ブリューゲル「絞首台の上のかささぎ」
⑦ルドン「キュクロプス」
⑧ボッティチェリ「ナスタジオ・デリ・オネスティの物語」
⑨ゴヤ「我が子を喰らうサトゥルヌス」
⑩アルテミジア・ジェンティレスキ「ホロフェルネスの首を斬るユーディト」
⑪ホルバイン「ヘンリー8世像」
⑫ベーコン「ベラスケス<教皇インノケンティウス10世像>による習作」
⑬ホガース「グラハム家の子どもたち」
⑭ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」
⑮グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」
⑯ジョルジョーネ「老婆の肖像」
⑰レーピン「イワン雷帝とその息子」
⑱コレッジョ「ガニュメデスの誘拐」
⑲ジェリコー「メデュース号の筏」
⑳ラ・トゥール「いかさま師」











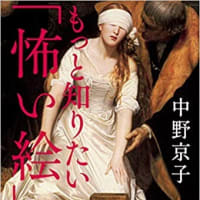






今日も楽しく拝読させていただきました。
ありがとうございます。
身分制度は支配者が、自分の立場を守るために与えただけのものだと捉えています。
だから、身分の高い家はずっと辿って最初の身分を得た人は殺人者?
貴種信仰は洋の東西を問わずあるものでしょう。
どうしても、人の心にそういうものは根付いている。
そういうものに動かされて歴史は動いている。
きっと欲望の一端なのでしょうね。
隣人との優位を確認する・・・猿でも順位があるのですもの。
家紋のこと、読ませていただきました。傍からはずいぶん小さなことでも、本人たちはレーゾン・デートル(古すぎ?)なので必死なのでしょう。困りますよね。
どんな貴族も最初から貴族ではありません。それにしがみつくのは、あまりにも多い特権の所為です。階級性を否定したはずの、社会主義国家は、特権階級を作り維持の為、様々な悪を犯しました。
北朝鮮の金一家など、天皇制日本軍を撃退しながら、天皇制そっくりの世襲権力。心底、ガッカリです。東欧も同じでした。チャイナも階級格差が日本以上。絶望です。歴史は、学ぶほど、虚しくなりませんか?
歴史を学べば学ぶほど「虚しい」というより、どうして人間ってエンドレスに同じ間違いをおかすのかなあ、と不思議・・・でもないか、自分もそうでした!懲りないというか。
ゆうひさんへ
「その地位を手放したくなくなる」--まさにそれですね。それとアントワネットを読んでいて思いましたが、今の地位が神に授けられた当然の権利であるという確固たる信念を持ってしまうという感覚も、まんざらわからなくはないのです。恐ろしいことではありますけど・・・
日本の武家もそう。
殊に日本では、武家は支配者階級ではあっても、必ずしも経済的には恵まれず、質実剛健を旨とし、尚且つ、格式を守り、文化の担い手であることを誇りとし、精神性を重んじていたから、なおさらです。
そう思うと、身分に拘り、尚且つ、それに伴う義務、ノブレス・オブリージュを忘れて、既得権にしがみ付くのは、なんとも見苦しい。
でも、欧米には、今でもその種の金持ち階級が厳然としているようです。尤も、日本の華族だって、似たようなものなのかもしれませんが。
確かにノブレス・オブリージュはすっかり忘れ去られていますよね。フランス革命もそれ故起こった、と言えるのかもしれません。
人間だって生き物の一種。
そうなってたまるか!!という遺伝子に刻まれた強烈な怯えが、階級差別を引き起こしてしまうのかもしれません。