2013年11月16日(土) 気仙沼あれこれ 1
少し前になるが、10/31日朝のNHK番組 あさイチで、東日本大震災で甚大な被害を受けた、宮城県の気仙沼(けせんぬま)が話題となった。(“JAPA”なび 今こそ 来てけらいん! 宮城 気仙沼 |NHK あさイチ)
この地が大震災に見舞われた時に、大津波で壊された石油施設に引火し、街の建物や港の船が一面火の海と化し、一部が、引き波で海へ流されていく映像を見たのを、今も鮮明に記憶している。(図はネット画像より)


火の海の気仙沼 宮城県と気仙沼市(桃色)
東北有数の重要な漁業基地が、壊滅的な大打撃を受けて、殆どが無くなってしまった。
あれから2年半余り、番組では、徐々に進んでいる復興の様子等が伝えられた。つい先日だが、陸に乗り上げたままだった大型漁船 第十八共徳丸が、漸くにして解体され、更地になったようだ。(「共徳丸」の解体終了 所有会社社長ら、気仙沼市に報告)
本稿では、この番組に触れながら、気仙沼に関連する話題を取り上げた。
●筆者は、山形県に生まれ、仙台で学生生活を過ごし、そこで知り合ったのが、仙台出身のワイフKとあって、宮城県には深い縁がある。勿論、気仙沼は知っているし、知人が、ここに勤務したこともある土地だ。
かなり以前だが、チリ地震津波で大被害を受けた旧志津川町(現南三陸町)へ応援に行ったことがあるが、此処より更に北に位置している気仙沼には、訪れたことはない。
上に示した地図にあるように、宮城県は、三陸海岸沿いに北に細長い手を延ばしたような面白い形をしているが、この延びた部分が気仙沼市である。
気仙沼と書いて、ケセンヌマ と読むのは、かなり難解で、一般的には、キセンヌマ となるだろうか。
ネット情報によれば、地名のケセンは、ケセマ、ケセモイ(アイヌ勢力の南の端の港)というアイヌ語からきているという説が有力で、発音に近い漢字が充てられたようだ。
また、陸側から海を見ると、海中にある島が、まるで、沼の中に浮かんでいる風なことから、地名に、沼が付いたともいう。(気仙沼の地名の由来を教えてください。)
●気仙沼市には、マスコットキャラクター「ホヤぼーや」がいる。このマスコット、番組の中のビデオだけでなく、スタジオにも登場してくれた。この子は、震災少し前の、H20年に一般から公募して誕生したが、くまもん等に比べ、知名度はまだまだのようだ。(気仙沼市観光キャラクター「海の子 ホヤぼーや」)

ホヤぼーやの、頭の形(角、いぼいぼ)と色はホヤ、右手に持っている刀はサンマ、ベルトの白いバックルはホタテ、を表していて、それぞれ、気仙沼の海の特産物という。
これらについて、以下に、2,3コメントしたい。
なお、気仙沼と言えばフカヒレ、フカヒレと言えば気仙沼、と言われる程の、フカヒレの全国一の産地だが、このホヤぼーやの装束には、敢えて外したのか、出てこない。
でも、ぼーやの好きな食べ物はフカヒレで、特技は、サメに乗ること、という。この辺の話題に付いては、稿を改めて触れる予定である。
○ホヤは、磯の岩等に張り付いている腔腸動物だ。下の写真のように、赤茶色で、いぼいぼがあり、グロテスクでやや気味悪い代物だ。形から、海のパイナップルなどとも呼ばれる。
これが食べられるとは信じられない位で、最初にチャレンジした人の勇気に敬意を表すべきだろうか?
 活きホヤ(ネット画像より)
活きホヤ(ネット画像より)
ホヤは、生で刺し身風にそのまま食べたり、干しホヤにしたり、塩漬けにして頂く。食べた時に味わえる磯の香りが堪らない魅力と言われ、知る人ぞ知る、海の珍味である。海が近い仙台で育ったワイフKは、ホヤには目が無い。
気仙沼を始め、三陸海岸一帯でよく獲れ、養殖も行われているようだ。
○サンマについては、今更、講釈の必要はないだろう。気仙沼は、秋の味覚の代表の一つであるサンマ漁の一大基地なのだが、大震災で失われた漁業関連施設類も復興し、漸く、嘗ての活気と賑わいを取り戻しつつあるようで、嬉しい限りである。
サンマと言えば、落語に因んで、目黒のサンマが有名で、例年、「サンマ祭り」を開いて来訪者に振る舞って来た。その材料のサンマを供給して来たのが気仙沼で、18年も前から、両地域の連携が続いているようだ。
このサンマ祭りだが、大震災でその継続が危ぶまれたものの、関係者の努力で続けられ、この秋も、サンマ不漁の中で、開催されたようだ。目黒の皆さんと一緒になって、気仙沼からやって来てサンマ焼きを手伝っている漁業関係者の法被姿が印象的だった。(大雨の中「さんま祭」 東京・目黒、不漁はねのけ5千匹ふるまう )

実は、今般初めて知ったことだが、サンマや関連食材の供給元が異なる、二通りの「目黒のさんま祭り」があるようだ。片や、本稿の気仙沼市と目黒区が連携した目黒区田道広場公園内の祭り(区民祭りの一環)で、片や、宮古市(岩手県)と連携した目黒駅前の祭り(駅前商店街主催)(目黒駅は品川区内)である。
元祖争いのような状況もあるように見えるが、両者の経緯や関連は不明なので、これ以上は触れないが、供給地のサンマ漁の時期が少し異なることから、二つの祭りは開催日をずらして行われて来ているようで、互いに競い合いながら、いい刺激になっているのかも知れない。
○ホタテについては、全国的な生産量では、北海道が約70%、青森県が約30%と、全体の99%以上を占め、宮城県(気仙沼)や岩手県の生産量は、残る、ほんの1%以下のようだ。(帝国書院 | 統計資料 日本 農業・漁業・林業 ほたてがいの養殖)
気仙沼としては、これからの、養殖漁業の一つの柱(貝柱?!)に育てたい、という狙いだろうか。
生のホタテ貝や貝柱を買ってきて、調理して食べる機会はそう多くはないのだが、以前は、出張の時などの長旅の友として、結構高価な、干した貝柱をよくしゃぶったものだ。


ホタテ貝 干し貝柱
偶々ネットを見たら、この9月に、横浜市で、気仙沼産の生ホタテの一部から、毒成分(麻痺性貝毒)が検出されたという、物騒なニュースがあったようだ。(卸売りの帆立から毒検出 横浜 - MSN産経ニュース)
自分には、これまで、生牡蠣を食べて、大変な思いをしたことが2回程あるが、ホタテでも、毒に中ることがあるのだろうか。










 フグの袋競り人形(ネット画像より)
フグの袋競り人形(ネット画像より) 
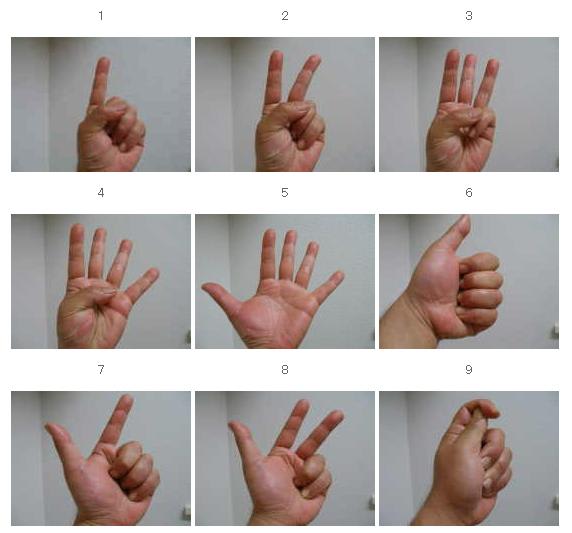




 伐採地地図 図右下に御小屋山
伐採地地図 図右下に御小屋山 巨大なモミの御柱
巨大なモミの御柱



