2013年3月20日(水) 四季の風景 夏~冬
先日、当ブログで、日本の四季について、
四季の風景 春 (2013/3/16)
で、春について触れたのだが、今回は、その続編で、夏~冬について触れ、最後に、締めくくりとして、四季全体を、話題にしている。
○夏では、爽やかさが漂う初夏は、梅雨になるまでの限られた期間だけだ。でも、この時期について、風景を表すような言葉を、色々探したが、
皐月晴れ 皐月闇
などはあるものの、ぴったりくるものは見つからなかった。
欧州では、6月は、June Bride(6月の花嫁)などと言われ、素晴らしい季節の様だ。でも、日本では、五月雨(さみだれ)とも言われる梅雨の風景は、じめじめ していて、あまり良い印象は無い。
そして、梅雨が明ければ、夏本番だが、何と言っても、日本の夏は蒸し暑く、情緒的な表現は無理のようだ。最近は、天気予報でも、真夏日はすっかり格が下がって、この上に、更に、猛暑日が加わって来た。熱夏 熱暑 炎暑などとも言われる。
真夏の風景を表す言葉としても、以下の様な
ぎらぎら (輝く太陽)
じりじり かんかん (日照り)
じーじー (アブラゼミ)
むくむく もくもく (入道雲)
ざーざー (夕立)
など、擬音的、擬態的で、直接的な表現が多い。
これらの中で、焼けつくような、汗ばむような日照りが連想される、じりじり を、夏らしい状況を表す言葉とすることで、ワイフKと意見が一致した。
一方、暑さから逃れるために、水に入って
すいすい じゃぶじゃぶ 泳ぎ
たくなったり、
りんりん 風鈴
の音で 涼風 を感じたり、日中を避けて夜に、団扇片手に、花火や盆踊りを、楽しむこととなる。
最近は、夏の暑さは、専ら、文明の利器であるエアコンや扇風機で凌ぐという、直接的な方法に頼るのが一般的で、季節感が無くなってしまい、淋しい感じもある。
甲子園球場の炎天下で、球児たちが覇を競う、夏の高校野球は、今も健在だが、プロ野球の方は、ドーム型球場が多くなり、天候に左右されずに日程が消化出来るようになったのだが、これも、素直に、喜んでいいことなのであろうか。
○秋の気候は、地球の動きからみれば、基本的には、春とは変わらないのだが、寒さから解放される春と、これから厳しい寒さに向かう秋とでは、感覚的には全く別のものだ。
気象的にも、水蒸気が漂う霞は、春の風景で、秋は、空気が澄んだ清涼感や、空の青さが印象的。天高く馬肥ゆる秋 などとも言われ、空が主役でもある。
秋と言えば、高校時代に接した、高村光太郎の詩「秋の祈」が忘れられない。
秋は喨々と空に鳴り 空は水色
鳥は飛び 魂いななき
清浄の水こころに流れ
こころ眼をあけ 童子となる (以下略)
ここで出て来た、喨々(りょうりょう)という言葉の響きが、強烈であった。 喨は、リョウ、ロウと読むようで、「喨々と」は、音が明るくほがらかに響きわたる、ということのようで、トランペットの音が喨々と響く、などとも使われるようだ。残念ながら、この漢字は、手持ちの漢和辞典には載っておらず、ネット辞書で探した。
この詩についての、ある解説によれば、ほがらかな音のような澄みきった秋空の下、作詩者の心は、空のごとく、みずのごとく、自らの心が清浄となり、純真無垢な子供の心になってゆく、と詩(うた)っているようだ。 (秋は喨々(りょうりょう)と・・・|今月の法話|京都花園 臨済宗大本山 妙心寺 公式サイト)
○秋の風景では、紅葉(もみじ)も主役の一人だろう。日本の紅葉は、赤や黄色の落葉樹と、緑の常緑樹との対比も素晴らしい。
いつだったか、パリ近郊のブローニュの森を案内された時、殆どの木々の葉が、黄色で、まさに黄葉だったのに驚かされたことがある。
日本でも、時代によっては、黄葉が愛でられた時もあったと言うが、日本の紅葉には、やはり、赤があることが特徴だろうか。赤い紅葉と言えば、
ウルシ、ナナカマド、カエデ、ハゼ
等だろうか。
紅葉に因む場景を表す言葉としては、
もみじの秋 秋の紅葉 燃えるようなもみじ もみじの錦 錦秋
などがあるが、これらの言葉には、秋 や もみじ が入っていて、全山が紅葉する秋の風景等を、間接的に表した言葉は、残念ながら、見つからなかった。
春の、うらら や おぼろ と同様に、いっそのこと、もみじ という言葉自体が、単なる名詞ではなく、状態を表しているとし、動詞や形容詞的に使えるとすれば、
全山が もみじだ
全山が もみじしている
谷川岳の天神平が もみじに包まれている
月山山麓に広がる もみじ風景
などの表現も可能となり、秋の風景を表す言葉になるがーー。
○秋のもう一つの重要な風景は、人事の集大成とも言える、実りの秋、収穫の秋の風景であり、丹精込めて育てた作物や果樹の、総仕上げの時だ。
これを表すのに、たわわ があり、なんとか見つかった、好きな秋の言葉である。
たわわ は、語源的には、枝や穂が たわむ(撓む)から来ていると言われ、農耕民族、稲作民族に相応しい言葉でもあろう。
たわわ たわむほどのさま
用例:たわわに実った稲穂 枝もたわわのりんご
漢字は、撓で、訓は たわ たわむ、音は トウである
用例
たわ:たわたわ 撓撓 枝などがたわみしなうさま
トウ:不撓不屈(フトウフクツ) 相撲界で口上等としてよく使われる
たわわ は、やまと言葉と思われる。
 たわわの稲穂と秋空 (ネット画像から引用)
たわわの稲穂と秋空 (ネット画像から引用)
○日本の冬の風景では、やはり、雪が降ることが素晴らしいことだ。台湾からの人達には、日本で雪に触れるのが嬉しいようだ。
雪が降る風景を表す言葉として、よく言われるのが
しんしん 涔涔 雪が降り積もるさま
だが、元々は、この、見慣れない漢字だったようだ。 残念ながら、この漢字も、手持ちの漢和辞典には載っておらず、ネット辞書で探した。
で、最近は
しんしん 深深 雪が降り積もるさま
しんしん 深深 夜の静かに更けゆくさま いりこんで奥深いさま
とも書かれるようだ。
この しんしん は、風のない穏やかな日、音も無く(しんしん と音がするように!)雪が降り積もる風景が、見事に表現されていると言えよう。
又、木枯らしや、寒い北風が吹く様は、
ぴゅーぴゅー ひゅーひゅー びゅーびゅー
となるだろうか。
◎前稿を含め、日本の四季の風景を表した言葉について触れて来たところだが、纏めとして、ここで敢えて、四季それぞれの言葉として、気に入った以下の4つを自選し、大切に味わっていくこととしたい。
春 うらら
夏 じりじり
秋 たわわ
冬 しんしん
○以前、NHK みんなの歌(2009.12~2010.1)で、「風がきれい」を、チキガリが歌ったものが放映されて印象に残り、下記ブログ記事にしている。
風の色は何の色 (2010/1/31)
その歌では、四季の風景を色で表していて、四季それぞれの色を、以下の様に歌っている。
春の色→花の色
夏の色→海の色
秋の色→空の色
冬の色→雪の色
これも、全く異論のない、それぞれに相応しい風景と言えよう。
○東北弁の童謡「どじょっこふなっこ」は、以下にあるように、歌の中に、春、夏、秋、冬 が出て来るが、捨てがたい味がある。 (ーー は、どじょっこだの ふなっこだの)
春になれば しがコも融けて ーー 夜が明けたと おもうべな
夏になれば わらしコ泳ぎ ーー 鬼コ来たなと おもうべな
秋になれば 木の葉コ落ちて ーー 舟コきたなと おもうべな
冬になれば しがコも張って ーー 天井コ張ったと おもうべな
 どじょっこ と ふなっこ(ネット画像)
どじょっこ と ふなっこ(ネット画像)
いずれも、四季それぞれの、良く目にする風景描写で、 春と冬にある、しがコ とは、氷のことだ。 特に、夏に、わらしコ(子供たち)が、川で水浴びする様をみて、そこに棲んでいる、どじょっこや、ふなっこどもは、鬼コが来たと思うだろうナ、というくだりが、なんとも可愛く楽しい。
○以前、芹 洋子 が歌って大ヒットした、「四季の歌」(荒木とよひさ 詞・曲)の歌詞では、以下の様になっている。
春を愛する人→心清き人 → 菫の花 → ぼくの友達 (恋人)
夏を愛する人→心強き人 → 岩を砕く波 → ぼくの父親
秋を愛する人→心深き人 → 愛を語るハイネ → ぼくの恋人 (友達)
冬を愛する人→心広き人 → 雪を溶かす大地 → ぼくの母親
四つの季節ごとに、心 清き/強き/深き/広き 人を充て、それぞれに、花/波/愛/大地 を持ってきて、最後に、具体的に 友達/父親/恋人/母親 とする辺りは、作詞者の並はずれた感性が感じられ、流石である。
余談だが、この歌の歌詞の原作では、春と、秋との最後が、( )の様に、現在とは、逆になっていたという。言われて見ると、オリジナルな歌詞の方が自然だろうか。
でも、現在の歌詞で、可愛い菫の花が、ぼくの(男)友達だったり、ぼくの恋人が、(男性の)ハイネのよう というのには、多少、違和感はあるものの、ハイネとは恋人の名前だ、等と思えば、殆ど支障はない。














 春らんまん
春らんまん 


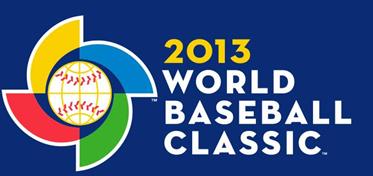 第3回WBCロゴマーク
第3回WBCロゴマーク 
 今回のユニフォーム等
今回のユニフォーム等 



