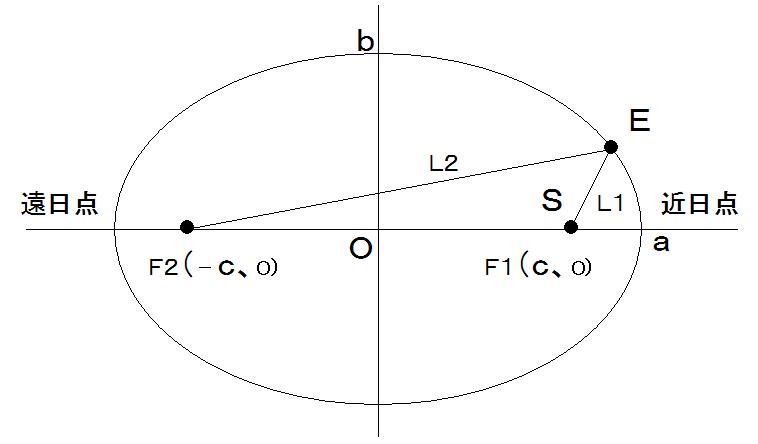2012年2月12日(日) 原発の再稼働 その2
停止している原発の再稼働については、当ブログの下記記事
原発の再稼働 その1 (2012/2/10)
で触れたところだが、今回は、その続編である。
大飯原発3、4号機について、関電が、今回の原発事故を教訓として、どのような問題点を見つけて、設備やシステムについて、どのような対策を打ったのか、そして、どのような評価をして、報告書を提出したかは、詳細は分らない。 一部報道で仄聞する所では、設計時の何倍もの地震や津波にも耐えられる、ともあるようだ。でも、設計時の何倍かが大事なのではなく、東日本大震災と同等の地震や津波に対しても、重大事態に至らない、と言うことが肝心なのは言うまでも無い。
対策と評価に当たってのポイントは、以下の2点と考える。
① 先ず、想定する自然の脅威だ。
自然現象として起こる脅威には、理論的最大値などはありえず、その対策にも、絶対安全とか、100%保障などは、あり得ない。
福島第一は勿論、国内のどの原発でも、これまでは、今回の大震災のような地震と津波は、起こるとは思っておらず、想定外だったのだが、実際に起こったのだ。
以下の情報は必ずしも正確ではないが、福島第一原発の設計値では、地震の震度は、5強 438ガル(実際は 6強 550ガル)、津波の高さは、6.5m(実際は 13.1m)だったようだ。
大昔の、貞観津波の例など、一部の識者は、その危険性を指摘していたのに、それが、安全神話の下に、配慮されなかった、とも言われる。
今回のように巨大な地震や津波は、少なくとも、東北の太平洋沿岸では、1000年に一度位だから、もう数100年は来ないだろう、また、日本海側など、原発の立地場所によっては、地盤の構造から、巨大地震は考えられない、と言えるかもしれない。
でも、これだけ深刻な放射能被害を経験した今は、腹を据えて、国内のどの原発でも、東日本大震災のような、或いは、それ以上の地震や津波が起こる、ということから評価を始めなければならないと思う。
前回の、その1で触れた、EUのストレステストの例にあるように、やはり、自然の脅威を、弱めに見積もりたい、という思考が働くようだ。
② 次のポイントは、どのような地震や津波の脅威まで、ほぼ完全に耐えられるか、という「防災」の思想と、仮に耐えられなくなって破壊されても、如何に重大な影響を押さえられるか、という「減災」の思想を区別することだ。
今回のような地震と津波に対しても、原発の安全性を、ほぼ100%保証するとすれば、膨大な費用がかかるわけだが、これは、防災の思想だ。
しかし、今回の事故を見るに、余りコストを掛けない工夫と対応で、決定的に深刻な事態(シビアアクシデント)に至らない様にする、或いは、それまでの時間を稼ぐことも、重要で、これは、減災の思想だ。このような減災の思想に立てば、深刻な事態は、かなり防げるのではないか、と思えるのである。
今回の事故で、現在の沸騰水型原子炉の最大の弱点は、全電源喪失という事態であることが分った(あるいは、元々、分っていたのかも知れない)。それが原因で、原子炉の冷却が出来なくなり、メルトダウンという最悪の状況になった。そして、専門家や関係者の誰も予想できなかった、水素爆発が起こり、これが、大量の放射性物質の拡散・飛散を招いている。
今回の事故で、地震と津波がどのように影響したのかは、今後の解明が待たれる所だが、大雑把に言って、地震に対しては、これまでも、機器や配管等でかなり配慮して来たと思われる。 一方、津波に対しては、殆ど、無防備だったと言えるのではないか。
素人的ながら、これまでのブログでも触れているが、減災の思想に立って、津波対策を主体に、比較的低コストで、比較的短期間に出来る、以下の様なものから実行可能と考える。
・商用電源系統の多ルート化、複数号機間の亘り配線の確保
・非常用電源設備とその燃料の配置場所の工夫
・原子炉建屋の出入り口等の防水措置の強化
・非常用復水器イソコンの習得訓練実施
・制御室全停電時の対応マニュアル整備と訓練
これらは、ストレステストなどと改めて言わなくとも、今回の事故の教訓として、経験的に分った対策であろう。
一方、防災の思想で、津波の被害を避けるために、中長期的に、場所を高台にしたり、複数の原発を集中させずに分散する、なども考えられる。が、高台では、海が遠くなると、輸送や冷却水の問題があり、分散すると、かえって危険が拡散し、地域との調整も面倒になる、と言った問題もある。
津波対策として、巨大で、長~い、万里の長城の様な防波堤を、原発の周囲に構築するといった対策もあろうか。
これらを実施するには、かなりの経費と時間を必要としよう。
○事故原因や、事故後の対応の問題等について、事故調査・検証委員会(畑村委員会)の中間報告が先日出された。
(当ブログの、下記記事 参照)
原発事故の検証 (2012/1/14)
この夏に、この委員会の最終報告が出される予定のようで、これが公表され、事故原因や問題点が分って、漸く、本格的な対策が取られる、と言うのが本来の筋である。2/8の公聴会でも、そのような発言もあったようだ。
でも、それを待ってからでは遅すぎる、という感じがあるのも事実で、ほぼ間違いないと思われる対策については、できるだけ早期に、実行に移して、次の災害に備えて行く事も必要である。
先述の様な対策については、中間報告でも指摘されているが、これらは、最終報告ではどのように位置づけられるのだろうか。 又、中長期的な対策については、どのように方向づけられるのだろうか。更に、新たな原因や問題点が判明して、今後の原発の安全性の方向づけで、有効な対策も出て来ることを、期待したいものだ。
○今回の原発の再稼働について、内容に関することではないが、情報の公開のやり方も、極めて重要だ。都合の悪い情報は隠して、見栄えを良くすることは世の常だが、いわゆる、安全神話の手法ではなく、ここは、オープンで行かなければならない。
もともとの設計値ではどうで、震災を教訓に、今回、何をどのように措置し、それによって、どのように改善されたのかを、明確にし、公表することが重要な点だ。
この手法は、化粧品のコマーシャル等で、使う前(before)と使った後(after)を、左右に対比した映像が良く出て来る、あれだ。 あれと同じ様に、震災前の設備等の状況と、対策後の設備等の状況を、対比する等して、誰にでも分るような形で、示して欲しいのだ。
密室に近い環境で、いくら専門家がチェックしたとはいえ、公聴会では、ややもすると、都合のいい意見しか言わない委員が居たり、事務局が無理やり結論を作文するようなら、原発に批判的な勢力や、地元の住民や自治体の関係者でない一般の国民にも、信用できないのは当然である。
○経済・社会活動の活性化に向けて、この夏の需要期は、必要な電力は大いに消費すべきで、それに向けてどう進めるかがポイントだ。
差し向きは、比較的短期間で、低コストで出来る対策を行い、beforeと、afterの違いを、分りやすく公表し、地域・国民の理解を得て、可能なところから、原発の再稼働を行う必要がある。
勿論、かなり近い将来に、大きな地震が想定される、関東から東海、中部、近畿、四国にかけた一帯の原発には、格段の対策が求められる。
一案だが、現状で可能な対策を施した上で、例えば、5年などの期間を限定して、原発を再稼働する。そして、再生可能エネルギーへの転換の筋道が、何とか見えてきたところで、原発を、徐々に、自然死に持っていき、お役御免とする、という案も考えられる。
完璧と思われる安全対策を施さない限り、原発の再稼働は、一切許さない! などと、思いつめる必要は無いのではないか。










 全機停止(2011年8月の番組)
全機停止(2011年8月の番組)