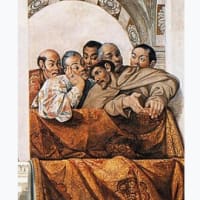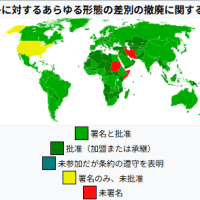2011年4月19日(火)原発事故の今後の工程表
福島第一原発事故は、現状では、予断を許さない状況が続いており、先が見通せる状況ではないのだが、4月17日(日)に、事故収束へ向けての工程表(ロードマップ)が、東京電力から発表された。
この工程表は、事故の収束に向けての、当事者としての作業工程の目標を示すと共に、他方で、農水産業も含めた、被災者や被害者、国民や国際社会に向けて、6~9か月後に、その後の展望の判断が行われる、との見通しを示したことで、これまでは、時期的な目標が無い、手探りの状況が続いていただけに、一歩前進、と言えよう。
勿論、この工程表に対しては、“絵に描いた餅だ”などの、色んな批判もあるのだが、それを承知の上で、何とか取り纏め、公表した、東電の責任と決意を見る思いである。
この工程表は、 国内と世界の人知を集めた上での、当事者としての、想定される予測と考えられる対策なのだが、ここにある時期的な目標は、最も、上手く進んだ場合のシナリオでの見通し、と言えようか。
今後、思わぬ事態に見舞われて、予定通りに行かない場合も、大いに予想されるのだが、そのようなシナリオの時は、工程内容や時期目標を修正すればいい。その場合は、変更せざるを得なかった要因は、明確にする必要があり、単純な、想定外、では済まされまい。
“東電は、約束したのに嘘をついた” 等と非難されようが、気にすることはない。修正せずに曖昧にしたり、事実を隠ぺいするなどは、最も避けるべき事と考える。
又、避難者等に対しては、今後は、最低でも6カ月間は辛抱し、覚悟を決めて、行動する必要がある、と言う、厳しいメッセージでもある、と言うことだ。

公表された工程表(ロードマップ)
工程表では、内容別に
Ⅰ冷却 (1)原子炉、(2)燃料プール
Ⅱ抑制 (3)滞留水、(4)大気・土壌
Ⅲモニタリング除染 (5)測定・低減・公表
に分けて整理してあり、それぞれに関して、現状から始まって、3か月単位で、ステップ1(3か月程度)、ステップ2(ステップ1終了後3~6か月程度)、中期的課題、と、時間軸で展開されている。
今回は、ステップ1について、触れてみたい。
先ずポイントとなるのは、ステップ1の3か月間である。事故の現状を踏まえた、ハード的な準備期間で、
「核燃料の冷却システムを確立し、放射性物質の放出を減らす」
事が狙いとなる。
このためには、自分なりに整理すると、以下のようになろう。
①現状より状況が悪化する、不測の事態に備える
a原子炉本体の爆発防止対策⇒窒素ガスの注入、淡水注入
b商用電源断対策⇒非常用電源車の配備と操作、給電系の相互融通
c自然の脅威(余震・津波・台風・豪雨・落雷)対策⇒溢水対策、防水等
②作業環境の調査と整備
aタービン建屋内の高濃度汚染水の移動と保管
集中廃棄物処理施設内部の緊急整備
b本体建屋内の線量調査(無人ロボット、有人)
③応急措置の実施
a格納容器に水を満たす(1、3号機)(水棺)
b圧力抑制室の破損個所修理(2号機)(コンクリート固め→その後水棺)
④放射性物質の飛散状況の調査と抑制対策
a現行の冷却用注水の継続(原子炉、燃料プール)
b高濃度汚染水の海への流出抑制
c燃料棒保管ブールの損傷調査
d本体建屋の覆いを検討
などが、喫緊の対策となる。

対策概要図
①が、最優先の課題だ。
①-aの、本体の爆発防止は、チェルノブイリ事故の二の舞という、最悪の惨事としないための、最重要事項であろう。一時、1号機で、水素と酸素の濃度が高まり、爆発の危険性があったため、それを避けるために、格納容器に、窒素ガスの注入・充填が行われた。4つある原子炉の各々は、その後は、安定しているようだ。又、各原子炉の中央制御室に表示されている、圧力計等の計器類は、正常なのかどうか、気になる所でもある。
①―bの、電源断対策については、先日の大きな余震で、東京電力、東北電力管内の、多くの原発で、外部電源が停止したが、応急措置等で、事無きを、得たようだ。
余震により、外部電源が止まった時に、用意していた電源設備に、自動的に切り替わるようになっておらず、その電源設備を操作できる人も、避難したために、結局、動かせず、役に立たなかった、という問題があった。又、給電系統の複数化はやっているものの、受配電盤間の接続が無かったために、片系だけでは全体を動かせなかった、という問題も見つかり、即、対策が取られたようだ。このように、今回の余震は、原発での電源の防災対策を検証する、貴重な場となったようだ。
電力会社の電源設備の不具合で、電力会社の原子炉が、無電力状態になった、と言うのは、笑い話ならいいのだが、怖い話ではある。
燃料棒を、常時、水で冷却しなければならず、そのため、給電が止まると、蒸発等で水が無くなり、燃料棒が露出し、水素爆発が起こる等、如何に怖い事態になるか、と言う、沸騰水型軽水炉(PSW)の、思わぬ弱点を、見せつけられている、思いである。
②は、冷却系の確立のためには、どうしても必要な作業のようだ。
②-aは、これまでも、何度も指摘されたことだ。タービン建屋内での作業がまずスタートになるだけに、その作業環境の整備が急がれる。高濃度汚染水で作業員が被曝したのは、2号機のタービン建屋地下であり、外の、トレンチやピットに、この汚染水が漏れていたのも、海に流出していたのも2号機だ。
2号機は、幸いに、本体の建屋が残っているので、放射性物質の外部への飛散が抑えられている。でも、本体の一部である圧力抑制室が破損しているようで、高濃度汚染水が漏れる等、最も、危険で、早急な対策が必要な炉だ。冷却システムの確立は、やはり、2号機から始める事になるのだろうか。
他の炉の、タービン建屋内や外のトレンチ等での、汚染水の状況はどうなのだろうか。4/19のNHK-TV情報では、汚染水の、滞留量は、以下のようになっている。
1号機関連 20500トン
2号機関連 25000トン(特に高濃度汚染水 水面上1000mSv/時)
3号機関連 22000トン
高濃度汚染水を保管する場所として、集中廃棄物処理施設が考えられている。この施設に保管されていた低濃度汚染水は、緊急事態を理由に、除染することなく、そのまま海に放出し、内部は空になって、これまで、施設内部の水漏れ等の点検を行ってきているが、NHK-TV情報によれば、今日4/19から、2号機の汚染水の移送を開始したと言う。
当面は、1万トンを移送すると言う。理由は、施設で、万一、漏れが起こった場合でも安全なように、汚染水の水位を、トレンチでの地下水の水位より低くしない、と言うバランスを考慮しているため、というが、良く理解できない。移送先は、3万トンもの容量があるのに、使わないのは勿体ない話だがーー。
この移送作業、思ったよりも時間がかかるようで、1日当たり480トンで、26日程かかり、5月14日頃に終了する予定という。続く作業として、この集中廃棄物処理施設に移送された、高濃度汚染水を、除染/塩分処理する水処理施設を建設し、きれいになった水を、再度、原子炉に供給するシステムをつくり、6月末頃までに完成させて、稼働させる計画だ。
この、汚染水の循環システムが上手く機能すれば、作業の邪魔になっている、タービン建屋内の汚染水は、どのように変わるのだろうか。
2号機のトレンチ等に残った、15000トンの汚染水は、仮設のタンクに移すとしているが、学校の25mプール1杯を500トンとしても、大変な容量が必要となる。
やはり、高濃度汚染水を、大量に保管する施設が、更に、必要になる、こともあるのではないか。これらの施設は、陸上が望ましいのだが、一時的には、海上案もあろうか。
静岡から曳航してきているメガフロートや、その他の船等は、今は、どうなっているのだろうか。これらの海上設備を、保管先として、一旦使用すれば、一定期間、安全に管理していかなければならない。それらの保管先が、地震や津波等で破壊され、2次、3次の、海の放射能汚染を引き起こすことは、絶対に避けねばならない。
②-bは、本体建屋内の線量等の調査である。タービン建屋内の作業だけでは、冷却システムの確立が出来ない場合は、本体建屋に入って作業する必要があり、これまでの、地震や爆発での、破損等を考えると、どうしても本体建屋での作業が必須となろう。 本体の一部である圧力抑制室が破損していると言われ、最も問題となる2号機で、この破損個所を修理(コンクリート固め)するには、地下まで入らなければならない。
最近行われた、原子炉建屋内の線量測定結果は以下である。作業員の被曝線量上限は、250mSv/時とされていることから、かなり厳しい数値と言える。
1号機 原子炉建屋 南二重扉 270mSv/時 作業員計測
北扉 49mSv/時 4/16 ロボット計測
2号機 破損しているとされる、圧力抑制室付近は、即刻、被曝反応が出る線量、と言われている
3号機 原子炉建屋 57mSv/時 4/16 ロボット計測
②―bで、本体建屋内の線量が分り、作業の安全性が、確保された後での対策が、③となる。
③-aの、水棺は、これまで行われた経験が無いようだが、原子炉本体内に水を入れるだけでなく、格納容器全体に水を入れて、原子炉毎冷却すると言う方法のようだ。勿論、格納容器の損傷や、配管の出入り口の水漏れ等が、問題となる。又、多量の水を格納容器に入れた場合、余震等での安全性も、問題になろう。格納容器に、新たに熱交換器を取り付ける時は、そのための作業環境の整備・確認も必要となる。
③-bは、2号機だけの問題のようだが、上述の様な高い線量が想定される環境での作業を、どうするかが問題だろう。先ず、ロボットで、破損状況や線量について、状況調査を行うこととなろう。その後、コンクリートで固めて破損個所を修理するとしたら、ロボットでホースを引き、ホースの先からコンクリートを流し込むようなやり方になるのだろうか。
④は、放射性物質の外部への飛散や流出を抑えることだ。④―aは、冷却システムの確立まで当面継続する必要があり、④-bは、トレンチからの海への流出は先日来止まったが、他から海への流出はないか確かめる一方、トレンチからの溢れ出るのを防ぐ対策等も、必須である。
④―cは、燃料プール内の、燃料棒の損傷程度を見極ることが重要だ。中期的には、損傷した燃料棒は、取り出して、然るべき保管場所に保管し、放射能の発生を抑えることとなろう。
④―cの調査の上で、④-dの、全体の覆いも有効であろう。この場合、密封型にしないなど、新たな建屋爆発を起こさないような、工夫が必要となろう。
飯舘村等の高濃度の汚染は、3月半ばの建屋爆発による飛散が原因と言われるが、その後も、各原子炉内や、各燃料プール内での燃料棒の損傷によって、弱いながら、かなりの放射性物質が飛散流出している可能性がある。
放射能と言う、見えない脅威を正面に見据えた戦いが、いま、始まった所である。