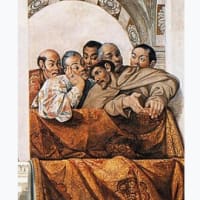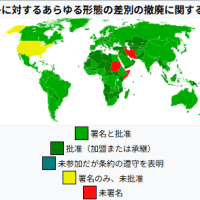2011年2月1日(火) 色の世界―交差点の信号機の色は?
言うまでも無く、自然界は、多様な色に満ち溢れているが、社会的に、色が決められているものが、幾つかある。 それらの中で、代表的なものの一つが、道路交通での信号機の表示色であり、今回は、色の世界の一環とした、これを取り上げてみたい。
交差点では、信号機の表示に従って、車や歩行者が行動している。 信号機の色で、赤(止まれ)と黄(注意)は良いのだが、気になるのが、進め(正確には、命令ではなく、進んでよい)の表示で、あれは、青なのか、緑なのか。 運転免許の講習などでは、青信号と言われるのだが、通常、青と言う時は、空の青などが連想されることから、常識的な感覚では、どうも、緑に見えるのだ。今回、色々、調べてみることとした。
国際的には、国際照明委員会(CIE)という国際機関で、交通信号機の色は、緑(green)、黄(yellow)、赤(red)と、明確に決められているようだ。 日本でも、信号機が初めて導入された、昭和の初期には、これと同じに、緑、黄、赤と決められていたようだ。
一方、日本では、伝統的に、青と緑とは、余り区別されず、緑色は青色の一種として、青野菜、青物市場、青菜(せいさい)、青菜に塩、などと使われてきていたので、当時のマスコミや庶民の間では、信号の色を、青と呼んだ、という。 その後、昭和22年になり、一般的な呼称に合わせて、法令上も、緑から青に変更され、現在に至っている、という。 その時に、実際の色について、どのように決められたのか、変更されたのか否かは、定かではない。 色の混乱の、一つの理由が、ここにある。
更に、混乱のもう一つの要因として、日本では、赤緑色覚異常の障害者に配慮して、緑色といっても、ぎりぎりの、極めて青に近い波長にしている、ということがあるようだ。
このことを確かめるため、各信号灯の色について、呼称は、青、黄、赤としているものの、色自身については、色見本や波長等で、どのように規定しているのか、調べたが、良く分からない。 が、数少ない情報として、某信号機メーカーのサイトの、LED式信号機の製品仕様によれば、各色灯の主波長は、
赤灯 630nm
黄灯 592nm
青灯 503nm (nmはナノメートル)
とある 。一方、各色の波長は、多少の差異はあるが、おおむね以下のように言われている。
赤 780~610nm
橙 610~590nm
黄 610~590nm
緑 570~500nm
青 500~460nm
藍 460~430nm
紫 430~380nm
これで見ると、赤灯は良いとして、黄灯は、やや橙寄りだ。 又、青灯は、緑の範囲内だが、ぎりぎりまで青に近くなっている、ことが分る。 呼称上の用語としては、青色なのだが、実際の色は、かなり青緑(シアン)に近い、青である事が、判明した。
当該メーカーのサイトにあるLED信号灯の写真と、光の三原色を混色した時の色を、以下に示 す。


実際のLED信号機の色灯 青B 青緑C 緑G 黄Y 赤R
信号機によっては、青の色に、微妙な違いがあり、歩行者用の信号機などには、可なり緑色をしているものもある。 緑のグリーンは、国際的に、安全の色でもあり、進んでよい を示す信号の色は、緑と呼びたい気持ちもある。
纏めとしては、前述の様に、青と緑に関する、日本人の、伝統的な色彩感覚も考慮すると、そう、神経質になる必要はない、と思われる。 信号の色を、青と呼ぼうと、緑と呼ぼうと、表示を黄や赤と間違えて、危険になることは、先ず考えられない。 従って、幼稚園や小学校などでの、交通安全教育では、余り拘らずに、“横断歩道は、信号が青、になったら涉りなさい”、と教えればよく、この場合、信号の色を、緑と言っても、一向に構わないだろう。
言うまでも無く、自然界は、多様な色に満ち溢れているが、社会的に、色が決められているものが、幾つかある。 それらの中で、代表的なものの一つが、道路交通での信号機の表示色であり、今回は、色の世界の一環とした、これを取り上げてみたい。
交差点では、信号機の表示に従って、車や歩行者が行動している。 信号機の色で、赤(止まれ)と黄(注意)は良いのだが、気になるのが、進め(正確には、命令ではなく、進んでよい)の表示で、あれは、青なのか、緑なのか。 運転免許の講習などでは、青信号と言われるのだが、通常、青と言う時は、空の青などが連想されることから、常識的な感覚では、どうも、緑に見えるのだ。今回、色々、調べてみることとした。
国際的には、国際照明委員会(CIE)という国際機関で、交通信号機の色は、緑(green)、黄(yellow)、赤(red)と、明確に決められているようだ。 日本でも、信号機が初めて導入された、昭和の初期には、これと同じに、緑、黄、赤と決められていたようだ。
一方、日本では、伝統的に、青と緑とは、余り区別されず、緑色は青色の一種として、青野菜、青物市場、青菜(せいさい)、青菜に塩、などと使われてきていたので、当時のマスコミや庶民の間では、信号の色を、青と呼んだ、という。 その後、昭和22年になり、一般的な呼称に合わせて、法令上も、緑から青に変更され、現在に至っている、という。 その時に、実際の色について、どのように決められたのか、変更されたのか否かは、定かではない。 色の混乱の、一つの理由が、ここにある。
更に、混乱のもう一つの要因として、日本では、赤緑色覚異常の障害者に配慮して、緑色といっても、ぎりぎりの、極めて青に近い波長にしている、ということがあるようだ。
このことを確かめるため、各信号灯の色について、呼称は、青、黄、赤としているものの、色自身については、色見本や波長等で、どのように規定しているのか、調べたが、良く分からない。 が、数少ない情報として、某信号機メーカーのサイトの、LED式信号機の製品仕様によれば、各色灯の主波長は、
赤灯 630nm
黄灯 592nm
青灯 503nm (nmはナノメートル)
とある 。一方、各色の波長は、多少の差異はあるが、おおむね以下のように言われている。
赤 780~610nm
橙 610~590nm
黄 610~590nm
緑 570~500nm
青 500~460nm
藍 460~430nm
紫 430~380nm
これで見ると、赤灯は良いとして、黄灯は、やや橙寄りだ。 又、青灯は、緑の範囲内だが、ぎりぎりまで青に近くなっている、ことが分る。 呼称上の用語としては、青色なのだが、実際の色は、かなり青緑(シアン)に近い、青である事が、判明した。
当該メーカーのサイトにあるLED信号灯の写真と、光の三原色を混色した時の色を、以下に示 す。


実際のLED信号機の色灯 青B 青緑C 緑G 黄Y 赤R
信号機によっては、青の色に、微妙な違いがあり、歩行者用の信号機などには、可なり緑色をしているものもある。 緑のグリーンは、国際的に、安全の色でもあり、進んでよい を示す信号の色は、緑と呼びたい気持ちもある。
纏めとしては、前述の様に、青と緑に関する、日本人の、伝統的な色彩感覚も考慮すると、そう、神経質になる必要はない、と思われる。 信号の色を、青と呼ぼうと、緑と呼ぼうと、表示を黄や赤と間違えて、危険になることは、先ず考えられない。 従って、幼稚園や小学校などでの、交通安全教育では、余り拘らずに、“横断歩道は、信号が青、になったら涉りなさい”、と教えればよく、この場合、信号の色を、緑と言っても、一向に構わないだろう。