アメリカ人ハーキュリーズ・ベルについて、彼が意味しているものについて寓意的に読み取ろうとしても、そう簡単にはいかない。時には経済至上主義的な勢力とも読めるし、彼が決起呼びかけの声明文に「呪術はたち切られねばならない!」と書いていることから、自由主義的な革命勢力を表象しているようにも読める。
さらに声明文の最後で「すべての若者はルーチファー党員になれ!」と呼び掛けていることから、神と対立するものとして位置づけられているようにも見える。ルーチファーはルシファー、つまりは堕天使であり、悪魔と同一視されることもあるから、神の反対概念でさえある。しかし、アメリカ人はパテラを「サタン」と呼んで批判しているのであるから、本来の「光をもたらす者」として「サタン」に対立する存在とみなすこともできる。
もともと「ハーキュリーズ」はギリシャ神話のヘラクレスのことであり、キリスト教にとっては異教の権力神であり、大きな暴力性を象徴している存在でもあるだろう。アメリカ人の表象するものがこれほど多義的である以上、それを単に寓意的に読もうとする試みは失敗するだろう。一方パテラの方はどうかと言えば、こちらは明らかにキリスト教の神のイメージをまとわされており、アメリカ人ほどの多義性はないかもしれないが、その代わりにヨーロッパがそれまで信仰してきた神とは、驚くほど異なった神の諸相を示している。だからパテラについても単純に神を寓意するものとして捉えることはできない。
私が言う神の諸相は、「私」とパテラとの対決の場面に表現されているのである。最初の対決の場面で、まずパテラは「私」に次のように言う。
「君はいちども私のところへ来ることができないといって、苦情をいっているが、しかし私はいつでも君のそばにいたのだ。君が私を非難したり、私に絶望したりしている姿を、私はいくども見かけた。なにを君のためにしてあげればいいというのだ? 君の願いを言うがいい!」
これが神の遍在の主張であることは明らかである。神は不在のように思われても、見えざる者として、いつでも人間のそばに寄り添っているということである。しかし、パテラの言葉は神の日常的な不在に対する言い訳のようにしか聞こえない。
また願いを問われた「私」はパテラに対して、健康を害した妻を救ってくれと懇願し、パテラは「助けてあげよう」と答えるが、結局この約束が果たされることはなく、妻は死んでしまうのである。ここには救いの約束をしながらそれを果たさない〝神の約束不履行〟の姿が示されている。神は自らの責任を遂行することができないのである。
二度目の対決で「私」はペルレの国の没落に際して、何もしようとしないパテラを難詰する。
「――私は最後の力をふりしぼって問いかけた。「パテラよ、きみはなぜ万事をなるがままにまかせているのだ?」」
「私」の問いにパテラは動揺したのか、しばらく返事を返さないでいるが、やがて返ってくる返事は次のようなものである。
「突然彼は金属的に響く低音で、「ぼくは疲れている!」と叫んだ。」
約束を履行することもなく、責任を遂行することもない神は、今度は自らの疲労をその理由とするのである。










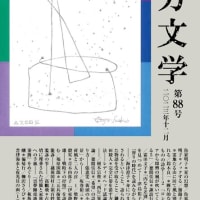

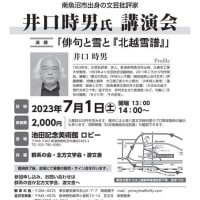

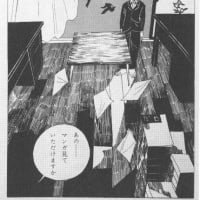
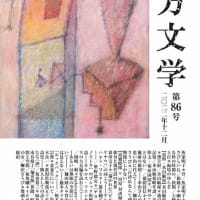
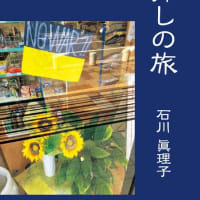
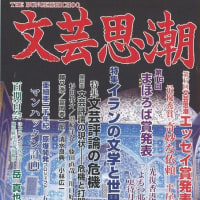
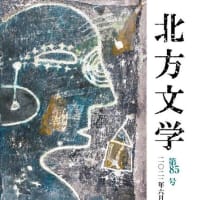


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます