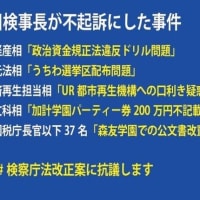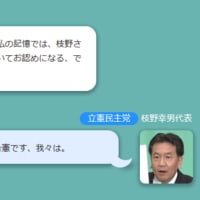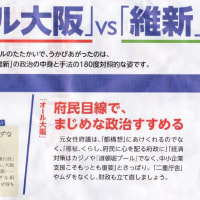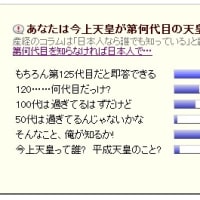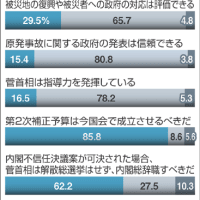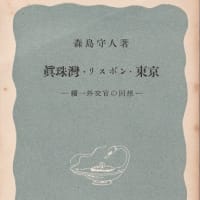6月30日の朝日新聞社説。
私はそもそも、地方公務員の世界で何故あれほど公然と政治活動が認められているのか不思議だった。
地方公務員も国家公務員同様、政治的行為は制限されているはずなのに。
国家公務員法には政治的行為の制限に違反した場合の罰則があるが、地方公務員にはそれがないことを、今回の騒動で初めて知った。
だが、地方公務員も地方政治には当然深く関与している。厳しい政治的中立性が要求されるのは同様のはずである。
このような差を設けることに、合理的な根拠はあるのだろうか。
橋下が、当初は条例で罰則を設けようとしたのも、そうした疑問に基づくものだろう。
だが、政府は、地方公務員法制定の経緯からして、条例で罰則を設けることは違法であるとの答弁書を閣議決定した。
制定の経緯がどうであれ、法律に「してはならない」と書いていないことをするのが果たして違法なのかどうか、私には大いに疑問だが、閣議決定である以上橋下はこれに従わなければならない。
ただ、制定の経緯は、「地方公務員の地位から排除すれば足りる」から敢えて罰則を設ける必要はないというものだったため、橋下はそれならと今度は懲戒処分を下すために具体的事例を定めた条例の制定に動いた。
しごく当然の反応であり、何の不思議もない。
国家公務員法の罰則規定が「時代にあわなくなっている」と考えるのは朝日の自由だ。
しかし、時代に合っていようがいまいが、国家公務員法でも地方公務員法でも現実に政治的行為は制限されているのである。
ならば、それに基づいて懲戒処分を下すために具体的事例を定めておくのは当たり前のことだろう。処分権者が恣意的に政治的行為を定義することを防ぐためにも。
条例が定める政治的行為の制限が厳しすぎるといった批判はともかく、条例を制定すること自体に問題があるという批判には賛同しがたい。
ならば、まず地方公務員法の政治的行為の制限の廃止を民主党政権に訴えるべきだろう。
ついでに言うと、
とあるが、仮にそうだとして、それによる弊害は生じていないのだろうか。本当にそれがわが国が進むべき方向なのだろうか。
さて、社説は、その条例案における政治的行為の制限の内容について、
と述べるが、果たしてこれが「すべての活動をしばりかねない」と言えるのか。
これらは、政治活動に単に参加するというレベルではない。 政治活動を主宰する、あるいはかなりそれに近いレベルの活動だろう。
検索すると、ある反橋下ブログに条例案が全文掲載されていたので読んでみたが、これらの制限項目は全て、国家公務員なら人事院規則で制限されているものばかりであり、特段問題があるとは思えない。
一方で社説は言う。
しかし、「休みのときに、一般の職員がデモや政治的集会に私服で出かける」ことはそもそもこの条例案では制限されていない。
橋下も、7月1日のtwitterでは、
と述べており、デモへの参加者を一律に懲戒処分にせよなどとは言っていない。
制限されていない事例をわざわざ持ち出して、それへの制限までが意図されているかのように「息苦しい制度によって社会の幅広さや活力をそぐ害が大きい」と語るのは、読者を惑わすものではないか。
さらに社説は、
と問うているが、何故このような問いが出てくるのか不思議だ。
この条例制定の動きは単なる橋下による抵抗勢力潰しであり、自分を支持する職員に対しても同じ原理を適用できるはずがないと高をくくっているのだろうか。
橋下がこれにどう答えるかはわからないが、仮に反・橋下の政治活動を公然と行った職員を、言葉どおり「バンバン懲戒免職にする」のなら、親・橋下の政治活動を公然と行った職員も同様に処分すればよいだろう。
その場合、朝日はこれをどう評するだろうか。
職員の飲酒運転による交通事故の続発に業を煮やした高島宗一郎・福岡市長(元九州朝日放送アナウンサー)は、職員に対し1か月間自宅外で酒を飲まないよう求め、話題になった。
その高島は、6月19日の朝日新聞オピニオン欄「耕論 「禁酒令」は妥当か」でこう述べている。
公務員の政治活動についても、同様のことが言えるのではないだろうか。
大阪政治条例―基本的人権を制約する
政治活動をした職員はバンバン懲戒免職にする――。
橋下徹大阪市長はいう。言葉どおり、そうした職員を原則として免職などにする「職員の政治的行為の制限に関する条例案」を市議会に提出する。
条例案では、制限する政治的行為を具体的にあげている。政治団体の機関紙の発行や配布をしてはならない。集会で拡声機を使って政治的意見をいうこともだめ。政治的目的をもって演劇を演出するのも禁止。
勤務中か否か、公務員とわかる姿かどうかを問わず、すべての活動をしばりかねない。
集会や結社、表現の自由は、憲法が保障する民主主義の基本だ。だから政治活動の自由も保障される。行政の中立を損なわない範囲での公務員の活動も、自由であるべきだ。
大阪市の条例案は、公務員の私的な生活領域にも踏み込むものであり、賛同できない。
国家公務員の特定の政治活動には法で刑事罰があり、地方公務員にはない。橋下氏は当初、条例に同じような規定を入れようとしたが、政府が「地方公務員法に違反する」との答弁書を閣議決定したため、断念した。
しかし、この答弁書で政府は「地方公務員の地位から排除すれば足りる」と、地公法ができた時の経緯を示したため、免職までができる条例案にした。
規制は最小限にとどめるという精神を取り違えている。
国家公務員法の罰則規定は、1948年、連合国軍総司令部(GHQ)が労組の活動を封じるために、当時の内閣につくらせた。今は、その規定の方が、時代にあわなくなっている。
むろん、公務員は自分の政治的な信条で行政を左右してはならない。しかし休みのときに、一般の職員がデモや政治的集会に私服で出かける。それは、本人の判断ですることだ。
社会の情勢や国民の考えは、大きくかわった。先進国ではごく限られた行為だけが規制されている。今さら戦後の混乱期のような考えに戻ることはない。息苦しい制度によって社会の幅広さや活力をそぐ害が大きい。
橋下氏が代表である大阪維新の会は、次の衆院選で全国に候補者を立てるという。脱原発や大阪都構想に共感した職員が、休日に街頭署名や集会を企画したら免職にするのだろうか。
大阪市では長年、役所と組合のもたれあいが言われてきた。昨年の市長選では前市長を職員労組が支援し、勤務中に職場を抜けて政治集会に出ていた職員もいた。このような問題は現行法で個別に正せばいい。
私はそもそも、地方公務員の世界で何故あれほど公然と政治活動が認められているのか不思議だった。
地方公務員も国家公務員同様、政治的行為は制限されているはずなのに。
国家公務員法には政治的行為の制限に違反した場合の罰則があるが、地方公務員にはそれがないことを、今回の騒動で初めて知った。
だが、地方公務員も地方政治には当然深く関与している。厳しい政治的中立性が要求されるのは同様のはずである。
このような差を設けることに、合理的な根拠はあるのだろうか。
橋下が、当初は条例で罰則を設けようとしたのも、そうした疑問に基づくものだろう。
だが、政府は、地方公務員法制定の経緯からして、条例で罰則を設けることは違法であるとの答弁書を閣議決定した。
制定の経緯がどうであれ、法律に「してはならない」と書いていないことをするのが果たして違法なのかどうか、私には大いに疑問だが、閣議決定である以上橋下はこれに従わなければならない。
ただ、制定の経緯は、「地方公務員の地位から排除すれば足りる」から敢えて罰則を設ける必要はないというものだったため、橋下はそれならと今度は懲戒処分を下すために具体的事例を定めた条例の制定に動いた。
しごく当然の反応であり、何の不思議もない。
国家公務員法の罰則規定が「時代にあわなくなっている」と考えるのは朝日の自由だ。
しかし、時代に合っていようがいまいが、国家公務員法でも地方公務員法でも現実に政治的行為は制限されているのである。
ならば、それに基づいて懲戒処分を下すために具体的事例を定めておくのは当たり前のことだろう。処分権者が恣意的に政治的行為を定義することを防ぐためにも。
条例が定める政治的行為の制限が厳しすぎるといった批判はともかく、条例を制定すること自体に問題があるという批判には賛同しがたい。
ならば、まず地方公務員法の政治的行為の制限の廃止を民主党政権に訴えるべきだろう。
ついでに言うと、
先進国ではごく限られた行為だけが規制されている。
とあるが、仮にそうだとして、それによる弊害は生じていないのだろうか。本当にそれがわが国が進むべき方向なのだろうか。
さて、社説は、その条例案における政治的行為の制限の内容について、
政治団体の機関紙の発行や配布をしてはならない。集会で拡声機を使って政治的意見をいうこともだめ。政治的目的をもって演劇を演出するのも禁止。
勤務中か否か、公務員とわかる姿かどうかを問わず、すべての活動をしばりかねない。
と述べるが、果たしてこれが「すべての活動をしばりかねない」と言えるのか。
これらは、政治活動に単に参加するというレベルではない。 政治活動を主宰する、あるいはかなりそれに近いレベルの活動だろう。
検索すると、ある反橋下ブログに条例案が全文掲載されていたので読んでみたが、これらの制限項目は全て、国家公務員なら人事院規則で制限されているものばかりであり、特段問題があるとは思えない。
一方で社説は言う。
むろん、公務員は自分の政治的な信条で行政を左右してはならない。しかし休みのときに、一般の職員がデモや政治的集会に私服で出かける。それは、本人の判断ですることだ。
社会の情勢や国民の考えは、大きくかわった。先進国ではごく限られた行為だけが規制されている。今さら戦後の混乱期のような考えに戻ることはない。息苦しい制度によって社会の幅広さや活力をそぐ害が大きい。
しかし、「休みのときに、一般の職員がデモや政治的集会に私服で出かける」ことはそもそもこの条例案では制限されていない。
橋下も、7月1日のtwitterでは、
政治活動には、デモなどの表現活動と、選挙活動そのものがある。前者はまあいいにしろ、しかし後者との区別があいまいなものもある。政治家は公人として基本的人権が大幅に制約される。公務員も同じ公人だ。公務員がどれだけの力を持っているか、朝日新聞は知らないのか?
と述べており、デモへの参加者を一律に懲戒処分にせよなどとは言っていない。
制限されていない事例をわざわざ持ち出して、それへの制限までが意図されているかのように「息苦しい制度によって社会の幅広さや活力をそぐ害が大きい」と語るのは、読者を惑わすものではないか。
さらに社説は、
橋下氏が代表である大阪維新の会は、次の衆院選で全国に候補者を立てるという。脱原発や大阪都構想に共感した職員が、休日に街頭署名や集会を企画したら免職にするのだろうか。
と問うているが、何故このような問いが出てくるのか不思議だ。
この条例制定の動きは単なる橋下による抵抗勢力潰しであり、自分を支持する職員に対しても同じ原理を適用できるはずがないと高をくくっているのだろうか。
橋下がこれにどう答えるかはわからないが、仮に反・橋下の政治活動を公然と行った職員を、言葉どおり「バンバン懲戒免職にする」のなら、親・橋下の政治活動を公然と行った職員も同様に処分すればよいだろう。
その場合、朝日はこれをどう評するだろうか。
職員の飲酒運転による交通事故の続発に業を煮やした高島宗一郎・福岡市長(元九州朝日放送アナウンサー)は、職員に対し1か月間自宅外で酒を飲まないよう求め、話題になった。
その高島は、6月19日の朝日新聞オピニオン欄「耕論 「禁酒令」は妥当か」でこう述べている。
私的な時間への強制の批判もありますが、公務員は夕方6時に完全に自由になるとは考えていない。公務員以外でも全ての職業の人は看板を背負っている。権利や自由は大切ですが、社会的立場を心のどこかにストックさせておくのは基本です。
飲酒不祥事が続けば、民間の企業だったら消費者はそこの商品を買うのをやめますよ。市民は行政サービスを受ける市役所を選べない。市役所は不祥事があっても潰れない。公務員は厳しい目で見られなければならない。市は内規で飲酒運転を一律懲戒免職と定めていますが、私は妥当と考えています。
〔中略〕
市民が私に求めていることは謝罪を繰り返すのではなく、この事態にトップとしてどうするのかを見せろということだと思う。
公務員の政治活動についても、同様のことが言えるのではないだろうか。